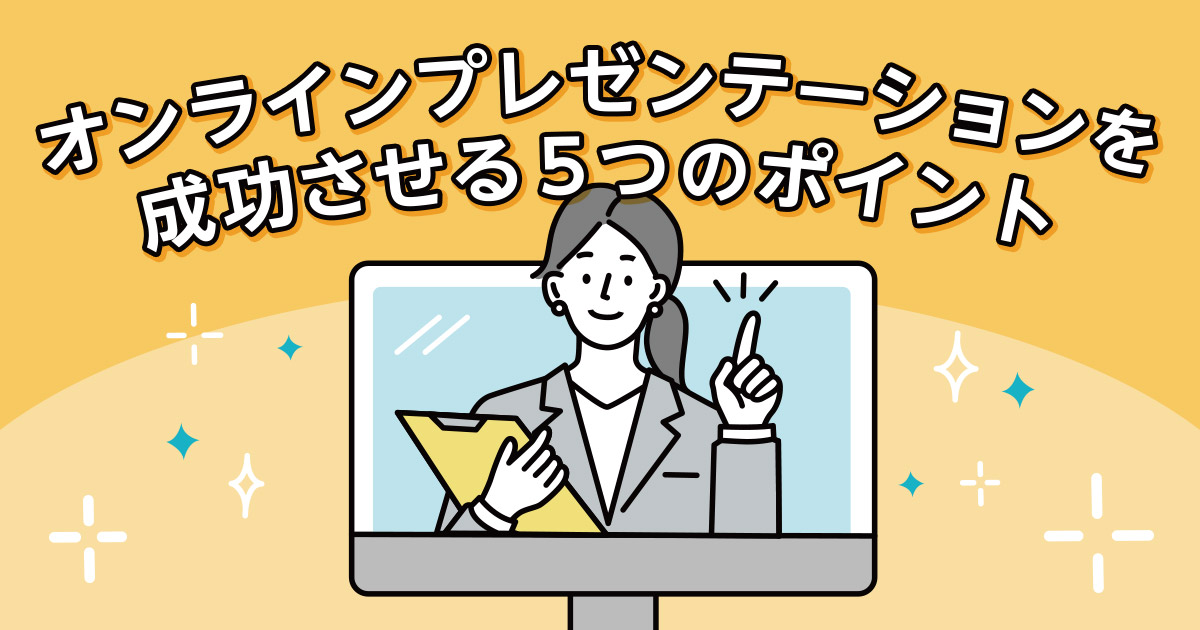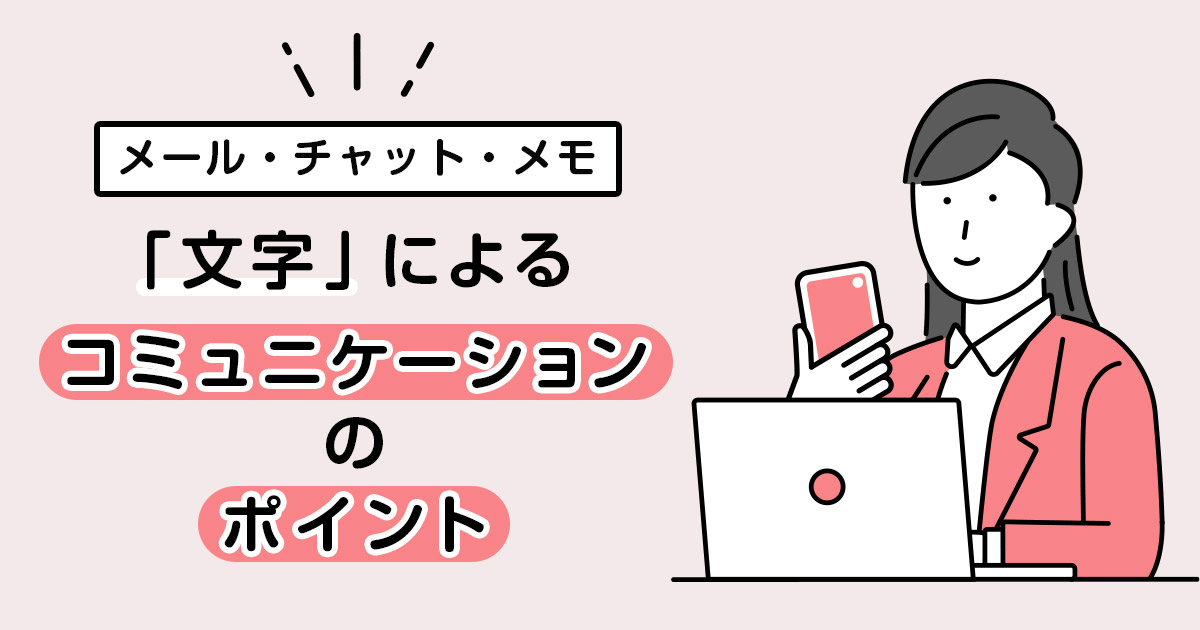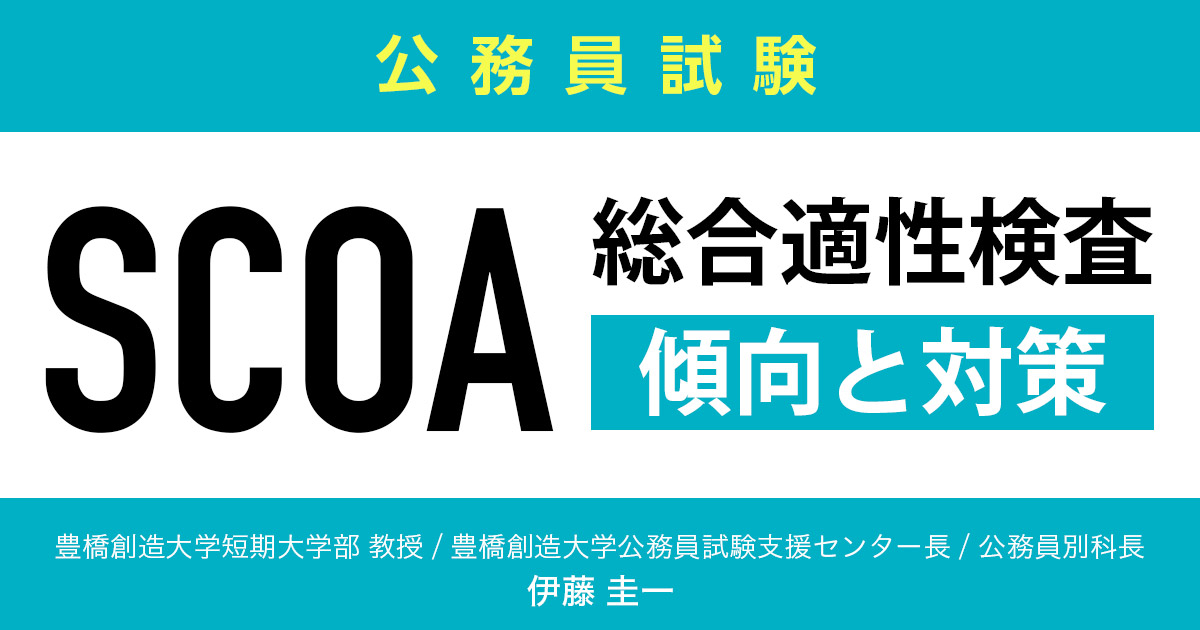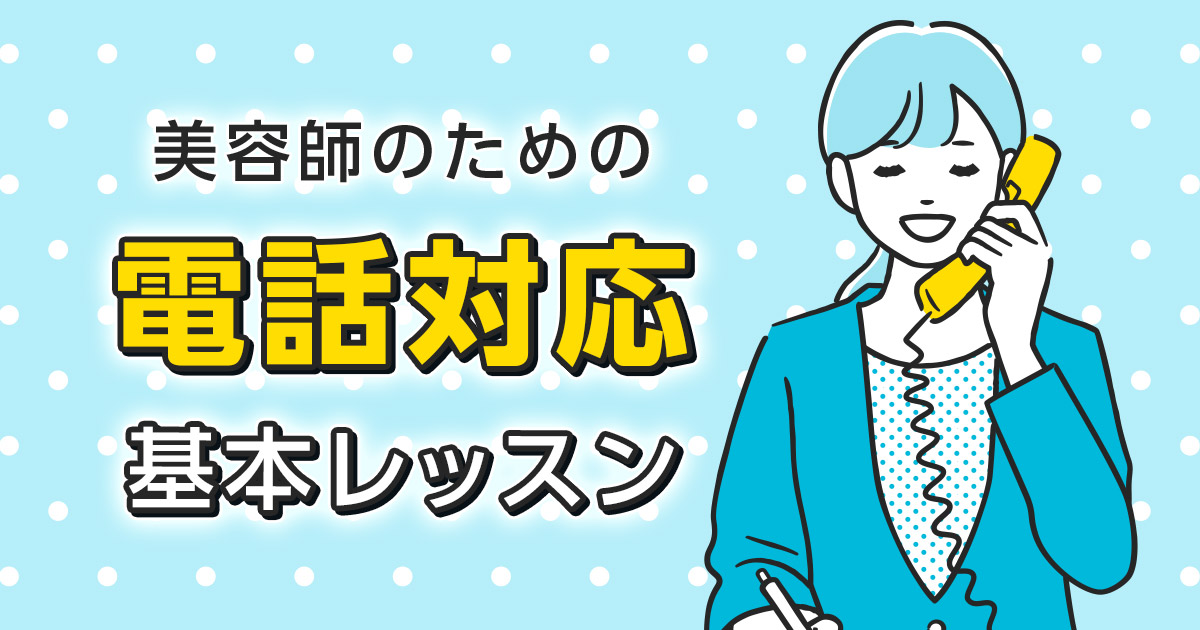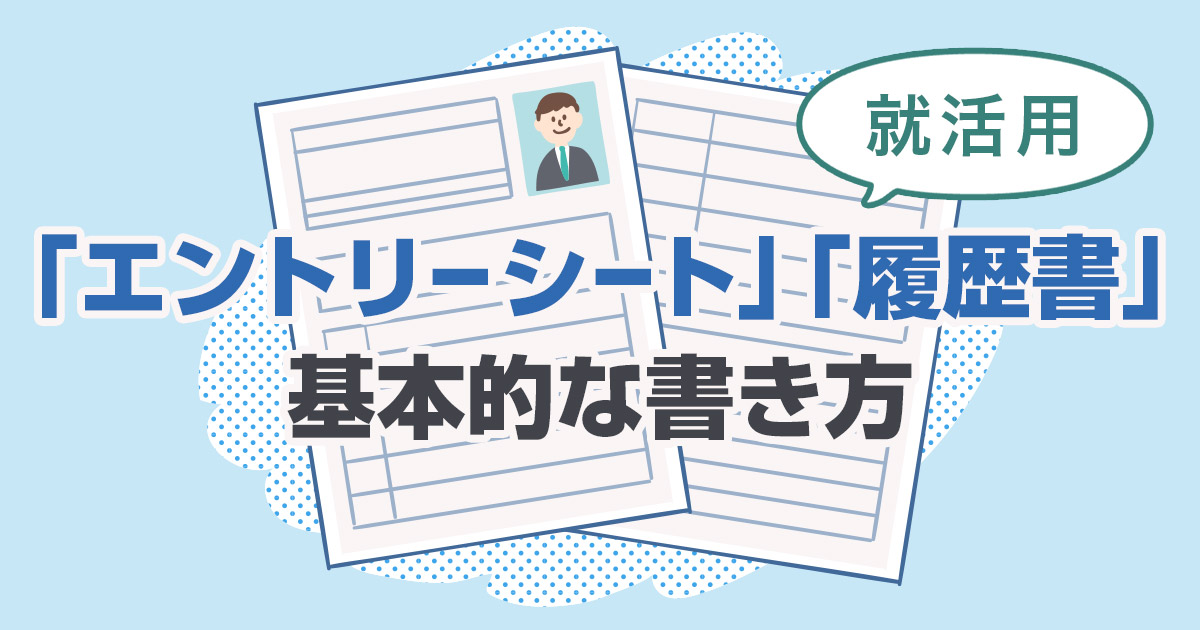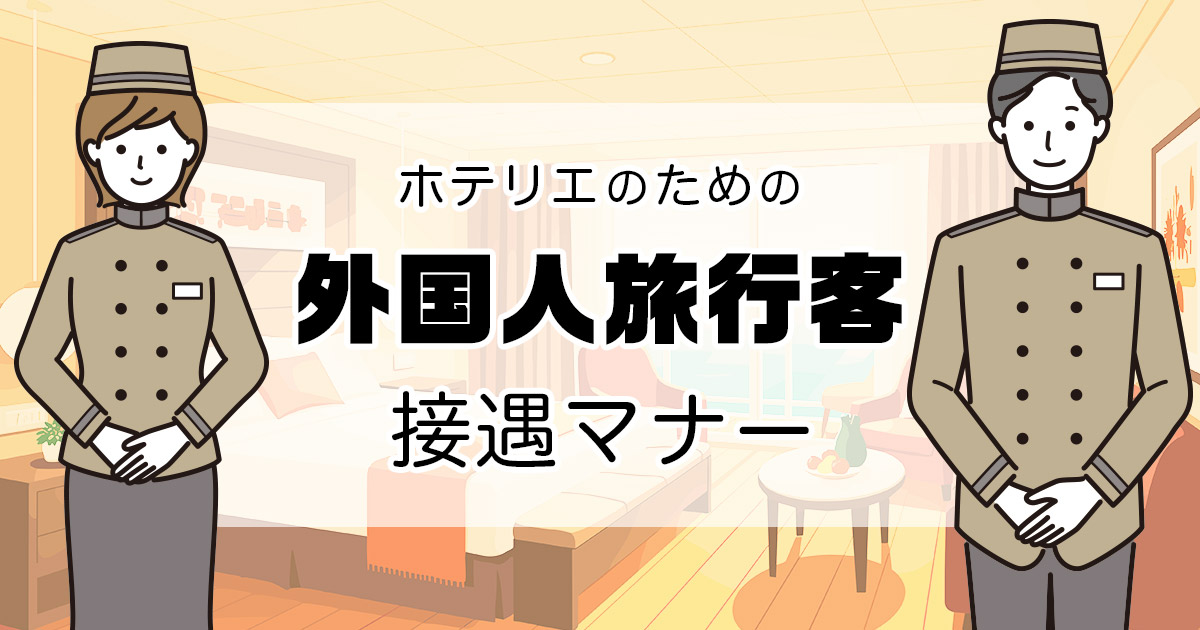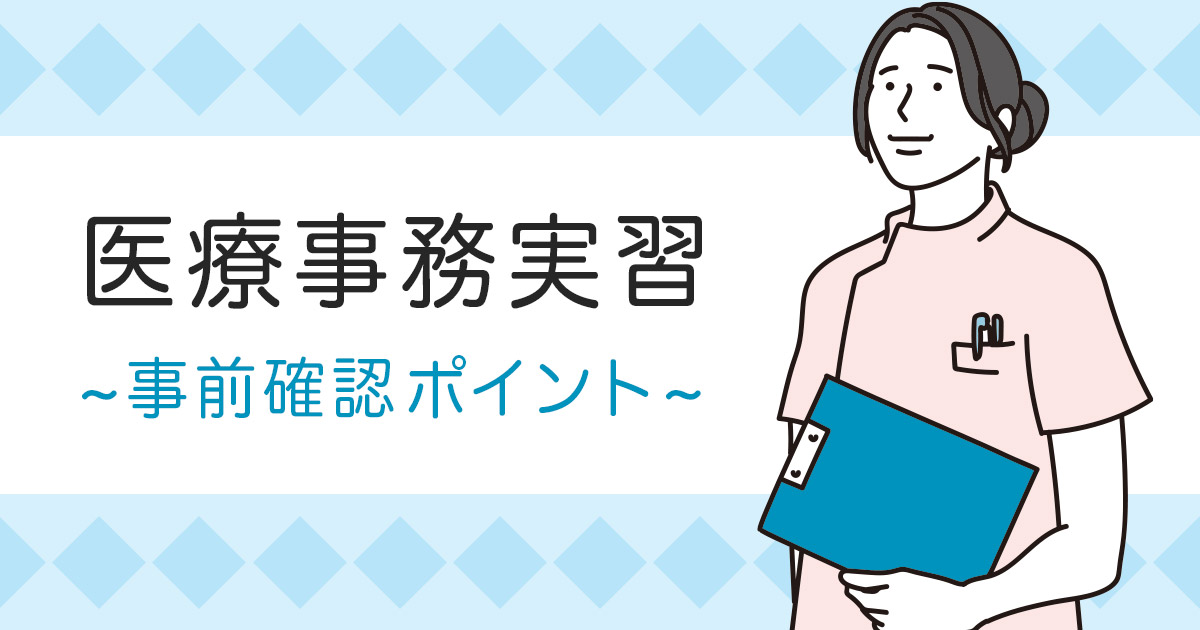
医療事務スタッフを目指す学生は、ほとんどの場合専門学校在学中に実習期間があります。学校としては、接遇マナーや心構えを押さえた質の高い学生を送り出したいですよね。
そこで今回は、医療事務実習前に学生に学んでおいてほしいポイントについてお伝えします。
※この記事は「医療事務実習テキスト」(ウイネット刊)の一部を抜粋・再編集したものです。
おすすめの資料
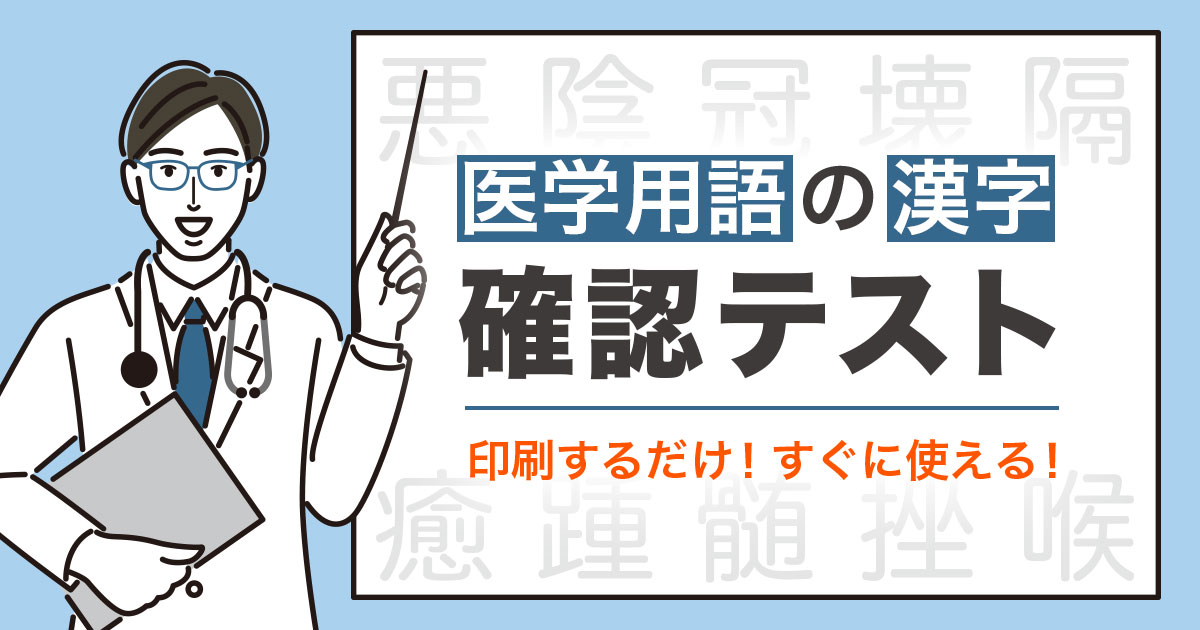
医療・福祉系学生のための漢字確認テスト
目次
事前確認項目

まずは、実習に臨む前の心構えについて解説します。学生が実習に入ってから困らないように、情報を整理したり、気を付ける点を指導しておくことが大切です。
実習先の医療機関から送付されている実習概要書を参考に、以下の点を整理、確認しておきます。
実習開始時間
遅くとも開始5分前には業務ができる状態になっているようにしましょう。
集合場所
院内の集合場所の確認はできているでしょうか。大きな病院の場合は院内で迷わないよう、案内図を確認しておきます。
自宅から実習先への通勤手段と通勤時間
公共交通機関を利用しての通勤が望ましいですが、車通勤となる場合は渋滞なども考慮する必要があります。実習中定期券が必要な人は実習担当の先生に相談しましょう。
遅刻・欠席する場合の連絡先
電車の遅延や体調不良などで、やむを得ず遅刻・欠席する場合の連絡先(実習先・学校)を確認しておきます。とくに感染症などの場合は、無理せず症状を伝えて指示を仰ぎましょう。
服装
実習先指定の制服、シューズ、髪型などを確認しましょう。
挨拶・返事
実習中は積極的に挨拶をしましょう。
- 患者、ご家族、職員、来客など区別なく挨拶する。
- 朝の「おはようございます」や業務終了時の「ありがとうございました。お先に失礼いたします」、入・退室時の挨拶は丁寧に行う。
- 業務の指示を受けたら、「かしこまりました」「承知いたしました」など、必ず言葉で指示者に対して意思表示をする。分からない場合は曖昧にせず、「もう一度お願いいたします」「○○について、もう一度よろしいでしょうか」など、確認する。
- 何かを教えていただいたときは、「ありがとうございました」と感謝の気持ちを表現する。
報告・連絡・相談
社会人に共通した重要なコミュニケーションに「ホウ・レン・ソウ」があります。「報告・連絡・相談」のことで、業務を行う上での基本事項です。
実習中は、主として「報告」が多くなると思いますが、職員の指示の下で業務を行う中で、「ホウ・レン・ソウ」を実行してください。
注意点
「ホウ・レン・ソウ」を実行する上での注意点を挙げます。
- 「ホウ・レン・ソウ」を受ける相手へのタイミングが適切かどうかを意識する。
- 「ホウ・レン・ソウ」を受ける相手が判断しやすいように、事実と自分の意見を区別して説明する。
タイミング
以下のような場合にはただちに「ホウ・レン・ソウ」を実行します。状況が悪化する前に対策を打つことが重要です。
- 指示された内容が自分の中で曖昧なとき
- 指示された方法で行っているが、問題が起きそうなとき
- 指示された時間内に終わらない可能性があるとき
- 指示された仕事が終わったとき
- ミスを犯してしまったとき
学生にはお客様として実習に参加するのではなく、職場の一員としての自覚をもつことや、ひとつでも多くのことを学ぶ姿勢を意識するよう指導しましょう。
守秘義務
実習中は、患者の個人情報や診療録内の病歴について、取り扱う業務に携わります。しかし、実習中に知り得た情報は、医療機関の内外を問わず漏えい(もらすこと)してはいけません。
医療従事者には、患者が安心して治療を受けることができるように、業務上知り得た情報を守り保護する義務(守秘義務)があるからです。実習期間中の行き帰りの交通機関内での会話には十分注意し 、Xや FacebookなどのSNSへの投稿は、絶対にしないよう気を付けましょう 。
医療機関での接遇マナー
医療機関では、患者に対してより良い医療を提供するという目的があります。「より良い医療の提供」(=医療産業サービスの提供 )の中には、医療技術や医療機器、設備だけでなく、医療提供者の接遇マナーや身だしなみ、言葉遣いなども含まれます。
サービス業の側面もある医療機関では、患者に対する「ホスピタリティ」(心をこめたおもてなしの考え方)が重視されています。
ホスピスを語源とするホスピタリティという考え方は、元々はホテル業界などを中心に発展してきました。医療機関におけるサービス受益者(サービスを受ける人)は、傷病で不安や苦痛を抱えている患者や家族ということになります。一方的にこちらの考えを伝えるのではなく、共に関係を築いていく「ケア・コミュニケーション」が必要となります。
参考書籍:ケア・コミュニケーション(ウイネット刊)
患者一人ひとりのニーズに対応し、安心して治療を受けていただくために、相手に気を配り、相手への思いやりを言葉や態度によって表現するスキルも重要です。
見だしなみと第一印象

医療機関の受付は、患者にとって来院して初めに出会う医療機関のスタッフとなります。最初に接したスタッフの印象 = 医療機関の印象となることも多くあります。丁寧で質の高い受付スタッフがいることは、医療機関の魅力につながるのです。
A.メラビアン(アメリカ)によると、人の第一印象は、見た目や表情など視覚的情報が55%、声の大きさやトーンなど聴覚的情報が38%、話した内容など言語的情報が7%という結果が出ています。
この結果をそのままコミュニケーションに適用はできませんが、言葉でやり取りをする前段階では、外見情報が伝わりやすいということです。実習先の職員にも患者にもよい第一印象をもってもらうため、身だしなみを整えて実習に臨みましょう。
言葉と言葉以外によるコミュニケーション
学生さんは普段、友人や先生、 家族とどのような方法でコミュニケーションを取っているでしょうか。コミュニケーション手段には大きく分けて、言葉によるもの(言語的メッセージ)と言葉以外によるもの(非言語的メッセージ)があります。
日頃、相手とのコミュニケーションで特に意識するのは、言葉を介するものかもしれませんが、実際にはコミュニケーションの 6~7割は、表情やアイコンタクトなど言葉以外のもので構成されるといわれています。話すときの表情や目線なども意識することが大切です 。
| 言語的メッセージ | 非言語的メッセージ |
|---|---|
| ・話し言葉、書かれた文字、点字文字 など | ・表情、視線、しぐさ、態度、見だしなみ ・服装、匂い、アイコンタクト ・声の大きさ、トーン、速さ、高さ、アクセント |
非言語的メッセージ
言葉以外の表情、視線、お辞儀などから伝わるメッセージについて解説します。コミュニケーションの半分以上は非言語で構成されるので、よいコミュニケーションをとるためには非常に重要な部分です。
表情
口角が上がり、目尻が下がり気味で、優しいまなざしは穏やかで優しい印象を与えます。一方、口角が下がり、目尻が上がり気味の表情は不快そうな印象を与えます。
視線
視線を相手に向けることは相手に関心があるという意思を表します。相手と視線を合わせることをアイコンタクトといい、微笑や頷き、挨拶へとコミュニケーションが発展していきます。
お辞儀
お辞儀は角度によって以下のような違いがありますが、いずれにも共通するのは、相手への敬意や感謝の気持ちを伝えるものであることです。心をこめたお辞儀を心がけましょう。
- 目礼(軽く目を伏せる)
→相手が他の人と話し中であるときなど 、邪魔にならないようにする挨拶 - 会釈(約15°上体を傾ける)
→人とすれ違うとき、案内するときなどの軽い挨拶 - 敬礼(約30°上体を傾ける)
→名乗るとき、お見送りするときなどの一般的な挨拶 - 最敬礼(約45°上体を傾ける)
→深い感謝やお詫びの気持ちを表すなどの丁寧な挨拶
言語的メッセージ
言葉はそのままメッセージとして伝わりますので、丁寧な言葉遣いや声がけを意識するようにしましょう。
声がけの基本
- ゆっくり、はっきりと相手に聞こえるように話す
- 相手の顔を見て、話に対する相手の表情の変化を確認しながら話を進める
- 笑顔、優しい表情で丁寧に名前を呼ぶ
- できるだけ相手の動作を急がせないように気を付ける
場面に応じた応対
具体的な声がけの例をご紹介します。いずれもよく使うフレーズなので、すっと口から出てくるように、実際に声に出して練習しておくとよいでしょう。
【受付時】
「本日はいかがなさいましたか。」
「保険証はお持ちですか。」
「こちらの用紙に、お名前とご住所、お電話番号をお書きいただけますか。」
「順番になりましたらお呼びいたしますので、お掛けになってお待ちいただけますか。」
【ご案内時】
「お待たせいたしました。こちらへどうぞ。」
「大変お待たせいたしまして申し訳ありませんでした。」
「本日の診察は終了となりますので、会計窓口の前でお待ちください。」
【会計時】
「お会計をさせていただきます。本日は〇〇円でございます。」
「〇〇円お預かりいたします。」
「〇〇円のお返しでございます。」
【帰宅時】
「お大事にどうぞ。」
「お気をつけてお帰りください。」
まとめ
医療事務実習では、患者との関わりの前に職員との関わりがあります。医療事務スタッフとしての技術だけでなく、社会人としての基本を学ぶ場でもありますので、先輩職員から挨拶・言葉遣いなども学ぶよい機会となるでしょう。
医療事務は、医療機関の顔となる職業です。穏やかで優しく、丁寧な受付スタッフがいる医療機関は、それだけで魅力的なものです。学生が実習前に接遇の基本を学習し、患者の心に寄り添えるスタッフに近づけるよう、本記事を参考にしてみてください。
\ぜひ投票お願いします/
株式会社ウイネット
ウイナレッジを運営している出版社。
全国の専門学校、大学、職業訓練校、PCスクール等教育機関向けに教材を制作・販売しています。