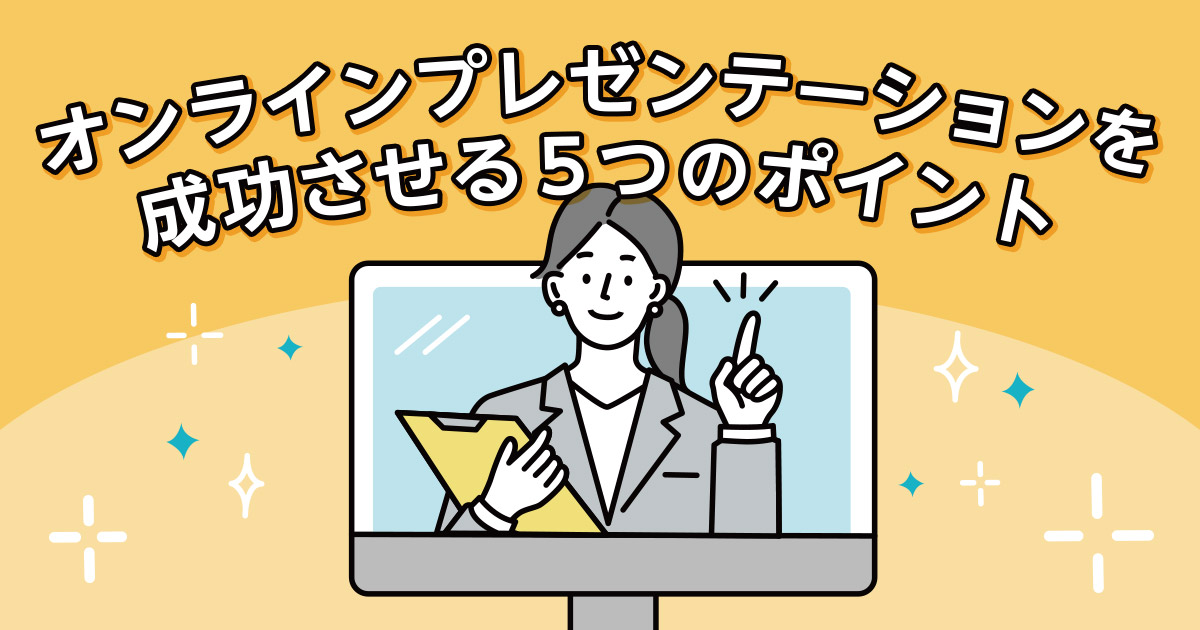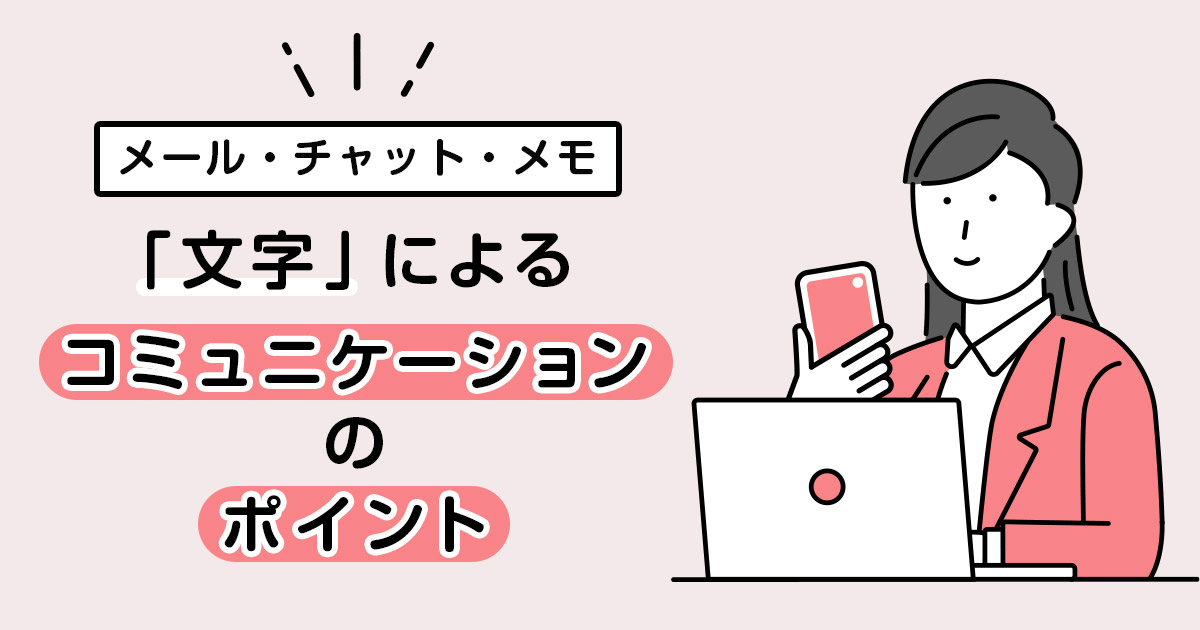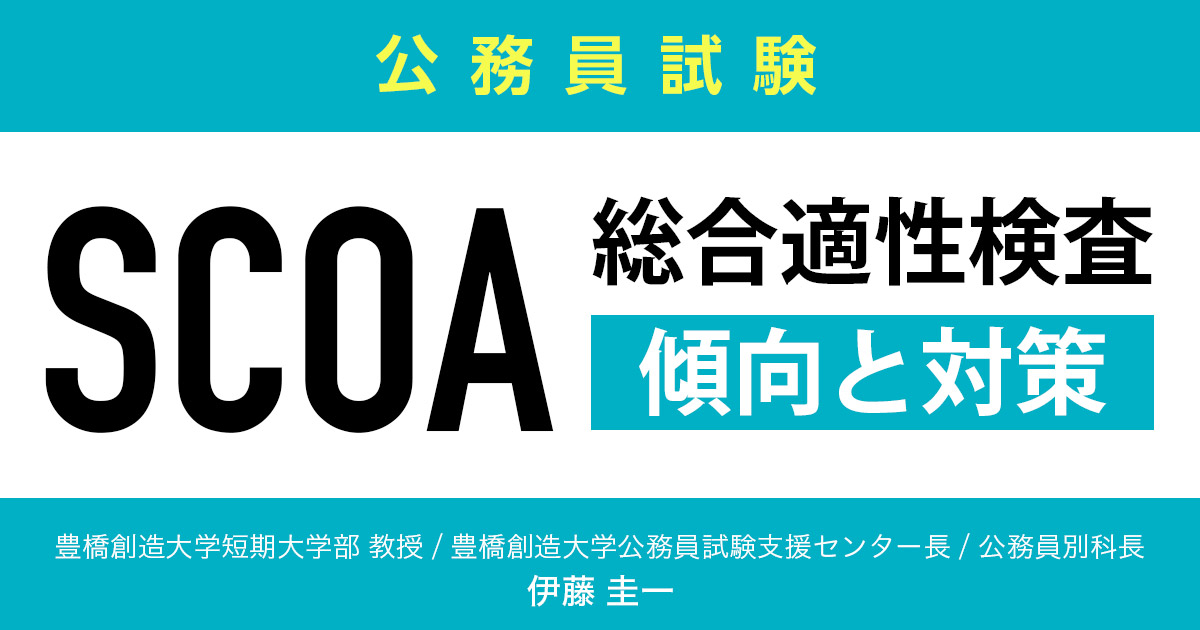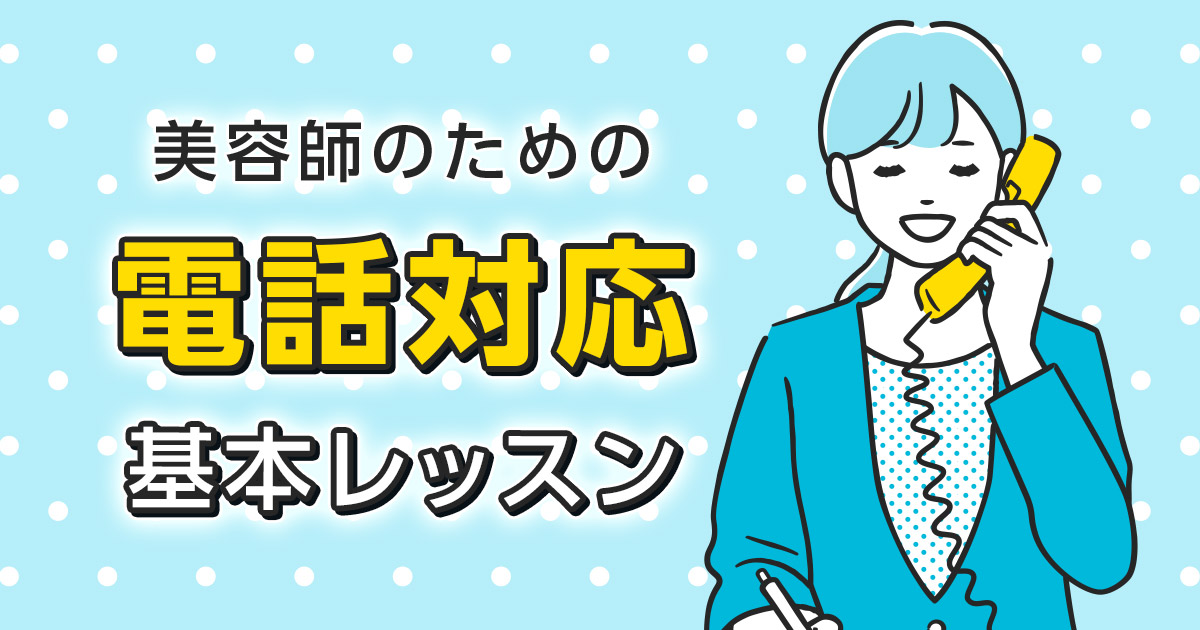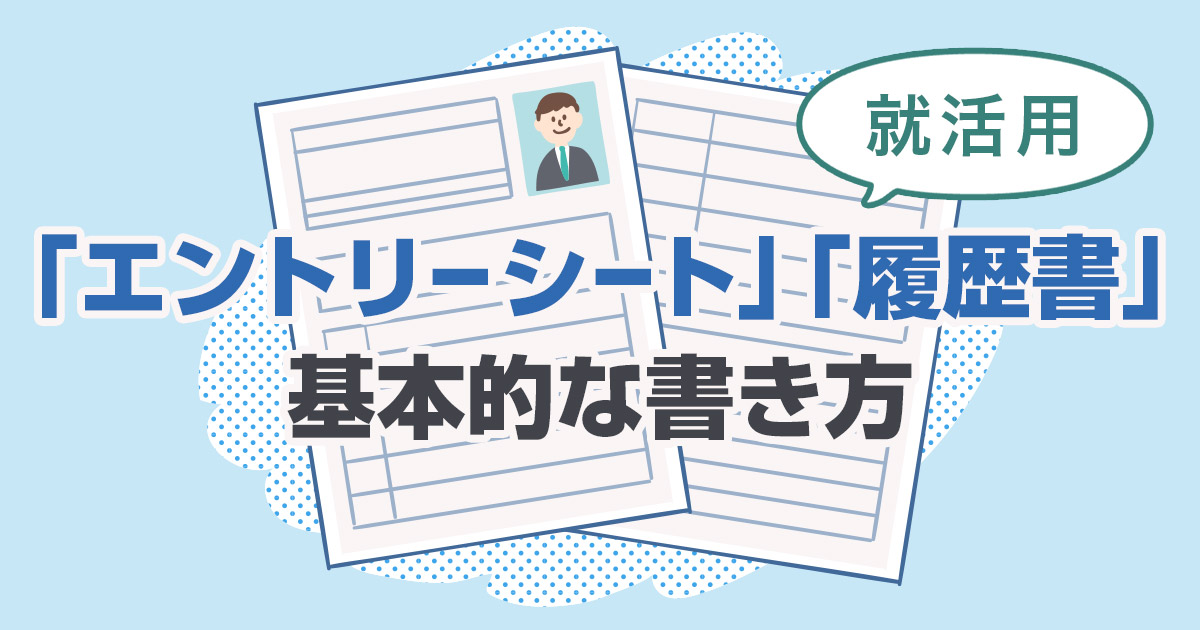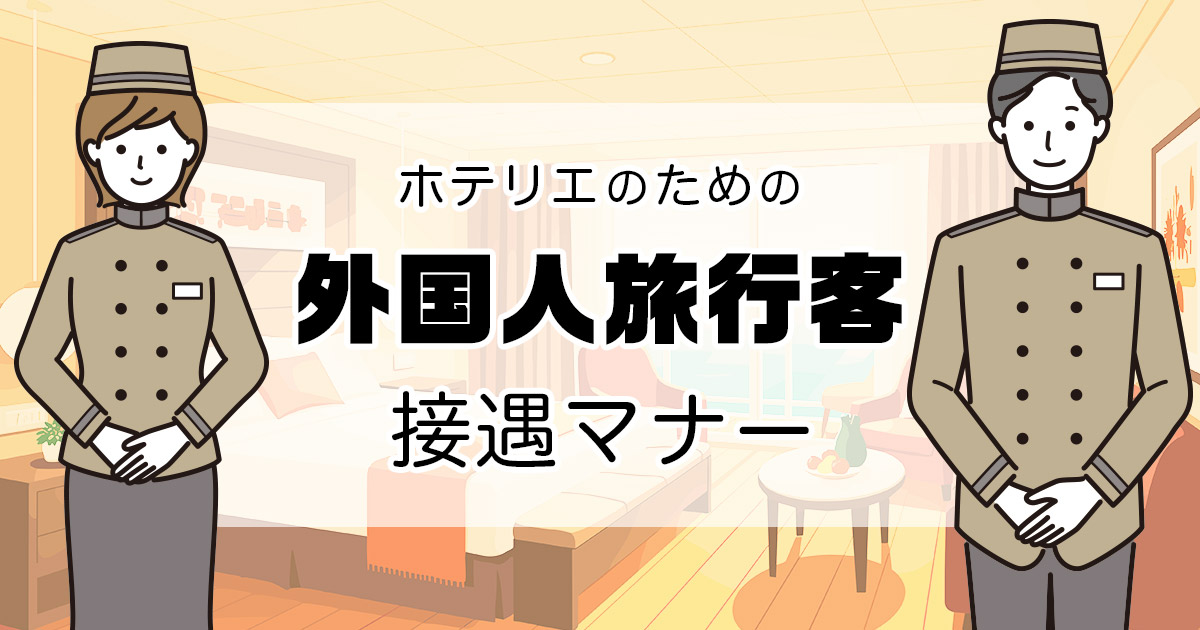連載知っておきたいインターンシップのこと
在学中の学生が企業内で就業体験を行う「インターンシップ」。インターンシップは、学生が自己の適正を把握したり仕事の内容を理解するための重要なイベントです。この連載ではそんなインターンシップについて様々な情報をお伝えします。
学生が将来のキャリアを考える際に役立つ、インターンシップ制度。参加者は年々増えているようですが、実施する企業はどのような目的を持っているのでしょうか。また学生も「周りが参加しているから何となく」ではなく、目的意識を持って臨むことが大切です。
本記事では、インターンシップ制度の基本に加え、企業・学生別の目的を解説します。学生が適切なインターンシップを選べるようサポートするためにも、ポイントを押さえておきましょう。
おすすめの資料

専門学生のためのインターンシップガイド
目次
インターンシップとはどのような制度?

まずはインターンシップの基本を理解しましょう。ポイントは、次の3つです。
- 興味のある職業を体験できる制度
- 無給インターンシップと有給インターンシップの違い
- インターンシップとアルバイトの違い
それぞれ解説します。
興味のある職業を体験できる制度
インターンシップは、学生が興味のある職業を実際に体験できる制度です。「将来、どのような仕事がしたいのか?」「適性は何だろう?」など、漠然とした就職活動の悩みを抱える学生にとって、インターンシップは貴重な機会といえるでしょう。
たとえばマーケティングに興味を持っている学生は、実際にマーケティングに携わる部署で企画立案やデータ分析を体験することで、仕事内容の面白さや難しさを肌で感じられます。興味のある分野に対して、深い理解を得られるのが大きなメリットです。
無給インターンシップと有給インターンシップの違い
インターンシップには、無給と有給があります。無給インターンシップは参加しても報酬が支払われず、内容はグループワークや簡単な仕事体験など企業の利益に直接繋がらないプログラムが基本です。実務に携わる機会は少なく、1日〜2週間程度で終了することが多い傾向にあります。
一方、有給インターンシップは参加時間や成果に応じて報酬が支払われます。社員と同様の業務やプロジェクトに参加できるのが特徴です。1カ月以上の長期になるケースが多く、就職後に役立つビジネスマナーや仕事に必要なスキルなど、実践的なことが学べます。
どちらのインターンシップを選ぶかは、学生が求める目的や経験に応じて判断するとよいでしょう。たとえば進む業界を迷っているなら、広く浅く体験できるよう、複数の企業の無給インターンシップに参加するのがおすすめ。すでに挑戦したい仕事が明確に決まっているなら、リアルな現場を体験できる有給インターンシップで経験を積むのがよいでしょう。
インターンシップとアルバイトの違い
インターンシップとアルバイトは、どちらも企業で働く点では共通していますが、目的や内容に違いがあります。アルバイトは主に収入を得ることが目的であり、業務もマニュアルに従って進めるのが基本です。
一方、インターンシップは将来のキャリア形成を目的としています。企業の利益に直接関わる業務を任せてもらえるチャンスもあり、自ら考えて行動しなければならない場面も多いでしょう。頑張り次第で大きく成長できる貴重な機会といえます。有意義な時間を過ごすためには、明確な目的を持って参加することが大切です。
インターンシップの種類4つ
インターンシップは、大きく分けて4種類あります。
- オンラインインターンシップ
- オープン・カンパニー(1dayインターンシップ)
- 短期インターンシップ
- 長期インターンシップ
それぞれの特徴を解説します。
1.オンラインインターンシップ
ビデオ会議システムを活用して開催される形式が、オンラインインターンシップです。新型コロナウイルスの影響から急速に広まり、場所の制約を受けないため全国どこからでも参加できます。
たとえば、地方在住で都心の企業を探している学生にとって、宿泊費や交通費をかけず自宅から参加できるのは大きなメリットといえるでしょう。
2.オープン・カンパニー(1dayインターンシップ)
企業や業界に関する情報提供を目的として開催されるのがオープンカンパニーです。以前は「1dayインターンシップ」という名称でしたが、インターンシップのルールが改正され、説明会やワークショップは「オープン・カンパニー」に分類されることとなりました。
インターンシップと同様に学生のキャリア形成を目的としていますが、厳密に言えばインターンシップに該当しません。基本的には1日のみの開催で参加のハードルが低いため、より多くの情報を集めたいと考えている学生に役立つでしょう。
3.短期インターンシップ
2日〜2週間程度の期間で開催されるのが短期インターンシップです。企業説明やグループワークが中心ですが、実際の仕事に近い体験をさせてもらえるケースもあります。短期間のため、複数の業界や企業を比較できるのがメリット。「仕事・業界への理解を深めたい」「複数の進路で迷っている」という学生に最適です。
4.長期インターンシップ
明確な定義づけはありませんが、1カ月以上の長期にわたって行われるものが長期インターンシップと呼ばれています。有給の場合が多く、実践的なスキルを身に付けられるのがメリットです。進みたい道が決まっていて「自分の適性を見極めたい」「スキルを磨きたい」と考えている学生に最適です。
企業がインターンシップを実施する3つの目的

なぜ企業はインターンシップを実施するのでしょうか。主な目的は、次の3つです。
- 自社を理解してもらうため
- 採用したい学生像を見極めるため
- 入社後のミスマッチを防ぐため
それぞれ解説します。
自社を理解してもらうため
多くの企業は納得したうえで自社を志望してほしいと考えていますが、企業説明会だけでは限られた情報しか伝えられません。インターンシップを実施すれば、企業文化や業務内容、現場で働く社員の雰囲気をリアルに知ってもらえます。また、企業の認知度向上やPRにも繋がるでしょう。
採用したい学生像を見極めるため
書類選考や面接だけで、実際の働きぶりや意欲まで把握するのは困難です。インターンシップでは学生の学歴やスキルだけでなく、コミュニケーション能力や問題解決能力、協調性など実務に直結する能力を観察できます。これらは適切な人材を見極めるための大切な情報です。今まで以上に採用したい学生像が明確になるでしょう。
入社後のミスマッチを防ぐため
なかには入社後に「思っていた仕事と違う」「雰囲気が合わなかった」と感じ、早期に離職の道を選ぶ学生もいます。これは思い描いていたイメージと、現実のギャップが大きいと起こりやすい現象です。学生にとってもつらいことですが、企業にとっても大きな損失となるでしょう。
インターンシップは、業務や職場の雰囲気に関して学生の理解を深められるため、ミスマッチを防ぐ点で有効です。早期離職のリスクを減らし、人材の長期的な育成に繋げられます。
学生がインターンシップに参加する3つの目的
学生がインターンシップに参加する主な目的は、次の3つです。明確な目的意識を持って臨むことで、より有意義な時間を過ごせるでしょう。
- 企業理解を深めるため
- 自己理解を深めるため
- 就活を有利に進めるため
それぞれ解説します。
企業理解を深めるため
就職活動を進めるにあたり、企業のホームページや説明会を通じて情報収集するのが一般的です。しかし、それだけでは企業の本質や働き方を充分に理解するのは難しいでしょう。「説明会では魅力的に感じたけど、実際のイメージと異なっていたらどうしよう」と不安を抱える学生も少なくありません。
インターンシップに参加すれば、業務の流れや職場の雰囲気をリアルに体験できます。自分の価値観や希望と一致するか判断しやすくなるため、より適切な進路を選べるでしょう。
自己理解を深めるため
企業への理解を深めるだけでなく、自分の適性や興味関心を知る場としても有効です。実務を経て自分の強みや弱みを客観的に把握できれば、自己理解を深められるでしょう。たとえば、食べることが好きという理由から食品メーカーのインターンシップに参加した結果、「自分は食を通じて人を喜ばせたい」という価値観を発見できるかもしれません。
また現役社員からのフィードバックや、ほかのインターンシップ生との交流を通して、さまざまな視点から気づきを得ることもできます。
就活を有利に進めるため
インターンシップで得た経験は履歴書や面接でアピールできるため、就職活動において大きな強みとなります。経験から得られた学びや成果も伝えることで、より企業に好印象を与えられる可能性が高くなるでしょう。
さらに25年卒採用から、条件を満たせばインターンシップに参加した学生の情報を採用活動に利用してよいことが認められました。これまで政府は企業に禁止を要請していましたが、正式に採用直結型のインターンシップが「公認」となったのです。
今まで以上にインターンシップでの実績が評価され、内定に繋がるケースも増えるでしょう。
学生にインターンシップへの参加を促す方法
インターンシップに対して「参加する必要性を感じられない」と考える学生もいるでしょう。しかし、参加することは学生にとって多くのメリットがあります。ここでは、参加してもらうための方法を2つ紹介します。
参加することで得られるメリットを伝える
たとえば「入社前に必要なスキルを学べる」「得た知識やスキルは自己PRや履歴書に書ける」「ミスマッチによる早期離職のリスクを減らせる」など、学生にとってのメリットを具体的に提示することで、興味関心を高められます。
実際に参加した先輩のインタビューを紹介する
インターンシップに参加した先輩の声を紹介するのも有効な手段です。リアルな体験談を伝えることで「自分も同じように成功を目指したい」という思いを引き出しやすくなります。教科書的な説明よりも心に響き、共感を得やすいでしょう。
インタビューは具体的な業務内容や学んだこと、どのように就職活動に役立ったかが伝わる内容にすることが大切です。事前に学生からインターンシップに対する不安や疑問を募り、先輩に答えてもらうのもよいでしょう。実体験に基づくアドバイスによって不安が軽減し、参加へのハードルを下げられます。
まとめ
興味のある仕事を体験できるインターンシップは、学生にとってはもちろん企業にとっても多くのメリットがあります。25年卒から採用直結型のインターンシップが公認となり、ますます参加への重要性が高まったといえるでしょう。学生が目的意識を明確にし、有意義な時間を過ごせるよう先生側もサポートしていくことが大切です。
おすすめの資料

専門学生のためのインターンシップガイド
\ぜひ投票お願いします/
株式会社ウイネット
ウイナレッジを運営している出版社。
全国の専門学校、大学、職業訓練校、PCスクール等教育機関向けに教材を制作・販売しています。