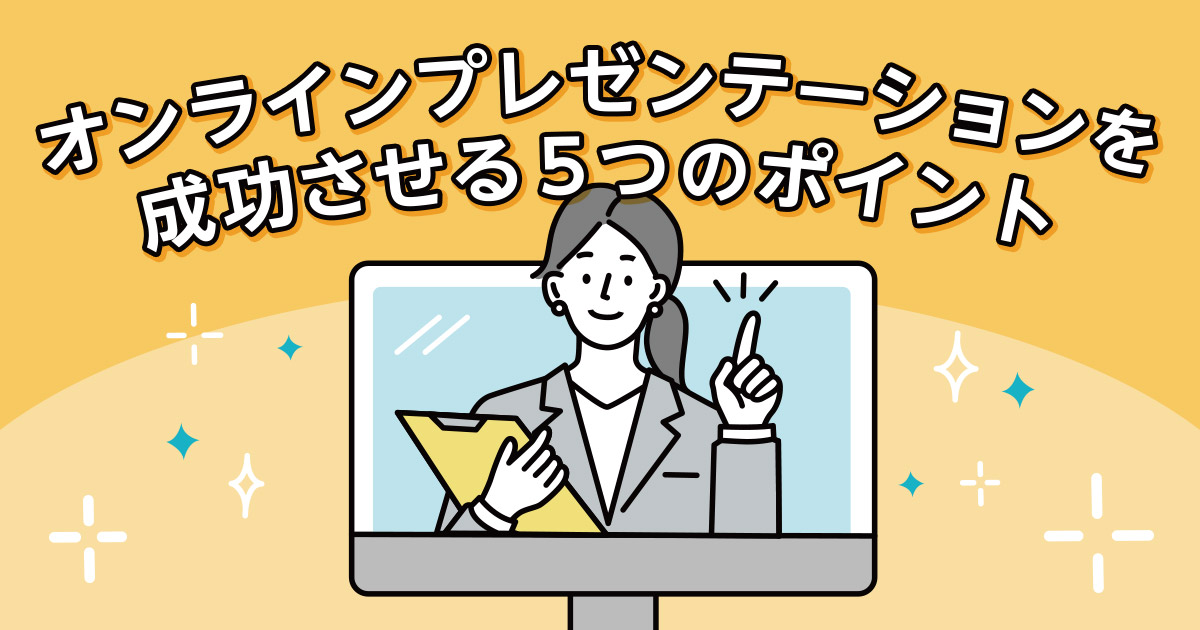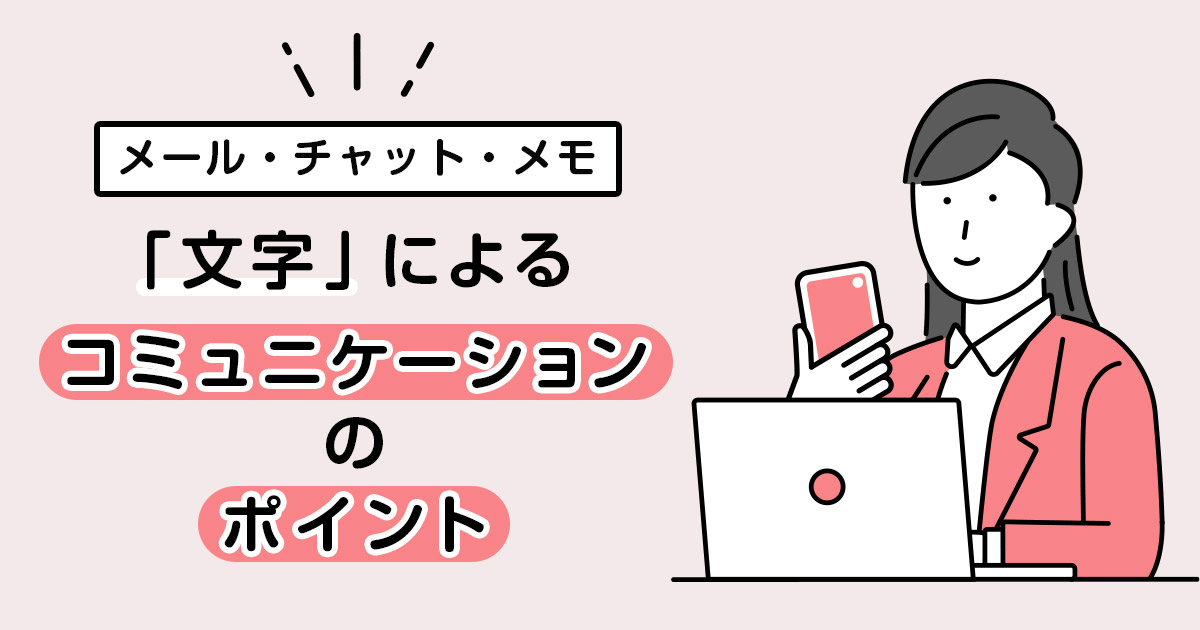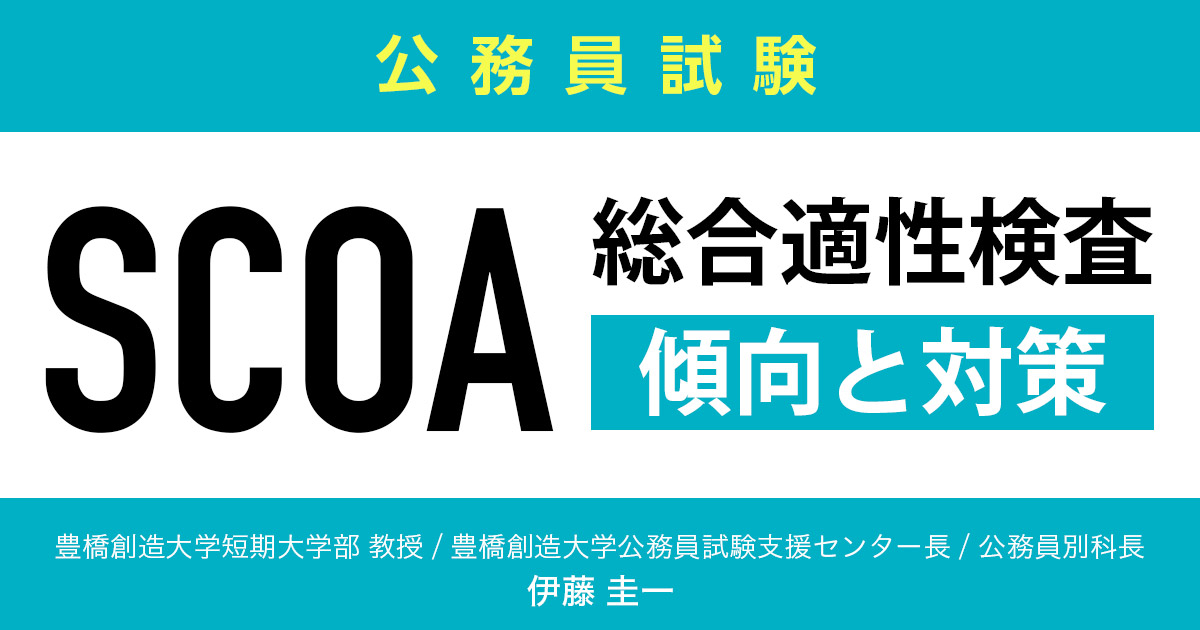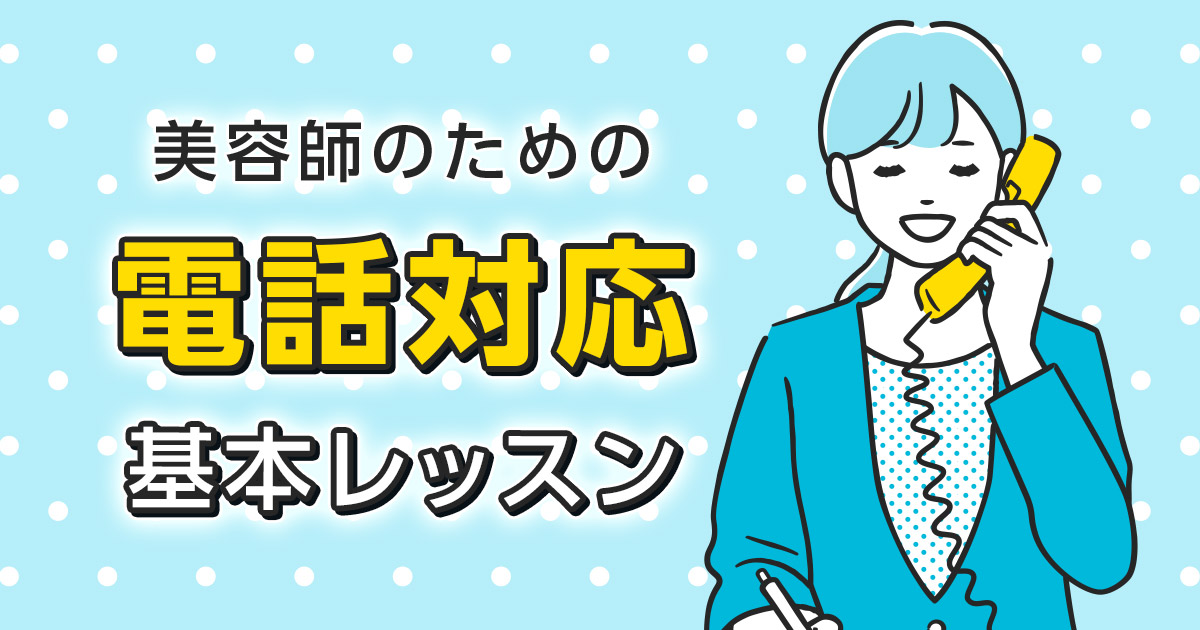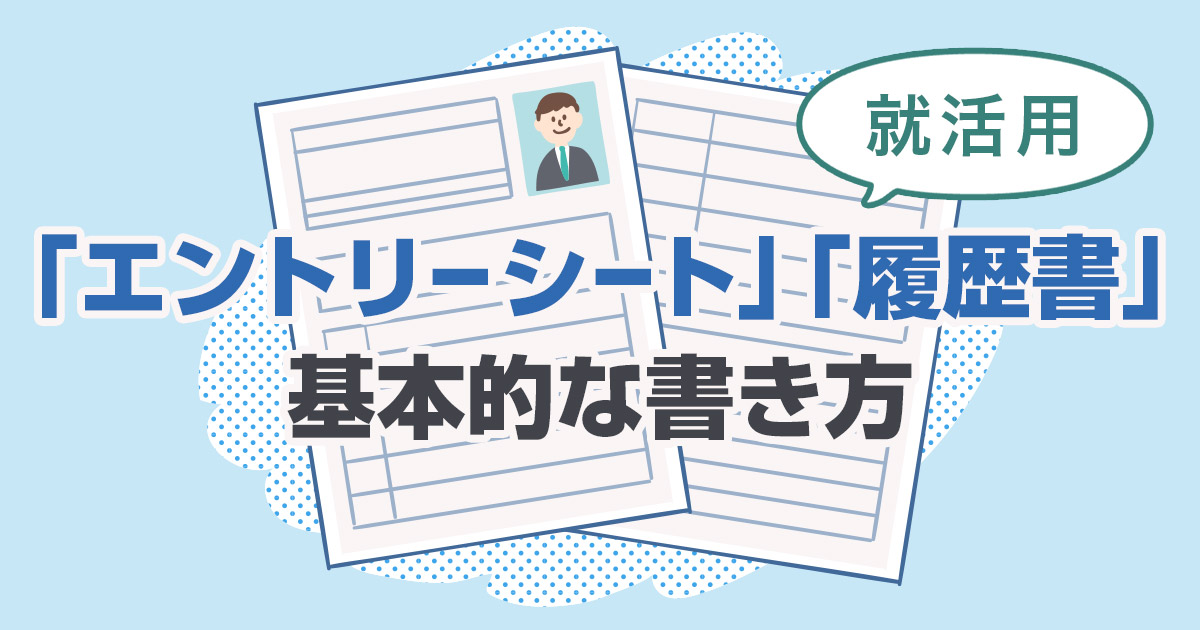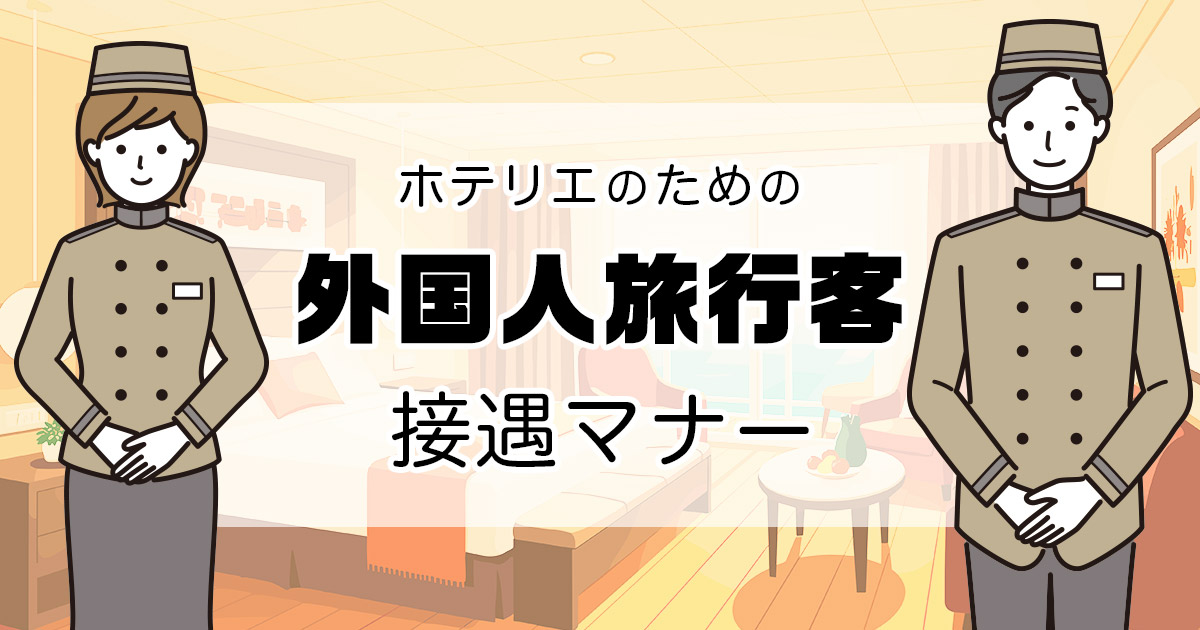連載知っておきたいインターンシップのこと
在学中の学生が企業内で就業体験を行う「インターンシップ」。インターンシップは、学生が自己の適正を把握したり仕事の内容を理解するための重要なイベントです。この連載ではそんなインターンシップについて様々な情報をお伝えします。
近年9割近くの学生が参加するといわれているインターンシップ。業界の研究や、自分に適性があるか見極めるために有効で、就職活動の一環として欠かせないものとなっています。しかし、2025年卒からインターンシップの「あり方」が見直され、1dayインターンシップの取り扱いが変更となったのをご存じですか?
本記事では、変更後の1dayインターンシップの内容や参加時の注意点を詳しく解説します。学生へ的確なアドバイスをするためにも、変更後の内容を把握しておきましょう。
おすすめの資料

専門学生のためのインターンシップガイド
目次
1dayインターンシップは「オープン・カンパニー」に名称が変更
これまでのインターンシップは主に実施期間の長さで区別され、なかでも半日〜1日の期間で実施されるものは1dayインターンシップと呼ばれていました。しかし「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」が改正され、2025年卒以降は以下のように区分が変更されます。
| 名称 | 期間 | 就業体験 | |
|---|---|---|---|
| タイプ1 | オープン・カンパニー | 超短期(単日) | なし |
| タイプ2 | キャリア教育 | 授業・プログラムによって異なる | 任意 |
| タイプ3 | 汎用的能力・専門型インターンシップ | 5日〜2週間以上 | 必須 |
| タイプ4 | 高度専門型インターンシップ | 2カ月以上 | 必須 |
従来の1dayインターンシップは就業体験がなく、企業説明のみで終わるプログラムも多いことからインターンシップには分類されません。超短期で実施されるオープン・カンパニーに該当するといえるでしょう。
今後インターンシップに該当するのは、タイプ3の汎用的能力・専門型インターンシップと、タイプ4の高度専門型インターンシップのみです。またタイプ3とタイプ4に該当する場合、企業側が取得した学生情報は採用活動の開始後に限り活用できることとなりました。つまりインターンシップの参加が、選考フローの一部免除や内定に繋がる可能性があるということです。
長期インターンシップとの違い
オープン・カンパニーは、業界や企業に関する情報提供やPRを目的としており、就業体験もないため、通常は半日〜1日の短期間で終了となります。一方、長期インターンシップに分類される取り組みでは就業体験が必須です。業界に関する知識を深く学び、スキルを身につけられる貴重な体験となりますが、短くて5日ほど、長ければ2カ月以上と長期間にわたって参加する必要があります。
オープン・カンパニーの主な内容4つ
オープン・カンパニーの開催内容は、基本的に1dayインターンシップと変わりません。企業によっては、複数のプログラムを組み合わせて実施されるケースもあります。
- 企業説明
- ワークショップ
- 職場見学
- 座談会
それぞれ解説します。
1.企業説明
企業説明は、オープン・カンパニーの基本となるプログラムです。具体的には事業や業務内容、働き方などについて学生に説明し、業界や自社への理解を深めてもらうことを目的としています。
2.ワークショップ
ワークショップは、学生が主体的に参加できる体験型プログラムです。企業の業務内容に関連したテーマで、グループワークやディスカッションを実施することが多く、問題解決のプロセスを疑似体験できます。
業界への理解がより深まるとともに、自分の適性を見極められる機会となるでしょう。ほかの参加者との交流を通じ、コミュニケーション能力やチームワークの重要性も実感できます。
3.職場見学
職場見学は、実際に社員が働いているフロアや設備を見て回ることで、社内のリアルな雰囲気を肌で感じられるプログラムです。
たとえば、IT企業のオープン・カンパニーで職場見学した場合、最新のコンピューター設備が整ったオフィスや、休憩で活用できるラウンジスペースを見学できるかもしれません。「ここで働いたら、このような環境で仕事に取り組めるんだ」と、具体的なイメージを持てるでしょう。
4.座談会
座談会は学生が社員と直接会話しながら、業務内容や社内の雰囲気を深掘りできる機会です。基本的には少人数のグループになって進めるケースが多いため、気になるポイントを率直に質問できるのがメリット。
企業のホームページやパンフレットには載っていない情報は「この企業で働きたいか」を見定めるための重要な判断材料となるでしょう。
企業がオープン・カンパニーを実施する3つの目的

企業がオープン・カンパニーを実施する主な目的は、以下の3つが考えられます。
- 学生と接点を持つため
- 長期インターンシップの参加へ繋げるため
- 自社社員の育成・モチベーションアップのため
それぞれ見ていきましょう。
学生と接点を持つため
オープン・カンパニーの実施によって、企業は自社をアピールしつつ学生との接点を持てます。たとえば業界では有名でも、学生にはあまり知られていない企業もあるでしょう。そのような企業にとって、オープン・カンパニーは自社の魅力を直接学生に伝えられる良い機会となるのです。学生のリアルな声を聞けるため、今後の採用戦略を考えるうえでも役立つでしょう。
長期インターンシップの参加へ繋げるため
長期インターンシップは業界を深く知れる機会となりますが、進路に悩む学生にとっては参加のハードルが高いことも。そこで、まずはオープン・カンパニーで自社への理解を深めてもらい、長期インターンシップへの参加に繋げたいと考えている企業もあります。
オープン・カンパニーで企業の雰囲気を気に入った学生が、次のステップとして長期インターンシップへの参加を検討するケースも少なくありません。オープン・カンパニーは、長期インターンシップへの参加を促す役割も担っているのです。
自社社員の育成・モチベーションアップのため
学生を受け入れる場を用意することは、企業にとってもプラスに働きます。たとえば学生に自社の魅力を伝えるためには、社員自身が事業内容や強み、働く環境などを深く理解していなければなりません。
オープン・カンパニーの準備を通じて、社員は自社について改めて学び直し、理解を深められます。また学生と接することで仕事の意義や社会的な役割を再認識でき、モチベーションアップにも繋がるでしょう。
学生がオープン・カンパニーに参加する3つのメリット
就職活動の一環として参加を検討している学生は多いですが、主なメリットは以下の3つです。
- 長期インターンシップに比べて参加しやすい
- 企業そのものや働く社員の雰囲気を確認できる
- ほかの就活生と交流する機会が生まれる
それぞれ解説します。
長期インターンシップに比べて参加しやすい
長期インターンシップが数週間から数カ月の期間を要するのに対し、オープン・カンパニーは半日〜1日で完結します。「2つの業界で迷っている」「いろいろな企業を見てみたい」と考える学生に最適です。忙しい時期に視野を広げつつ、効率良く企業リサーチできる点は学生にとってメリットといえるでしょう。
企業そのものや働く社員の雰囲気を確認できる
企業の社風や文化が自分に合っているかどうかを見極めることは、入社後のミスマッチを防ぐうえで大切なポイントです。オープン・カンパニーでは、インターネットやパンフレットだけでは得られないリアルな情報を得られるため、その企業で働くイメージを具体的に掴めるでしょう。
ほかの就活生と交流する機会が生まれる
学生にとって就職活動は不安なもの。オープン・カンパニーではグループワークや座談会などを通じ、ほかの就活生と交流する機会が生まれます。互いに情報交換や悩みを共有することで、就職活動のモチベーションを高められるでしょう。
また、ほかの参加者を観察することで「もっと積極的に行動しよう」「あの人の姿勢と言葉遣いは素敵だな」と刺激を受けることもあります。
学生がオープン・カンパニーに参加する際の注意点3つ
多くのメリットがあるオープン・カンパニーですが、3つの注意点が考えられます。
- スキルの習得は難しい
- 就活のアピール材料にはなりにくい
- 明確な目的を持たないと無意味になる恐れも
それぞれ解説します。
スキルの習得は難しい
気軽に参加しやすいオープン・カンパニーですが、就業体験は組み込まれていないため、実務的なスキルの習得は難しいです。企業理解を深めるための場であり、スキルアップを目的とする場ではないことを理解しておきましょう。
入社前に専門的な知識やスキルを身につけたい場合は、長期インターンシップへの参加を検討する必要があります。
就活のアピール材料にはなりにくい
企業理解を深めるうえでは有益なオープン・カンパニーですが、実践的な経験は得られません。たとえば、エントリーシートや面接で「〇〇社のオープン・カンパニーに参加しました」と書いても、大きなアピールポイントにはなりにくいです。あくまでも、企業研究や業界研究の一環として捉えておきましょう。
明確な目的を持たないと無意味になる恐れも
「みんなが参加しているから」「就活に有利になりそうだから」など、主体的な目標を持たずに参加しても得られるものは少ないでしょう。たとえば、IT企業のオープン・カンパニーに参加したとします。単に「IT業界が良さそう」など漠然とした理由で参加すると「社内の雰囲気は良いようだ」「難しそうなプログラムが並んでいた」といった、表面的な感想だけで終わってしまうかもしれません。
一方で「この企業が開発しているサービスについて詳しく知りたい」「エンジニアとしてのキャリアパスを具体的に聞きたい」といった明確な目的を持って参加すれば、より深い理解や具体的な情報を得られます。
オープン・カンパニーに参加する流れ
オープン・カンパニーに参加する一連の流れは、以下のとおりです。
- オープン・カンパニーを実施している企業を見つける
- 参加する目的や目標を設定する
- ふさわしい服装で参加する
- 積極的に質問する
- 参加後はすぐにお礼メールを送る
それぞれのポイントを解説します。
1.オープン・カンパニーを実施している企業を見つける
オープン・カンパニーに関する情報は、企業のホームページや就職情報サイト、大学学校のキャリアセンターなどで収集できます。「興味のある業界はどこか」「どのような企業に可能性を感じるか」といった観点から、参加したい企業をリストアップしていきましょう。
2.参加する目的や目標を設定する
参加するオープン・カンパニーが決まったら、目的や目標を具体的に設定します。何を学びたいのか、どのような情報を得たいのかを明確にすることで参加時の焦点が定まり、より充実した時間を過ごせるでしょう。事前に企業研究して、質問したいポイントをまとめておくのもおすすめです。
3.ふさわしい服装で参加する
オープン・カンパニーに参加する際は、服装にも気を配りましょう。基本的にはスーツを着用するのが無難ですが、企業によっては私服を指定されるケースもあります。企業からの案内に沿って、ふさわしい服装で参加しましょう。服装に関しては、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
関連記事: インターンシップの服装は何を着るべき?スーツ・私服・自由のパターン別で解説
4.積極的に質問する
多くのオープン・カンパニーでは、質問の時間が設けられています。より深く理解するためにも、企業からの説明を聞くだけでなく積極的に質問しましょう。「御社の強みはどのような点ですか?」「入社後のキャリアパスについて教えてください」など、いくつか質問を用意しておくとスムーズです。
5.参加後はすぐにお礼メールを送る
オープン・カンパニーに参加したら、なるべく早めに担当者へお礼の連絡を入れると好印象に繋がります。基本的には、以下の要素を含めるとよいでしょう。
- 感謝の言葉
- 印象に残った点や学んだこと
- 今後に向けての意気込み
メールを送ることで感謝の気持ちを伝えるとともに、企業との繋がりを深められます。企業側からの返信で、さらなる情報を得られることもあるかもしれません。
メール文例
件名:
オープン・カンパニー参加の御礼(ウイナレッジ専門学校 山田太郎)
本文:
ウイナレ商事株式会社
田中様
ウイナレッジ専門学校の山田太郎です。
本日はオープン・カンパニーに参加させていただき、
ありがとうございました。
田中様のお話から、貴社の企業サービスへの強いこだわりを感じ、より一層興味が湧きました。
今後は長期インターンシップへも参加し、実践経験を積みたいと考えています。
貴重な機会をいただいたことへの感謝を一言お伝えしたいと思い 、メールを送らせていただきました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
—————————————————
山田 太郎
ウイナレッジ専門学校 IT科 2年
携帯番号:090-0000-0000
メール:taro.y@uinare.jp
—————————————————
まとめ
「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」の改正により、企業情報の提供やPRを目的とした取り組みはオープン・カンパニーに分類されるようになりました。基本的な開催内容は、1dayインターンシップと変わりありません。企業理解を深めるために役立つので、気になる企業や業界のオープン・カンパニーへ積極的に参加するとよいでしょう。学生がインターンシップについて悩んでいるときには、学校側でも寄り添いサポートしていくことが大切です。
おすすめの資料

専門学生のためのインターンシップガイド
\ぜひ投票お願いします/
佐藤 なおか
移住により新潟で活動するWebライター
趣味は飲み歩き(ビール好き)とドライブ