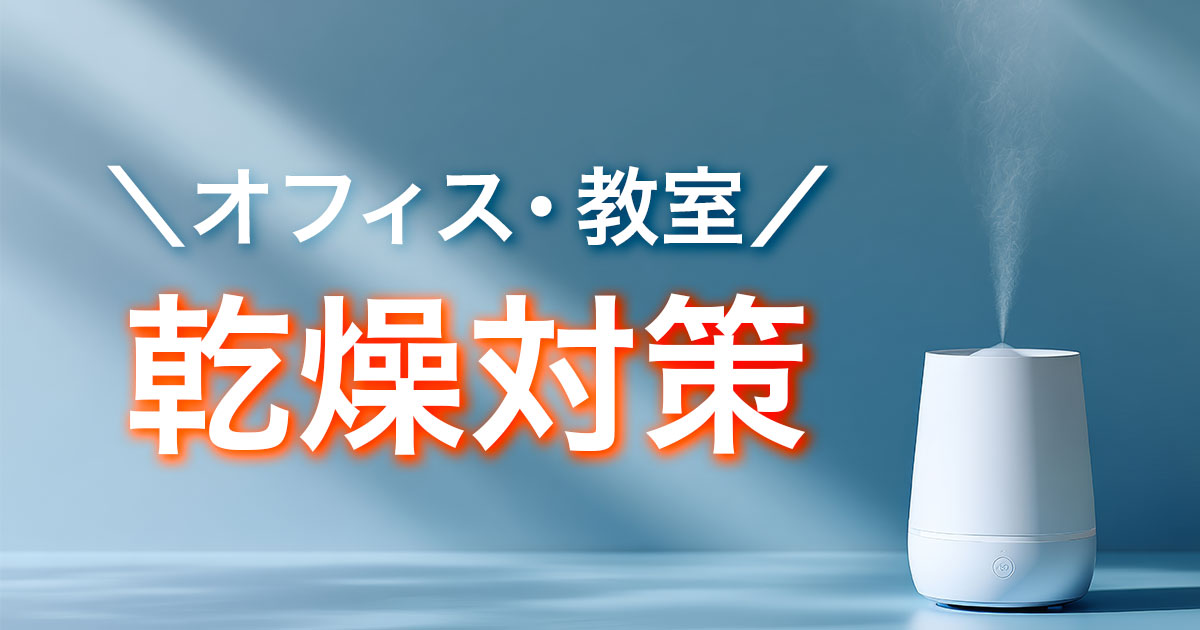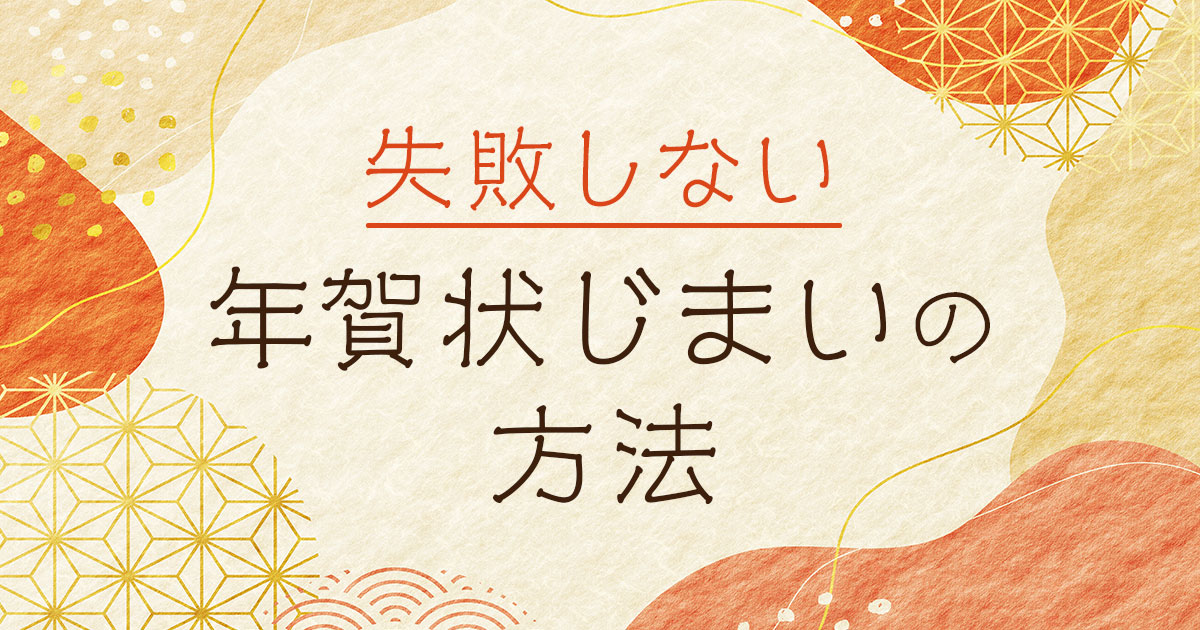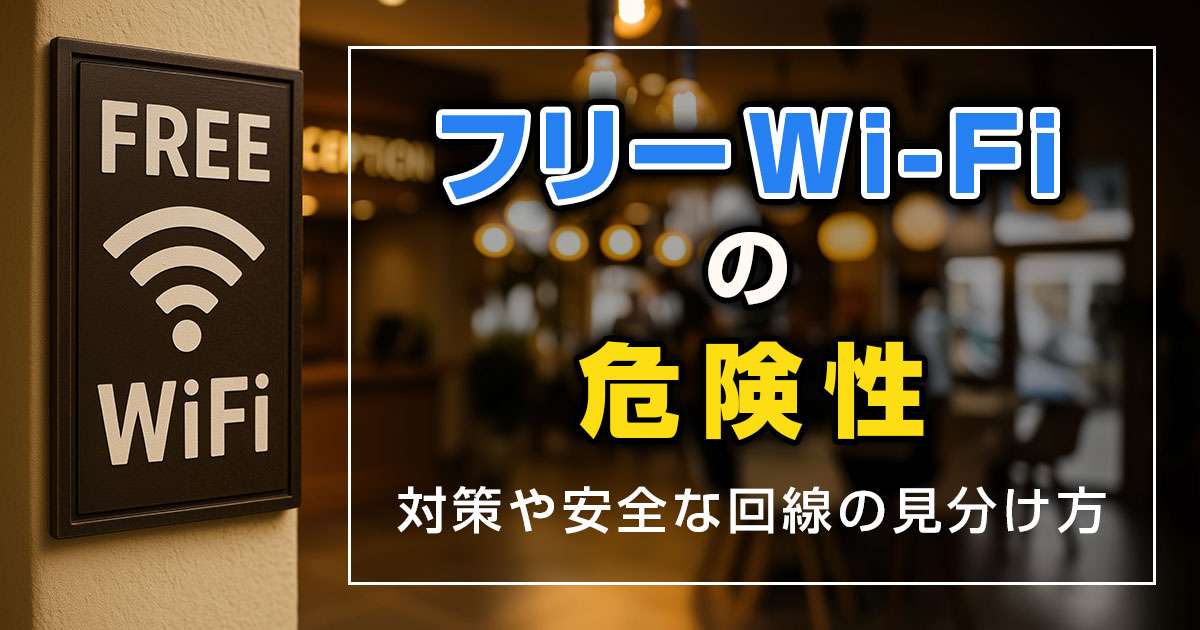多くの学校では、独自に校則を定めています。基本的には教育にあたり必要な内容が定められていますが、なかには「理不尽では?」と感じる内容や、思わずクスっとしてしまうものも。
そこで本記事では、思わずツッコミを入れたくなる校則を集めてみました。仕事中の息抜きにどうぞ。学生に「前通っていた学校に不思議な校則はあった?」と聞いてみるのも面白いかもしれませんね。
目次
学生を追い込むブラック校則とは?
教育に関係ない厳しすぎる内容は「ブラック校則」と呼ばれています。ときには学生を追い詰める原因にもなるため、近年では全国の学校で問題視されているようです。
とはいえ、厳しいかどうかの判断基準は学校によって異なりますよね。ブラック校則の明確な定義はありませんが、文部科学省が公開している生徒指導提要(改訂版)によると、校則の在り方は以下のとおりだと記載されています。
校則の在り方は、特に法令上は規定されていないものの、これまでの判例では、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から校長が定めるものとされています。
生徒指導提要(改訂版)
基本的に、上記から外れる内容はブラック校則といってよいかもしれません。
本当に必要?ブラック校則の事例5選

学校生活を円滑に運営するために必要なルールですが、あまりに厳しければ学生にストレスを与えるでしょう。ここでは、ブラック校則の事例を5つ紹介します。
- 授業中の水分補給禁止
- ツーブロックやポニーテール禁止
- 登下校でダウンや防寒具すべて禁止
- 自毛証明書の提出
- 男女での登下校禁止
それぞれの特徴と問題点を解説します。
1.授業中の水分補給禁止
熱中症対策が叫ばれる現代において、授業中の水分補給を禁止する校則は厳しすぎるといえます。定める理由としては「授業中に水を飲むと集中力が低下する」「机が濡れる」などが挙げられるようです。
しかし、適度な水分補給は集中力や健康維持に欠かせません。授業中の水分補給を禁止することは、学生の健康を害する可能性があります。
2.ツーブロックやポニーテール禁止
髪型を厳しく制限する理由は「見た目が派手」「清潔感を損なう」などが挙げられます。なかには「就職活動に不利だから」という理由で禁止する学校もあるようです。しかしツーブロックやポニーテールだからといって、企業からの印象が悪くなるとは限りません。個性を抑えすぎる校則は、学生が窮屈に感じるでしょう。
3.登下校でダウンや防寒具すべて禁止
冬場の寒い時期にもかかわらず防寒具を禁止するのも、思わず首をひねりたくなる校則の一つです。NHK鹿児島放送局の記者が調査したところ、定めた理由を明確に把握している学校がなかったという結果に。健康を害する恐れもあるため、見直す必要があるかもしれません。
4.自毛証明書の提出
染髪が禁止されている学校では、自毛証明書の提出を求めることがあります。理由は、髪色やクセ(天然パーマ)が生まれつきであることを証明するため。しかしプライバシーの侵害にもなりえる行為であり、学生に負担を与えるでしょう。
5.男女での登下校禁止
早すぎる男女交際を防止するため、男女での登下校を禁止する学校もあります。しかし、一緒に登下校=男女交際とは限りません。コミュニケーション力や社会性を育む妨げになる恐れも。学校側が必要以上に学生同士の交流を制限することは、ブラック校則に該当するといえます。
ブラック校則?全国にあると噂の変な校則8選

ブラックではないけれど、思わず笑ってしまうような珍しい校則もあります。ここでは、全国にあると噂の変わった校則を8つ紹介します。
- 登下校中、流氷に乗ってはいけない
- 飼っている馬や牛が出産するときは休んでもよい
- 交際相手は我が校の生徒でないといけない
- 恋人が出来たら報告する
- 服装違反者は半年間、教頭と交換日記する
- 学校に草履はいいが下駄で来てはいけない
- 弁当に寿司を持ってきてはいけない
- 廊下を歩くときに、靴の裏を見せてはいけない
それぞれ見ていきましょう。
1.登下校中、流氷に乗ってはいけない
北海道の学校で実際にあったという校則です。理由は、流氷が突然割れて海に落ちる危険があるため。確かに安全面を考えると仕方ないかもしれませんが、ユニークな校則ですよね。
2.飼っている馬や牛が出産するときは休んでもよい
学生の家族が営む農家で、馬や牛が出産する際は休んで手伝うことが許されていたようです。学生が動物との絆を強め、責任感を育むことを目的としているのかもしれません。心がほっこりする校則ですね。
3.交際相手は我が校の生徒でないといけない
閉鎖的な校風を感じさせる、ちょっと厳しい校則。理由は「校外の人と付き合うとトラブルになる」からのようです。しかし恋愛は自由であり、校則で規制するのは厳しすぎるかもしれません。
4.恋人が出来たら報告する
先生が学生の恋愛事情を把握しようとする、ユニークな校則。もしかしたら、学生の健全な恋愛をサポートしようとする意図があったのかもしれません。とはいえ、学生にとってはプライバシーの侵害と感じるでしょう。
5.服装違反者は半年間、教頭と交換日記する
服装違反の罰則として、教頭と交換日記をするというユニークな校則もあります。学生に反省を促すための斬新なアイデアといえますが、教頭にとっても負担になるかもしれませんね。
6.学校に草履はいいが下駄で来てはいけない
草履はOKなのに下駄はNGという、なんとも微妙な校則です。理由は不明ですが、見た目や音などが関係しているのかもしれません。いずれにせよ、現代にはそぐわない校則といえます。
7.弁当に寿司を持ってきてはいけない
「お昼ごはんは学生の楽しみだから制限しないであげて」と、思わずツッコミを入れたくなる校則です。衛生面からの配慮かもしれませんが、寿司だけピンポイントに禁止されているのは少し疑問。なかには、焼きそば単品で持ってくるのを禁止している学校もあるようです。
8.廊下を歩くときに、靴の裏を見せてはいけない
日常的なふるまいや、マナーを重視していたのかもしれません。しかし、常に足の裏を見せずに歩くのは難しい気がします。校則を守るため、すり足で歩く学生もいたとか。靴がすぐに傷んでしまいそうです。
理不尽なブラック校則がなくならない3つの理由
ブラック校則と呼ばれ問題視されているにもかかわらず、なぜ現代でも採用している学校があるのでしょうか。考えられる理由は3つあります。
- 非行に繋がる行動を抑えるため
- 周辺住民からのクレーム対策
- 校則を見直す文化がない
それぞれ解説します。
非行に繋がる行動を抑えるため
1970年代後半頃から、学校内で学生の問題行動が頻発しはじめました。そのため、校則で細かく規制して集団生活での秩序を守らせるという風習が広まったようです。当時は髪型や服装を制限することで、非行に繋がる行動を減らせると考えられていました。
しかし、近年は多様性の時代。学生の個性を尊重する考えが広まりつつあり、従来の校則は合わないという声も増えています。また服装や持ち物と非行との関係も、科学的に証明されていません。
周辺住民からのクレーム対策
周辺住民から学生の騒音やマナー違反に関するクレームが寄せられないよう、校則を厳格に設定している場合もあります。
しかし、学生の声を無視してクレーム対策するのは、本末転倒といえるでしょう。反発心から問題行動を起こす学生もいます。学校は学生と住民双方の意見を尊重し、バランスをとることが大切ではないでしょうか。
校則を見直す文化がない
「伝統的な決まりだから守って当たり前」「おかしいと感じるけど先輩先生が指導しているから従う」など、そもそも校則を見直す文化がないのも原因の一つと考えられます。
校則を見直すには、各方面からの意見をまとめ調整しなければなりません。時間と労力のかかる作業であり、後回しにしている学校も多いでしょう。しかし時代に合わせて校則を見直していくことは、学生がのびのびと学校生活を送るためにも大切なことです。
全国でブラック校則が見直しされつつある
問題視されているブラック校則ですが、全国の学校で少しずつ見直しの動きが高まっています。
たとえば鹿児島県教育委員会では、県立と公立の小・中・高等学校を対象に校則の見直し状況についての調査を実施。各学校に対して学生の実情や保護者の考え、地域の状況を踏まえて積極的に校則を見直す必要があると周知しました。
時代の流れに対応しつつ学生一人ひとりの尊厳を守るためにも、このような動きが今後も広まっていくとよいですね。
まとめ
クスっとしてしまうものからツッコミを入れたくなるものまで、全国には多くの不思議な校則が存在します。会話のネタとして同僚の先生や学生に、通っていた学校の校則を聞いてみてはいかがでしょうか。驚きの内容が聞けるかもしれませんよ。
\ぜひ投票お願いします/
鶴巻 健太
新潟在住のSEOディレクターで「新潟SEO情報局」というサイトを運営中
ウイナレッジのコンテンツ編集を担当
朝は農業を楽しみ、昼はスタバのコーヒーと共にパソコンに向かうのが日課