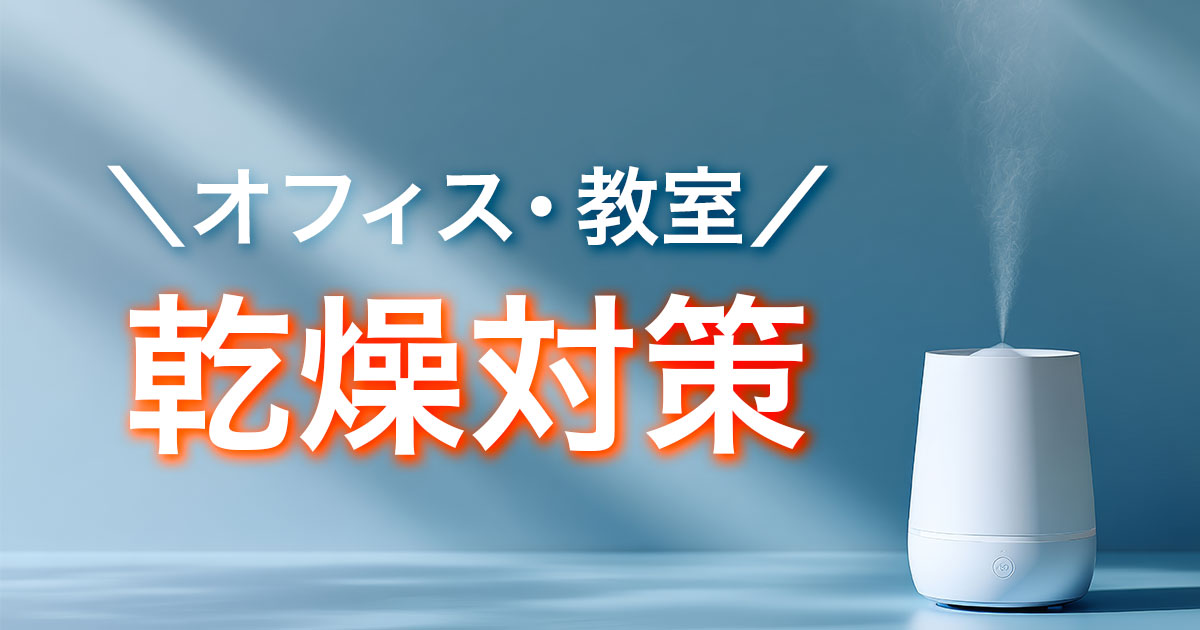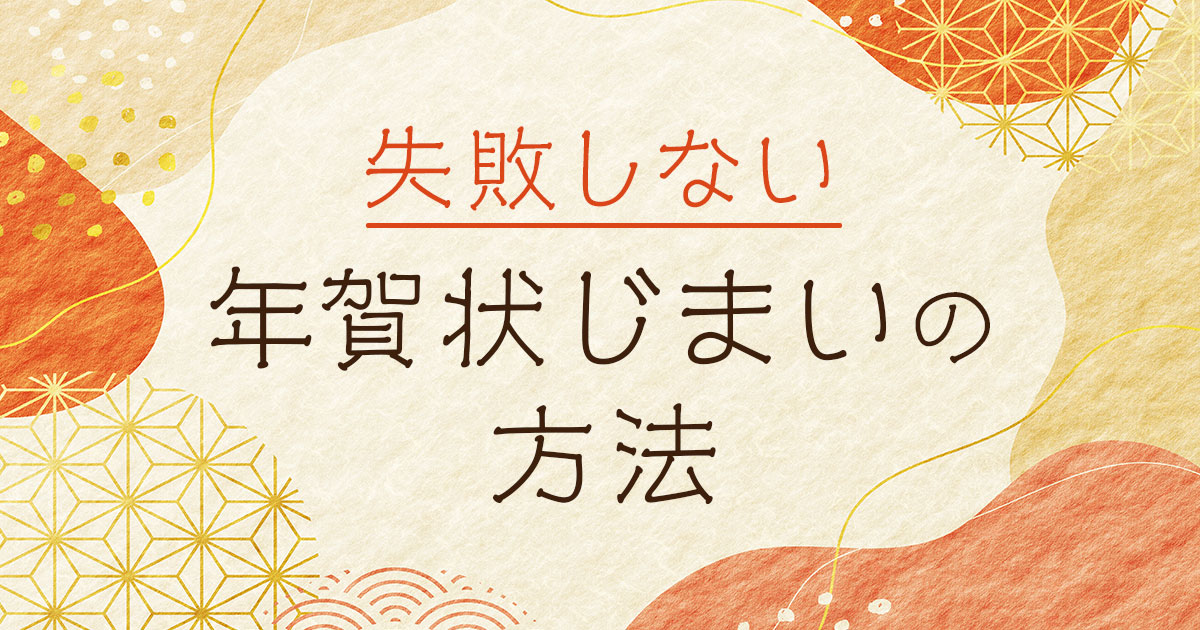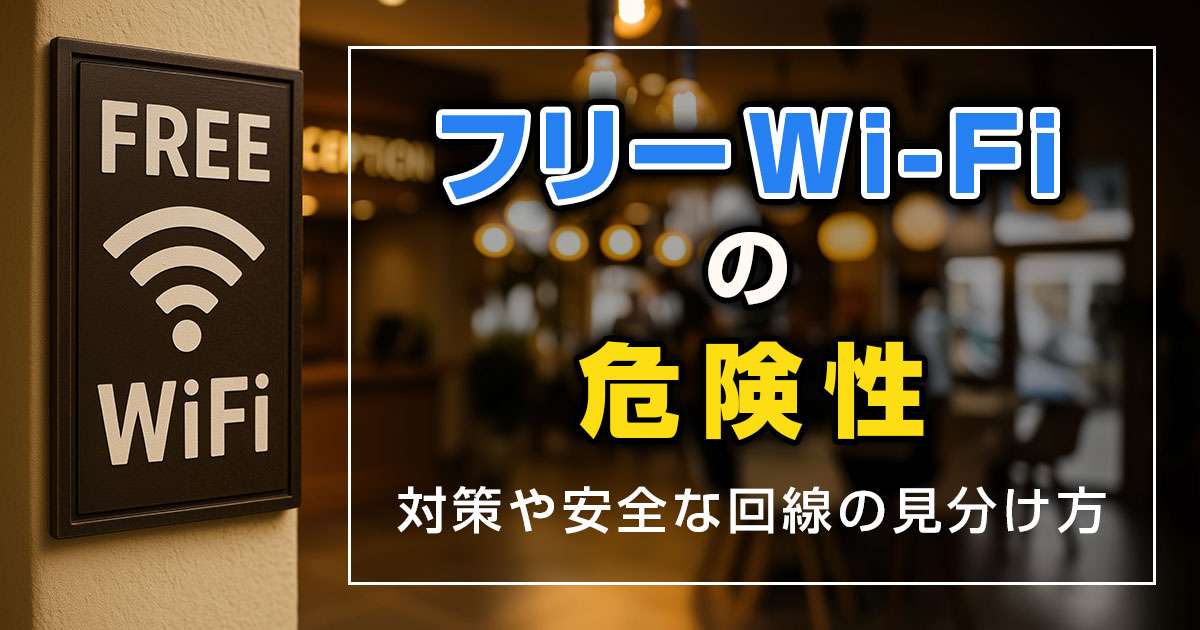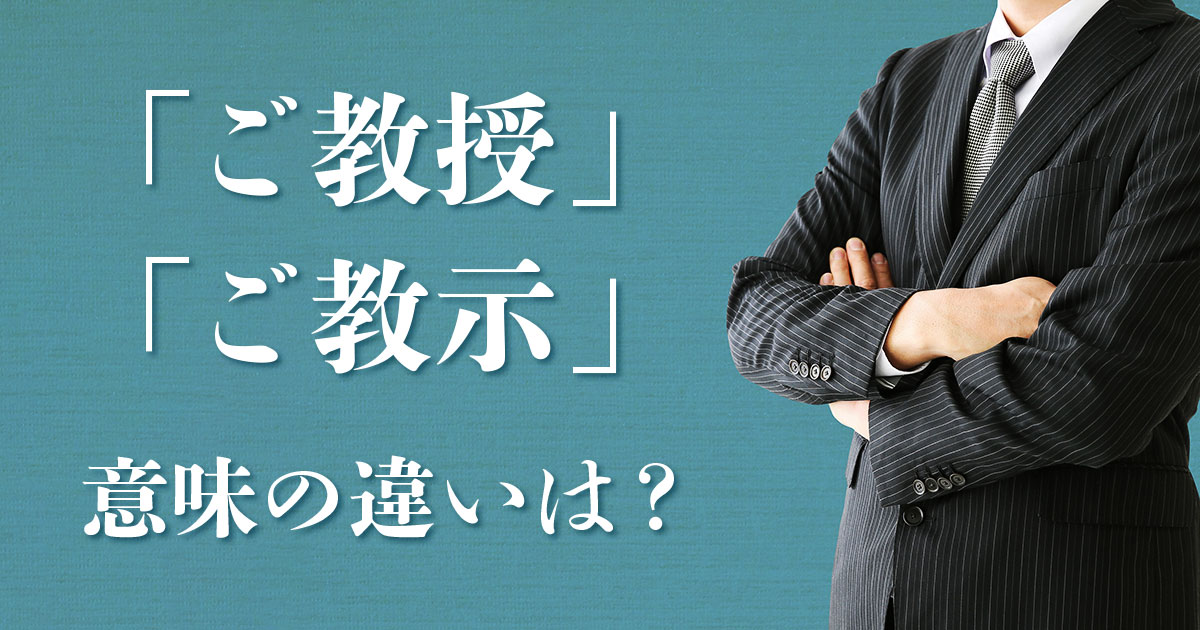
ビジネスの場面で頻繁に登場する「ご教授」と「ご教示」という言葉。どちらも相手に何かを教えてもらう際に使う丁寧な表現ですが、意味合いや使い分けに迷う先生も少なくないのではないでしょうか。2つの言葉が持つニュアンスには、微妙な違いがあります。
敬語は間違えると印象が悪くなるだけでなく、相手に失礼になる恐れも。そこで本記事では、2つの言葉の正しい意味や使い方を例文を交えながら解説します。それぞれの違いを理解し、自信を持って使えるようにしましょう。
目次
「ご教授」と「ご教示」の意味とは?
同じ意味のように思える2つの表現ですが、実は用いられる状況や示す意味合いに差があります。まずは、2つの言葉が本来どのような意味を持つのか確認しましょう。
| 単語 | 意味 |
|---|---|
| ご教授 | 専門分野の知識や技術など、高度な内容を相手から授けてもらうこと |
| ご教示 | 必要な情報や方法を示してもらうこと(専門性の高さは問わない) |
「ご教授」の意味
「ご教授(ごきょうじゅ)」は、相手の高度な知見やスキルから長期的・専門的な指導や助言を受ける際に使用する丁寧表現です。たとえば大学の指導教官に研究テーマや卒業論文の指導を依頼するとき、あるいは業務に関連する専門的アドバイスをお願いするときなどに使うのが一般的です。
ビジネスの場面においては、高度な専門知識を活用する場合や、複雑な問題の解決策を求める際などに用いられることが多いでしょう。単発的に情報を聞くだけではなく、ある程度継続的な指導や助言を受ける場合に適した表現です。
「ご教示」の意味
「ご教示(ごきょうじ)」は、やり方や知識を教えてもらう際に使われる敬語です。必ずしも専門性の高い領域とは限らず、日程や手順などの基本的な情報を尋ねる場合にも広く用いられます。
たとえば、会議の日時の確認や書類の提出先を尋ねるなどのシンプルな問い合わせの際に使うのが適切です。短期間での情報提供を求めるときに、多用される表現といえるでしょう。「ご教授」に比べて、より広い範囲で使える言葉ですが、丁寧な言葉であることに変わりはありません。
判断に迷ったときのポイント
どちらを使うべきか迷った場合は、以下の点を考慮して判断するとよいでしょう。ポイントをまとめたので、参考にしてください。
| ご教授 | ご教示 | |
|---|---|---|
| 内容の専門性 | 専門知識や高度な技術を伴う | 比較的簡単な情報や手順 |
| 指導の期間 | 長期的・継続的な指導を想定 | 一度きりの質問や短期的な確認 |
| 相手との関係性 | 専門知識を持つ相手や先生 | 幅広く使える |
「ご教授」「ご教示」の正しい使い方と例文

「ご教授」と「ご教示」は、いずれも相手を敬う言い回しですが、内容や状況によって使い方が異なります。ここでは具体的な使用例を挙げながら、それぞれの使い方を見ていきましょう。
「ご教授」の正しい使い方と例文
「ご教授」は、専門性の高い知識や長年培われた経験を踏まえた指導や助言をお願いする際に使います。特に、以下のようなケースで適している表現です。
- 長期的に高度なノウハウやスキルを身につけたいとき
- 解決が難しい課題についてアドバイスを求めたいとき
- 豊富な経験に基づく見解や指導を仰ぎたいとき
「ご教授」の使用例は、以下のとおりです。
【例文】
「AIの先端技術について、ご教授いただけますと幸甚に存じます。」
「長年にわたるご教授のおかげで、業務の視野が大きく広がりました。」
「このたびは新しいプロジェクトについてご教授いただきたく、ご連絡いたしました。」
「ご教示」の正しい使い方と例文
「ご教示」は、一度きりの回答や具体的な手順、比較的簡単な情報を尋ねる場面で使われます。以下のようなときに使うのが適切です。
- 複雑ではない情報の提供をお願いしたいとき
- 一定の事実や方法を確認したいとき
「ご教示」の使用例は、以下のとおりです。
【例文】
「担当部署の連絡先をご教示いただければ助かります。」
「ご教示いただきました内容を参考に、資料を作成いたしました。ご確認いただけますでしょうか。」
「新しいシステムのログイン方法をご教示いただきたいです。」
知っておきたい!「ご教授」「ご教示」を使う際の注意点3つ
どちらも相手に敬意を払う丁寧な表現ですが、使い方を間違えると失礼にあたる可能性も。ここでは、使用するうえでの注意点を3つ解説します。
- 「享受」とは意味が異なる
- 会話で使うのは避ける
- 「ください」「願います」は失礼になる場合も
それぞれ見ていきましょう。
「享受」とは意味が異なる
「ご教授」と似ている言葉に「享受」があります。読み方は同じですが、「享受」は権利や恩恵を受け取るという意味であり「教えを受ける」とは異なります。誤変換や書き間違いには、十分留意しましょう。
会話で使うのは避ける
基本的に文面で用いられる敬語表現のため、会話では使わないようにしましょう。口頭で話す場合は「この業界は初めてなので、ご指導のほどお願いいたします」「来週の打ち合わせ日程を教えていただけますでしょうか」などの表現に置き換えるのが望ましいです。
「ください」「願います」は失礼になる場合も
「ください」や「願います」は、命令形に近いニュアンスを持つため、相手によっては不快に感じるケースもあります。特に目上の人や取引先に伝える場合は「ご教示いただければ幸甚です」「ご教授いただけますようお願い申し上げます」など、柔らかく丁寧な表現を選択するとよいでしょう。
自分が「ご教授」「ご教示」を依頼されたら?
仕事をしていると、相手から指導や助言を求められるケースもありますよね。そのような場合は、快く引き受けるとともに丁寧な対応を心がけましょう。
「お声がけいただき、ありがとうございます。微力ながら、お役に立てれば幸いです。」「私でよろしければ、喜んでご協力させていただきます。」など、感謝の気持ちと引き受ける姿勢を丁寧に伝えることで、より相手との信頼関係を深められます。
「ご教授」「ご教示」と似た3つの言葉
相手から指導や助言を得たいときに使われる尊敬表現は、ほかにもあります。状況や目的に合わせて使い分けられるよう、意味を把握しておくと便利ですよ。ここでは、代表的な3つの言葉を紹介します。
- ご指導
- ご鞭撻
- ご指南
それぞれの意味を解説します。使いこなすことで、より細やかなニュアンスを表現できるようになるでしょう。
ご指導
目標や目的に向かって、人に知識や技能などを教え導くことを意味します。たとえば「プロジェクト遂行にあたり、ご指導いただければ幸いです。」「新人研修でのご指導をよろしくお願いいたします。」などのように使います。「ご教授」と似ていますが、より広い意味で使われる言葉です。
ご鞭撻
相手からの厳しい指導や、励ましをお願いする際に使います。厳しくも温かい指導を期待する際に用いられ、ビジネスの場面では「今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします」など「ご指導」とセットで使われることが多い表現です。
ご指南
武芸や芸事などを、教え示すことを意味します。師匠から弟子への道の伝授というニュアンスが含まれるため、ビジネスの場面で使われることはほとんどありません。「華道の上達のために、先生にご指南いただければと存じます。」「長期間にわたり、ご指南いただきありがとうございました。」などのように使います。
まとめ
「ご教授」と「ご教示」はどちらも丁寧な敬語ですが、それぞれの意味や使われる場面には細かな違いがあります。正しく使うことで相手に対する敬意を的確に伝えられますが、一方で誤った使い方をすると意図せず相手に不快感を与えたり、誤解を招いたりする可能性も。この機会に違いを学び、実践的な場面で自信を持って活用できるようにしましょう。
\ぜひ投票お願いします/
鶴巻 健太
新潟在住のSEOディレクターで「新潟SEO情報局」というサイトを運営中
ウイナレッジのコンテンツ編集を担当
朝は農業を楽しみ、昼はスタバのコーヒーと共にパソコンに向かうのが日課