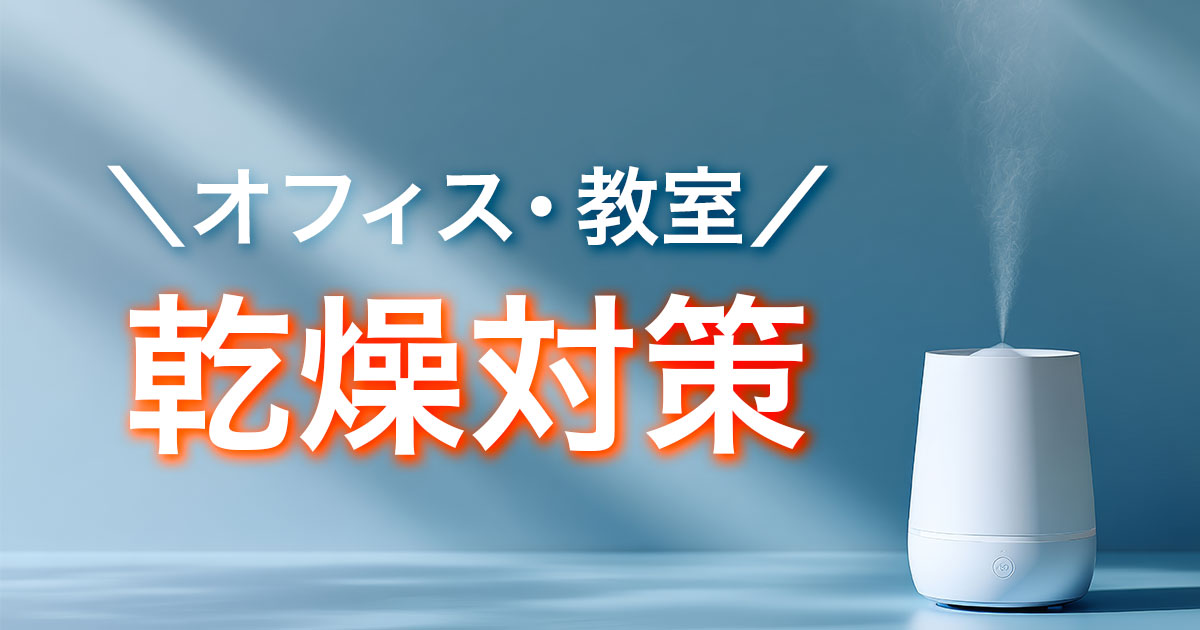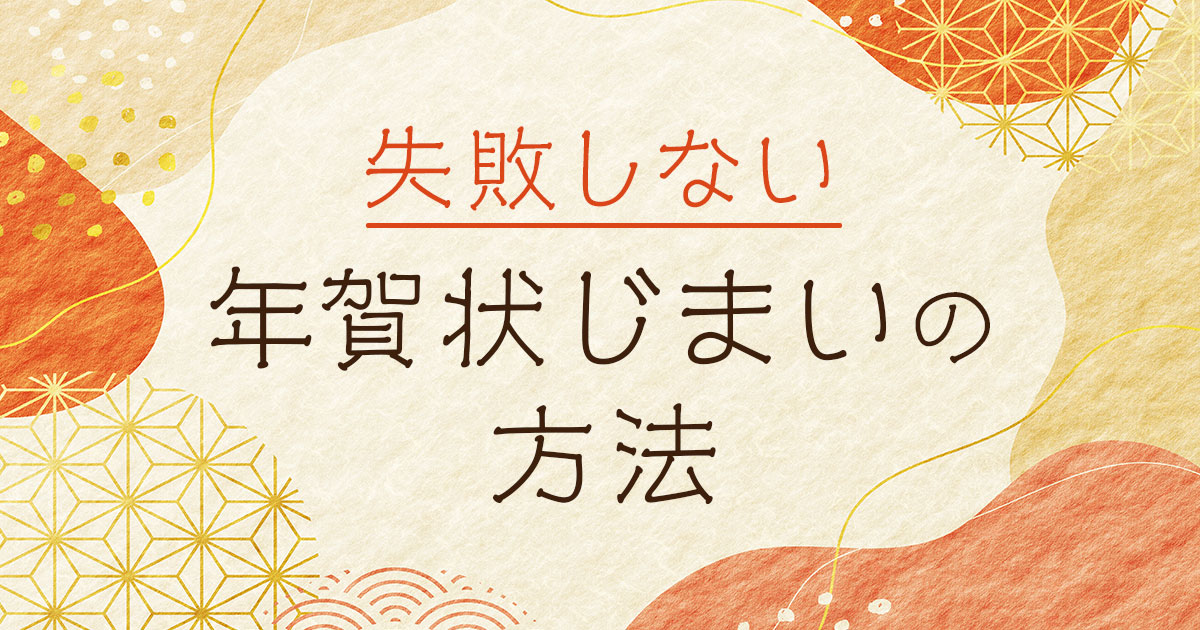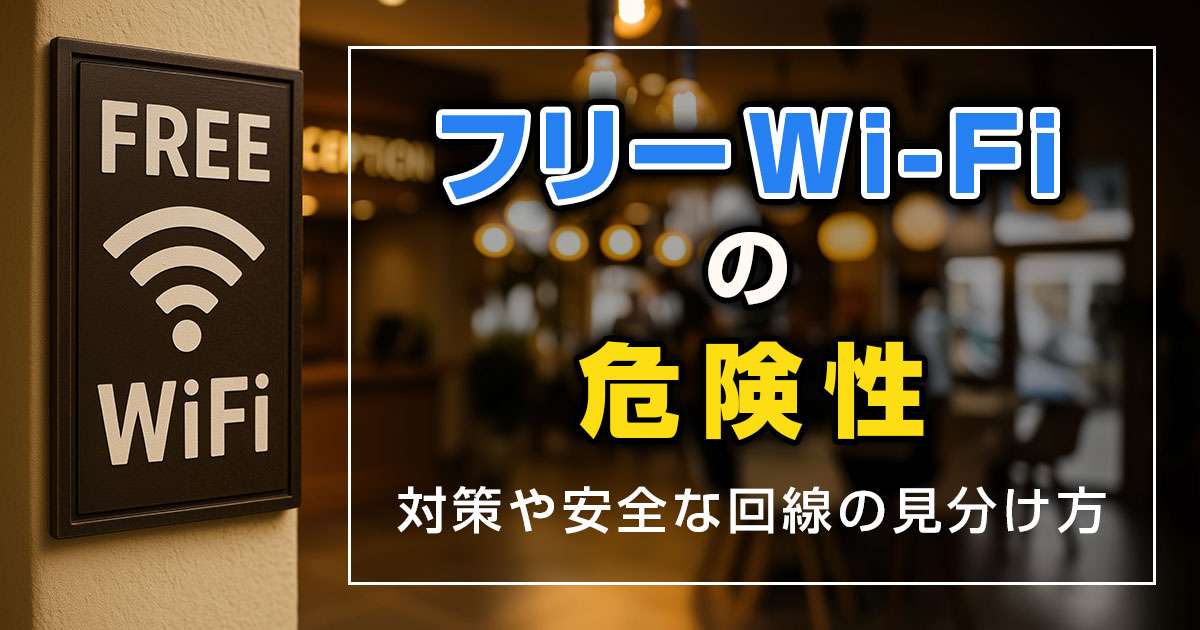雪景色は美しいですが、ときに自然災害の要因にもなります。普段は降らない地域で大雪が降ると、交通マヒや事故など日常生活に大きな支障が出るケースも。いざというときに慌てないために、日頃からの備えが大切です。
そこで本記事では、事前にしておきたい7つの対策を解説します。外出せざるを得ない状況での対処法もまとめたので、参考にしてください。
目次
大雪の定義とは

そもそも、どの程度が大雪と判断されるのか疑問に思う先生もいるのではないでしょうか。ここでは、大雪に関する基礎知識を解説します。
- 特定の時間内に大量に降る雪のこと
- 積雪深と降雪量の違いも理解しておこう
- 国も取り組みしている
それぞれ見ていきましょう。
特定の時間内に大量に降る雪のこと
大雪の基準は地域によって異なります。たとえば北海道札幌市と東京都の基準を比較してみましょう。
- 北海道札幌市→6時間で60cmあるいは12時間で40cmの降雪(平地の場合)
- 東京都→12時間で10cmの降雪予想(多摩西武を除く)
大雪が降ると、転倒事故だけでなく交通障害や建物の倒壊リスクが増加します。近年は関東圏で大雪が降るケースも増えているため、いつでも対処できるよう日頃からの対策が大切です。
積雪深と降雪量の違いも理解しておこう
天気予報を見ると「積雪深」と「降雪量」の単語を目にしますが、似ているようで明確な違いがあります。積雪は地面に降り積もってできた層の厚さを指し、積雪計やレーザー光を使って測定されます。
降雪量は、一定期間内に降った雪の量のことです。直接測ることができないため、気象観測では1時間ごとの積雪深の差を降雪量としています。たとえば午前10時の積雪深が10cm、午前11時の積雪深が15cmだった場合、増加分の5cmが降雪量になります。
国も取り組みしている
大雪は、私たちの生活に大きな影響を与える自然現象の一つです。そのため国や地方自治体では、大雪への備えや対策を進めています。たとえば内閣府防災担当のX(旧:Twitter)公式アカウントでは、大雪をはじめ自然災害に関する情報提供や呼びかけをしています。
また内閣府の防災情報ページでも、雪害対策による取組や対策状況が閲覧できるので、一度目を通しておくとよいでしょう。
事前に取り組みたい大雪対策7選

大雪による被害を最小限に抑えるためには、事前の備えが大切です。ここでは、自宅でできる対策を7つ紹介します。
- 防寒グッズを用意する
- 防災グッズを用意する
- 食料を備蓄しておく
- 除雪用具を準備しておく
- 安否確認の方法を決める
- 水道管の凍結にも注意
- スタッドレスタイヤへ履き替えする
それぞれ解説します。できるところから取り組んでみましょう。
1.防寒グッズを用意する
大雪が降った場合、停電が発生する恐れがあります。暖房器具が使えないと体調を崩すリスクが高まるため、防寒対策は必須です。カイロや毛布、灯油ストーブなど電気がなくても暖をとれるグッズを準備しておきましょう。
2.防災グッズを用意する
大雪による停電が発生した場合、防寒対策だけでなく電源確保も考えなければなりません。スマートフォンの電池切れに備え、モバイルバッテリーを準備しておくとよいでしょう。電池式のラジオもおすすめ。
またケガをしたときの救急用品や常備薬など、ほかの災害時にも対応できるグッズをリュックにまとめておくと便利です。
3.食料を備蓄しておく
大雪が降ると、外出も困難になります。また外出できたとしても、物流マヒによって思うように食料が調達できない可能性も。そのような状況も想定し、最低3日分の食料や飲料を準備しておきましょう。缶詰やインスタント食品など、調理が簡単で長期保存が可能な食品がおすすめ。電気が使えないケースもあるため、カセットコンロも準備しておくと安心です。
4.除雪用具を準備しておく
大雪が降った際は、玄関先や歩道の雪かきが必要になります。事前にスコップや雪かき用のブラシなど、除雪用具を準備しておきましょう。滑りやすい場所での作業となるため、靴は滑りにくい靴底を使った長靴がおすすめ。除雪作業中に屋根から雪が落ちてくる可能性もあるため、ヘルメットも必須です。
5.安否確認の方法を決める
大雪が原因で電話が繋がりにくくなるなど、通信環境が悪化するケースもあります。そのような状況でも、家族や親しい人との安否確認がスムーズにできるよう、事前に連絡方法を決めておきましょう。たとえば災害用伝言ダイヤルの利用方法や、集合場所を確認しておくと安心です。
6.水道管の凍結にも注意
気温が氷点下になると水道管が凍結する恐れもあるため、忘れずに対策しましょう。水道管がむき出しになっている部分にタオルや発泡スチロールを巻き付けて紐で縛り、濡れないようにビニールテープで覆えばOKです。
万が一凍結した場合は、凍った部分にタオルをかぶせ、上から40℃程度のぬるま湯をゆっくりかけます。直接熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂する恐れがあるため避けてください。
7.スタッドレスタイヤへ履き替えする
車で通勤している場合は、必ずスタッドレスタイヤへ履き替えましょう。雪道や凍結路をノーマルタイヤで走行することは、スリップや立ち往生の原因となり大変危険です。また道路交通法違反にもなります。重度の積雪や凍結に備えて、タイヤチェーンも車に積んでおくとよいでしょう。
大雪でも外出しなければならないときの対処法5選
大雪発生時は、あらゆる場所で通行止めや車両の立ち往生、公共交通機関の大規模遅延が考えられます。そのため、基本的に不要不急の外出は控えましょう。しかし、やむを得ず外出しなければならない状況もありますよね。そのような場合の対処法は、次の5つです。
- 手荷物は持たない
- 手袋と帽子を着用する
- 滑りやすい場所を避けて歩く
- なるべく前傾姿勢で歩く
- 底に深い溝のある靴を履く
それぞれ解説します。
1.手荷物は持たない
大雪の日に外出する際は、手荷物を極力持たないようにしましょう。両手がふさがっているとバランスを崩しやすくなり、転倒の原因となります。荷物を持ち運ぶ場合は、リュックサックなど両手が空くバッグがおすすめです。
2.手袋と帽子を着用する
寒さから身を守るためにも、手袋と帽子の着用は必須です。特に手袋は、防寒だけでなく転倒時の怪我を防ぐ役割も果たします。保温性・防水性の高いタイプを選びましょう。帽子はフライトキャップなど耳まで覆える形状だと、より暖かさを保てます。
3.滑りやすい場所を避けて歩く
雪が積もっている道は滑りやすく、転倒の危険性が高まります。特に、日陰になっている場所は凍結している可能性があります。なるべく雪が少なく、凍結している可能性が低い場所を選んで歩くようにしましょう。また、屋根からの雪が落ちてくる可能性がある場所も避けてください。
4.なるべく前傾姿勢で歩く
雪道は平らな場所でも滑りやすいため、なるべく前傾姿勢で歩くことを心がけましょう。重心を低くすることでバランスをとりやすくなり、転倒リスクを防げます。また足の裏全体で地面を捉えるように、小さい歩幅でゆっくり歩くこともポイントです。
5.底に深い溝のある靴を履く
靴によって、歩きやすさが大きく変わります。基本的に、靴底がフラットなタイプは滑りやすいため避けましょう。底に深い溝のある長い靴やスノーブーツがおすすめです。また登山用のトレッキングシューズも溝が深いため、滑りやすい雪道で活躍します。
まとめ
普段は降らない地域でも、突然の大雪に見舞われるケースがあるため事前の対策が大切です。本記事を参考にして、できるところから対策してみてくださいね。不要不急の外出は控えるのが基本ですが、やむを得ず外出しなければならない場合は充分に注意しましょう。
\ぜひ投票お願いします/
鶴巻 健太
新潟在住のSEOディレクターで「新潟SEO情報局」というサイトを運営中
ウイナレッジのコンテンツ編集を担当
朝は農業を楽しみ、昼はスタバのコーヒーと共にパソコンに向かうのが日課