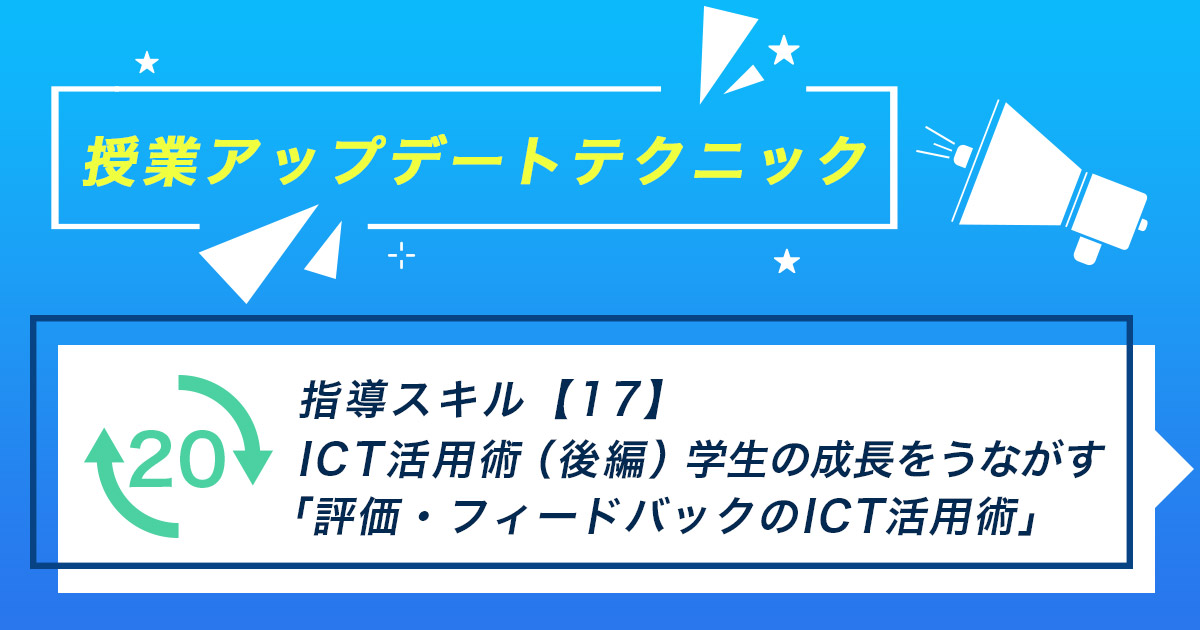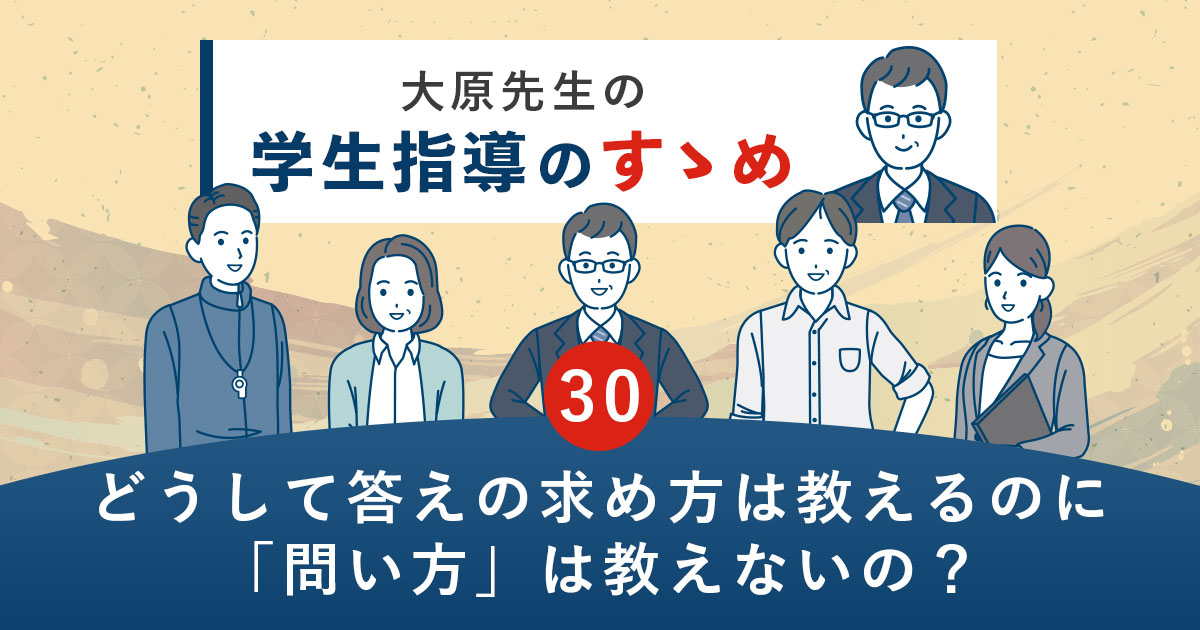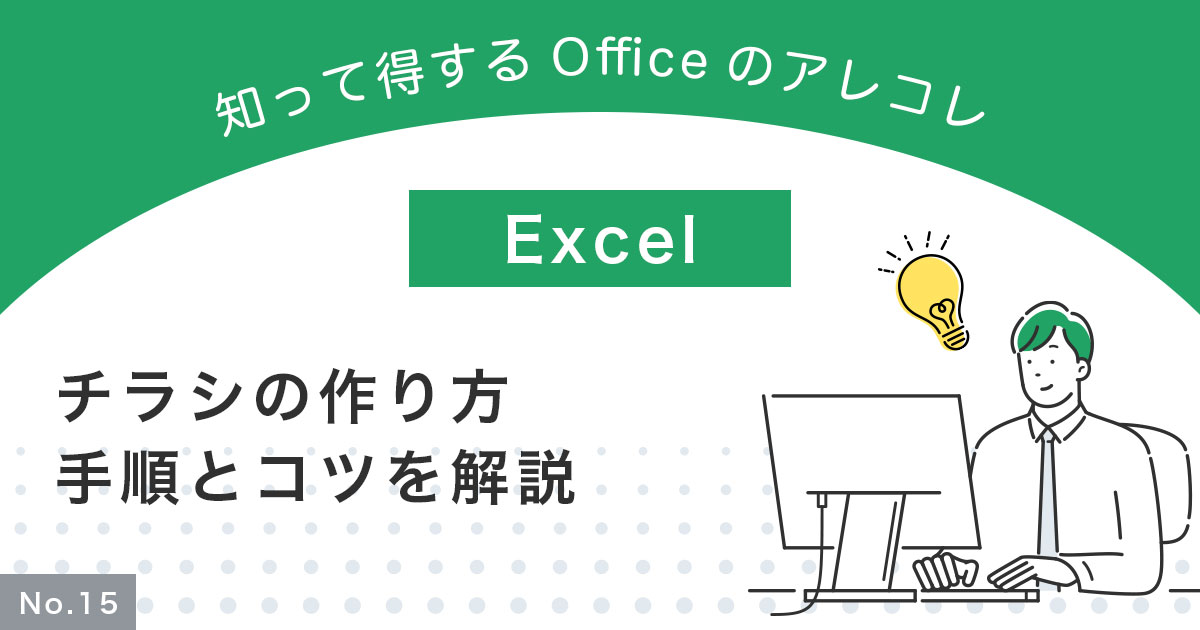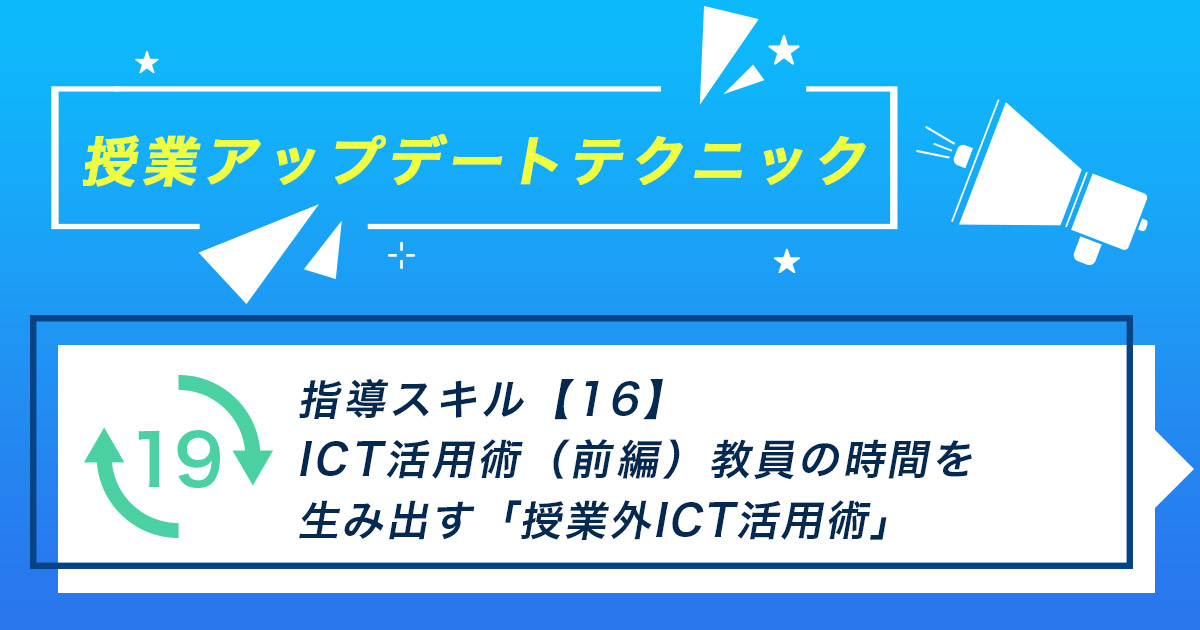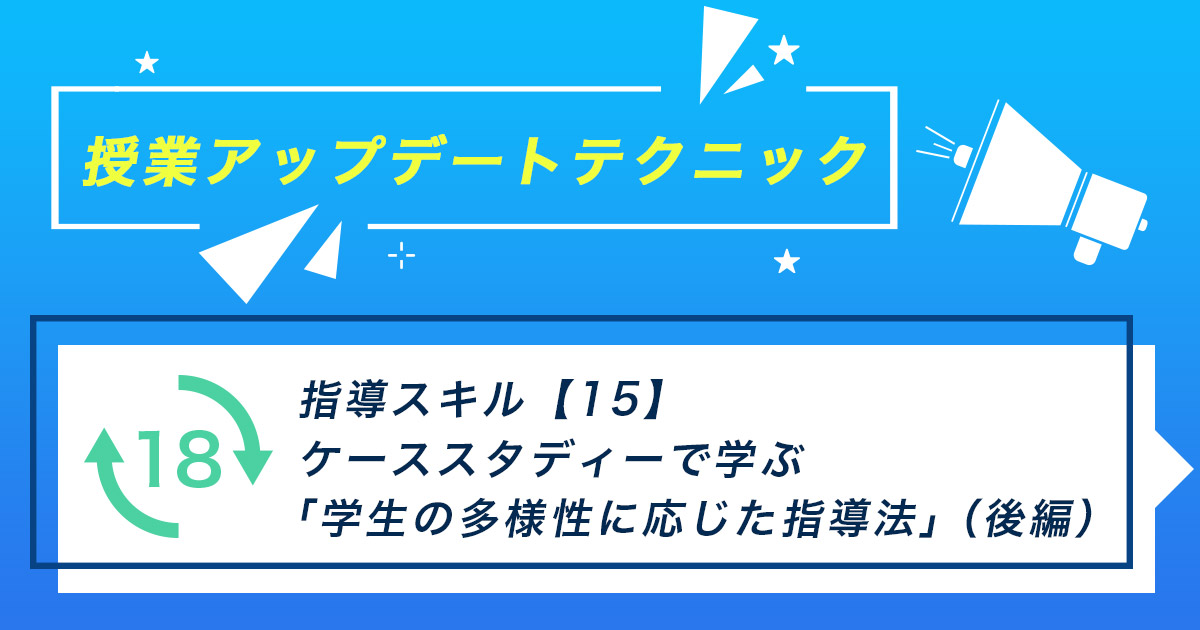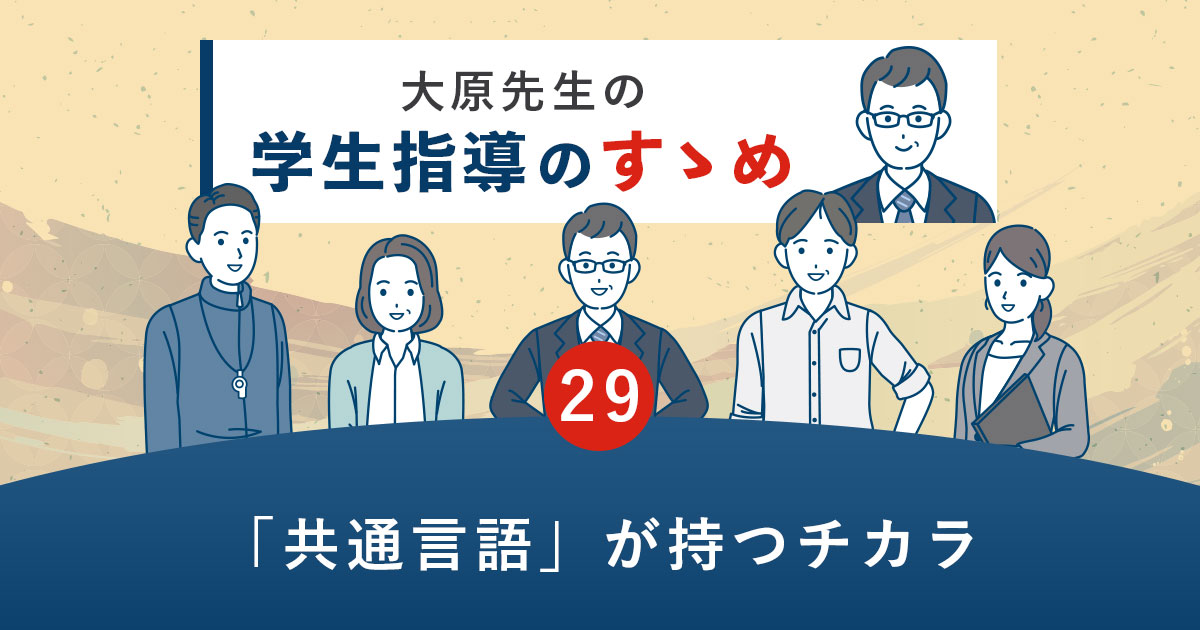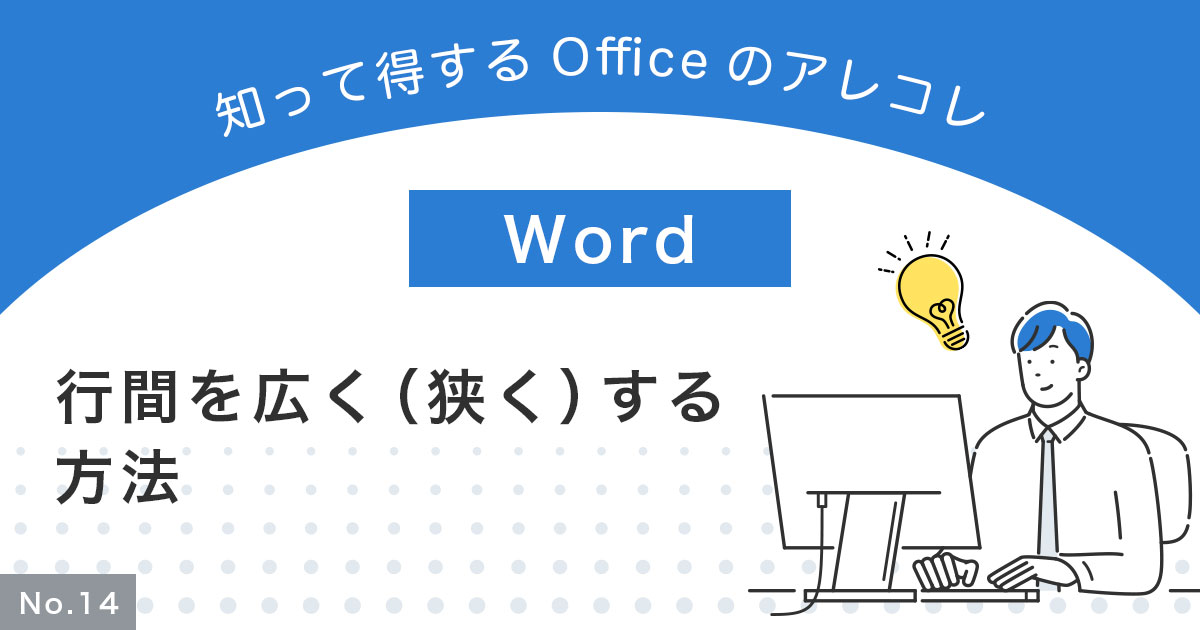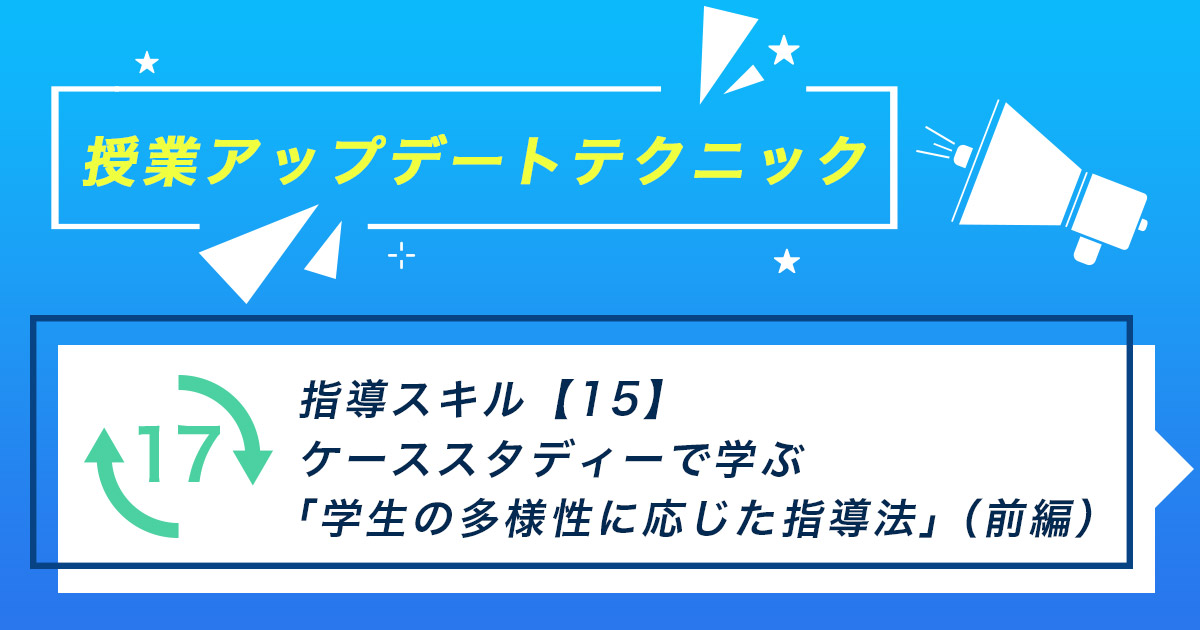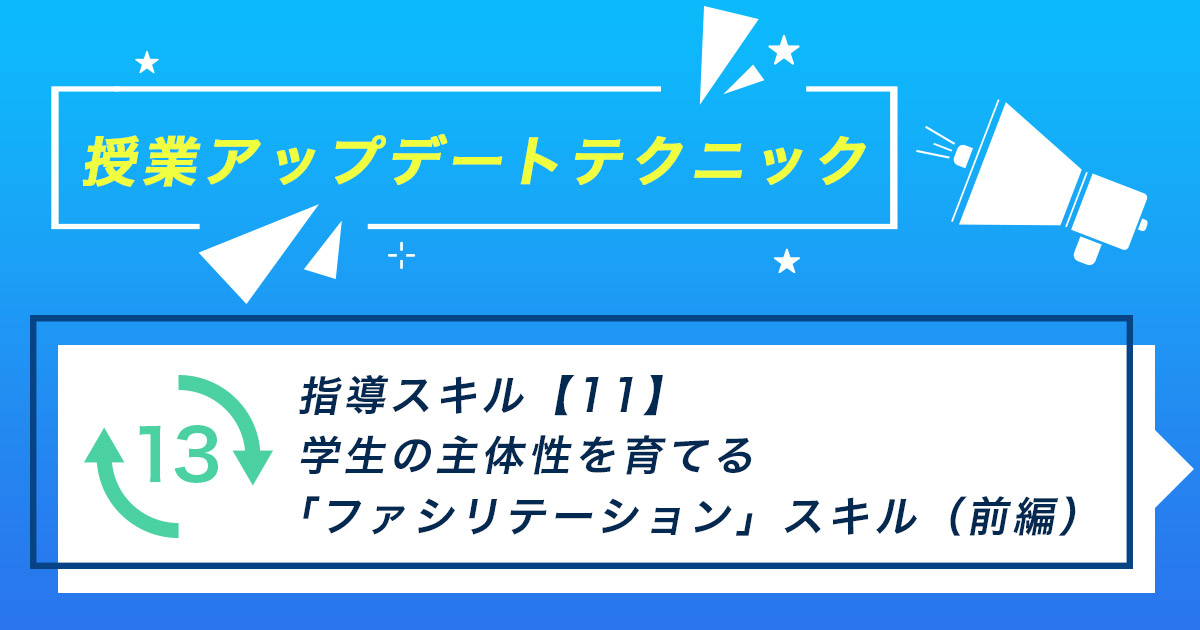
連載授業アップデートテクニック
変化する学生のニーズ、技術やツールの進歩、多様性の受け入れなど、常に進化が求められる現代の教育現場。授業をアップデートしなくてはいけない時期が到来しています。この連載では、教員向け研修や教員志望者の育成を行う「RTF教育ラボ」の代表で、年間300もの授業観察を行う教育コンサルタントの村上敬一さんから、専門学校の先生に向けた「令和の授業テクニック」を教えてもらいます。
早いもので、2025年もすでに半年が過ぎようとしています。夏の長期休暇まで、残すところあと1カ月ほどとなりました。専門学校の学生にとってこの時期は、テストや実習、各種行事の準備、国家資格取得に向けた勉強、就職活動(インターンシップを含む)など、非常に重要な時期です。一方で、遊びやアルバイトにも力を入れたいと感じる季節でもあります。
だからこそ、学生自身が現実的で主体的な計画を立て、限られた時間をうまくやりくりする経験が非常に重要になります。
そこで、今回から数回にわたり、「学生の主体性を育てる『ファシリテーション』スキル」についてお伝えしていきます。
教員の役割は、単に知識を伝えることにとどまりません。これまでにもお話ししてきたとおり、学生一人ひとりが自らの将来について主体的に考え、セルフマネジメントができるようになるために、ファシリテーションスキルを活用してサポートしていきましょう。
目次
1.ファシリテーションとは

ファシリテーション(Facilitation)とは、会議や研修、プロジェクトチームなどの集団活動が円滑に進むように、中立的な立場から話し合いをサポートし、目的達成や課題解決を容易にする技法のことです。その効果として、参加者から主体的な発言が増えたり、新しい視点の意見が出たり、参加者同士の強みを活かした相互作用が生まれたりします。ですから、単に会議の司会進行役をすることがファシリテーションではありません。参加者一人ひとりの能力や意見を最大限に引き出し、チームとしての成果をつくり出すことが目的なのです。
2.ファシリテーションにおける前提となる考え方
ファシリテーションを行う上で意識してほしい5つの考え方を紹介します。
(1)中立的な立場を維持する
ファシリテーター(ファシリテーションを担う人)は、課題解決や目的達成を念頭に、特定の意見に偏らないように心がける必要があります。教員という職業は「答えありき」になりがちです。教員がファシリテーションを行う場合には、特に注意が必要です。
(2)目的/目標を明確にする
ファシリテーションの場では、何のための話し合いなのか、何を達成したいのか、事前に目的や目標を明確にすることが重要です。議論のゴールを共有し、参加者が方向性を理解できるようにしましょう。
(3)傾聴を積極的に行う
参加者の意見を尊重し、話をよく聴く姿勢をファシリテーターがとることで、議論が活性化します。また、キーワードのオウム返しや適切なフィードバック(簡単な感想でも可)を返すことで、より深い議論が生まれることがあります。
(4)多様性を受け入れる
自分自身の価値観と違う意見が出ることは多々あります。さまざまな立場や意見を尊重し、異なる視点を積極的に取り入れることで、より充実した議論が可能になるのです。ただし、議論の中で目的や目標からずれていると感じる意見が出た場合には、ファシリテーターがその真意を問いかけ、確認することが必要です。
(5)話し合いの過程を管理する
議論が停滞したり、一部の参加者だけが発言したりする状態を防ぐために、最低限の管理が必要です。タイムマネジメントや話し合いの流れを適切にコントロールすることを意識しましょう。
3.ファシリテーションを行う際のメリット
まずはメリットです。大きくは5つあります。
(1)グループ内の円滑なコミュニケーションが期待できる
参加者間の意見交換がスムーズになり、グループ内の対話が活性化します。
(2)多様な意見が出やすくなる
参加者が意見を出しやすくなり、より幅広いアイデアや視点が得られます。
(3)グループ内の意思決定の早期化
参加者全員の意見を聞いたうえで対話が進むので、チームや組織の合意形成をスムーズに進めることができます。
(4)参加者の当事者意識が向上する
参加者間の対話を活発にすることで、参加者の主体性を引き出し、議論に対する当事者意識が向上します。
(5)グループ内での創造性が期待できる
参加者間での自由な発言を促すことで、革新的なアイデアが生まれやすくなります。
4.ファシリテーションを行う際のデメリット
次にデメリットです。大きくは4つあります。
(1)ファシリテーターのスキルによる差が出やすい
ファシリテーターのスキルが不足すると、議論が停滞したり、一部の人が発言しづらくなったり、話が目的からずれ、脱線してしまう可能性があります。
(2)時間がかかることがある
グループ内の意見を十分に出し合うために、通常の会議よりも時間を要する場合があります。授業のように時間制限がある場合は、高度なタイムマネジメントが求められます。
(3)双方の感情が出た意見の対立がある
グループ内で多様な意見が出ることで対立が起こるのは珍しくありません。しかし、何かしらの感情が中心となった双方の意見(価値観)の違いで起こる対立の場合、合意形成が難しくなることがあります。
(4)参加者の人間関係による影響がある
グループ内の雰囲気や人間関係によって、議論の進行が左右されることがあります。
5.専門学校でファシリテーション(ファシリテータースキル)が必要な理由
まず前提として、専門学校は学生に専門的な知識や技術を身につけさせ、社会に送り出すことを目的とした場です。したがって、「個」の力と「集団」の力の両方を育てることが非常に重要になります。
つまり、専門技術といった“個人の力”を高めると同時に、チームで成果を出す“集団としての力”を伸ばす必要があるのです。
現代の職場では、「他者と協働する力」は不可欠です。そのため、授業やグループワークの場でファシリテーションを活用することは、学生が社会へ出たときに即戦力として活躍するための有効な手段となります。
また、専門学校の教員としては、自らがファシリテーターとなってクラス全体(=学生集団)を育成していくという視点と、グループ内の1〜2名をファシリテーター役として育てるという視点とを切り分けて考えることで、より効果的な学生指導が可能になります。
6.次回に向けて
今回は、「学生の主体性を育てる『ファシリテーション』スキル(前編)」として、ファシリテーションを行う前に知ってほしい知識を中心にお伝えしました。
次回は教員が授業においてファシリテーションを行う際のスキルについて詳しくお伝えいたします。
\ぜひ投票お願いします/
村上 敬一
RTF教育ラボ代表/教育コンサルタント/東京都杉並区内中学校学校運営協議会委員
全国の公立および私立の小学校・中学校・高等学校、専門学校、塾などで教員研修、講師研修、授業や学級経営を中心とした教育全般に関するアドバイスを行う。また、現在まで18年間に渡り、毎年約150名の教員志望者を育成。年間の授業観察数は300を超え、これまでに約5000の授業を観察している。
RTF教育ラボ(https://goseminarcourse01.wixsite.com/rtfkyouikulab)