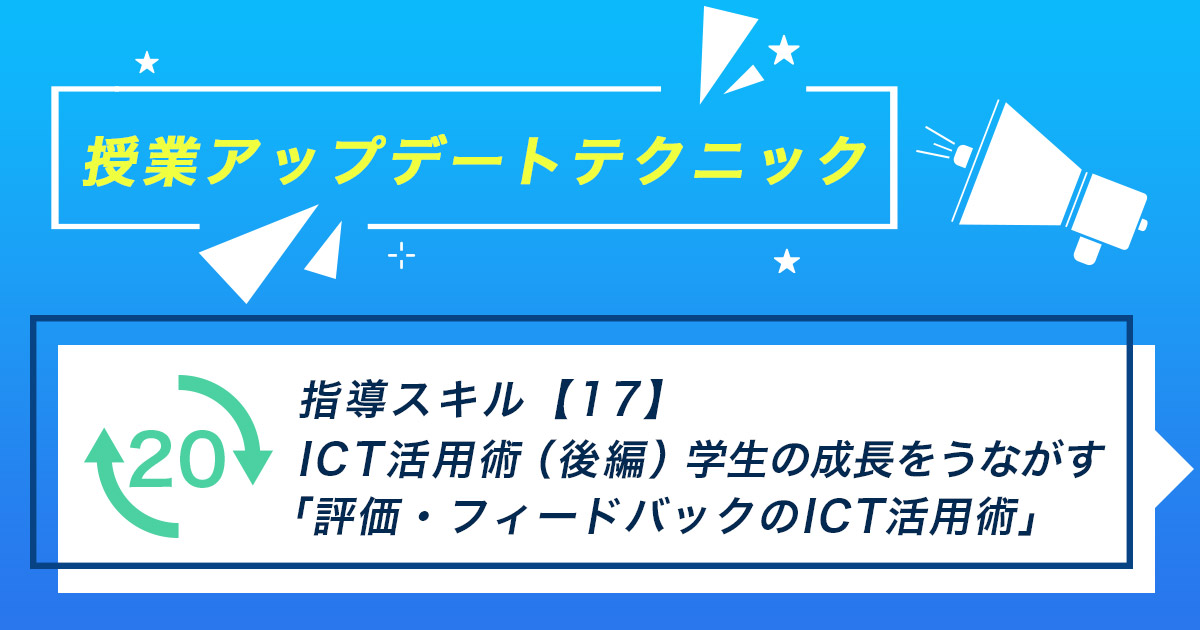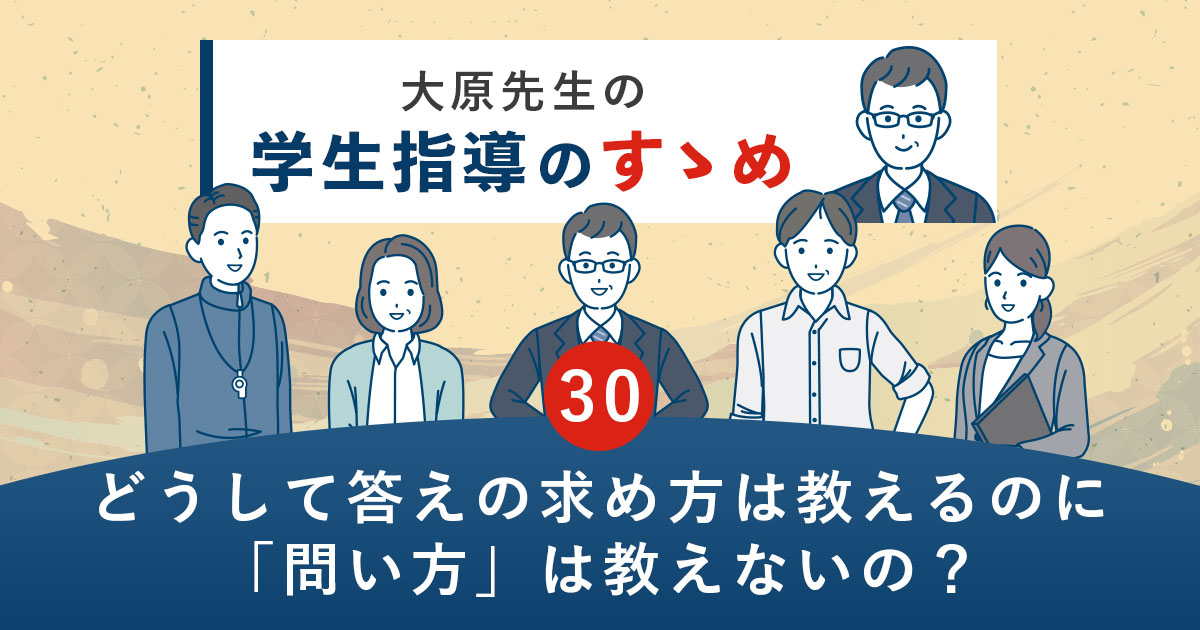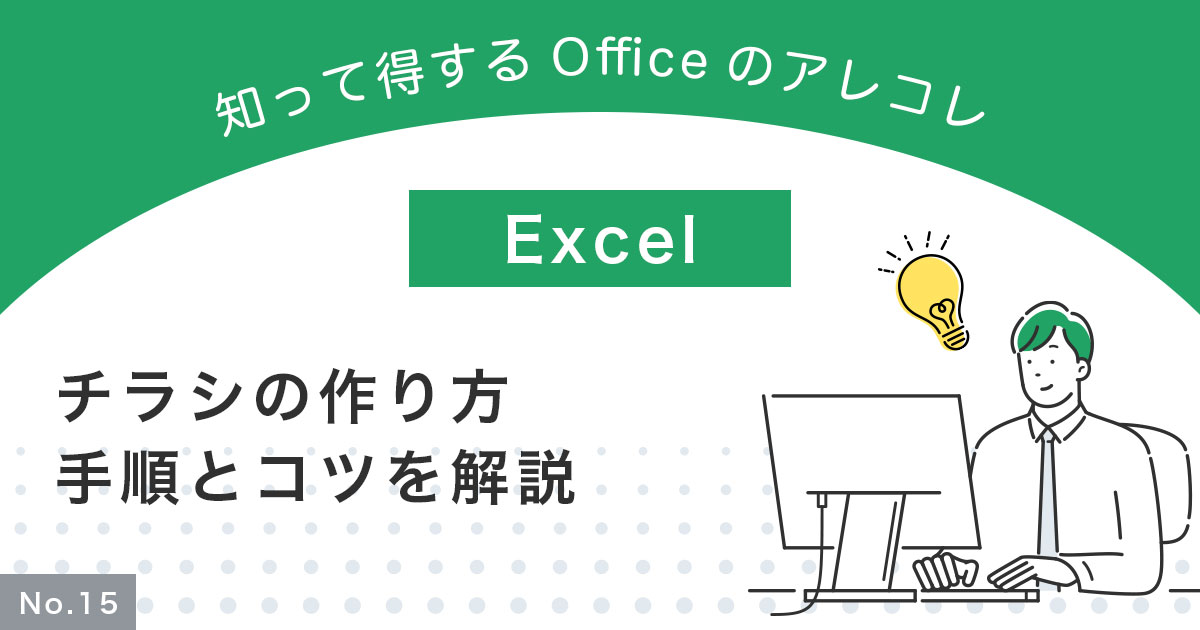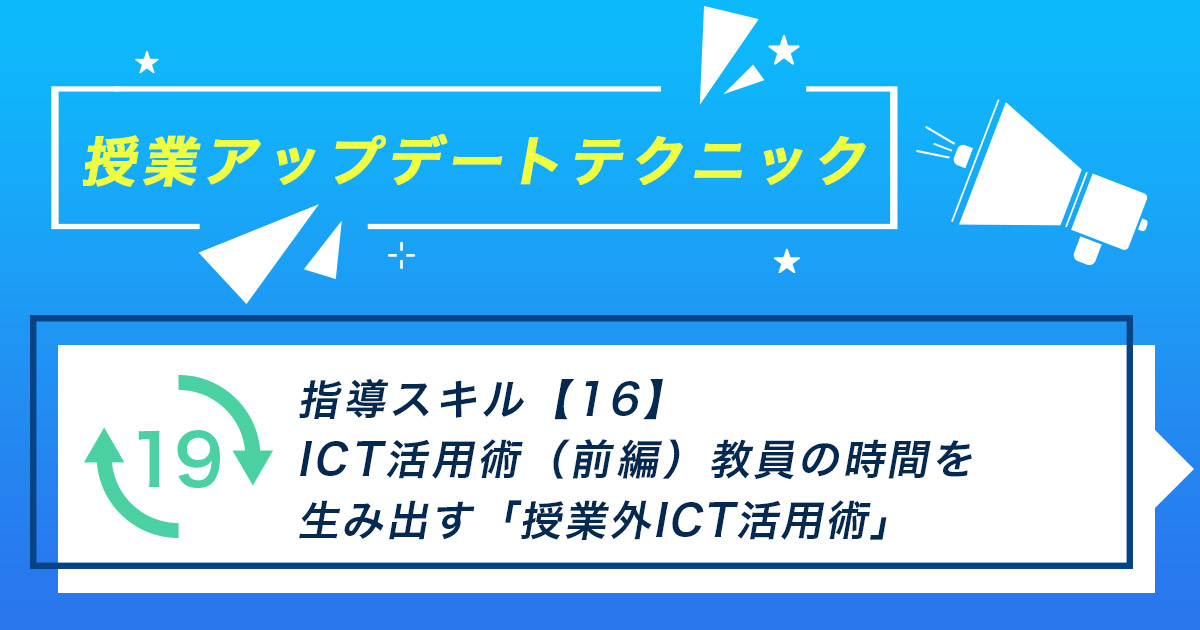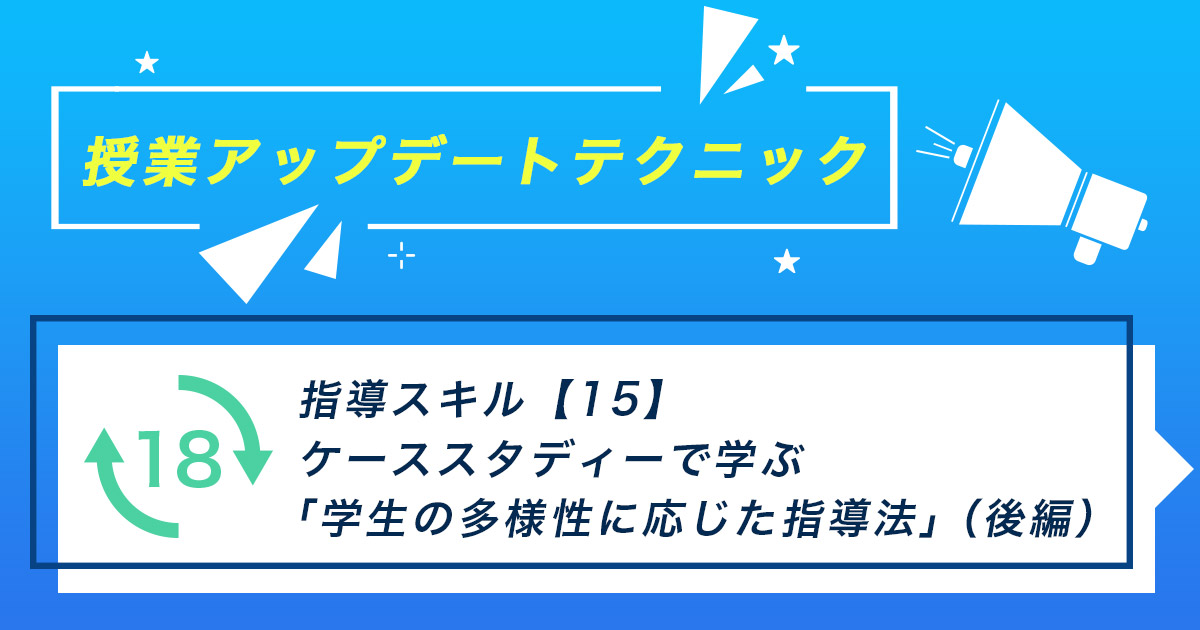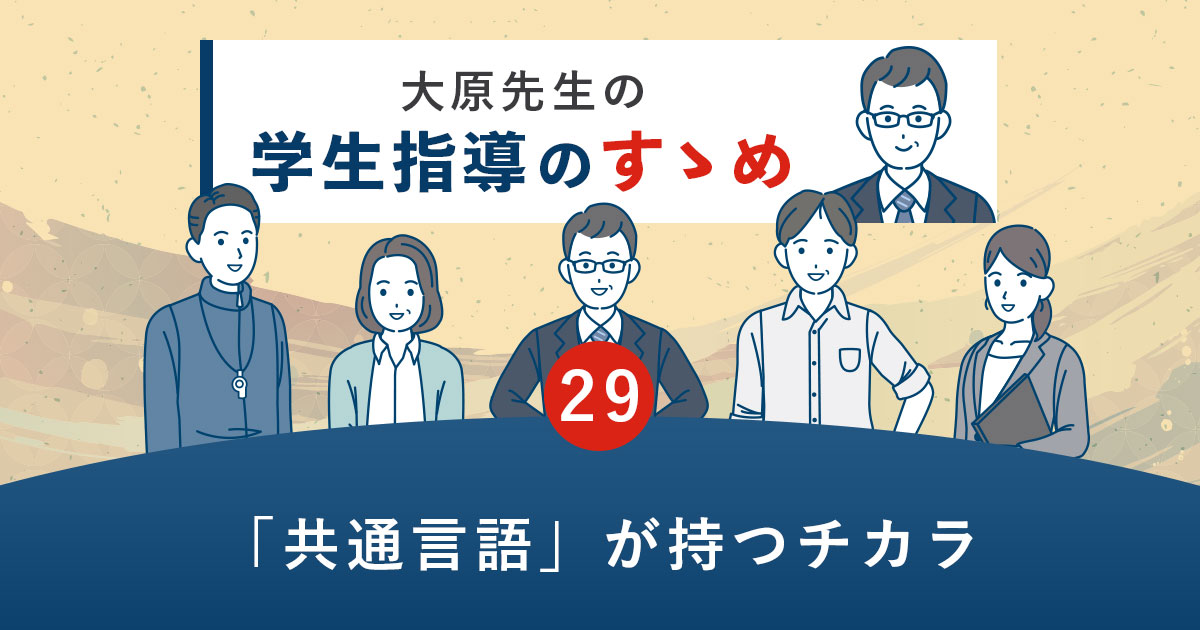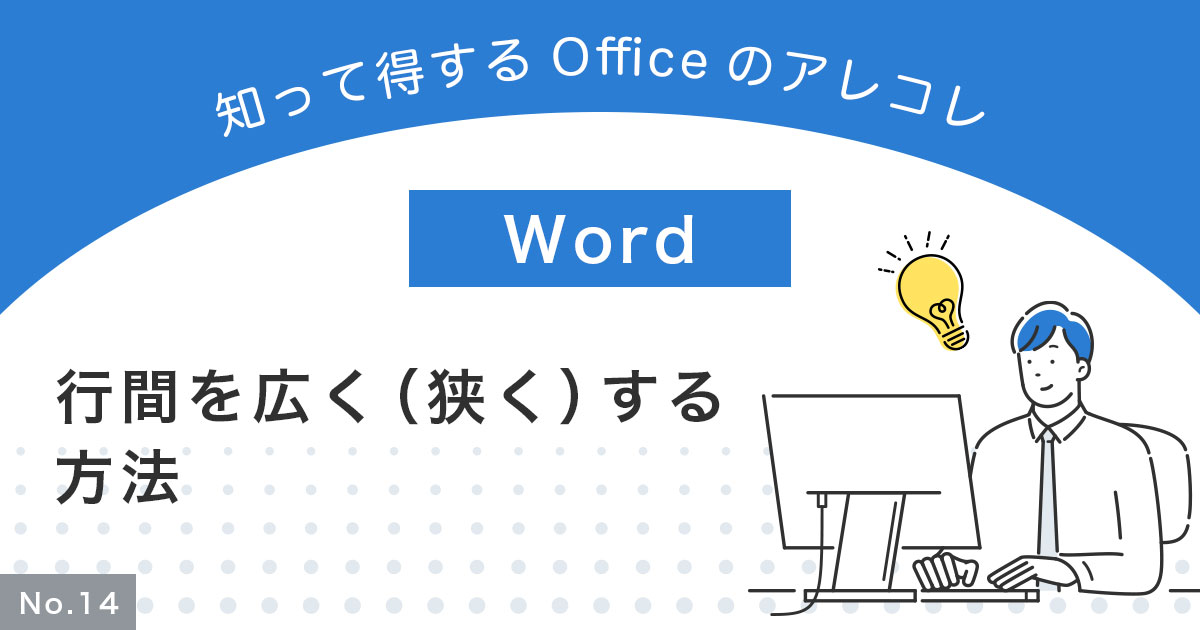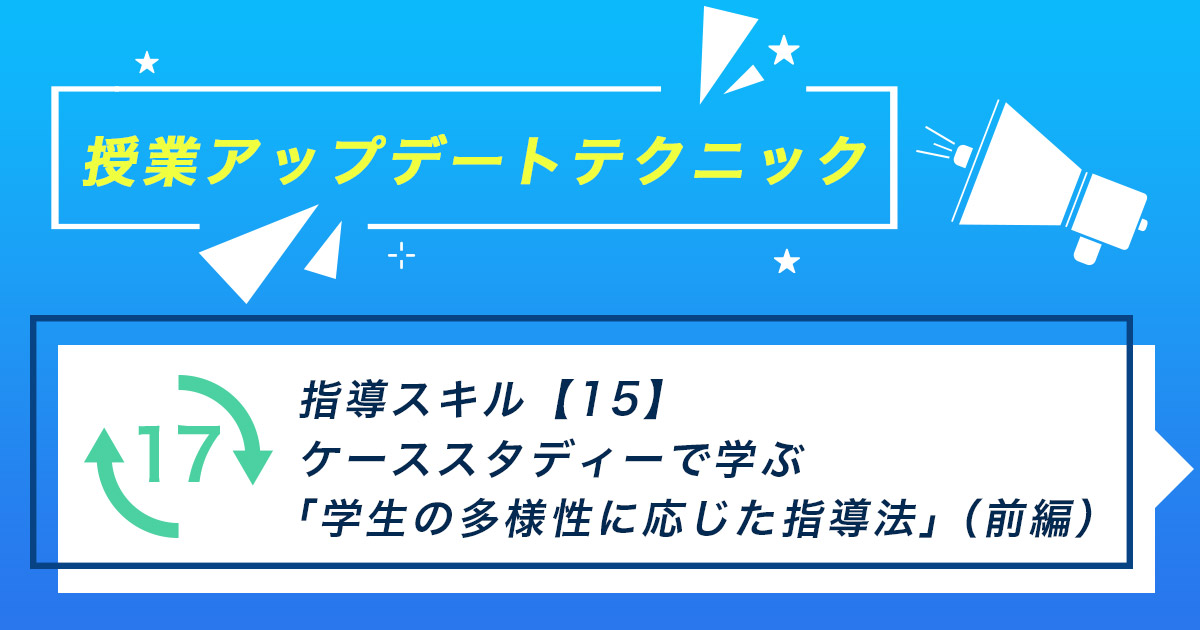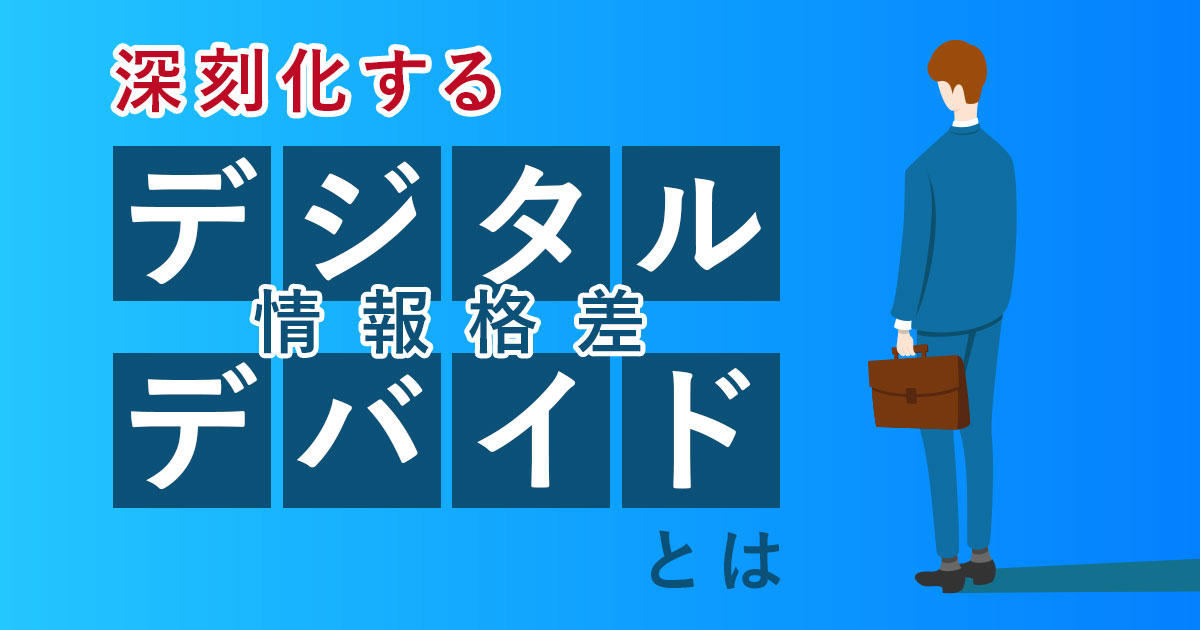
インターネットや情報通信技術(ICT)の発展は目覚ましく、私たちの生活に不可欠なものとなりました。教育現場でも、タブレットを導入する学校が増えてきていますよね。一方で、新たな問題が深刻化しています。それが「デジタルデバイド(デジタル・ディバイド)」です。
本記事ではデジタルデバイドの意味や発生する原因、問題点を解説します。学校ができる対策にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
デジタルデバイドの意味や種類とは?

耳馴染みのない先生も多いかもしれません。ここでは、意味や種類について解説します。デジタルデバイドとは、情報通信技術を利用できる人とできない人の格差を意味する言葉です。
インターネットやパソコンを使いこなすスキルだけでなく、情報収集能力・情報活用能力・情報発信能力などの側面を含みます。
情報格差とも呼ばれ、社会的な不平等や経済格差につながる恐れも。たとえば就職や行政手続き、経済活動などにおいて、デジタル技術を使いこなせない人が不利な状況に置かれる可能性があるのです。
デジタルデバイドの種類は主に3つ
デジタルデバイドは、大きく3つに分類できます。
- 個人間・集団間
- 地域間
- 国際間
個人間・集団間デジタルデバイドは、年齢・性別・収入・教育レベルなどの違いによって、情報通信技術の利用能力に差が生じるものです。たとえば、高齢者や低所得者層はデジタル端末の使い方に慣れていない場合が多く、情報格差の影響を受けやすい傾向があります。
地域間デジタルデバイドは、都市部と地方部で格差が発生するものです。都市部では高速インターネット回線が普及している一方で、地方部では回線が不安定だったり料金が高かったりといった問題があります。
国際間デジタルデバイドは、先進国と途上国の間で利用環境や利用能力に格差が発生するものです。先進国のインターネット普及率は高いですが、途上国ではインターネット環境が整っていない地域も多く、情報格差が広がっている傾向にあります。
デジタルデバイドが発生する6つの原因

深刻な問題となっているデジタルデバイドですが、発生する原因は主に以下の6つといわれています。
- 教育・学歴格差
- 収入・経済的格差
- 都市部と地方部の差
- 身体的・精神的障がいの有無
- 高齢化
- ITインフラやIT人材の不足
それぞれ解説します。
1.教育・学歴格差
一般的に、高学歴の人ほど情報通信技術に関する知識やスキルを習得する機会が多く、インターネットを積極的に活用する傾向があります。
一方で低学歴の場合は身につける機会が少なく、デジタル技術への苦手意識を持つ人も少なくありません。また、教育機関によっては情報通信技術に関する教育が充分にされていないケースもあり、格差を助長する要因となっています。
2.収入・経済的格差
収入や経済状況も、影響を与える要素です。低所得で金銭的な余裕がないために、インターネット環境の整備が難しいケースも少なくありません。結果的に情報通信技術に触れる機会を得られず、情報格差が生まれてしまいます。
3.都市部と地方部の差
地域によって、情報通信技術へのアクセス環境に大きな差があります。一般的に、都市部では高速インターネット回線が普及しており、スマートフォンなどの端末も広く利用されている状況です。
一方、地方部ではインターネット回線の速度が遅かったり料金が高かったりするケースが多く、デジタル機器の普及率も低い傾向にあります。
4.身体的・精神的障がいの有無
身体的・精神的な障がいを持つ人も、影響を受けやすいといわれています。たとえば視覚障がいを持つ人は、画面上の文字を読むことが難しく、音声読み上げソフトなどの支援ツールが必要です。
しかし、このような支援ツールは充分に普及しているとはいえません。障がいを持つ人が情報通信技術を活用するうえで、大きな壁となっているのが現状です。
5.高齢化
高齢者は情報通信技術に関する知識やスキルが不足している場合が多く、スマートフォンなどの端末操作に苦手意識を持つ人も少なくありません。
また新しい技術を習得する意欲や能力が低下している場合もあり、それがデジタルデバイド解消の妨げとなっています。高齢者向けのIT教育プログラムや、支援サービスが充分に整備されていないことも格差を拡大する要因といえるでしょう。
6.ITインフラやIT人材の不足
たとえば高速なインターネット回線が充分に普及していない地域では、住民がインターネットを利用しにくくなります。結果的に、スキルや知識を習得する機会を得られにくくなるでしょう。
またIT人材が不足している地域では、情報通信技術に関する住民へのサポート体制が整っていないケースも多く、深刻化する要因になります。
デジタルデバイドによって生じる5つの問題点
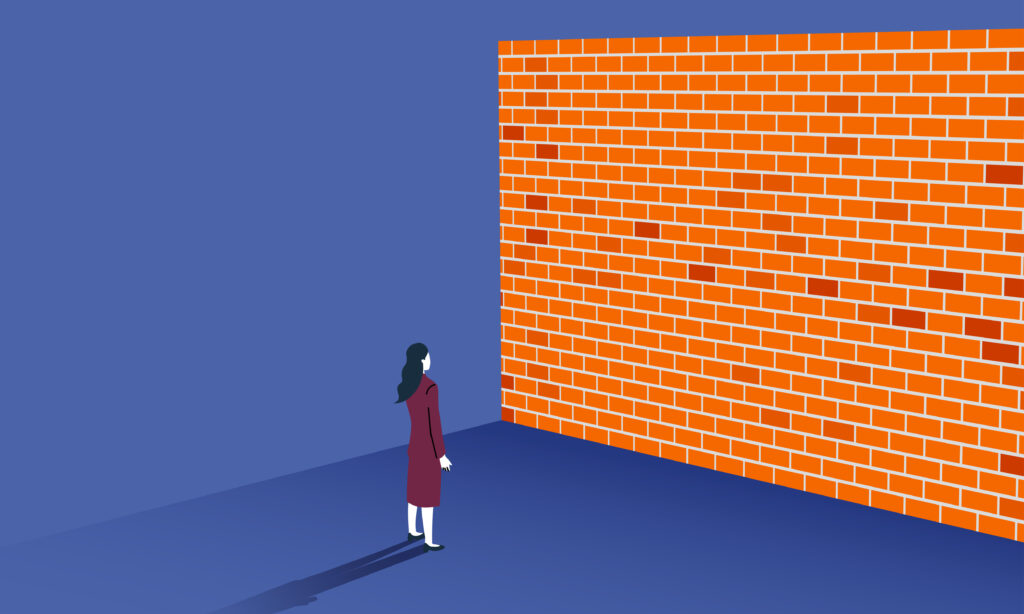
デジタルデバイドの深刻化により、さまざまな問題が発生する恐れがあります。主な問題点は以下の5つです。
- 優秀な人材が育たない
- セキュリティリスクが高まる
- トラブルに巻き込まれるリスクの増加
- IT人材の流出
- 孤立する高齢者の増加
それぞれ解説します。
1.優秀な人材が育たない
デジタルデバイドは、優秀な人材の育成を妨げる要因になります。現代社会において、情報通信技術は多くの分野で必要不可欠なスキルです。
特に、注目を集めている人工知能(AI)やビッグデータなどの分野では、情報通信技術に関する高度な知識やスキルが求められます。情報格差によって情報通信技術を使いこなせる優秀な人材が不足することは、日本の国際競争力を低下させる原因にもなるでしょう。
2.セキュリティリスクが高まる
デジタル機器の利用に慣れていない人は、サイバーセキュリティに関する知識が不足しがちです。そのため、ウイルス感染や情報漏洩などのリスクも高まるでしょう。
企業においてもテレワークの普及に伴い、今まで以上にセキュリティ対策が重要な課題となっています。デジタルデバイドの解消は、サイバーセキュリティ強化にも大きな影響を及ぼすでしょう。
3.トラブルに巻き込まれるリスクの増加
近年、インターネットに関連した悪質な犯罪が増えています。デジタル機器の扱いに慣れていない人はITリテラシーが低いケースも多く、詐欺などのトラブルに巻き込まれるリスクが高いでしょう。
たとえば架空請求や悪徳商法などの被害は、高齢者や低所得者層を中心に深刻な問題となっています。もし学校内でトラブルを発生させてしまった場合、学校の信頼低下にも繋がりかねません。
4.IT人材の流出
インフラの整備やIT支援を促進するためには、企業の取り組みが不可欠です。しかし日本のIT業界は常に人材不足であり、思うように情報格差を埋める政策を進められない企業もあります。
さらに情報通信技術に精通した人材は世界中から需要があり、好条件かつスキルを発揮できる海外企業への転職を検討する人も少なくありません。結果的に優秀な人材が流出し、より格差が広がる懸念があります。
5.孤立する高齢者の増加
近年、シニア世代のスマートフォン利用率は向上していますが、今でもデジタル機器を利用できない高齢者は多く存在します。
情報格差が広がれば行政手続きや買い物などの場面で困りごとを抱え、社会から孤立する高齢者が増えるでしょう。認知症の発見が遅れたり、労働者の介護離職が増加したりするなどの問題につながる恐れもあります。
デジタルデバイドの解消に向けて!学校ができる3つの対策
デジタルデバイドは、社会全体で取り組むべき問題といえます。解消に向けて学校ができる対策は、次の3つです。
- 定期的にIT技術を学ぶ機会を作る
- 授業内で積極的にデジタル機器を取り入れる
- 地域と連携してITに触れるイベントを開催する
それぞれ詳しく解説します。
定期的にIT技術を学ぶ機会を作る
業務中、難しいパソコン操作を得意な先生に頼んでいませんか?それでは情報格差を解消できず、学生への指導も難しいでしょう。まずは、先生全員がIT技術に関して理解を深める必要があります。
少なくとも学校で使っているシステムを全員が使いこなせるよう、定期的に研修を実施しましょう。
授業内で積極的にデジタル機器を取り入れる
教育体制が原因で情報格差を広げないために、授業内で積極的にデジタル機器を取り入れるのがおすすめです。タブレット端末やオンライン教材を取り入れることで、学生が自然と技術を身につけられるでしょう。
ただし、経済的な事情からデジタル機器を持てない学生もいます。そのような学生を取り残さないためにも、可能な範囲で貸し出しを検討するのも方法です。
地域と連携してITに触れるイベントを開催する
地域と連携し、ITに触れるイベントを開催するのも有効です。たとえば地域住民向けのIT教室やスマートフォン体験イベントを開催すれば、地域全体でデジタルデバイド解消に取り組めます。地域に住む高齢者の孤立を防ぐ効果も期待できるでしょう。
さまざまな年齢の人と交流できるようにすれば、学生の社会性を養うきっかけにもなります。就職活動の一環として、IT企業とコラボするのもよいかもしれません。
情報の追い過ぎに注意!デジタルデトックスも取り入れよう
デジタルデトックスとは、デジタル機器と物理的に距離を置いて疲労やストレスを軽減しようという取り組みのこと。矛盾しているようですが、ときには「デジタルデトックス」も大切です。
常にデジタル機器を使って情報を追い求める状態では、心身への負担が大きくなります。健全にデジタルと付き合っていくためにも、定期的に取り入れるよう意識しましょう。
デジタルデトックスについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:疲れた脳に体にデジタルデトックスのすすめ!やり方やメリットを解説
まとめ
デジタルデバイドは個人だけではなく、社会全体の問題として深刻になりつつあります。学生がデジタル技術に関して充分な教育を受けられなければ、将来の選択肢を狭めることにもなりかねません。学校側でできる対策を取り入れ、デジタルデバイド解消を目指しましょう。
\ぜひ投票お願いします/
佐藤 なおか
移住により新潟で活動するWebライター
趣味は飲み歩き(ビール好き)とドライブ