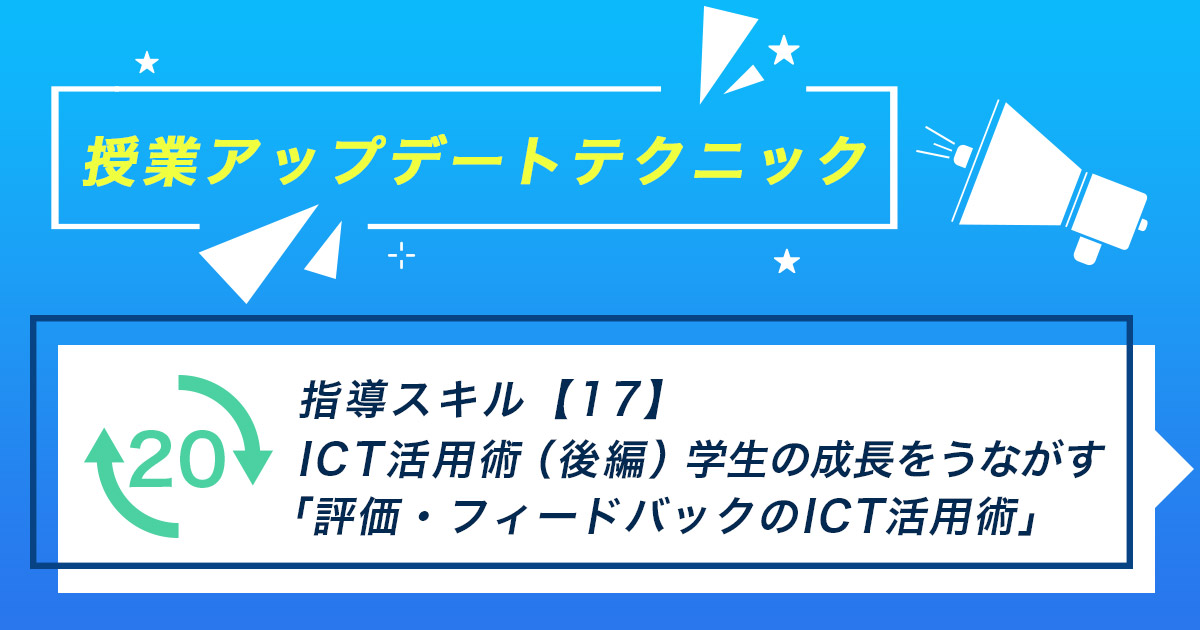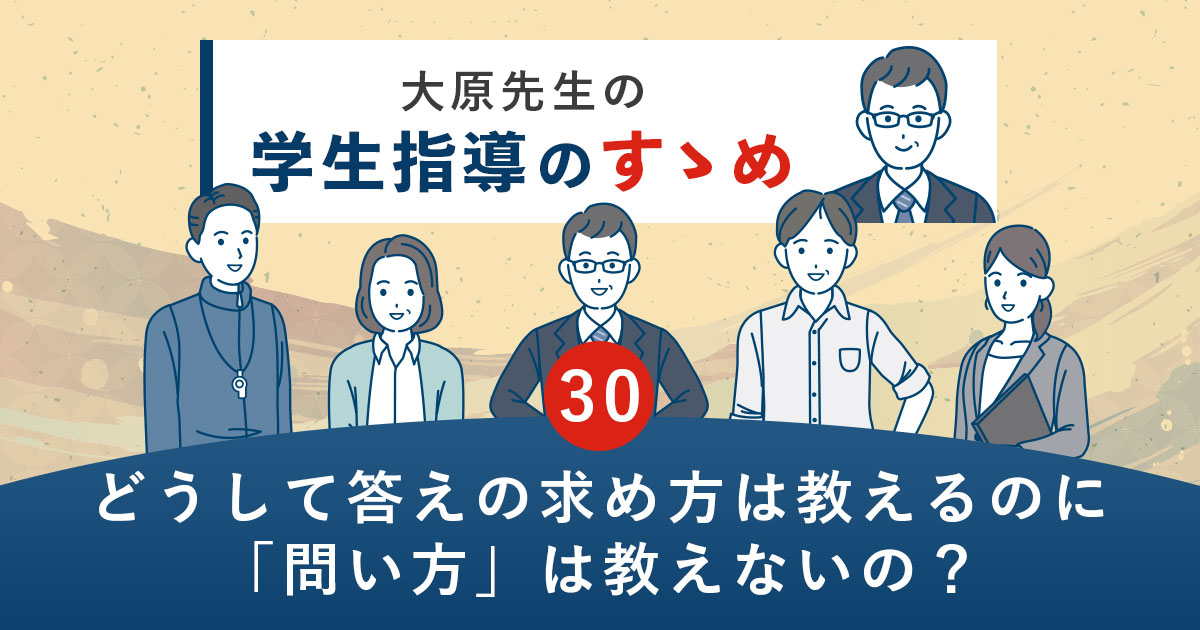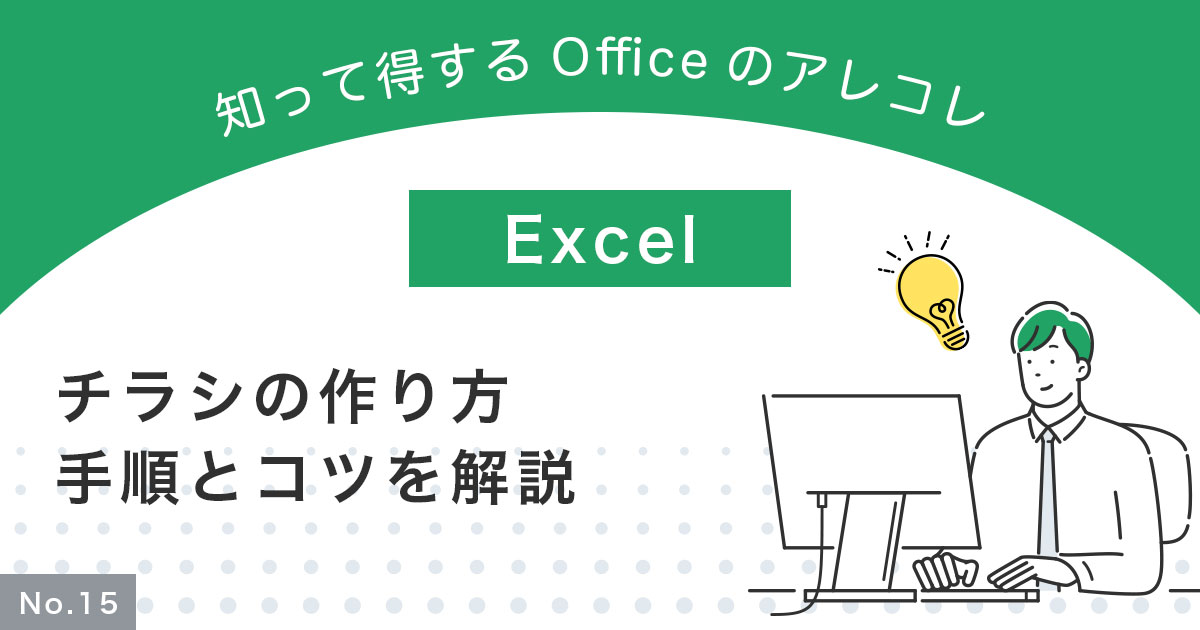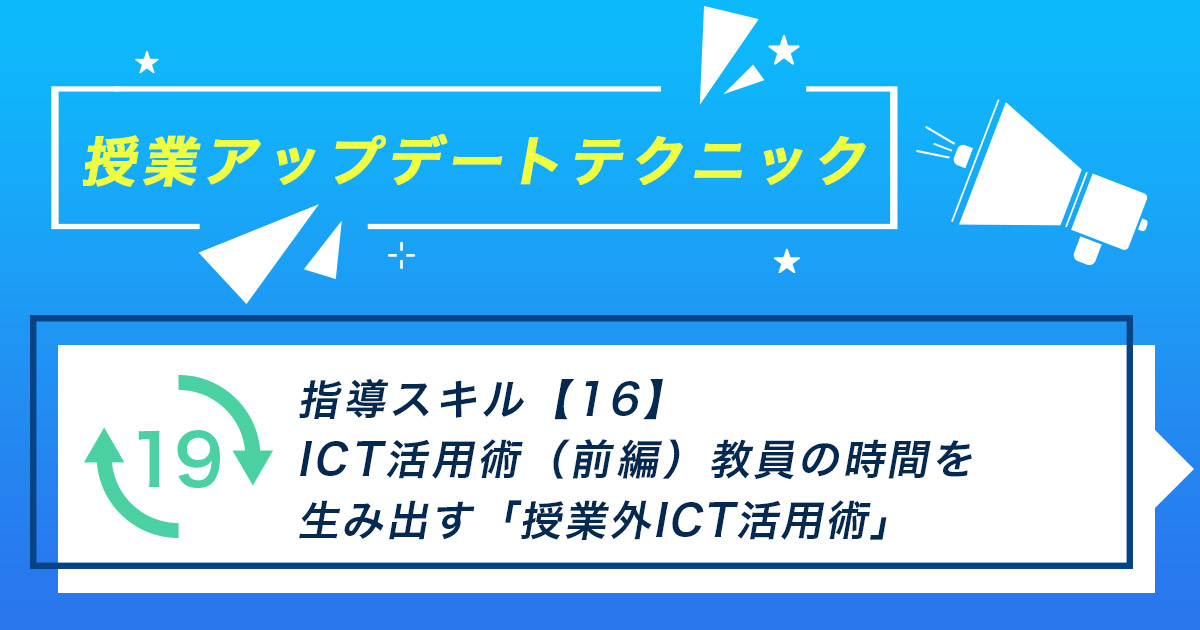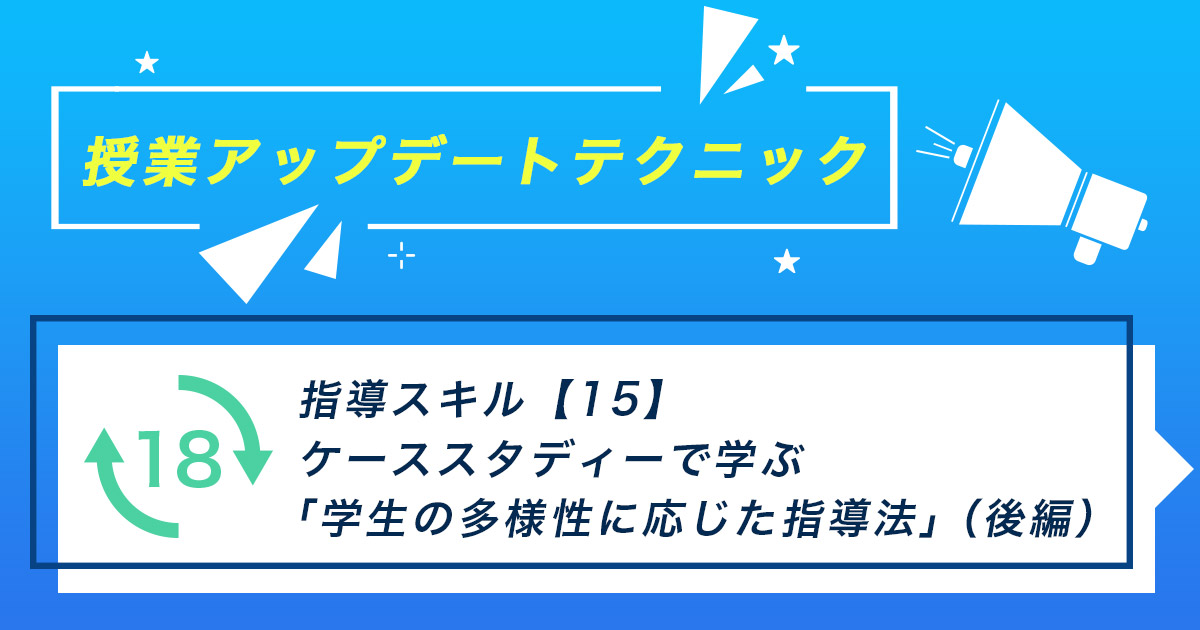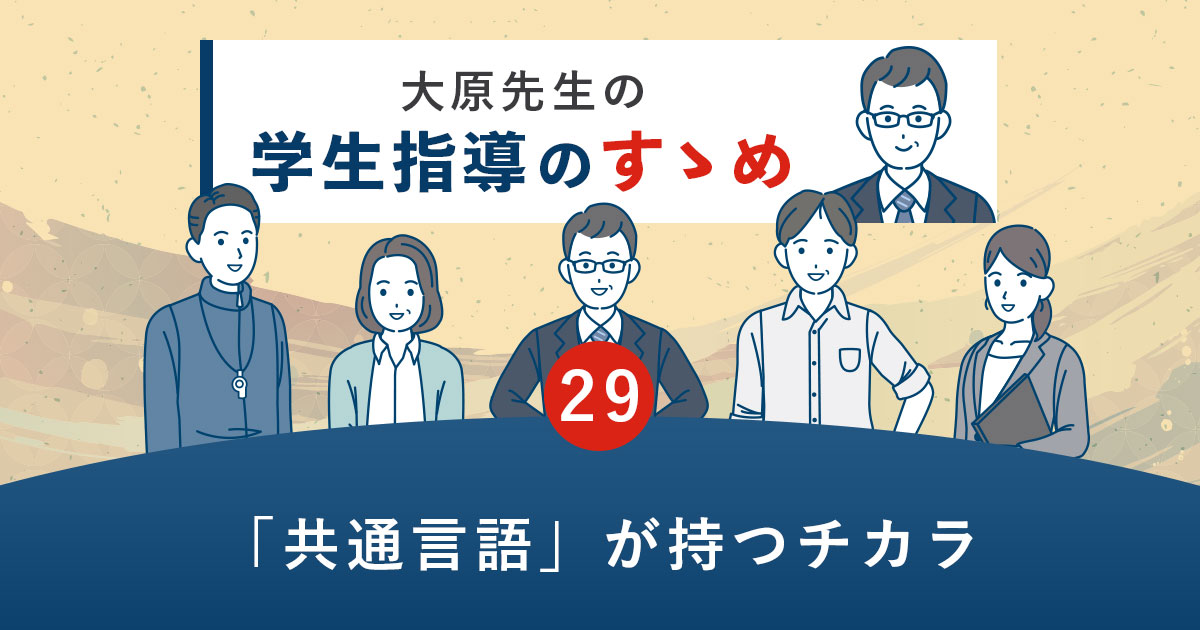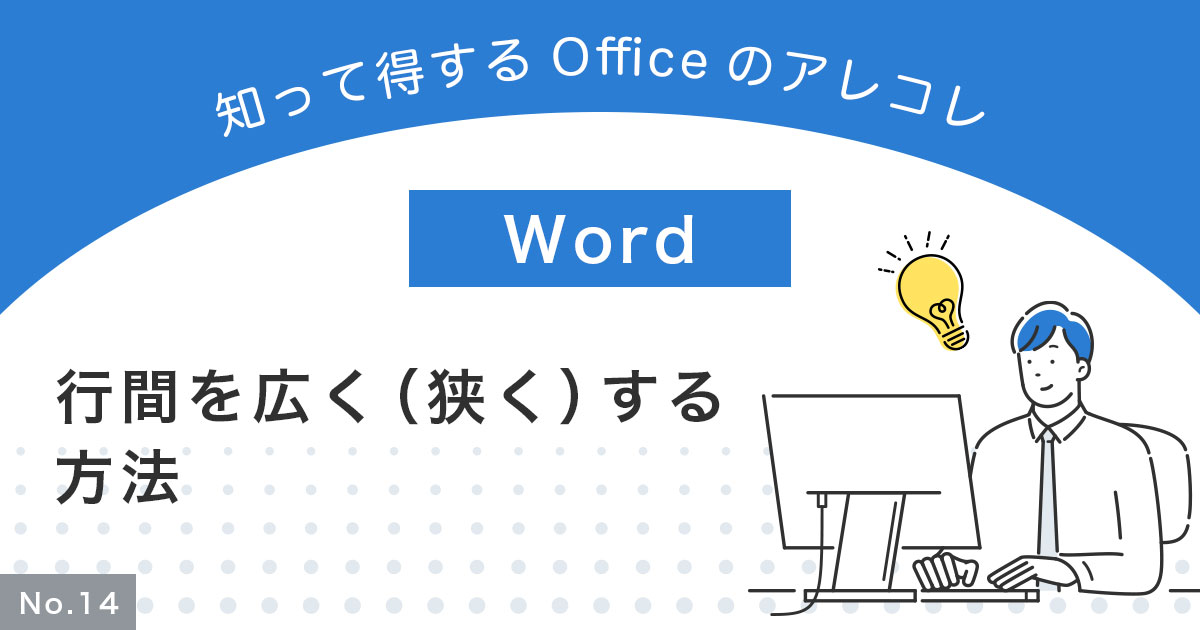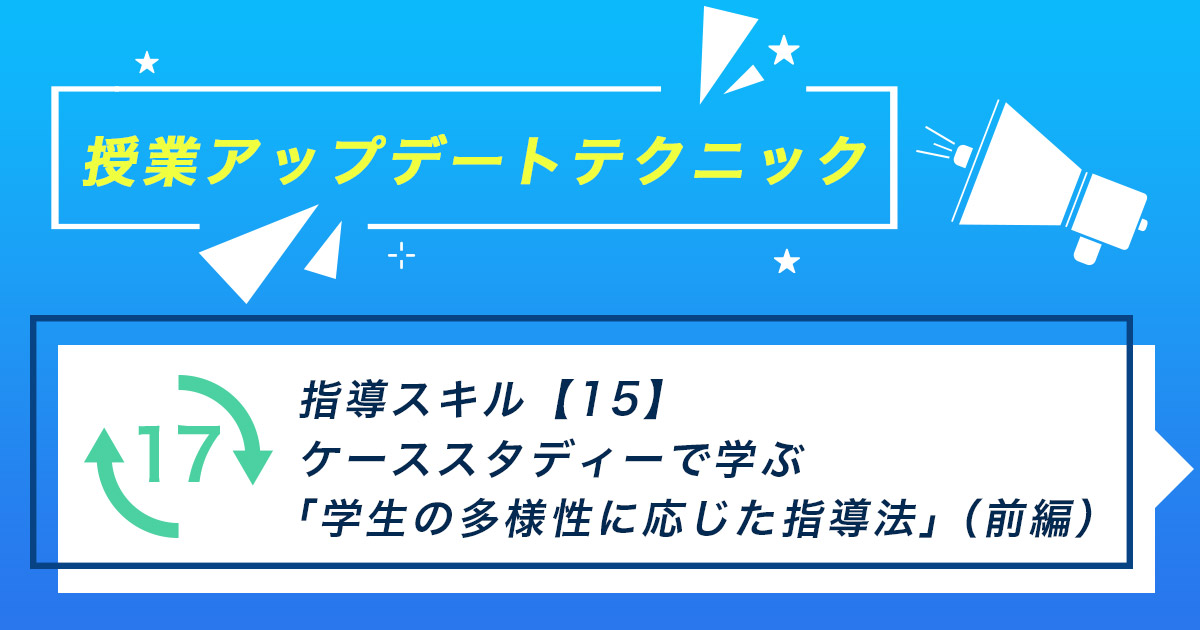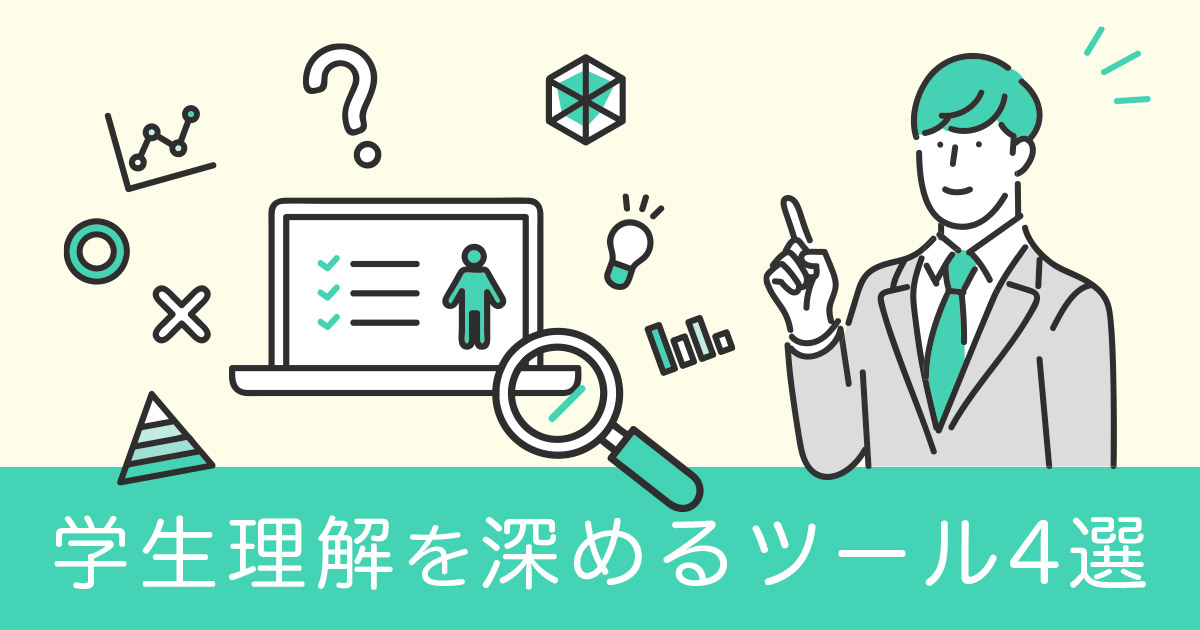
資格取得や就職活動など、やるべきことが多い専門学生にとって、高いモチベーションを維持し続けるのは難しいもの。学校側のサポートが不可欠といえるでしょう。しかし目に見えない要素のため、対応に苦労している先生も多いのではないでしょうか。
そこで効果的なのが、性格診断ツールの導入です。本記事では、性格診断ツールを活用するメリットやおすすめツールを4つ紹介します。活用時のポイントも併せて解説しているので、学生理解を深めたいと考えている先生は参考にしてください。
おすすめの資料

【中退防止】今すぐ使える!モチベーション低下対策チェックリスト
目次
性格診断ツールとは?

性格診断ツールは資質や特性、モチベーションを「見える化」できるツールのことです。アンケートや質問に回答することで性格や特徴を数値化したり、タイプ分けしたりできます。
教育現場では、学生の心理状態や行動特性を理解するための補助ツールとして活用されており、学生指導やモチベーションの改善・向上に役立ちます。なお、企業でも従業員の配属先選定やモチベーション維持・向上を目的として取り入れられているようです。
性格診断ツールを導入するメリット3つ
専門学校で性格診断ツールを導入する主なメリットは、次の3つです。
- 学生の状況を可視化できる
- 適切なフォローができる
- 課題の早期発見に繋がる
それぞれ詳しく解説します。
学生の状況を可視化できる
従来の学生指導やモチベーション管理は先生の感覚や経験に頼るケースも多く、客観的な把握が困難でした。経験が浅いと特に難しく、たびたび学生対応に頭を悩ませる先生も。
性格診断ツールの導入により、学生一人ひとりの性格特性や行動傾向を可視化でき、クラス全体の傾向を把握することも可能です。たとえば、全体的に協調性が高い傾向にあるとわかれば、グループワークを多く取り入れた授業設計が有効だと判断できるでしょう。先生同士の情報共有もスムーズになり、学生への支援体制も整えやすくなります。
また、学生自身も自分の内面や現状を可視化できるため、自己理解を深める機会となるでしょう。どのような状況なのか自己分析できれば、モチベーション管理だけでなく就職活動にも役立ちます。
適切なフォローができる
目に見えない部分を可視化できれば、今まで以上に適切なフォローが可能です。たとえば完璧主義の傾向が強い学生がなにかを失敗した際には、すぐに励まし、失敗から学ぶことの大切さを伝えるなどして、自信を持てるようサポートできるでしょう。
また学生のストレスレベルを可視化できれば、学校生活に対する不安や悩みの早期発見にも繋がります。個別面談や進路指導時にも、学生の状態に寄り添った対応が可能です。
課題の早期発見に繋がる
学校生活への満足度を把握し、より良い学習環境を提供するための改善策を立てやすくなるのもメリットです。たとえば、クラス全体がモチベーション低下傾向にあるとわかれば、授業の流れや仕組みに課題が隠れているかもしれません。
結果を基に素早く対処することで、学生の満足度向上やモチベーションの早期回復に繋がります。退学防止の効果も期待できるでしょう。
退学防止への対策については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事: 学生の退学を防止するために学校ができる対策とは?取り組み事例も紹介
学生の状況把握やモチベーション管理に役立つ!おすすめツール4選

性格診断ツールは多く開発されていますが、ここでは学生対応におすすめのツールを4つ紹介します。
- Q-U
- YG検査
- エゴグラム
- サカセルラボ
それぞれの特徴を見ていきましょう。
1.Q-U
Q-U(Questionnaire-Utilities)は、学級集団の状態や個人の意欲、満足度を測定する心理検査です。「学校生活意欲」と「学級満足度」の2つの尺度で構成されており、多くの教育現場で利用されています。たとえば「友人が少なく孤立しているのではないか」「周囲と衝突が増えていないか」などを把握できれば、早期に予防と対策ができるでしょう。
またQ-Uにソーシャルスキル尺度を加えたhyper-QUを活用すれば、コミュニケーション能力や対人関係スキルも把握でき、より学生への理解が深まります。
2.YG検査
官公庁・大手企業の採用試験や人材開発、大学の授業でも利用されている実績ある性格検査がYG検査(矢田部ギルフォード性格検査)です。12の性格特性を測定でき、情緒安定性、社会的外向性、活動性など、多面的な性格特性を評価できます。
心理学者が作成し、学会や論文などで客観的な評価を受けたエビデンスに基づいているため、より深い学生理解が可能となるでしょう。
3.エゴグラム
エゴグラムは、交流分析理論に基づいた性格診断ツールです。「批判的な親(CP)」「養育的な親(NP)」「大人(A)」「自由な子ども(FC)」「順応した子ども(AC)」の5つの自我状態を測定し、性格傾向をグラフ化します。
たとえば専門学校のように実技指導が多い場面では「なぜ、この学生は指示を素直に受け入れないのだろう」と感じるシーンもあるでしょう。エゴグラムで学生の特性を可視化すれば、アプローチ方法を考えるヒントが得られるかもしれません。学生との関わり方を考えるうえで役立つでしょう。ただし、多くのエビデンスに基づいて検証された心理検査と比較すると、妥当性は高いとはいえません。
4.サカセルラボ
サカセルラボは、学生自身の強みや、成長の種を発見するツールです。
本当の自分が見つかる「マイタネ」と、目標管理を通じて自分の成長を記録する「マイノビ」の2つの機能があります。
長期・短期目標の達成支援で学生の成長をサポートする新しいツールです。
性格診断ツールを活用する際のポイント3つ
性格診断ツールの活用は先生の負担軽減に繋がりますが、より効果を得るために3つのポイントを押さえておきましょう。
- 結果に頼りすぎない
- 伝え方に配慮する
- 定期的に実施する
それぞれ解説します。
結果に頼りすぎない
分析結果だけに頼りすぎると、レッテル貼りのようになるリスクがあります。たとえば「この学生は消極的な性格だから」と決めつけてしまうと、内側に眠っている才能や学生が自分の殻を破ろうとしている状況を見逃してしまうかもしれません。大切なのは、1人の人間として向き合う姿勢を持つことです。どんなに精度の高いツールでも、ひとつの判断材料として活用しましょう。
伝え方に配慮する
分析結果に良い悪いはありませんが、伝え方にも注意が必要です。たとえば「あなたは協調性がない」と短所のように指摘すれば、学生が落ち込んでしまうかもしれません。
このような場合、学生の良い部分もセットにして伝えるのがポイントです。「問題意識が高く、行動力もあるのはすごいことだよ。ただ大勢で行動しなければならないケースでは、もう少し周囲に配慮できるようになると、さらにあなたの強みが活かされるよ。」のように伝えることで、学生のモチベーションを維持しやすくなるでしょう。そのような意味でも結果に頼りすぎず、学生本人を観察していくことが大切です。
定期的に実施する
学生の状況は時間と共に変化します。入学当初はモチベーションが高かった学生も、日々を過ごすうちにストレスが溜まり、半年後にはやる気をなくしているかもしれません。学生の変化を見逃さないためにも、診断ツールを使った検査は定期的に実施するのがおすすめです。継続実施によって最新の状況を把握でき、素早く適切な対応ができるでしょう。
まとめ
学生一人ひとりの特性を把握しやすくなる性格診断ツールは、最適なフォローや指導計画を立てるうえで役立ちます。学生対応の負担軽減にも繋がるでしょう。ただし、結果だけに頼りすぎるのはNGです。ツールの特徴を理解して適切に活用できれば、より充実した支援の実現を目指せます。
おすすめの資料

【中退防止】今すぐ使える!モチベーション低下対策チェックリスト
\ぜひ投票お願いします/
株式会社ウイネット
ウイナレッジを運営している出版社。
全国の専門学校、大学、職業訓練校、PCスクール等教育機関向けに教材を制作・販売しています。