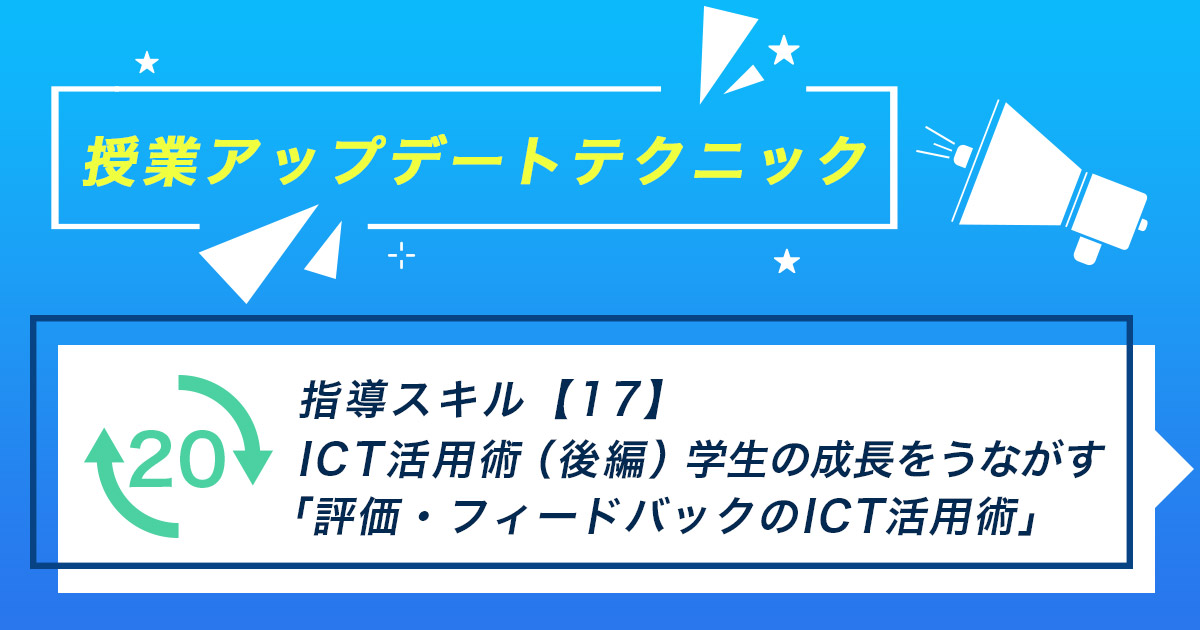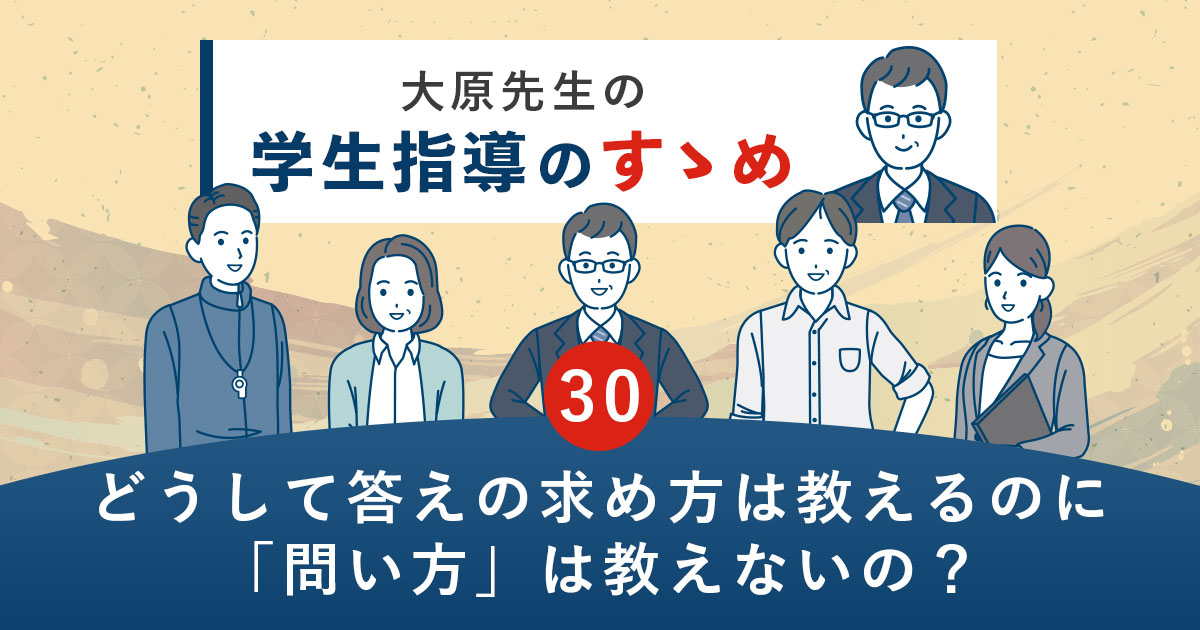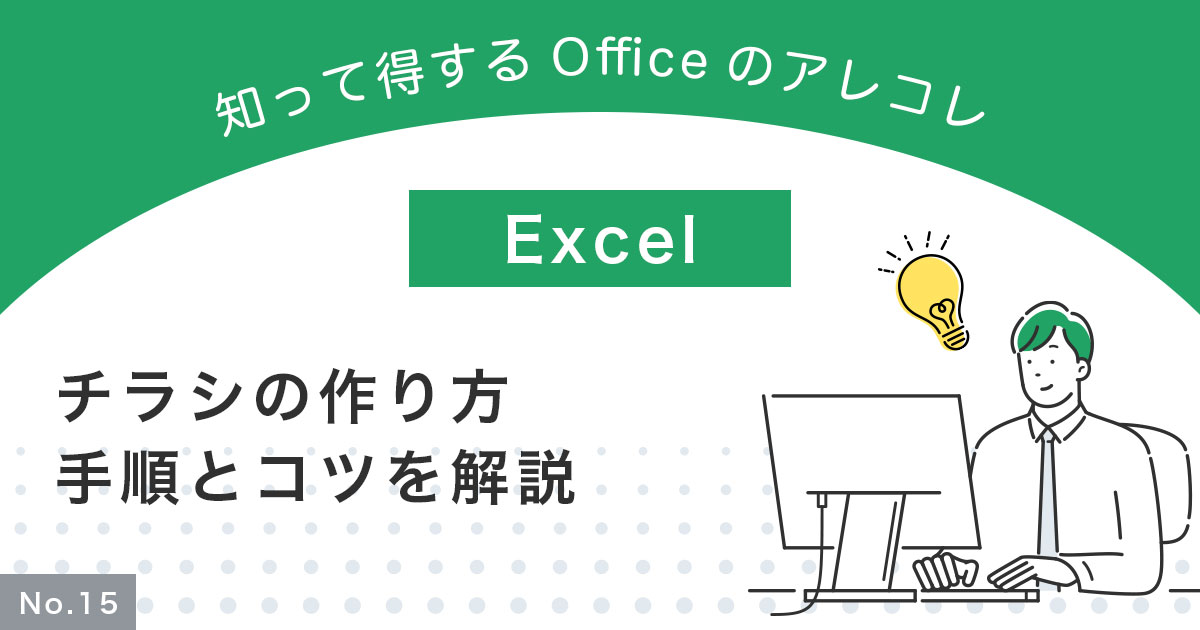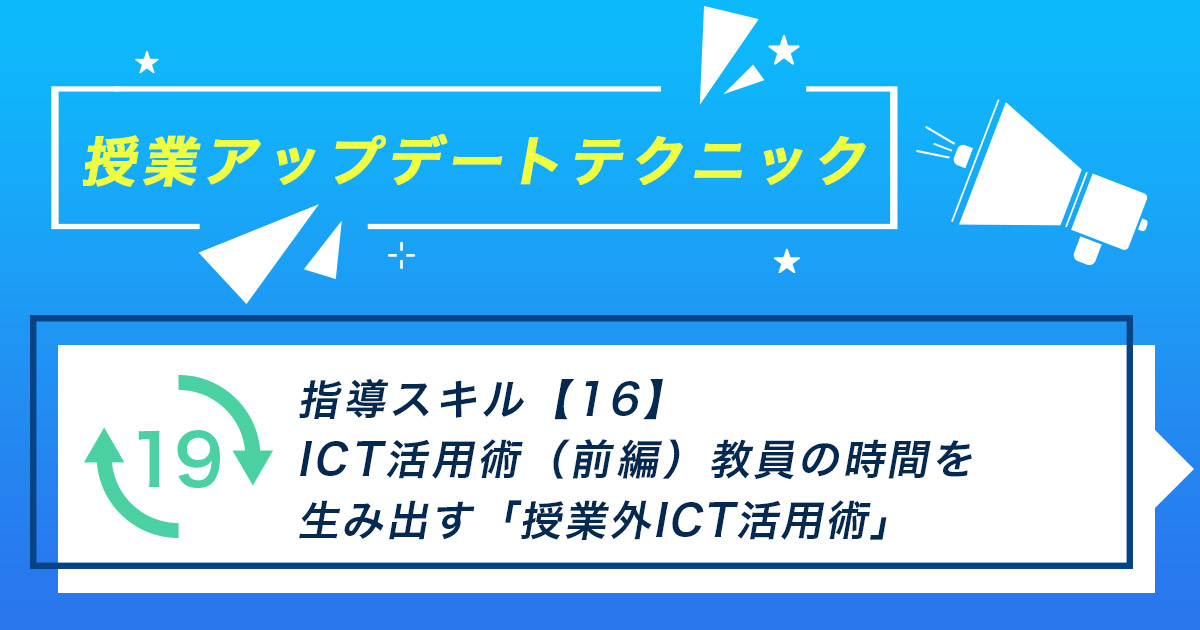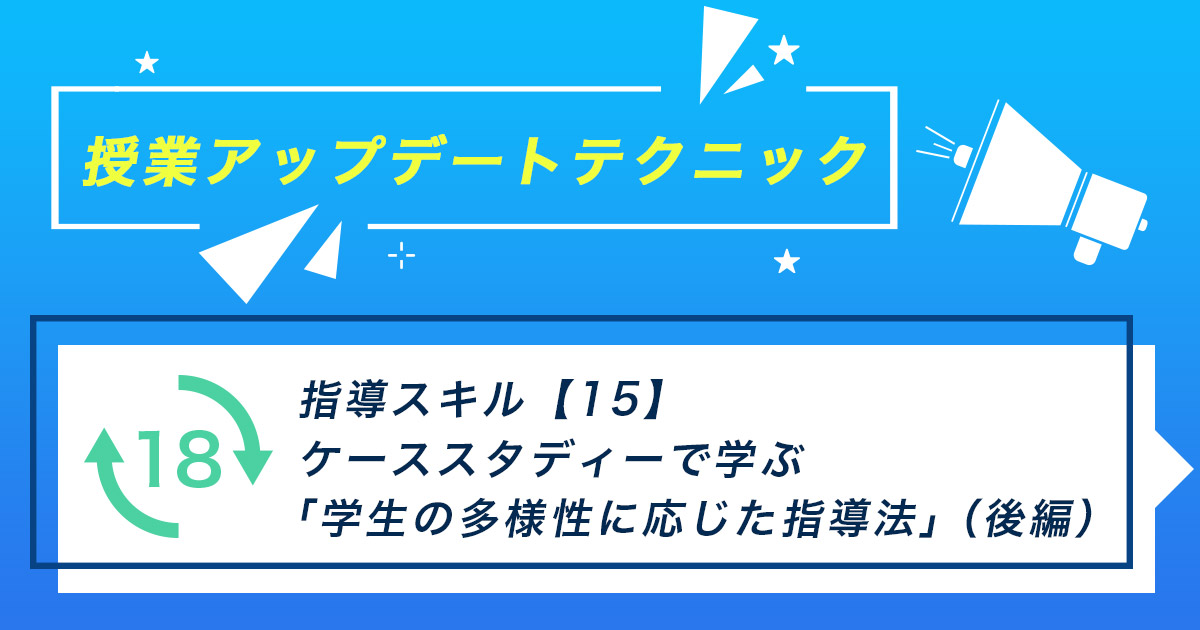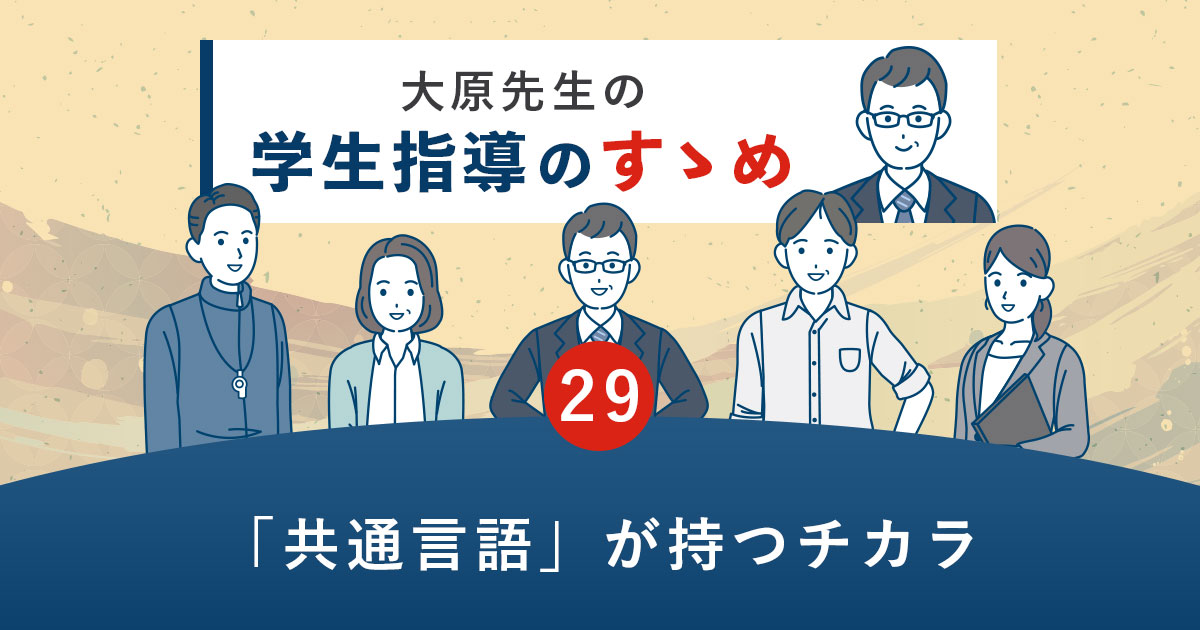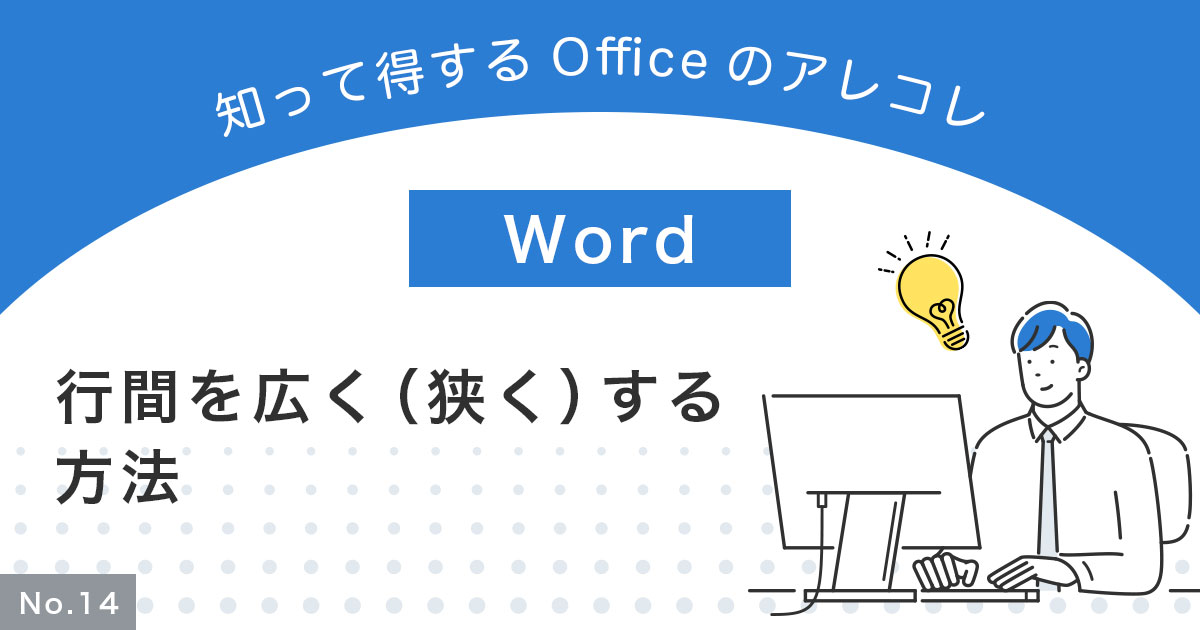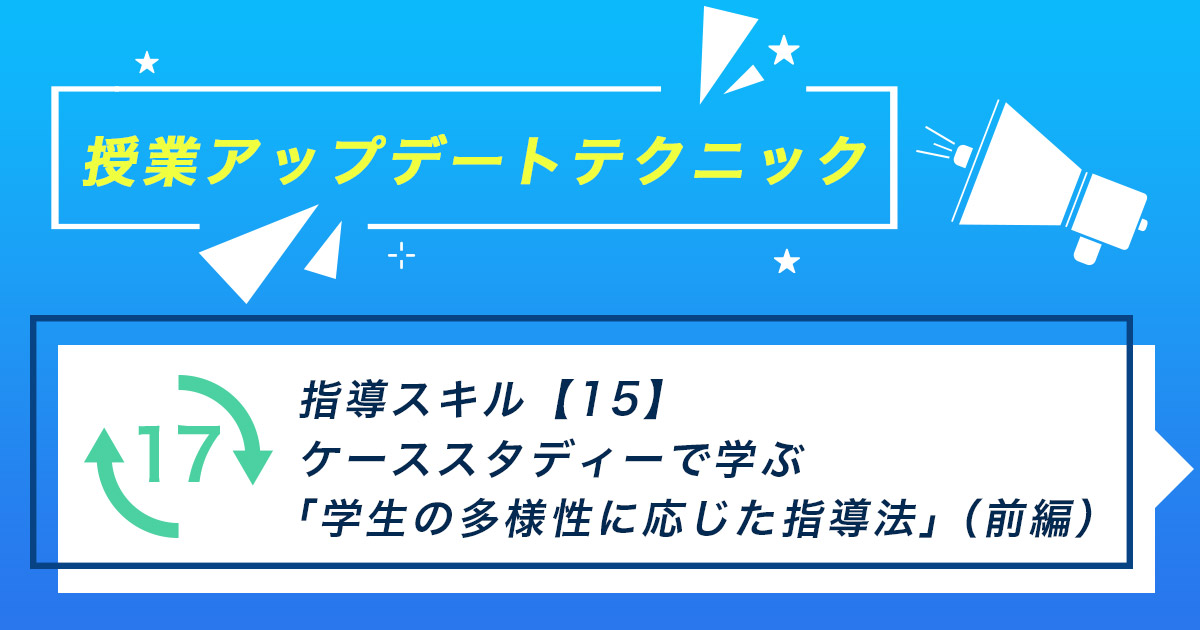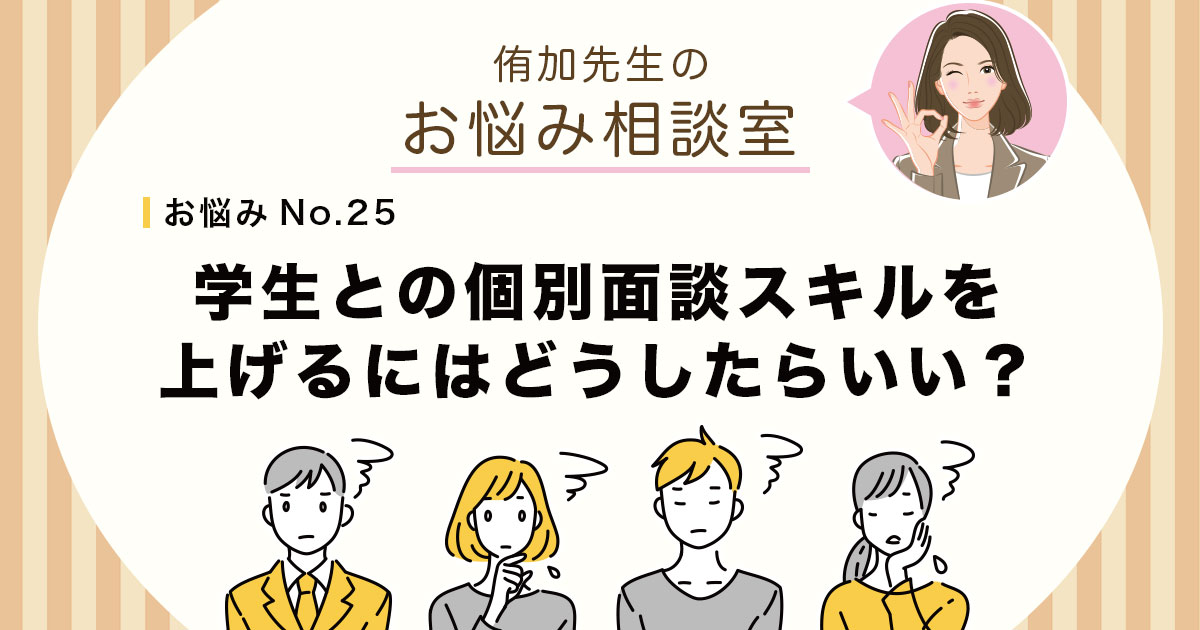
連載侑加先生のお悩み相談室
先生に特有のお悩みから、ワークライフバランス、キャリアデザインまで。「他の学校はどうなんだろう、他の先生はどう考えているんだろう……」と思ったら、学校の現場にも詳しい侑加先生に相談してみませんか?
\あなたのお悩みも相談してみませんか?/
今回は、「学生との面談スキル」についてのお悩みです。
多くの学校様において、入学直後や長期休み明けのタイミングで、学生と個別面談をする機会があるのではないでしょうか。面談は、1人1人の学生を深く理解することができる絶好のチャンスですが、思うような対話ができず、消化不良で終わってしまった経験も中にはあるかと思います。
学生にオープンな心で想いを素直に語ってもらうためにはどうしたらよいのでしょうか?
……侑加先生に聞いてみましょう!
目次
【今回のお悩み】学生との個別面談スキルを上げるにはどうしたらいい?
相談者:堀口先生(仮名)(男性・30代前半)
私はIT・Web・CG系の専門学校で教員をしています。
クラス担任もしており、年に数回クラスの学生全員と個別面談をする機会があります。
教員になりたての頃は正直何をしてよいかわからず、個別面談に対して苦手意識を持っていましたが、最近は少し慣れてきました。
個別面談は先生の確認のための場ではなく、双方にとっての信頼関係構築の場としたいと考えています。特に入学直後の初回面談は重要な時間だと思いますが、まだお互いの理解が不十分なため探り探りとなってしまいがちです。
学生のためにもっと面談スキルを向上させたいと思っているのですが、何か意識するポイントや、日々の業務でできることはありますでしょうか?
面談では学生が主役となり、色々な想いを話してもらいたいのですが、時には私がしゃべりすぎてしまい、学習状況の進捗確認のような場となり反省することがあります。
学生にとって話しやすい雰囲気作りも含めてぜひアドバイスをいただけると幸いです。
以上が今回のお悩みです。
それでは侑加先生の回答をご覧ください!
18歳の学生と30代前半の先生、受けた教育やコミュニケーション手法が違います
堀口先生、お悩みをお寄せいただき、ありがとうございます。
先生は、ITの専門家でいらっしゃるのですね。今の学習指導要領を見ると、小学校で簡単なプログラミング教育の授業があります。中学の「技術・家庭科」では、パソコンスキルやワード・エクセルの実習も行います。高校で「情報」科目を習い、大学入学共通テストでも「情報」の試験を受けます。社会の需要に追いつけるように、ますます存在感を増す分野ですね。
学生の皆さんの中には、高校卒業までに、簡単なゲームやアプリを開発した人がいるかもしれません。将来有望な若い皆さんとの毎日は、刺激的だと思います。
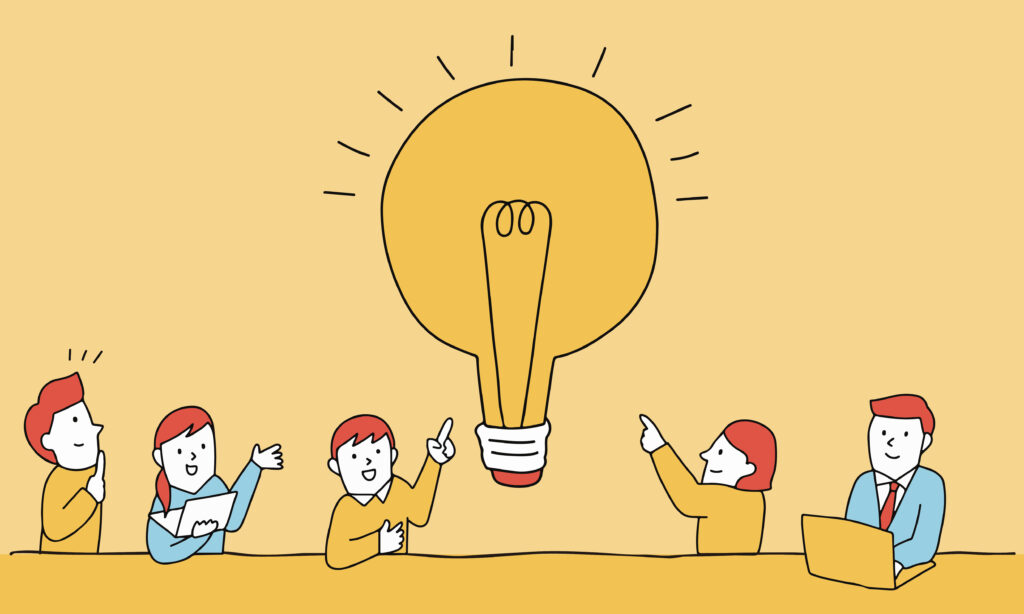
先日、会社の研修で、管理職の方からこのような話を聞きました。
「若手社員が、簡単に一言、口で言ってくれれば済むのに、わざわざメールしてくる。その場にいるんだよ。」
20代の方にとって、メールやLINEでやり取りする方が、口に出して会話するより、簡単ということなのでしょう。
一方、上司の側からすると、話の内容だけでなく、話す様子から雰囲気もつかめるのだから、その場にいるのなら、顔を見て話すのが普通だという感覚があるのですね。よくある世代間ギャップだと思います。
こうした感情面での行き違いが重なると、信頼関係を築くのも難しくなるのではないでしょうか。
IT系の学生は、口で会話するよりも、メールやLINE、チャットでの会話を好むかもしれませんね。2020年のコロナ禍に入る前から、会社の新人研修では「今時の新人は、伝わっているのか、伝わっていないのか、無表情でよく分からない、反応が薄い」と人事部の方からよく聞きました。
コロナ禍の5年間で、それが加速したようです。マスク着用中は、顔の表情筋は動きづらいです。オンデマンド授業の画面を、無表情で見ながら受講する、電話ではなくチャットで相談するなど、人間対人間の生身の関わりが随分減りました。
30代前半の堀口先生が小学生の頃は、スマホは持たず、プログラミングの授業もありませんでしたよね。
家族や友達との会話も、対面か電話が中心でした。婚礼や葬儀では親戚も多く参列する慣習があったと思います。合唱コンクールで歌ったり、チームスポーツを経験したり、同級生、先輩や後輩、地域の人々と関わる中で、自然にコミュニケーション力がつくということがありました。上手くいくことばかりでなく、もめ事やケンカも経験しながら、その時々で、対処方法を習得してきました。
今の時代は、親戚が一堂に会するイベントやクラス全体で参加する学校行事も減り、タブレットを操作する学習が増えました。世の中全体を見渡してみても、一人暮らし世帯が一番多く、一人カラオケや一人焼肉、お一人様旅行などが流行っているようです。
4月入学時点から、信頼関係の構築を日々心掛け、初回の面談日を迎えたいですね

18歳の学生にとって、堀口先生は、専門学校で初めて出会う大人で、緊張もするでしょう。先生の側はいかがですか。
オープンキャンパスに来てくれた学生を覚えていますか。入試や面接試験で会った学生の名前と顔を一致させることができますか。事前に個人の写真やプロフィールを受け取っていると思いますから、できるだけ名前と顔を覚えて入学式を迎えたいですね。
先生が緊張していると、学生も緊張します。温かい笑顔で、「あなたの入学を待ち望んでいたよ」と、大歓迎の気持ちを表現しましょう。
『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社、安達裕哉 著)は、コンサルタントとして社長の相談に乗り、課題解決を仕事としてきた著者が「傾聴」の極意やコミュニケーションについてまとめた本です。
「『信頼』が生まれる瞬間」について、次のように述べられています。
では、なぜ社会人1年目の若造が、その道30年の社長の相談役を務めることができたのでしょうか?まず、社長の心情が「この人に任せて大丈夫かな?(ちゃんと考えられるか?)」⇒「優秀だな(ちゃんと考えてるな)」と変わったと考えられます。しかし、“優秀だな”と思っただけで、次の仕事を頼むでしょうか?継続的に仕事をもらい、長期的な関係を築くには、信頼が必要です。信頼が生まれるには、“優秀だな”だけでは足りません。つまり、単なる“頭がいい”だけでは、ただ頭がいいだけで終わってしまい、結果につながらない可能性があるのです。信頼が生まれる瞬間の心情はこうです。“この人、我々のためにちゃんと考えてくれてるな”相手がこの心情になったとき、信頼が生まれ、長期的な関係につながります。
先生は、「初回面談は重要な時間だと思いますが、まだお互いの理解が不十分なため探り探りとなってしまいがち」とおっしゃっていますね。
面談スキルを向上させるのは、大切だと思いますが、一番意識したいのは、学生一人一人の特徴を捉えて、褒めるポイントを探すことではないでしょうか。
初回の面談は、恐らく5月だと思います。4月から、日々の業務の中でも行えることですよね。
受講態度が積極的だったり、提出課題が早かったり、授業に遅れがちな仲間をさりげなくサポートしていたり、決して派手ではないこれらの行為の中に、素晴らしさがあります。それは、きっと本人も気づかない点であり、今までもそんなに褒められていない場合が多いと思います。
高校卒業までは、成績が上がったり、生徒会長を務めたり、大会で優勝したりするなど、誰が見てもすぐに分かる立派な成果が褒められます。そして、それが推薦入試などの進路決定に影響してきました。
口数が少ない人は、大人の中にも大勢います。もっと話してくれないとミーティングにならない、と感じることはよくあります。先生が「面談では学生が主役となり、色々な想いを話してもらいたい」という理想は、とても良いですね。
先生という職業の中には、いつも自分が主役となり、話し過ぎてしまう人がいるようです。相手を主役にする、自分が聞き手に回るというのは、事前の準備や配慮、工夫が必要です。
学生一人一人を把握しようと努め、良い点を言語化して伝えることで、学生は「自分のことをちゃんと見て、考えてくれている。堀口先生と色々話したい、悩んだら相談したいな」という気持ちになるのではないでしょうか。
もし、先生の側がまとまった話をするとしたら、学生の悩みに寄り添えるような、ご自身のちょっと面白い失敗談をユーモアを交えて紹介する程度がいいですね。優秀過ぎる先生には近寄りがたいですから。
学生一人一人を大好きになり、成長を一緒に喜ぶ姿勢を見せていきましょう
30人の学生がいれば、30人分の把握が必要で大変ですが、ここが先生の頑張りどころです。
全体への呼びかけでは、学生は自分事として聞いていません。集団指導塾より個別指導塾が流行っています。
子どもの頃から、ずっと消費者であった学生は、いつも大切にされ、寄り添ってもらう側でした。徐々に働く側のマインドを伝えたいですが、まずは、先生が寄り添ってあげてください。
そして、授業中の課題クリアや検定合格にも、一緒に喜びの感情を表現しましょう。すると、休憩中や授業後にも、学生から声を掛けられるようになるでしょう。信頼関係の上に成り立つコミュニケーション、面談になりますように、心から応援しています!
***
先生のお悩みにズバッと回答!
連載「侑加先生のお悩み相談室」
すべての記事はこちらでご覧いただけます。
***
\あなたのお悩みも相談してみませんか?/
\ぜひ投票お願いします/
侑加先生
一般企業を経て、専門学校に正教員として勤務。
現在は、企業・大学講師、小中学生の塾経営。
趣味は、お笑いと高校野球、旅行。一児の母。