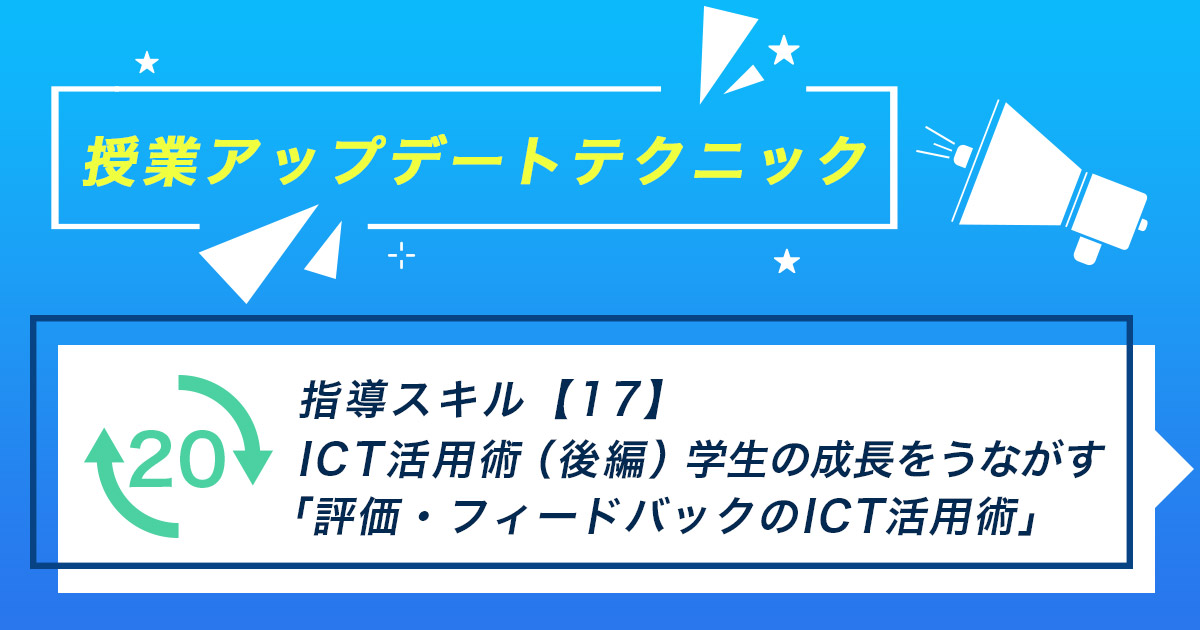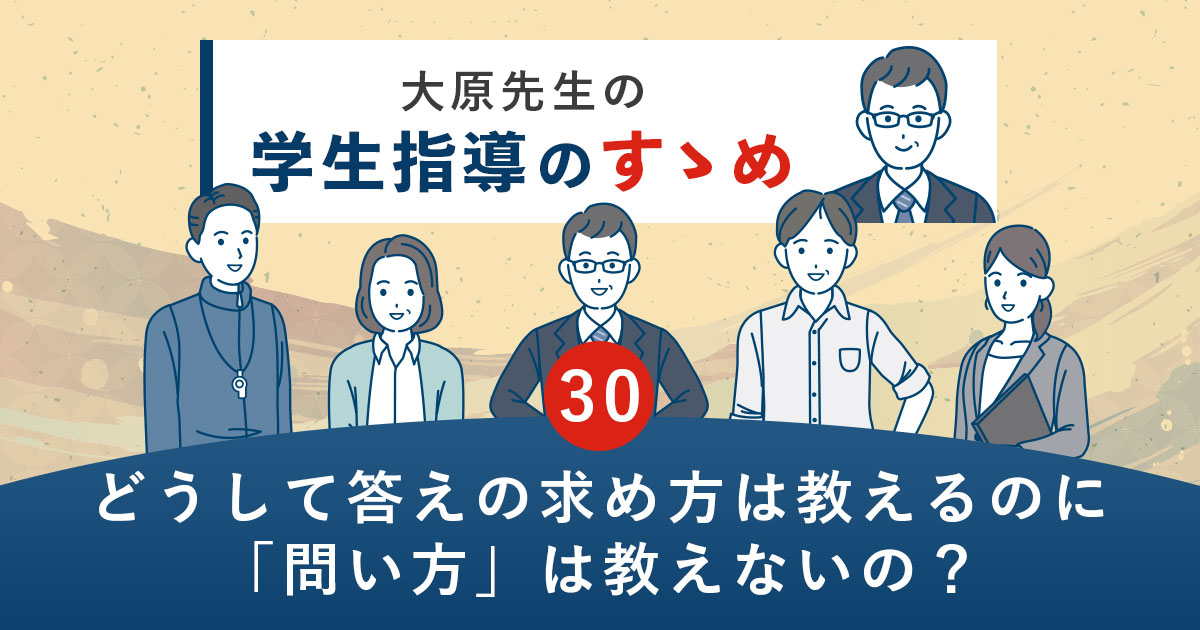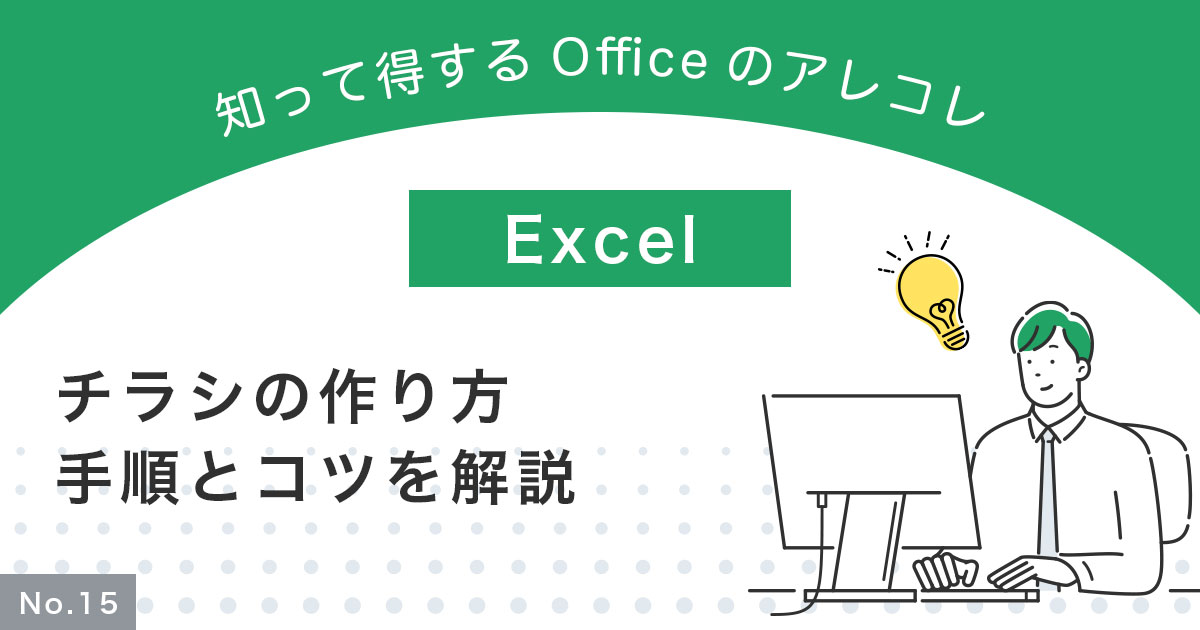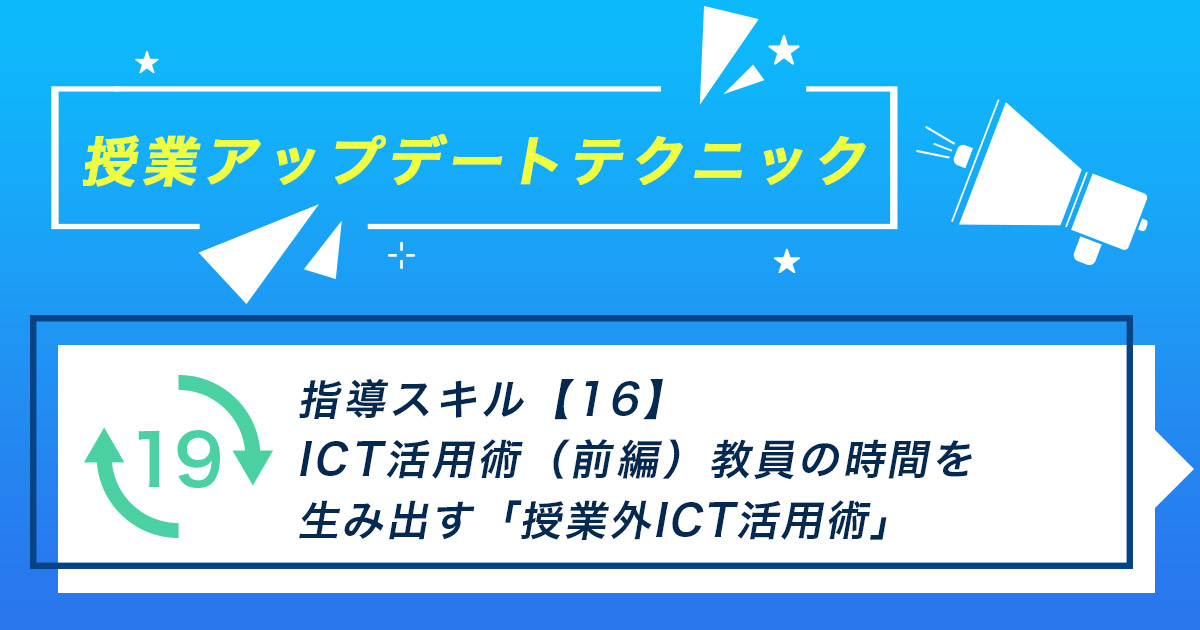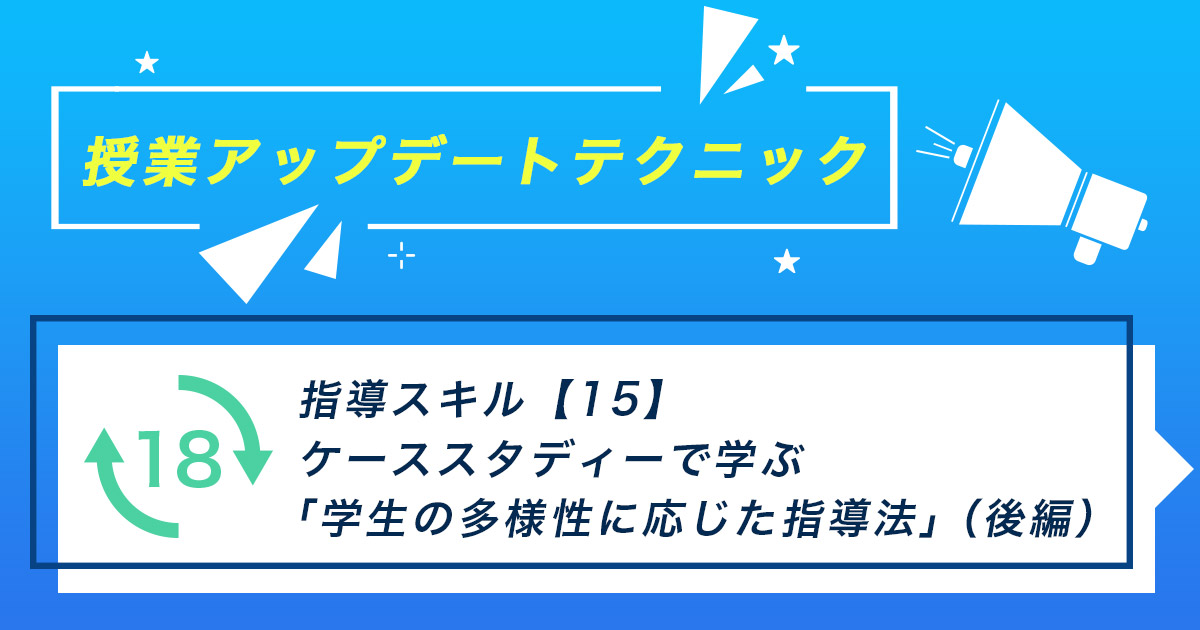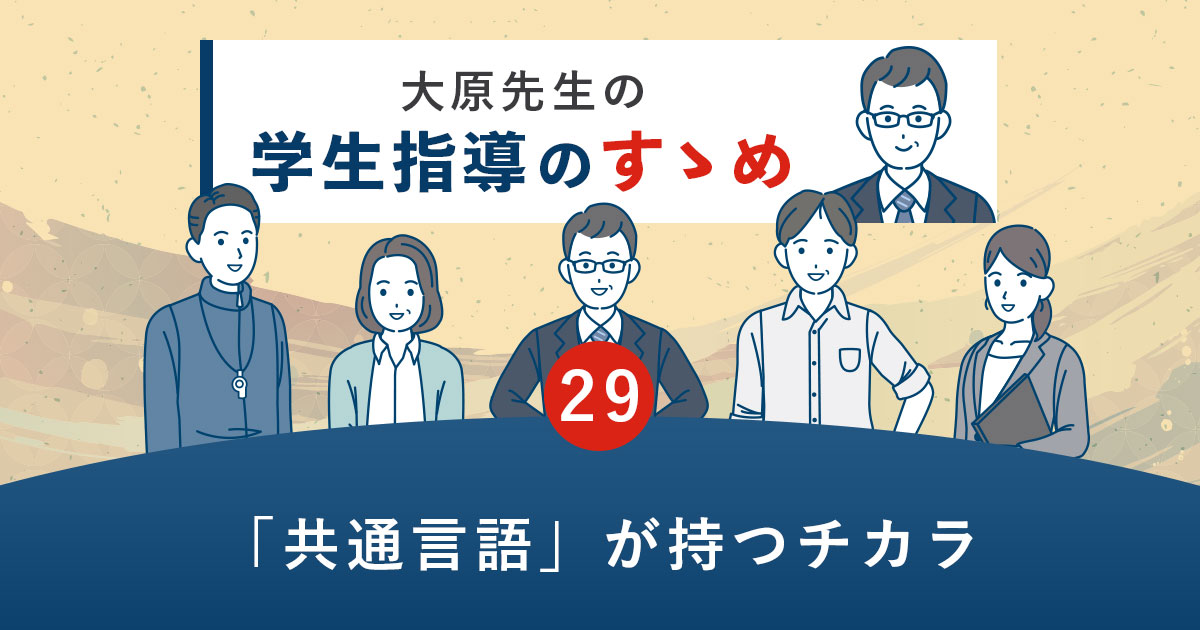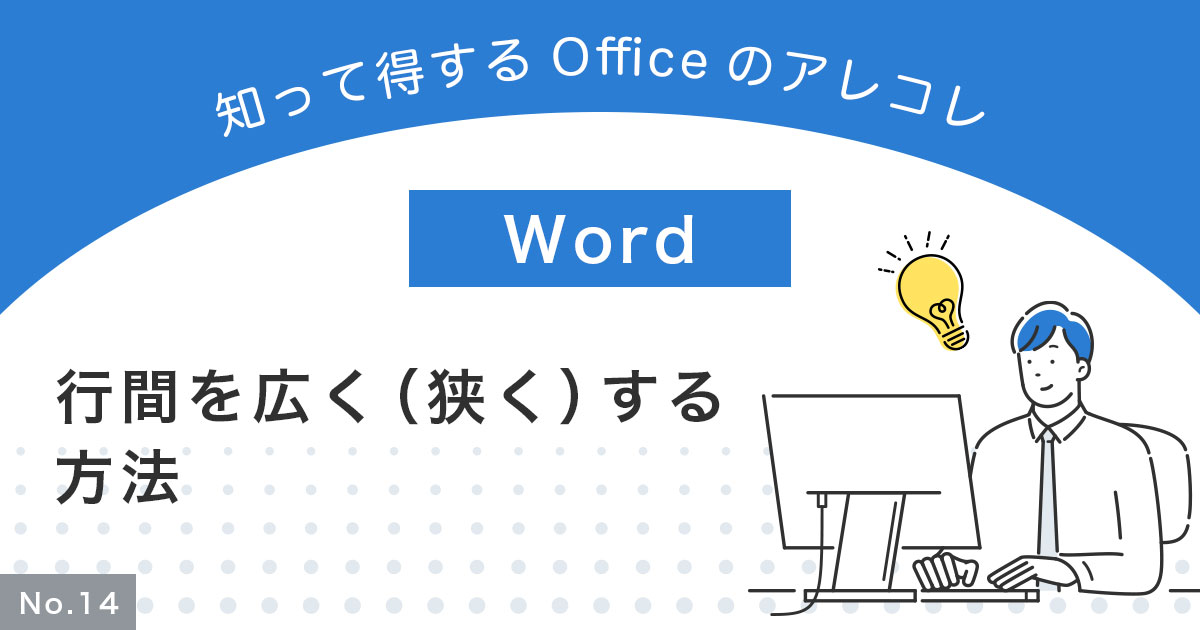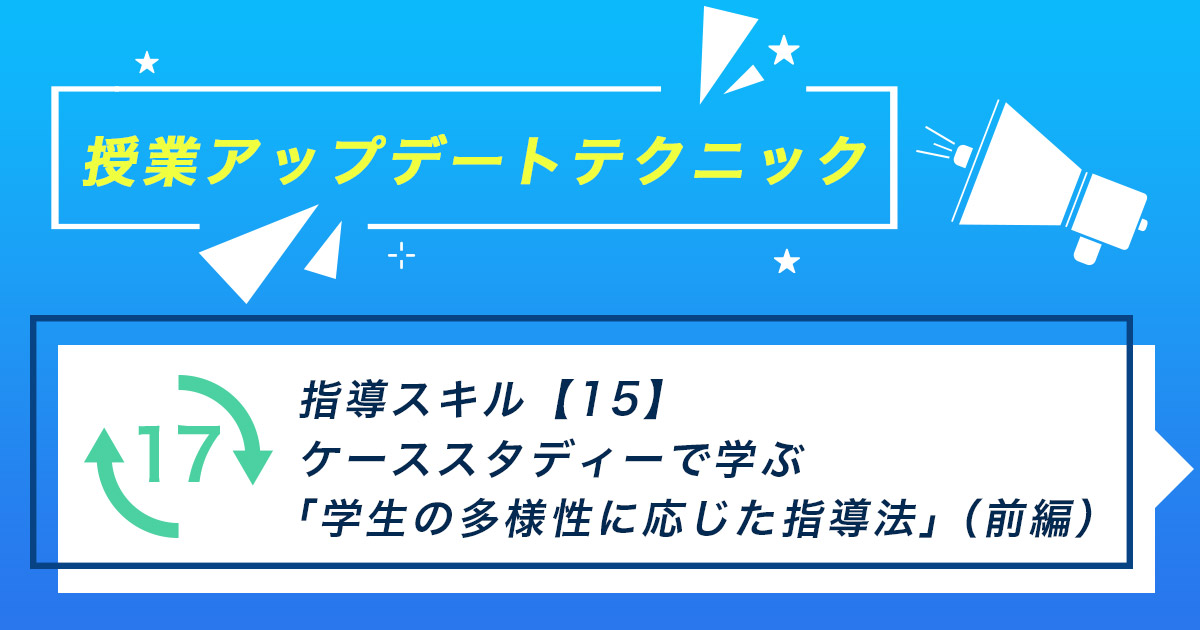連載大原先生の学生指導のすゝめ
動機づけ教育プログラム「実践行動学」を開発する「実践行動学研究所」大原専務理事の学生指導のすゝめ。 学習塾での指導歴25年の大原先生が、実例を用いて学生への接し方をお伝えするシリーズです。 テンポのよいユニークな文章は、一度読んだらハマること間違いなし。
本連載の執筆者である大原先生が専務理事を務める「実践行動学研究所」のセミナーでは、コミュニケーションに関する講演を行っています。
この度、その講師である法政大学キャリアデザイン学部教授廣川進様より、2記事を寄稿していただきました。
今回はその1本目です。
コロナ以後の若者の特徴や傾向を廣川先生がわかりやすく整理し、解説しています。コロナ禍が若者に与えた影響や学生の気質変化について、現場の先生方は日々肌で感じているのではないでしょうか。
ぜひ先生方の体感している若者の特徴と比較してみてください。
目次
コロナ禍を経て変化した学生たち
コロナ禍は次第に収まってきたようにみえますが、若者たちにはどんな影響を与えたのでしょうか。
私の大学のゼミ生についてみてみましょう。
今年新社会人になった学年は、高校の卒業式がなかったり、大学の入学式も翌年になってから行ったり、入学当初から全面的なオンライン授業になったりと、4年間もっともコロナの影響をうけた人たちです。
私のゼミ生にしては珍しく、都庁、県警、県立高の教員など、公務員として就職した学生が多くいました。みな前々からコツコツと就職対策をしないと合格できないところです。
安定志向はコロナ禍の期間の不安も多少影響したかもしれません。
昨年、ゼミ恒例の夏合宿が解禁となり、学生たちに企画の多数決を採ったところ、否決されてしまいました。私はやる気満々でしたが、学生たちは合宿の経験に乏しくイメージが湧かなかったのかもしれません。ショックでした。私の20数年の教員歴の中でも、コロナで行けなかった2回を除けば、初めての経験です。
このように、コロナ禍を経て学生が変わってきたように感じています。
ここでコロナ禍が若者に与えた影響について、高校生の国際比較のデータからご紹介しましょう。日本・米国・中国・韓国の4カ国での比較調査(2021年〜22年)です。みなさんの教室の学生の年代とも重なるのではないでしょうか。
青少年機構の調査結果からみる高校生の生活と意識
出典:国立青少年教育振興機構「コロナ禍を経験した高校生の生活と意識に関する調査報告書-日本・米国・中国・韓国の比較-(令和4年6月)」
調査で分かった、コロナ禍を経験した日本の高校生の特徴を以下にあげます。
人とのつながりの大切さを感じている一方、勉強への意識が変わった割合は低い
「友達の大切さ」や「対面のコミュニケーションの大切さ」を感じるようになったと回答した者の割合は5割を超えているが、「勉強の大切さを感じるようになった」「勉強を自らするようになった」「勉強の負担が大きくなった」と回答した者の割合は4カ国中で最低であった。
悩みは少なくなっている
米・中・韓に比べて、「友人、異性、家族、先生との付き合い」「健康」「家の経済事情」について悩んでいると回答した者の割合が最も低い。2017年と比べてほとんどの項目で悩む割合が下がり、「特に悩みがない」の割合が高くなっている。
家族や友だちとのコミュニケーションや関係性を大切にしている
「家族との関係が良好」「友だちと一緒にいる時は、楽しい」「つらい時、助けてくれる人がいる」と回答した者の割合が4カ国中で最も高い。2014年、2017年のデータと比べて、いずれの項目も高くなっている。
有名大学への入学やリーダーになることよりも、気楽で安定した生活を送ることを望んでいる
「のんびり気楽に暮らす」「安定した仕事に就く」「円満な家庭を築く」「自分の趣味をいかす暮らしをする」について「とてもそう思う」がいずれも5割を超え、米国についで高い。
他方、「お金持ちになる」「高い社会的地位に就く」「有名な大学に入る」「リーダーになる」は4カ国中で最低であった。
マイペースで優しい子たち
みなさんの日頃の実感と照らし合わせて、いかがでしょうか。正直、私はとても納得するところがあります。
いまの学生を一言で表現すると「無理せずマイペースで優しい子」たち。
「ハングリーモチベーションの終わり」といわれる現象は、コロナ前からの兆候かもしれませんが、その傾向がさらに強まってきた気がします。
上昇志向がないので目指すべき目標と現状とのギャップに葛藤することも、また悩むこともありません。無理もしないのでストレスも高くならず、家族や友人との関係もよく、メンタルも安定している子が多い。プラス面も多くあります。
一方で、高い目標をめざして、勉強して資格をとって専門性の高い仕事に就く、というようなモチベーションが低くなっているとすると、専門学校にとってもなかなか頭の痛い現象かもしれません。
産業界に目を向けると、自律型キャリア、ジョブ型雇用、DXとリスキリングなど、「マイペースで優しい子」たちが卒業後に晒されるであろう過酷な現実社会が待っています。そこでどう生き残っていけるのか、はなはだ心配にもなります。社会における、さまざまな格差がコロナ禍で加速されてきました。非正規雇用の割合はすでに37%です。
学校現場はコロナ禍前の対面授業にほぼ戻りましたが、学生一人ひとりの多様化が進み、保護者の対応も複雑化、教員の精神的な負荷は少なくないと聞きます。
また教員の学校でのコミュニケーションは学生だけでなく、保護者や同僚相手にも求められています。それらの関係を円滑に進めるために、求められるスキルは異なります。学生や保護者、同僚とよい関係性を築くために、学校内でのコミュニケーションを見直してみることが必要です。
次回は学校内でのコミュニケーションのスキル向上について考えてみたいと思います。
▼ウイナレッジ編集部からのお知らせ
本記事を寄稿してくださった法政大学 廣川教授が、「実践行動学Webセミナー」にて基調講演講師として登壇されます。
実践行動学は、学生の夢の実現、目標達成に必要な「心のあり方」と「達成のスキル(技能)」を身につけることを目的とした、アクティブ・ラーニング型動機付け教育プログラムです。ぜひこの機会にご参加ください。
【実践行動学Webセミナー】
・基調講演タイトル:教員に求められる『スクールコミュニケーション』のスキル向上のために(法政大学 教授 廣川進様)
・日にち:2024年6月27日(木)および2024年7月10日(水)
・会場:オンライン会場(Zoom)
・主催:一般社団法人 実践行動学研究所
・後援:株式会社 ウイネット
・参加費:無料
詳細はこちら
\ぜひ投票お願いします/
廣川 進
法政大学 キャリアデザイン学部 教授(公認心理師・臨床心理士・文学博士)。
1959年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、株式会社ベネッセホールディングスにて、雑誌編集(『ひよこクラブ』の創刊等)の傍ら、大正大学大学院臨床心理学専攻修士・博士課程を修了。2001年退社後、大正大学心理社会学部臨床心理学科教授を経て現職。