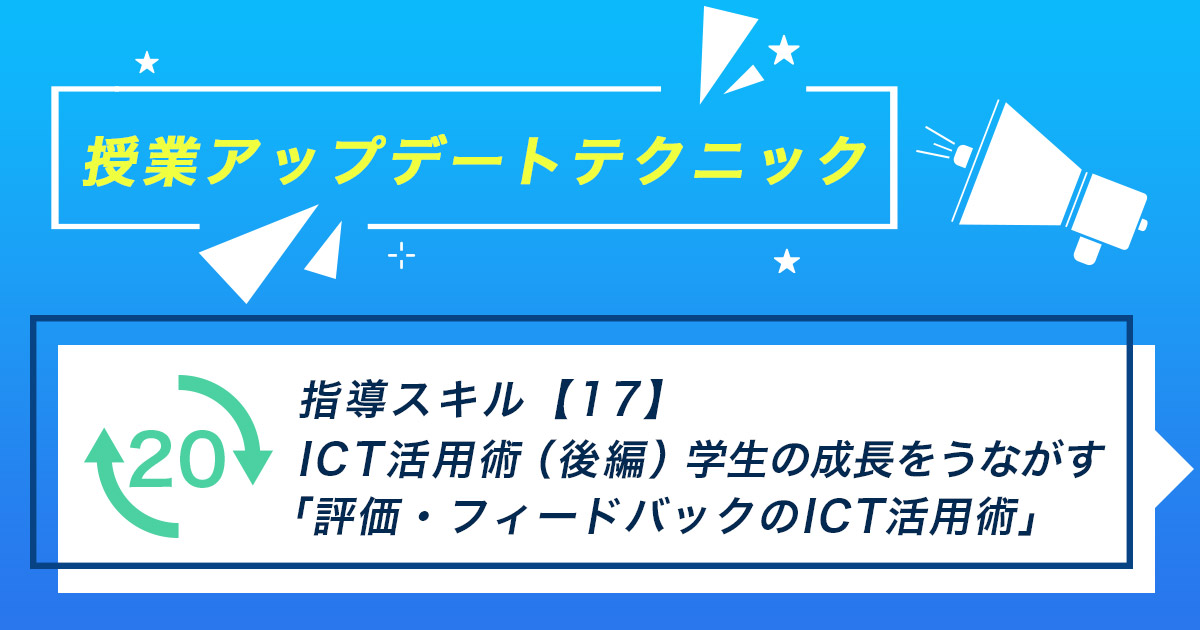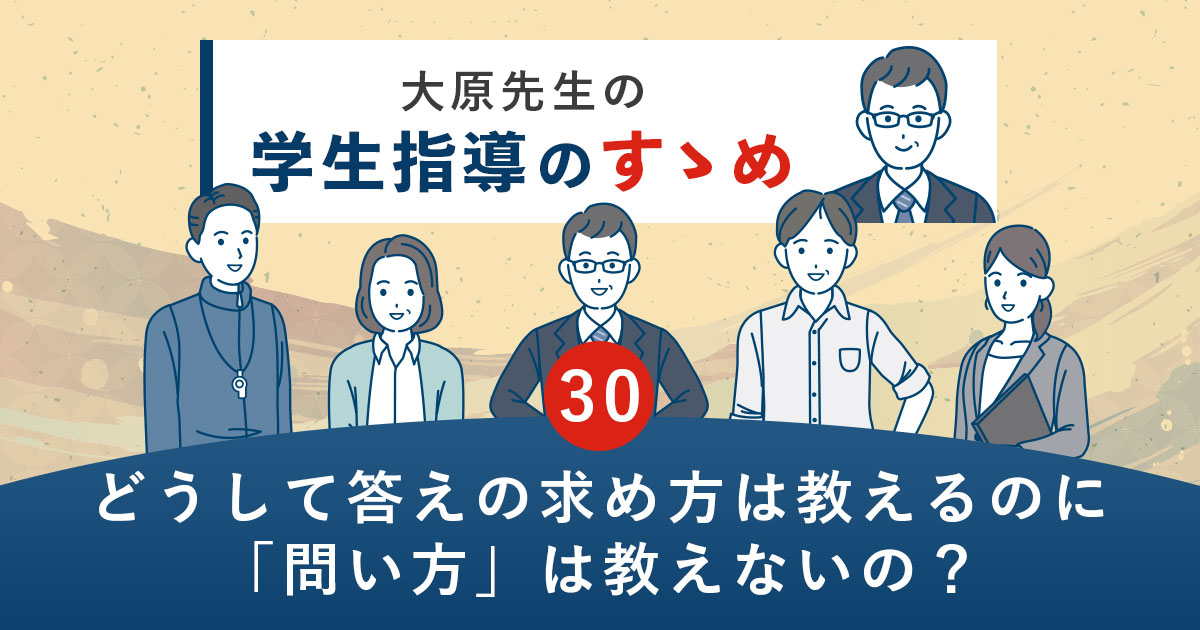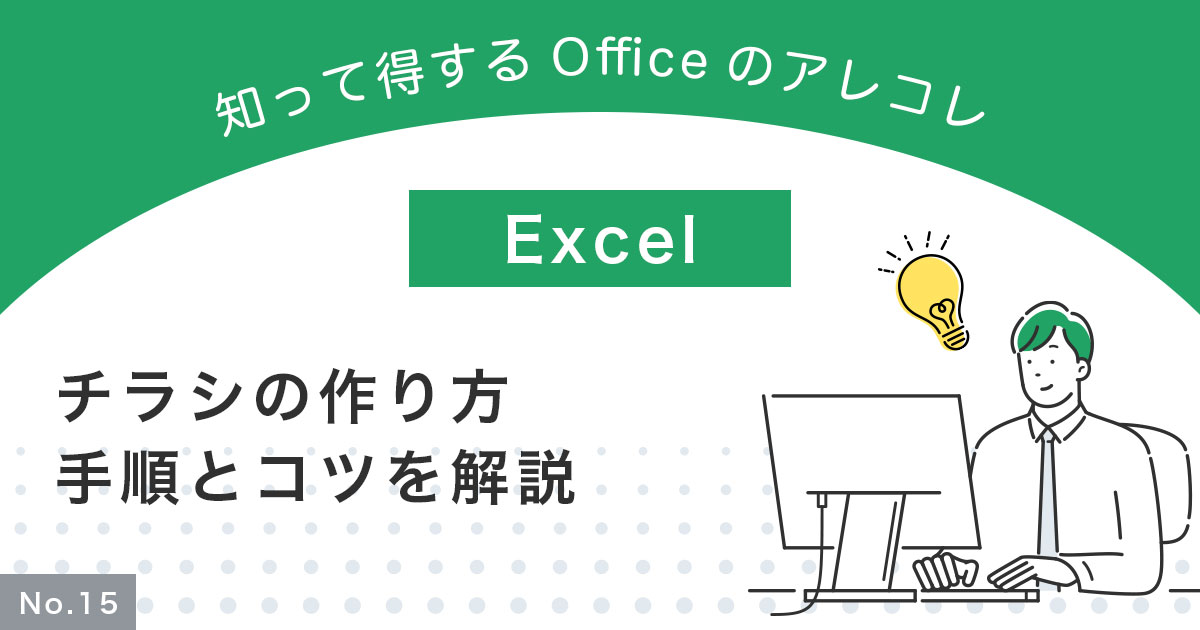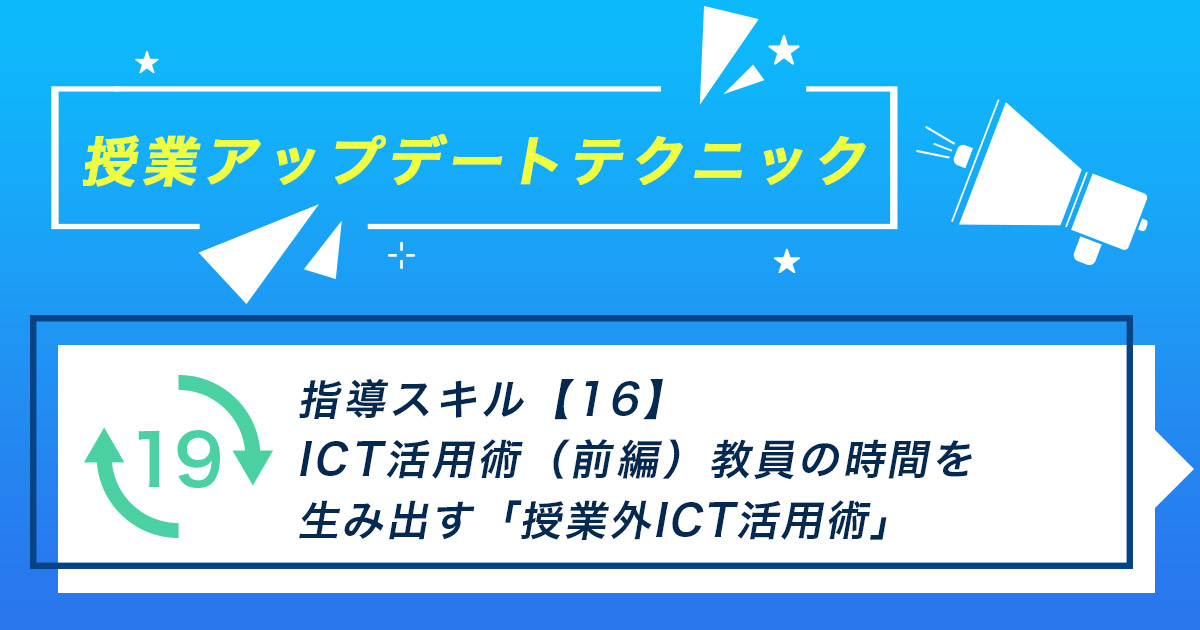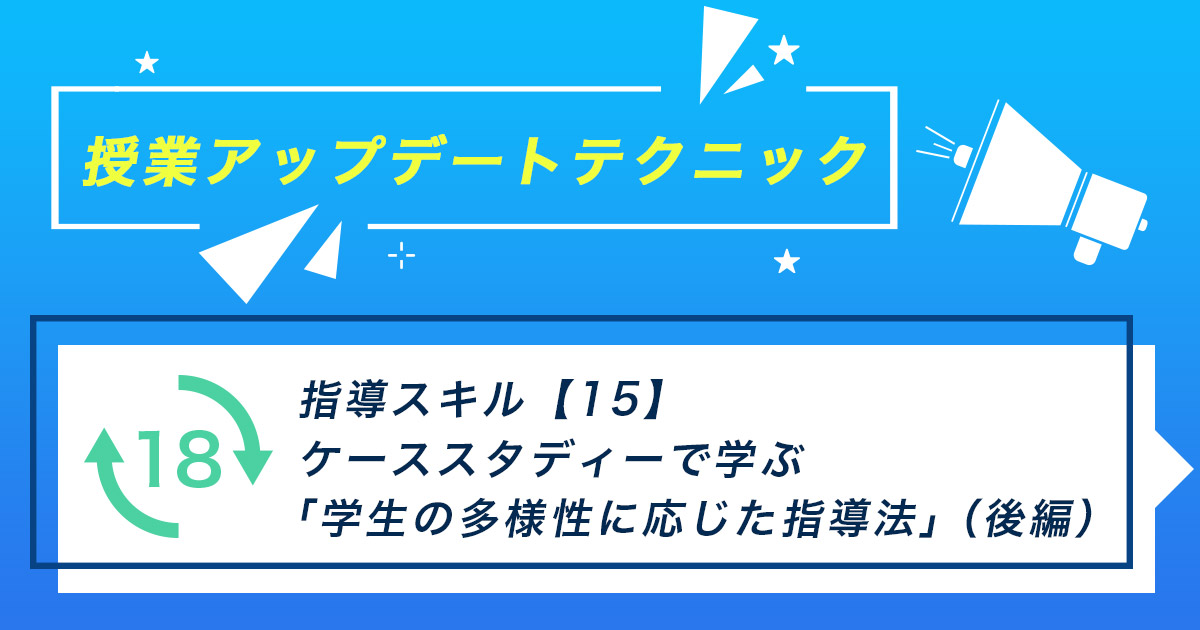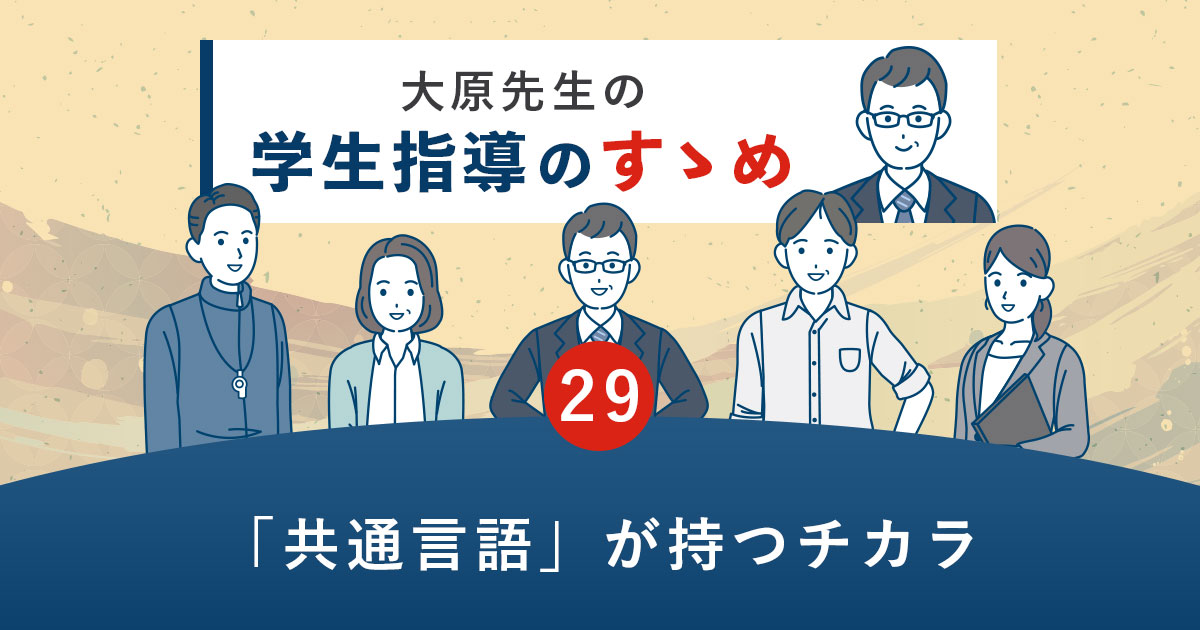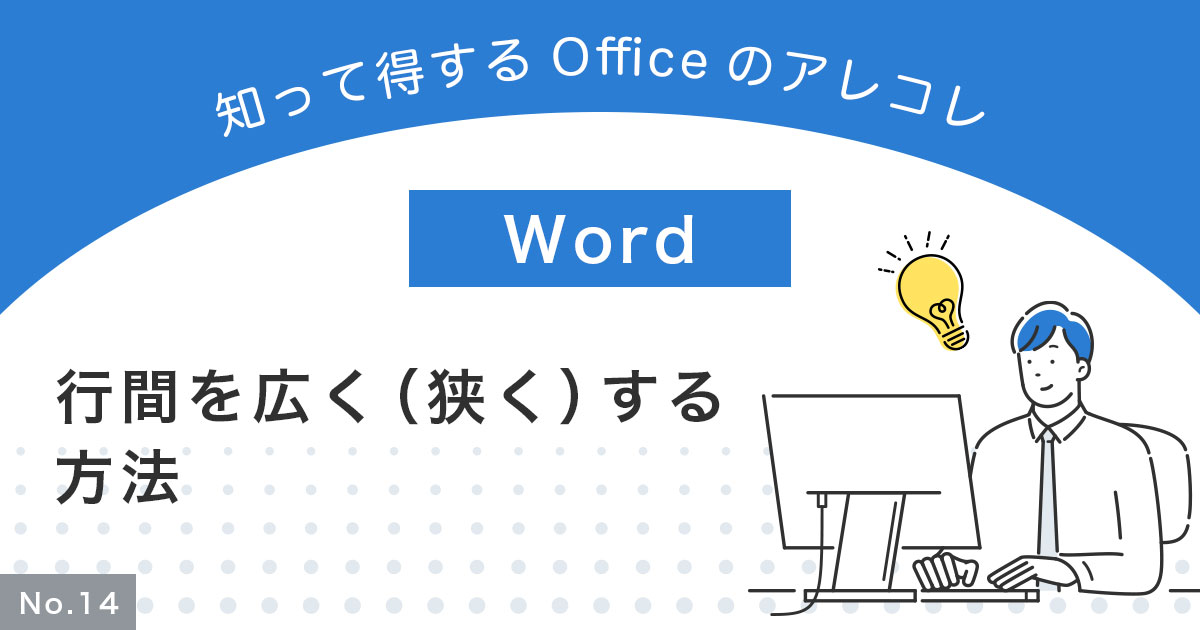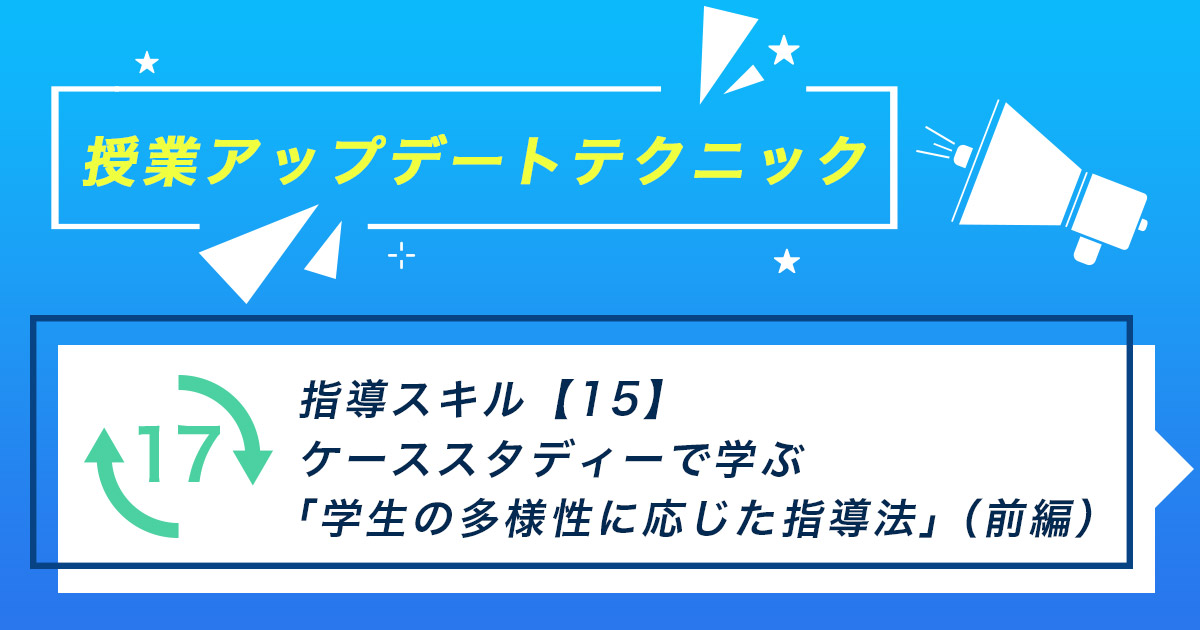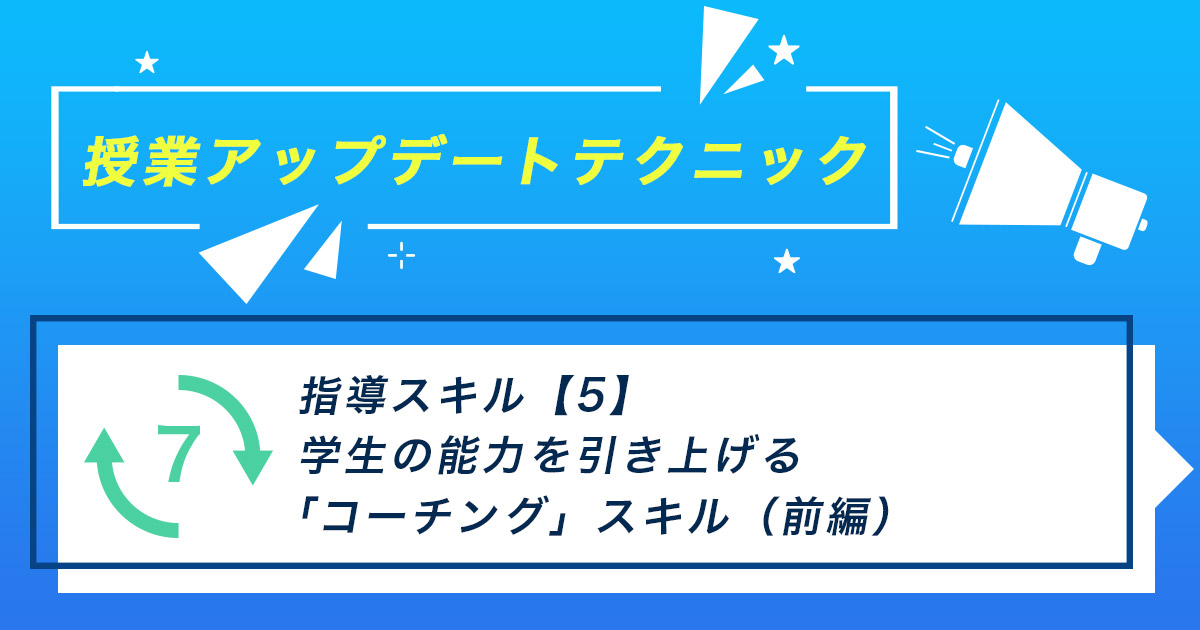
連載授業アップデートテクニック
変化する学生のニーズ、技術やツールの進歩、多様性の受け入れなど、常に進化が求められる現代の教育現場。授業をアップデートしなくてはいけない時期が到来しています。この連載では、教員向け研修や教員志望者の育成を行う「RTF教育ラボ」の代表で、年間300もの授業観察を行う教育コンサルタントの村上敬一さんから、専門学校の先生に向けた「令和の授業テクニック」を教えてもらいます。
2024年もあと数日となりました。先生方は一年を振り返り、来年(来年度)の展望を立てられている時期だと思います。
今回は、学生の能力を最大限に引き出す「コーチング」スキルについてお伝えします。専門学校教員を含め、教員が果たす役割は単に「知識を伝えるだけ」でないのは言うまでもありません。教員は、学生一人ひとりの潜在能力を見つけ、引き出し、自己成長を促すことが求められています。そのために有効な手段が「コーチング」なのです。また、これは前回の記事でお伝えした「モチベーションを向上させる方法」としても効果的な方法です。
目次
コーチングとは

「コーチング」とは、相手の話をよく聴き、感じたことを伝えて承認し、質問することで、自発的な行動を促すコミュニケーションのことです。人材開発の技法の1つで、対話によって相手の自己実現や目標達成を図ります。簡単に言えば「学生が自ら考え、行動し、目標を達成するためのサポートをする手法」です。ティーチングが「教えること」に重点を置くことに対して、コーチングは「引き出す/引き上げること」に重点を置きます。学生が自ら気づき、自分の力で課題を解決し、成長するためのプロセスをサポートする形で実行します。
コーチングの前提となる考え方
コーチングを行う前に意識してほしい考え方があります。それは「相手の可能性は無限大である」「答えは必ず相手の中にある」「答えを引き出すパートナーに徹する」の3つです。
教員として「現在の学生」を観察していると、今までの経験から「この課題を解決することは難しいだろうな…」と学生の限界を推測してしまったり、我慢しきれなくなり、つい「こうすればいいよ」と方法論を提示してしまったりすることが少なくありません。実は私もよく失敗していました。これはコーチングを行う上では良くないことですので、注意しましょう。 また、サポートパートナーとして「エラー(失敗)も成長の一部ととらえ、何度もトライさせる気持ちのゆとりを持つこと」「価値観が違うことは当たり前。手段・方法は人それぞれ、遠回りだと感じても本人の決めたやり方を尊重すること」も重要な考え方です。
コーチング使用のメリット
コーチングのメリットは大きく4つあります。
- 個人の能力を大きく伸ばせる
- 言語でコミュニケーションがとれれば、年齢に関係なく応用できる
- 潜在的なことが顕在化する
- 依存性が減少する
まず1つ目は「個人の能力を大きく伸ばせる」ことです。相手から押し付けられる問題の解決策ではなく、自分自身の気づきと自ら考えた解決策であるからこそ「内発的動機づけ」となります。だからこそ行動も継続しやすく、結果もでやすい状況になるのです。その過程と成果が自信となり、自己肯定感や自己効力感が高まるため、さらに高みを目指すチャレンジができるようになります。結果として、本人の能力自体が伸びることにつながるのです。
2つ目は「言語でコミュニケーションがとれれば、年齢に関係なく応用できる」ことです。会話によってコーチングを行うので、言語によるコミュニケーションは必要ですが、例え幼児でもご年配の方でも、正しくコーチングを行えば効果が期待できます。
3つ目は「潜在的なことが顕在化する」ことです。次回詳しく説明しますが、コーチングのスキルの1つに「質問スキル」があります。質問スキルを活用しながら質問すると、コーチングを受ける側は気づいていなかった能力や考え方、無意識に行っていた行動の意味など、わかっていなかったこと(潜在的なこと)を、自分自身で理解(顕在化)できるのです。それにより自己理解が進み、気持ちが軽くなったり、自己肯定感が高まったりすることもあります。
4つ目は「依存性が減少する」ことです。ティーチングのデメリットにもなっている「わからなければ聞く」の繰り返しによる「自分で考えて解決できない」といった誰かへの依存性がコーチングにはありません。コーチングは「答えは必ず相手の中にある」という考え方で進めますので、気づきを与えることはあっても、教えることは基本的にありません。その結果、自分自身で考える癖がつきやすいので、依存性が減少するというわけです。
コーチング使用のデメリット
次にデメリットです。大きくは以下の3つです。
- 1回の指導に時間がかかる
- 受け手の状態に不向きがある
- 集団より個別指導に向く
1つ目は「1回の指導に時間がかかる」ことです。答えや手段・方法をすぐに伝えることが多いティーチングと比較すると、何倍も時間がかかってしまいます。私の場合ですが、コーチングを行う際は1人1時間確保しています。短い場合でも20分はかかります。時間の確保はコーチングを行う際の重要なポイントになります。
2つ目は「受け手の状態に不向きがある」ことです。鬱に近い状態(精神心理的にマイナス)の学生にコーチングは不向きです。無理してコーチングを行うと、かえって精神状態を悪化させてしまう可能性があります。もし面談中にマイナス状態だと気がついた場合はコーチングを中止し、その時間は傾聴に徹したうえで、終了後すぐに専門家に相談してください。あくまでも私の経験則ですが、精神的にマイナス状態の学生は、話の流れとは関係なく突然泣き出す、普段は目を合わせる学生がずっと下を向いたまま目を合わせない、目が虚ろなどの症状がみられました。この状況が見られたら要注意です。迷ったらほかの教員へも相談することをおすすめします。
3つ目は「集団より個別指導に向く」ことです。1人ひとりの状況に寄り添って、能力などを引き出したり、引き上げたりするコーチングは集団で行うことが難しいというのは想像しやすいと思います。集団の話し合いを活性化させ、グループの成果を高める手法の1つが「ファシリテーション」であるならば、「ファシリテーション」が集団におけるコーチングに近いとも言えるでしょう。
コーチング使用の効果

最後にコーチングの効果をまとめます。
- 主体的な行動が増える
- 自己肯定感/自己効力感が高まる
- 自己理解が進み、強みがわかる
- 物の見方に柔軟性を持てる
- 目的意識を持ちやすくなる
- 内発的動機づけによるモチベーションの継続が期待できる
- リーダーシップスキルが養える
以上のことなどが効果として挙げられます。
「スキルコーチング」と「メンタルコーチング」
専門学校の教員としては、この2つのコーチングを切り離して考えたほうが学生指導をしやすいと思いますので、ここでお伝えします。
まず「スキルコーチング」とは、個人(学生)の専門的スキルの向上を目的としたコーチングで、コーチングする側にその分野の専門的知識が必要です。
例えば美容師を目指す学生に対して、髪を切るスキルを習得させるコーチングを行うとイメージしてください。コーチングを行う際の質問には、美容師特有の専門用語や髪質の違いによるアプローチ方法など、専門性を熟知していないとできない質問が含まれるはずです。そうなるとコーチングを行う側の専門性が高いほうが「質問の質」は高くなるでしょう。またコーチング後、スキルを習得できたかのチェックや評価を行う場合、専門性があればより正しいリフレクション(振り返り)を行うことができます。一点気を付けるとすると、専門性があるがゆえについ口をはさんでしまい、結果的にティーチングになりやすいということです。少しのティーチングは構いませんが、教えすぎないことを常に意識してください。
もう1つの「メンタルコーチング」とは、個人(学生)の情報や感情の整理を手伝い、異なった視点や考え方を促すことを目的としたコーチングです。これは、コーチングする側に特定分野の専門的知識は不必要という点が特徴です。
例えば学生が文化祭の実行委員のリーダーとして「チームがまとまらない」と悩んでいる場合に、コーチングを行ったとイメージしてください。この場合、学生の学んでいる専門分野や教員の専門分野とは関係なくコーチングができます。担任や行事の担当として学生にコーチングする場合は、こちらの「メンタルコーチング」の機会が多くなると思います。
次回に向けて
今回は、『学生の能力を引き上げる「コーチング」スキル(前編)』としてコーチングを行う前に知っておいてほしい知識を中心にお伝えしてきました。次回は後編としてコーチングの3つのスキルである「傾聴スキル」「承認スキル」「質問スキル」について詳しくお伝えいたします。
\ぜひ投票お願いします/
村上 敬一
RTF教育ラボ代表/教育コンサルタント/東京都杉並区内中学校学校運営協議会委員
全国の公立および私立の小学校・中学校・高等学校、専門学校、塾などで教員研修、講師研修、授業や学級経営を中心とした教育全般に関するアドバイスを行う。また、現在まで18年間に渡り、毎年約150名の教員志望者を育成。年間の授業観察数は300を超え、これまでに約5000の授業を観察している。
RTF教育ラボ(https://goseminarcourse01.wixsite.com/rtfkyouikulab)