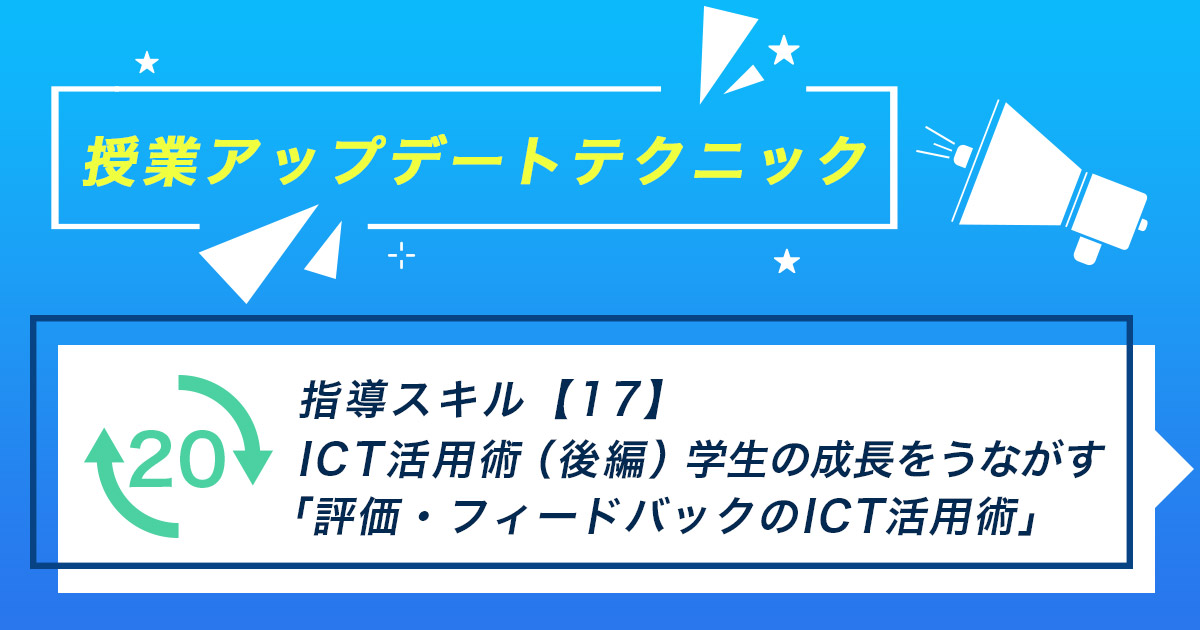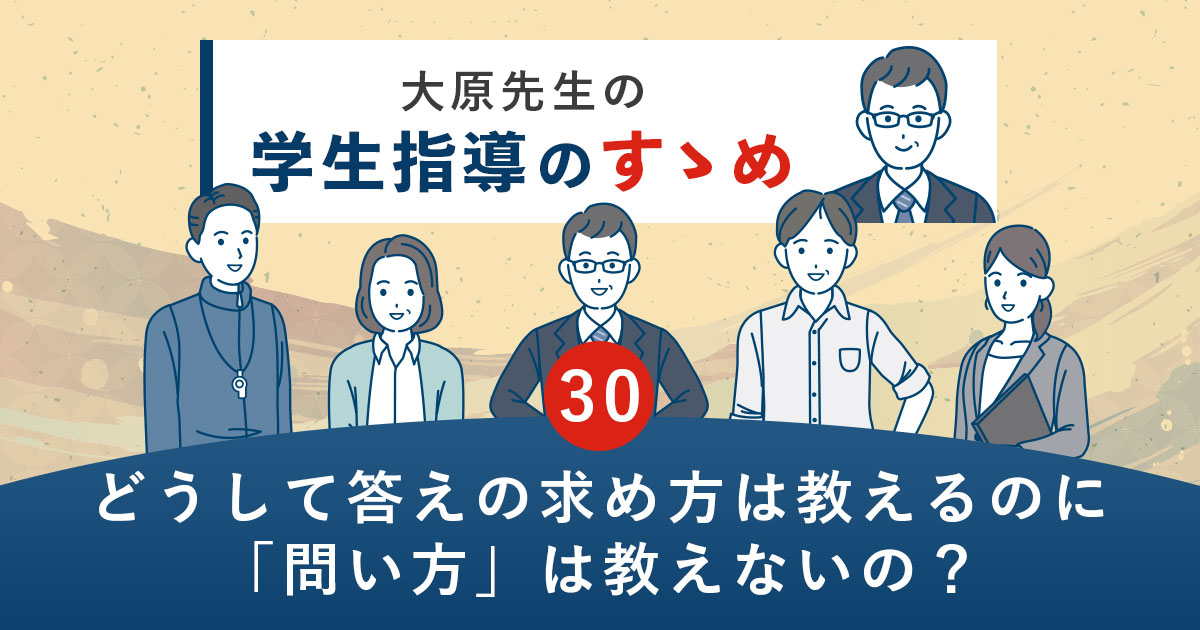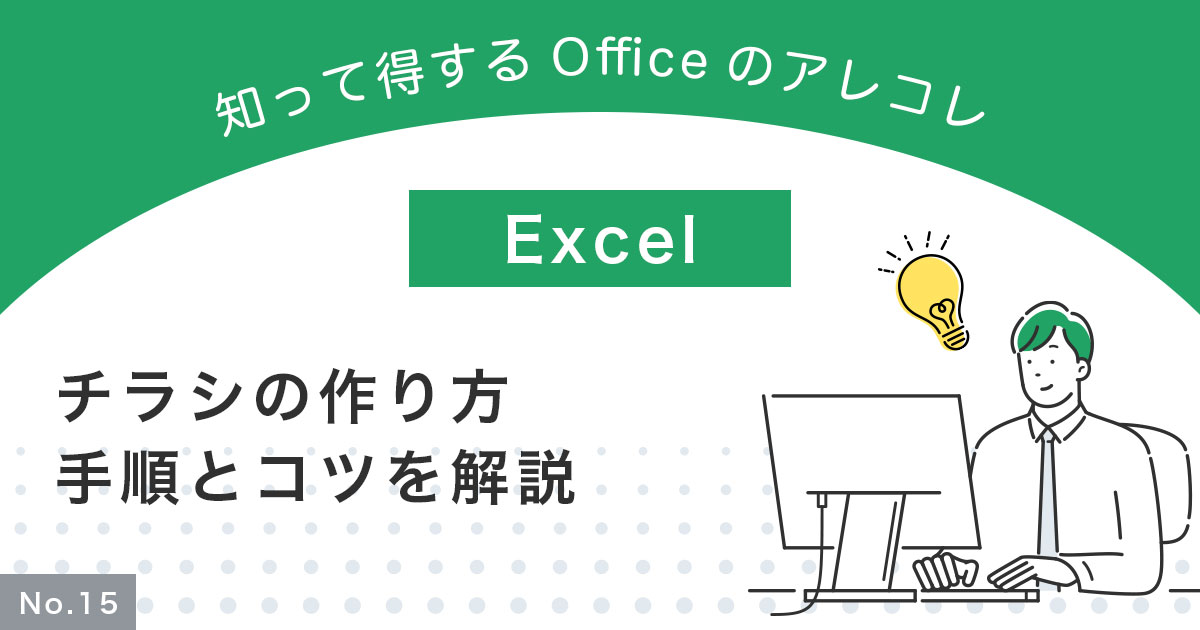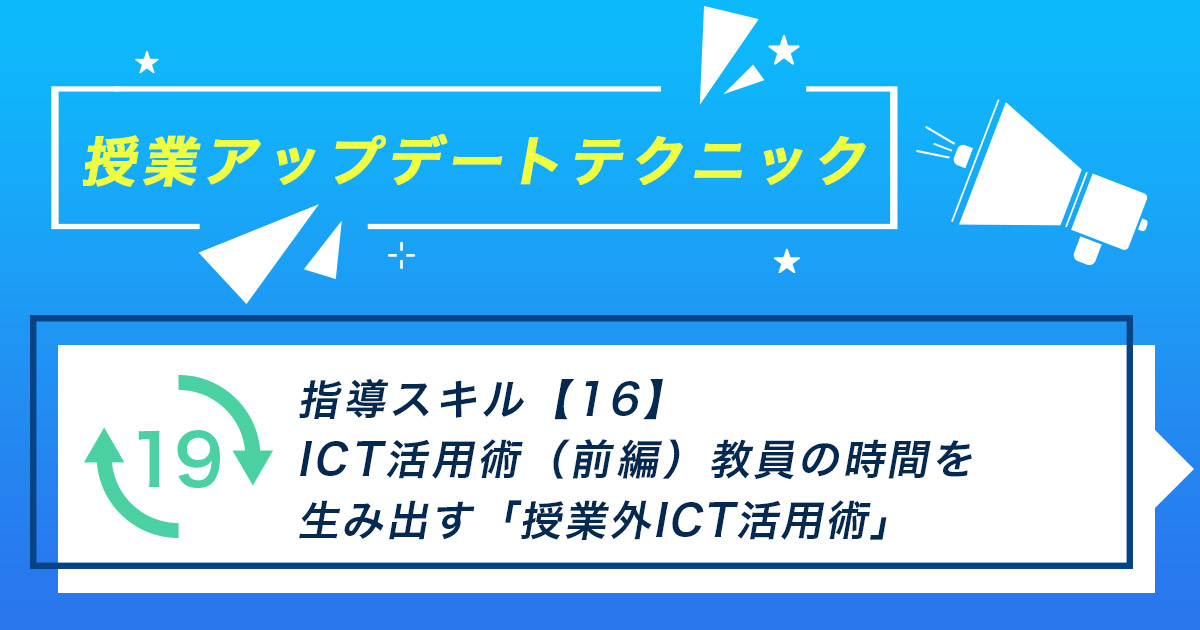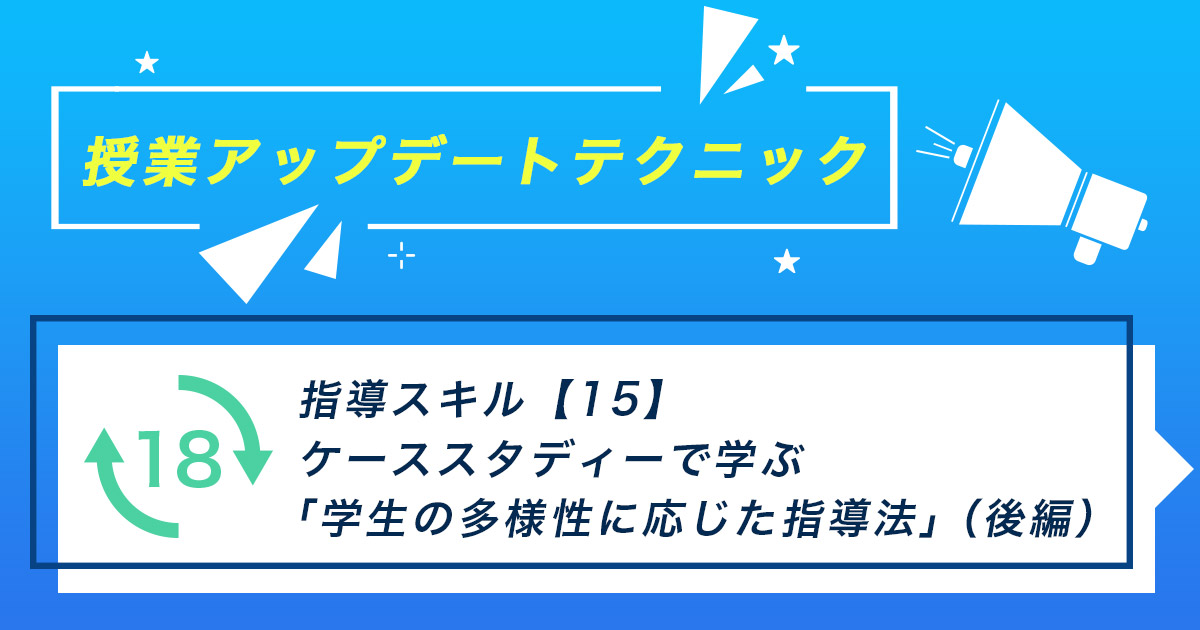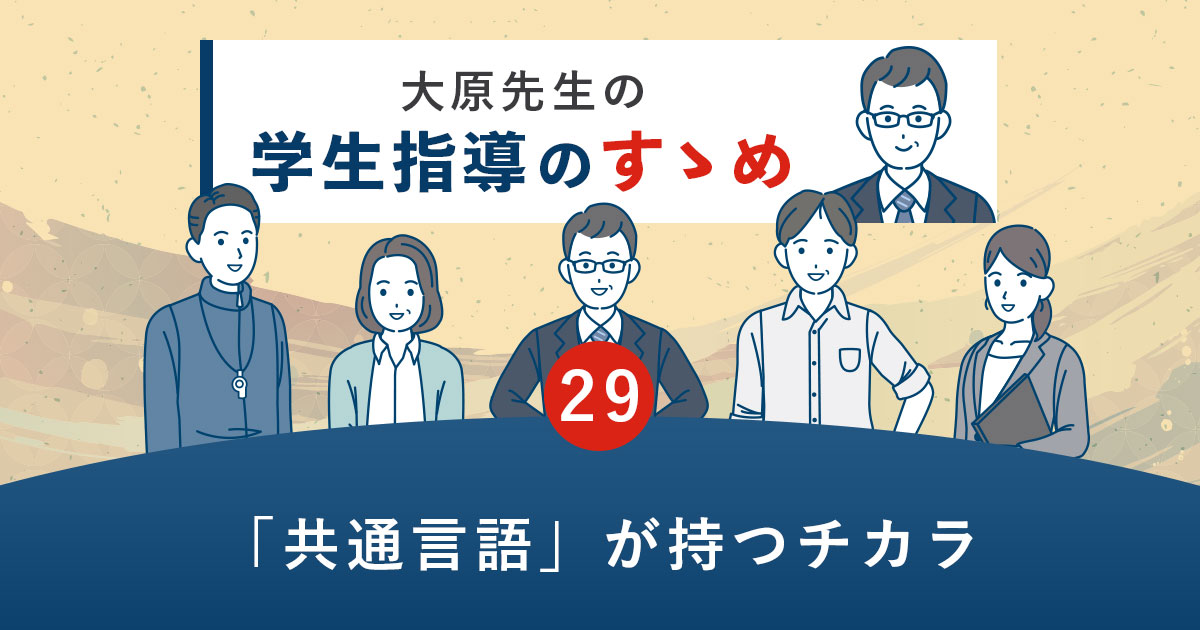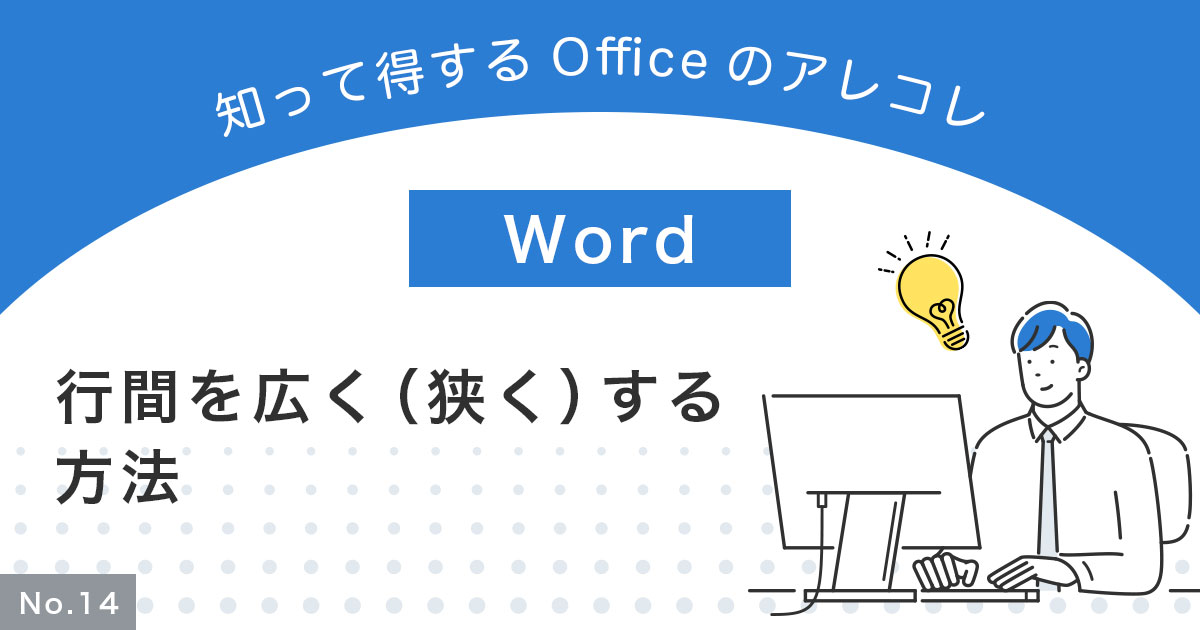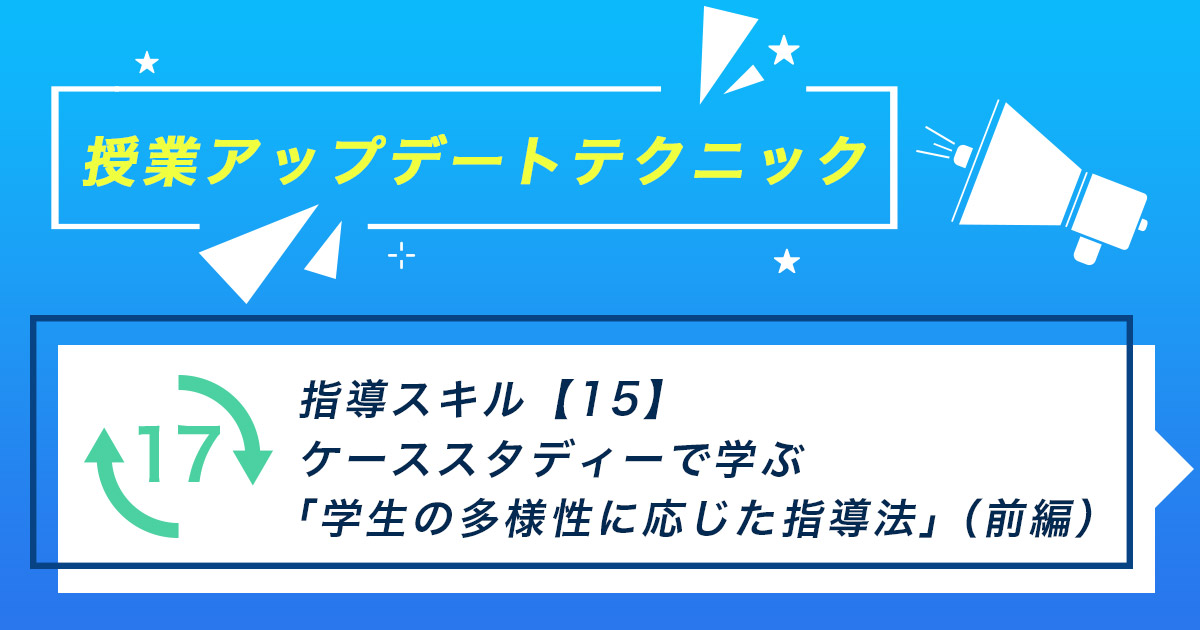指導スキル(7)~演習/実習型授業の効果を高めるアクティブラーニング(AL)型授業法(前編)
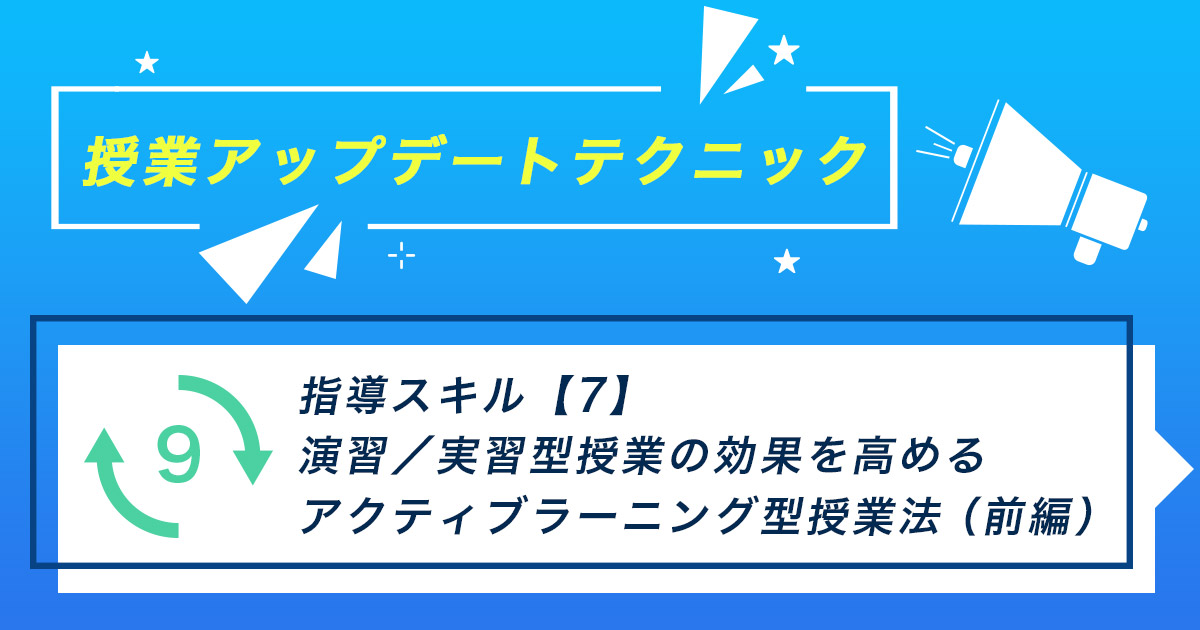
連載授業アップデートテクニック
変化する学生のニーズ、技術やツールの進歩、多様性の受け入れなど、常に進化が求められる現代の教育現場。授業をアップデートしなくてはいけない時期が到来しています。この連載では、教員向け研修や教員志望者の育成を行う「RTF教育ラボ」の代表で、年間300もの授業観察を行う教育コンサルタントの村上敬一さんから、専門学校の先生に向けた「令和の授業テクニック」を教えてもらいます。
いよいよ今年度もあと1カ月程度となりました。担当している授業はすでに終わったという先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
改めて、私が専門学校の先生方と話したことを振り返ると、多くの方々は「講義型授業」よりも専門性が特に問われる「演習/実習型授業」に自信を持っている様子が伺えます。ただ、課題もあるようで、多くの先生が「学生の主体性の育成/学生のワークの活性化」に悩みを抱えているようです。今回はこの「主体性の育成及び、学生同士の対話の活性化や学びを深めること」に効果が高い「アクティブラーニング型の授業方法」をお伝えいたします。
また、「指導スキル(4)~心理学を活用したモチベーションUP術」、「指導スキル(2)~学生の思考力を鍛える『発問』」も併せて読んでいただくと、より効果が見込まれますので、ぜひご覧ください。
目次
アクティブラーニングとは

「アクティブラーニング(Active Learning)」とは、学生が能動的・主体的に学習に参加し、自らの経験や考えを基に知識を構築していく学習方法です。簡単に言うと「あらゆる能動的な学習」のことを指します。学生が受動的に知識を吸収するだけの学習以外であれば、全てアクティブラーニング型授業と定義している大学もあります。「ペアワーク」「グループワーク」「プレゼンテーション」などのように、「言葉を発する活動があること」がアクティブラーニングだと勘違いされている方が多いのですが、実は小テストやレポートであったとしても、学生が能動的に取り組んでいればアクティブラーニングと捉えられます。逆にグループワークであっても、ただ受動的に参加している場合は、アクティブラーニングとは言えない可能性もあるわけです。
具体的なアクティブラーニングの特徴として、以下が挙げられます。
- 学生が授業において能動的な役割を担う
- 教員は学生の学びをサポートするファシリテーターとしての役割を果たす
- プレゼンテーション/対話や記述などのアウトプットを活用する
- 学生同士を中心とした協働作業が重視される
- リフレクション(内省)と他者からのフィードバックなどを通じて深い学びを促進する
- 学びの継続を意識させる
アクティブラーニング型授業が必要な理由
現代社会は変化が激しく多様で、誰も正解を持っていない未知の課題が増加しています。例えば、生成AI(人工知能)の発達、新型コロナウイルス感染症のような世界規模のウイルス、地震や津波などの災害増加、SNSといったコミュニケーションツールの多様化によるコミュニケーションの変化や情報の複雑化などです。このような状況に対応するため、学生には単に知識を暗記するだけでなく、世の中のことを自分事として捉え、自ら考えて判断し、行動する能力が求められます。アクティブラーニング型授業は、これらの能力を育成する上で非常に有効です。
アクティブラーニング型授業の主なメリット
アクティブラーニング型授業を成功させると、以下のような効果が期待されます。
- 学習意欲の向上:
主体的に学習に関わることで、学習意欲が高まる - アウトプット能力の向上:
グループワークやプレゼンテーション、レポートなどの機会が多いため、アウトプット能力が強化される - 協働力の向上:
グループワークやディスカッションを通じて、コミュニケーション能力やチームワークが強化される。また、チームでのプロジェクトを通じて、各自の役割を果たしながら目標を達成する経験が得られるため、協調性が高められる - 深い理解の促進:
学生が自ら考え、探究することで、知識の理解が深まる - スキル定着の促進:
行動と振り返り(リフレクション/フィードバック)の繰り返しにより、効率よく効果的に専門技術を習得できる - 問題発見/解決能力の向上:
さまざまな視点から問題を考え、自分の考え方になかった他者の考え方を聞くことで気づく力が向上。これにより問題発見能力も高まる。何度も継続的に問題解決の学習にチャレンジすることで解決能力も身に付く - 学びの継続力:
学びがつながっていくことを体験する機会が増えるので、物事に興味や関心を持ちやすくなり、学びが継続する
学生を主体的・協働的な学習者へ育成するために教員ができること
教員側ができることは以下の通りです。
- 学習環境の整備:
安心して自由なディスカッションが行える空間のレイアウト調整や、必要な教材/教具を準備する。活動に必要な資料やデジタルツールを提供する - 意識の伝達:
主体的/協働的な学習者の大多数が意識している「目的意識及び当事者意識」を何度も学生に伝える - 発問の活用:
学生のさまざまな視点や思考を促す発問を活用する
(詳細は「指導スキル(2)~学生の思考力を鍛える『発問』」をご覧ください) - フィードバックの活用:
学生の発言や課題に対して具体的なフィードバックを行い、学びの方向性をサポートする。また学生が書いたレポートに対して、次の行動へつながるような強みと改善点を具体的に伝達するフィードバックを行う - リフレクションの活用:
学生が自らの学習進捗を振り返り、次の行動目標を設定して行動できるよう、自己評価シートなどを活用する
アクティブラーニング型授業導入の問題点
アクティブラーニング型授業の導入には、いくつかの問題点も存在します。
1.教員側の問題点
- 授業準備の負担:
慣れるまでは、講義形式の授業に比べて、準備に時間を要する場合が多い。そのために準備不足となってしまうことがある - ファシリテーションスキル不足:
アクティブラーニング型授業を成功させるためには、教員にファシリテーションスキルが多少必要になる - 時間管理の困難さ:
アクティブラーニング型の活動を行うには十分な時間が必要。準備段階での予測の甘さが原因で、学生の活動時間が足りなくなってしまうケースもある - ヘルプし(教え)すぎる:
学生の活動において、サポートは必要だが過度なヘルプは不要。つい教えたくなってしまうところを我慢する必要がある - 評価方法の確立の難しさ:
アクティブラーニング型授業の評価は、従来の評価とは異なる方法で行うことが多いため、どのように評価すればいいか分からなくなってしまう
2.学生側の問題点
- 目的理解の不足:
目的の伝達が不十分で、何のための活動か分からないまま行動する学生は、能動的になりづらい傾向がみられる - 基礎知識の欠如:
学生の中には、演習/実習に最低限必要な知識を覚えていない場合がある。演習/実習前に全体へ確認するか、学生同士(グループなど)で教え合いや学び合い学習をさせる - 協働への苦手意識:
グループワークに苦手意識を持つ学生は少なからず存在する。少しずつ体験させ、慣れさせる必要がある - 「受動的な学習からの脱却」の難しさ:
受動的な学習に慣れている学生は、主体的に参加するアクティブラーニングを難しく感じる場合がある。自ら意見を述べることに抵抗を感じる学生は少なくない。学生が慣れるまで継続することが求められる - 学習意欲の個人差:
多少の差は仕方がないが、差が大きい場合は対応が必要。グループで協働する場合、一部の主体的な学生だけに負担がかかってしまうことがある
次回に向けて
今回は、「演習/実習型授業の効果を高めるアクティブラーニング(AL)型授業法(前編)」として、アクティブラーニング型授業を行う上での留意点を中心にお伝えしてきました。次回は後編として、アクティブラーニング型授業の基本構成や成功のための意識、ポイントなどを詳しくお伝えします。
\ぜひ投票お願いします/
村上 敬一
RTF教育ラボ代表/教育コンサルタント/東京都杉並区内中学校学校運営協議会委員
全国の公立および私立の小学校・中学校・高等学校、専門学校、塾などで教員研修、講師研修、授業や学級経営を中心とした教育全般に関するアドバイスを行う。また、現在まで18年間に渡り、毎年約150名の教員志望者を育成。年間の授業観察数は300を超え、これまでに約5000の授業を観察している。
RTF教育ラボ(https://goseminarcourse01.wixsite.com/rtfkyouikulab)