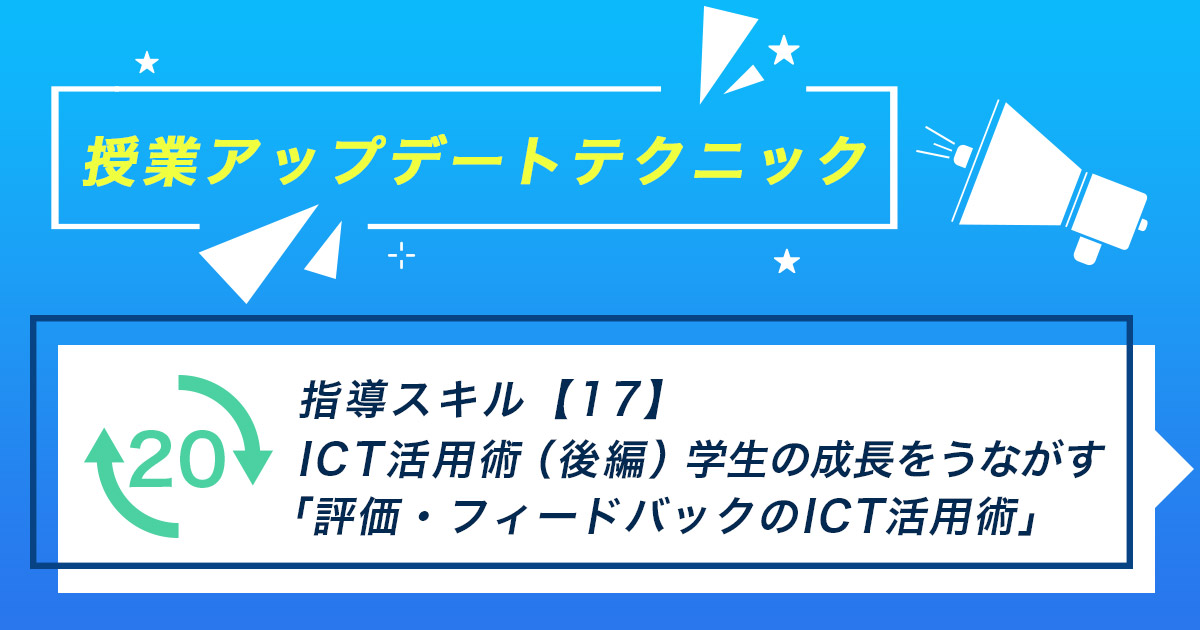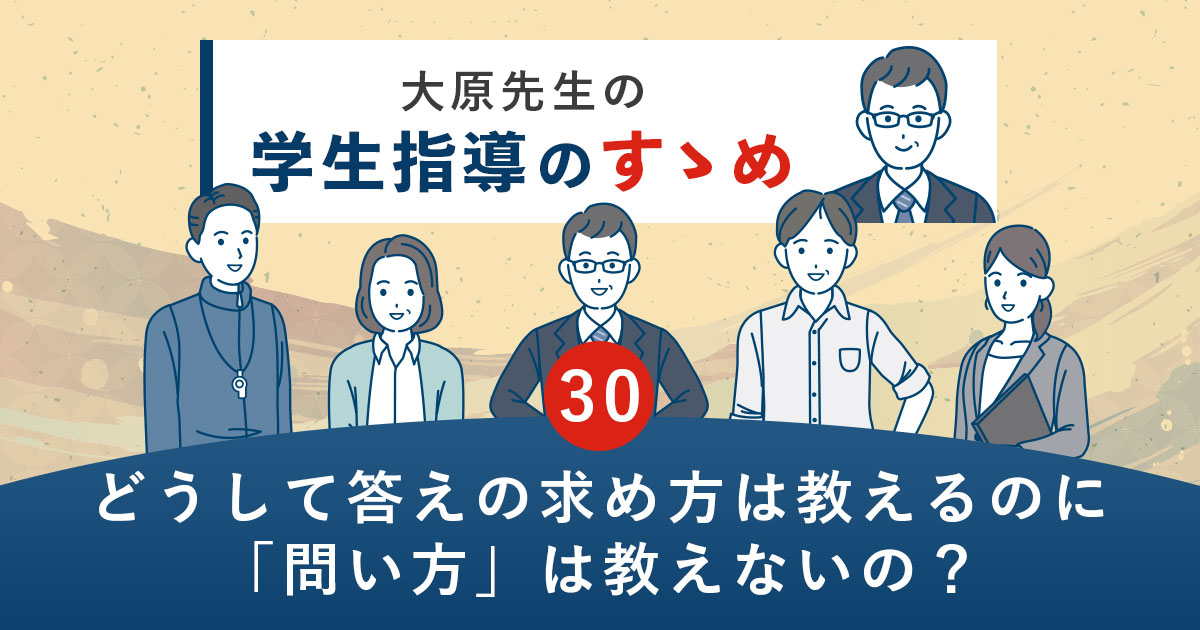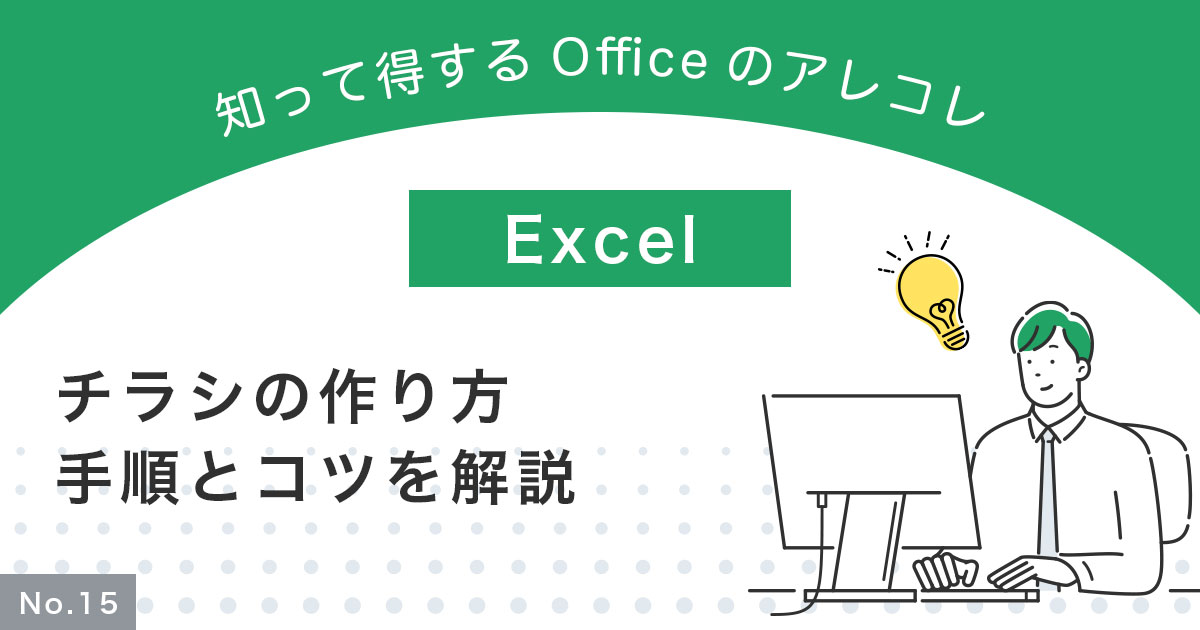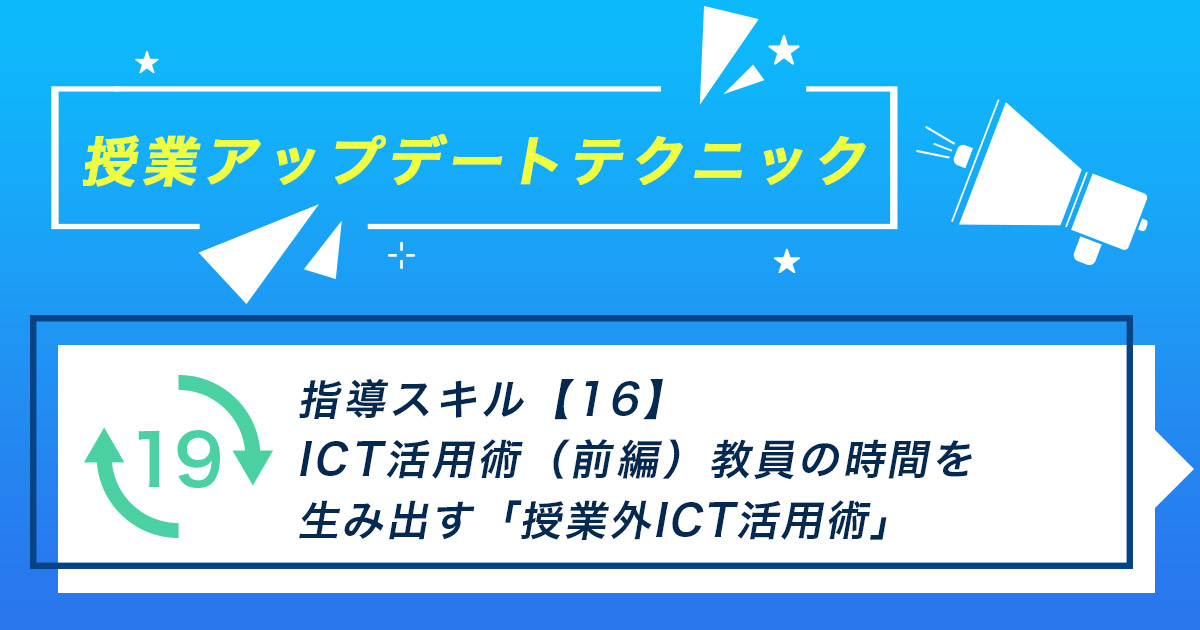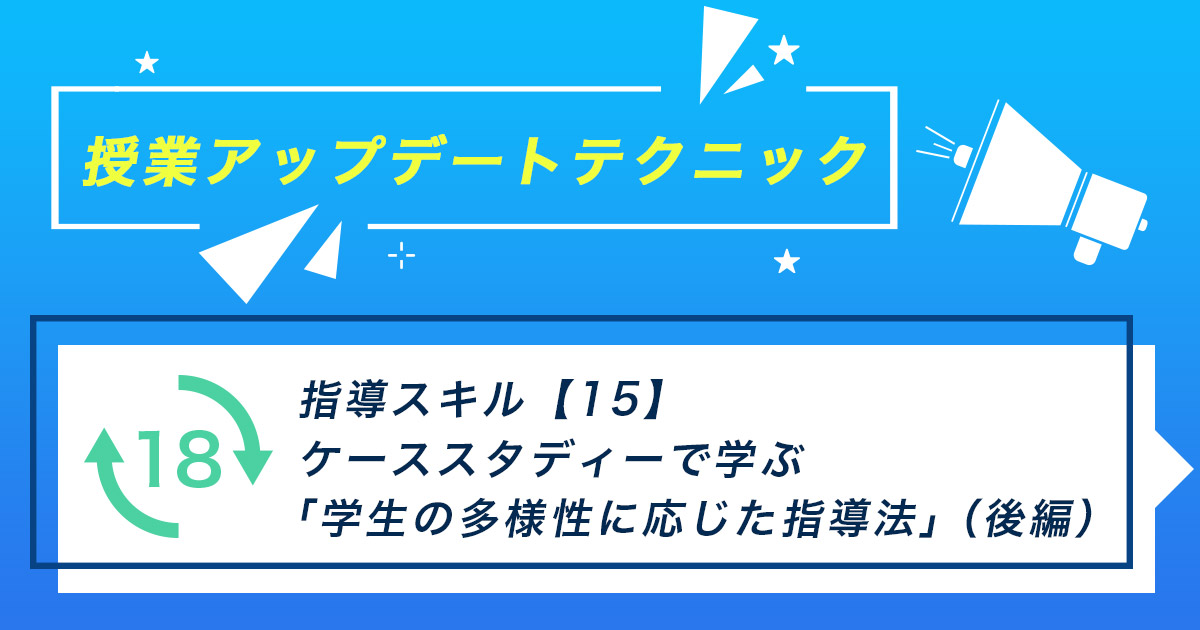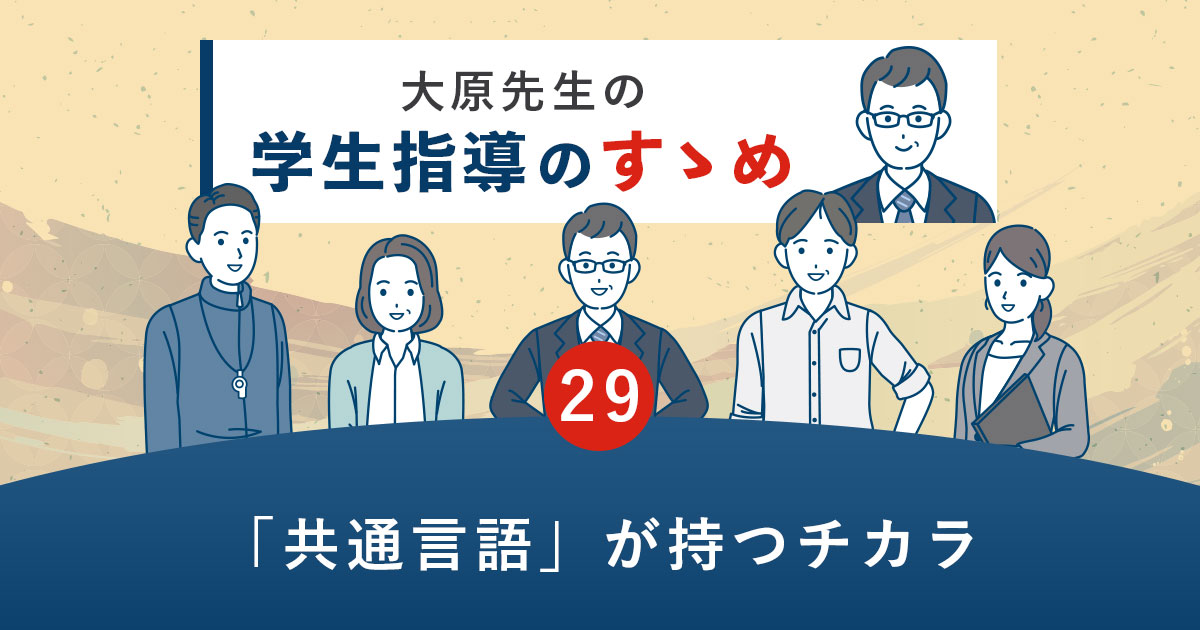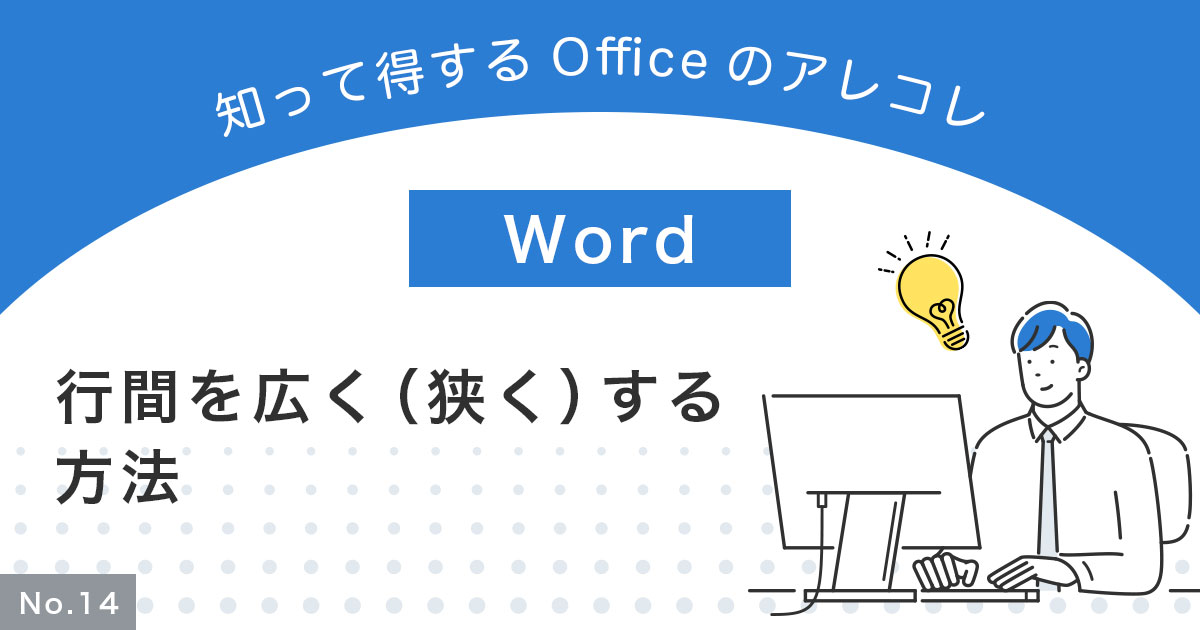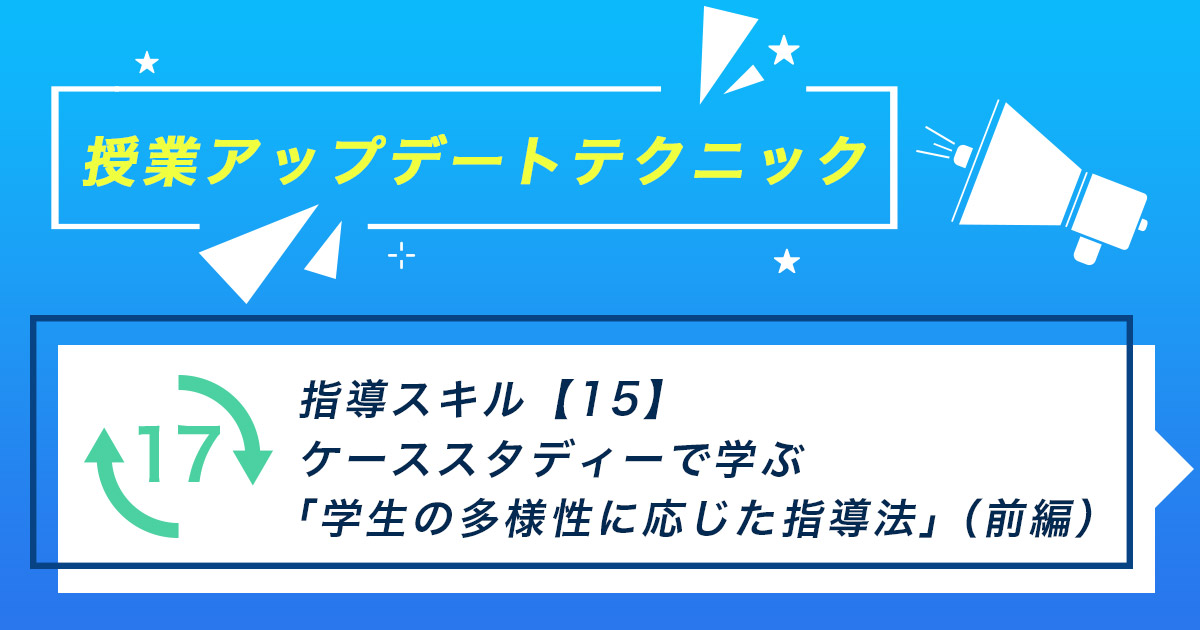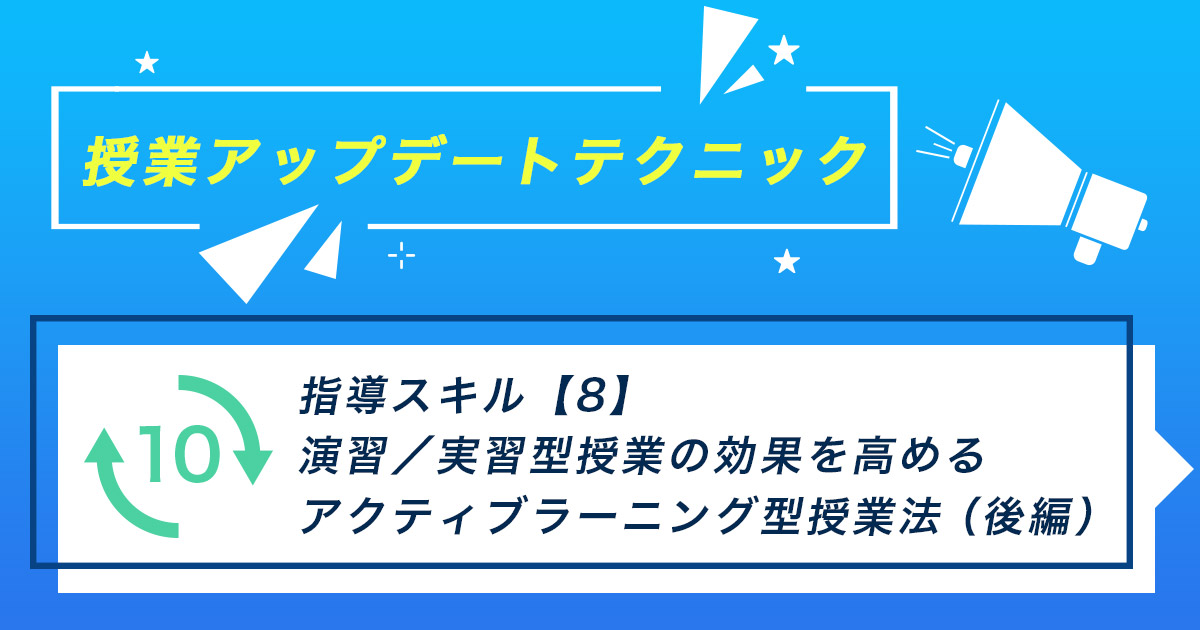
連載授業アップデートテクニック
変化する学生のニーズ、技術やツールの進歩、多様性の受け入れなど、常に進化が求められる現代の教育現場。授業をアップデートしなくてはいけない時期が到来しています。この連載では、教員向け研修や教員志望者の育成を行う「RTF教育ラボ」の代表で、年間300もの授業観察を行う教育コンサルタントの村上敬一さんから、専門学校の先生に向けた「令和の授業テクニック」を教えてもらいます。
まもなく新年度が始まりますね。今回は前回に引き続き、「演習/実習型授業の効果を高めるアクティブラーニング(AL)型授業法(後編)」をお伝えします。
念のため「アクティブラーニング」の定義を確認しますと、小テストやレポートであっても、学生が能動的に取り組んでいればアクティブラーニングと捉えています。逆にグループワークであっても、ただ受動的に参加している場合は、アクティブラーニングとは言えない可能性もあるということです。
前回の記事はこちらからご覧ください。また、「指導スキル(4)~心理学を活用したモチベーションUP術」、「指導スキル(2)~学生の思考力を鍛える『発問』」も併せて読んでいただくと、より効果が見込まれますので、ぜひご覧ください。
目次
アクティブラーニング型授業(グループ活動あり)の基本構成

グループ活動を中心とした、アクティブラーニング型授業の基本的な構成は以下のとおりです。
1.趣旨説明
授業の目的や課題を説明し、個人やグループでの達成目標を共有します。学生にとって具体的なイメージがしづらい演習の場合は、教員や学生の代表によるデモンストレーションを行い、行動イメージを明確に持たせることが重要です。
2.個人活動
今回の課題解決や目標達成に必要だと考える情報収集と整理を、個人で行わせます。この時点でグループワークを行うと、まじめな学生や優秀な学生に任せてしまい、考えなくなる学生が出る可能性があります。そのリスクを減らすためにも、個人で考える時間が必要です。
3.グループ活動
最初に個人で考えた内容について1人ずつ発表し、グループ内で共有します。その後、グループ内で課題解決や目標の達成に向けて、話し合い及び実演や演習などの活動を行います。状況によっては、他グループの演習を観察させ、自グループの演習に改良を加える活動を行うように促します。
4.全体共有
課題解決や活動の結果をグループの代表が発表し、他グループと共有します。発表しないグループへは「質問を考えながら聞くこと」と指示を出しておくと、発表をより真剣に聴くようになる効果があります。また質問されることにより、グループ内の話し合いでは気づかなかった「新しい視点」が見つかる可能性も増します。
教科や単元にもよると思いますが、単なる共有のための発表ではなく、プレゼンテーションとして提案させることで、伝える力の向上につなげても良いでしょう。
5.振り返り
学生に自らの学びを振り返らせる「リフレクション」、グループ内の学生から良かった点や改善点などのアドバイスをもらう「フィードバック」、グループとして次回に向けた話し合いの方向性を定める「フィードフォワード」の時間を設けることで、学習が継続的になりやすくなります。また、知識理解が目的の場合は「小テスト」も振り返りとなります。
振り返りは、「上手くいった/いかなかった」という感想ではなく、以下の3点を軸に行いましょう。
【振り返りのポイント】
(1)目的や目標に対して達成度合いがどうであったかという「アチーブメント」
(2)何が要因だと考えるかという「分析」
(3)どのようにすればより良くなると考えているかという「未来思考」
基本構成における注意点
グループや全体の構成において気を付けるべきことは、以下の5点です。
1.グループの人数
グループの人数は4名程度が適切です。毎回同じメンバーで行うより、変えたほうが効果は高いため、少なくとも1カ月に1回はグループを変えたほうが良いでしょう。
2.グループメンバーの構成
初期段階では友人同士でグループを組ませても良いですが、できるだけ交流がない人同士で組ませるほうが良いでしょう。男女混合グループのほうが良いですが、はじめは話し合いが活性化しない場合もあるので、しばらくは様子をみることが必要です。
3.グループ内の役割分担
初期段階では司会進行役や書記兼内容調整役、発表役、時間調整役など役割を指示したほうが話し合いは進みやすいでしょう。ただし、慣れてきたら役割分担と決定を含めて、グループに任せるようにしましょう。
4.時間設定
話し合いの時間設定は1人3分×人数+αで決めるのがおすすめです。例えば4人グループの場合は【3分×4人+3分=15分】を目安にしましょう。課題が難しく時間がかかりそうな場合は、この限りではありません。
5.構成と時間の共有
上述の基本構成(趣旨説明/個人活動/グループ活動/全体共有/振り返り)と大まかな時間構成は、学生が確認できるように板書やスライドなどで提示しましょう。
アクティブラーニング型授業(グループ活動あり)を成功させるためのポイント
1.環境と雰囲気づくり
リレーション
学生同士の人間関係のことです。アクティブラーニング型授業では普段友人ではない、複数人との活動が多くなります。そのため「苦手な人とも協働できる」人間関係が必要です。4月の段階やグループ再編成時にはアイスブレイクやエンカウンターの活動を取り入れて、人間関係の構築をサポートしましょう。
ルール
グループでの活動や話し合いにおいて確認しておいたほうが良いことは、あえてルールとして伝達することをお勧めします。教員が「当たり前」と思っていることでも、学生からすると「当たり前ではない」ことが意外に多いものです。
環境の整備
自由に意見交換ができる雰囲気づくりや、適切な場の提供も大切です。例えば、ICT機器やホワイトボードなど記録できるツール、照明の明るさや室温、机や椅子の配置なども重要な要素です。学生が意見を述べやすいように、安心できる学習環境をサポートしましょう。学習環境の整備自体を学生に考えさせることも良い方法です。
2.授業設計
明確な目標設定
何度も伝えていますが、授業の目的や到達点を明確にして共有しましょう。また、目標や課題の設定レベルも大切で、学生の能力より少し上のレベルを意識しましょう。そしてなにより、毎回の授業で目的や到達点を学生に伝えて、学生の中で習慣化することが重要です。
多様な活動の導入
学生にさまざまなスキルを身に付けさせるために、多様な活動を取り入れることもおすすめです。例えば、ディスカッション、ディベート、プレゼンテーション、ロールプレイ、ケーススタディ、ケースメソッド、デモンストレーション、実践的なプロジェクトなど、さまざまな活動を取り入れてみましょう。
フィードバックとリフレクション
学生の取り組みに対してタイムリーなフィードバックを行い、学びをサポートすることが大切です。例えば、授業後に簡単なフィードバックシートを配布し、学生の意見を収集して、それに対してコメントするなどの方法です。また、学生自身で振り返る「リフレクション」も重要です。リフレクションが上手な学生は、スキルの習得も早くなる傾向にあります。
効果的なファシリテーション
グループ内で1人はファシリテーターをできる学生がいることが理想です。教員側の意識として「ファシリテーターの育成」を持っておいてください。ファシリテーターに必要な要素に関しては、別の機会にお伝えします。
3.評価方法
プロセスの評価
学生の取り組みのプロセスや参加態度を評価します。例えば、授業中のディスカッションやグループワークでの発言の質、役割の達成状況を評価ポイントとします。学生の学習過程や成果をポートフォリオとしてまとめ、評価する「ポートフォリオ評価」が「プロセスの評価」の1つです。
成果(物)の評価
グループワークやディスカッションの成果物を評価対象とします。例えば、最終的なプレゼンテーションやレポートの内容を評価します。また、グループとしての評価は一定の場合もあれば、グループ内の活躍度合いによって差をつける場合もあります。評価項目を明確にし、到達度を基準に評価する「ルーブリック評価」が「成果の評価」の1つです。
自己評価と相互評価
学生自身による自己評価や他の学生からのフィードバックを相互に行う相互評価を実施します。学生の主観が強く反映される場合があるので、成績の評価に取り入れる場合は慎重に進める必要があります。
まとめ
前回、今回と「演習/実習型授業の効果を高めるアクティブラーニング(AL)型授業法」をお伝えしてきました。アクティブラーニング型授業は、現代社会で求められる能力を育むための効果的な教育方法です。教員の工夫とサポートが求められますが、その効果は大きく、学生の主体的・協働的な学びを促進します。
来年度、授業での実践を通じて、アクティブラーニング型授業を最大限に活用し、学生の更なる成長を促していきましょう。
\ぜひ投票お願いします/
村上 敬一
RTF教育ラボ代表/教育コンサルタント/東京都杉並区内中学校学校運営協議会委員
全国の公立および私立の小学校・中学校・高等学校、専門学校、塾などで教員研修、講師研修、授業や学級経営を中心とした教育全般に関するアドバイスを行う。また、現在まで18年間に渡り、毎年約150名の教員志望者を育成。年間の授業観察数は300を超え、これまでに約5000の授業を観察している。
RTF教育ラボ(https://goseminarcourse01.wixsite.com/rtfkyouikulab)