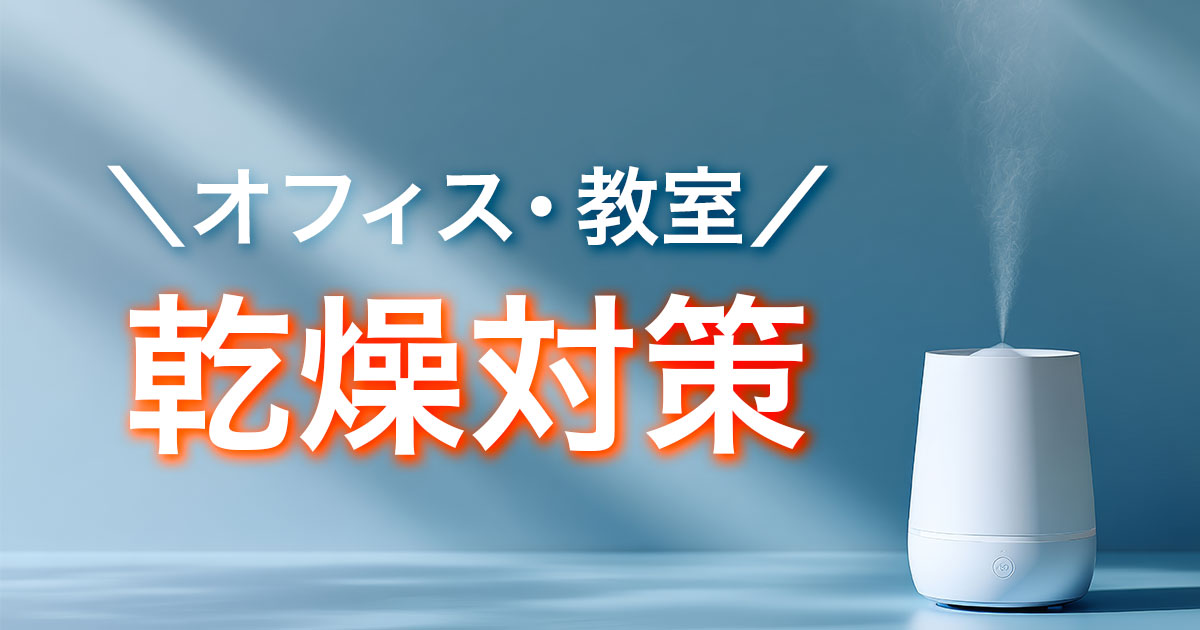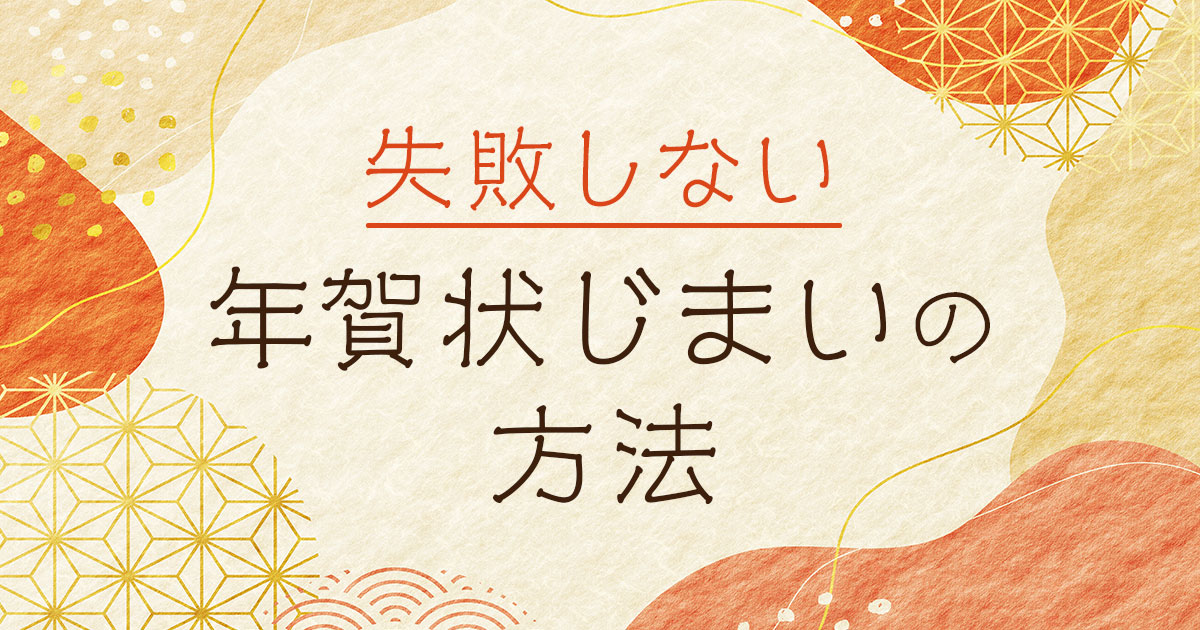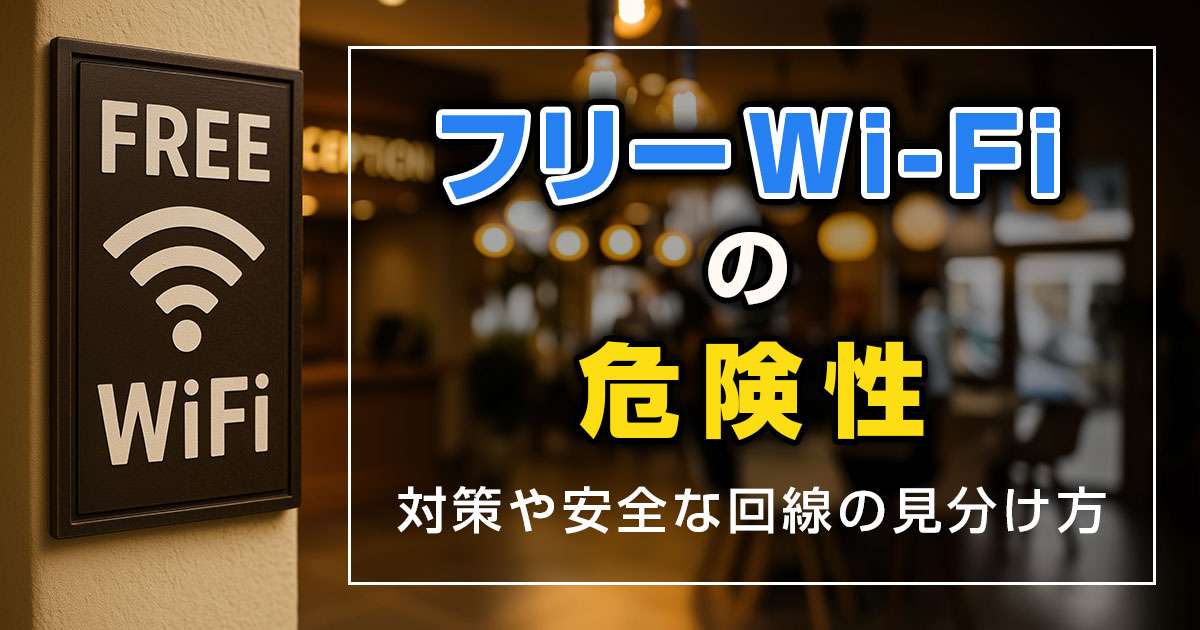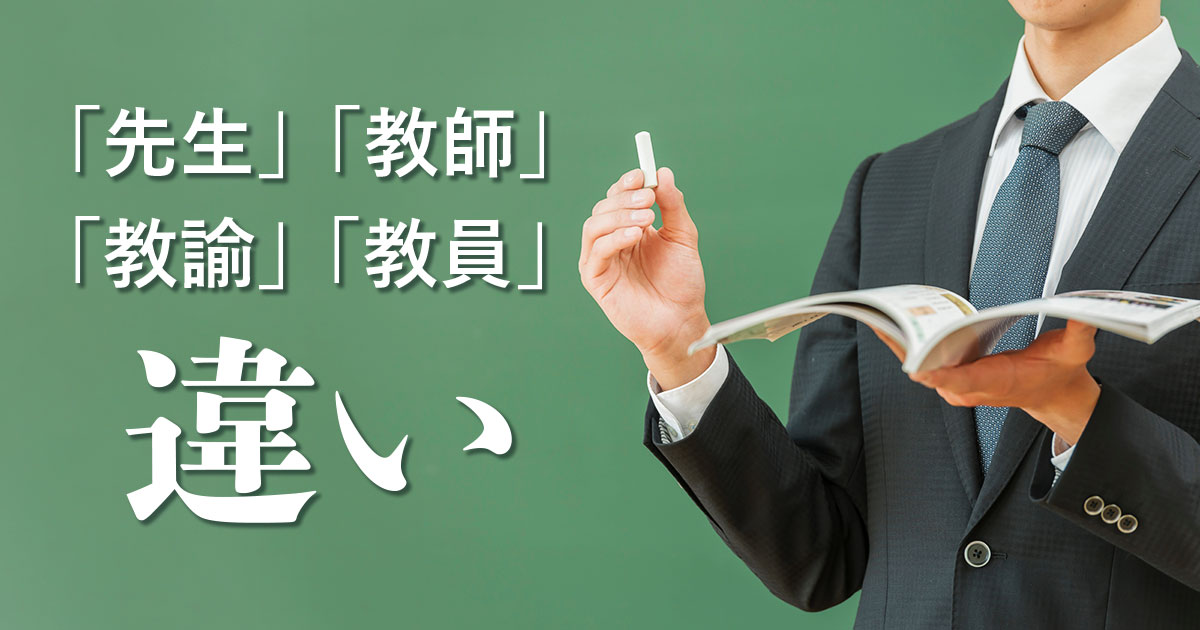
カフェオレはドリップコーヒーにミルクを入れたフランス語、カフェラテはエスプレッソにミルクを入れたイタリア語。
シェイクはシェイカーでミルクと果物などを混ぜたもの、スムージーは凍らせた果物などをシャーベット状にしたもの。
ちゃんと説明される機会は少ないけれど、「たぶんこういう違いがあるのかな?」と自己解決したままの言葉ってありますよね。
今回はそんな微妙な差のある言葉のうち、学校生活にまつわる言葉について解説していきます。
目次
先生・教師・教諭・教員の違い
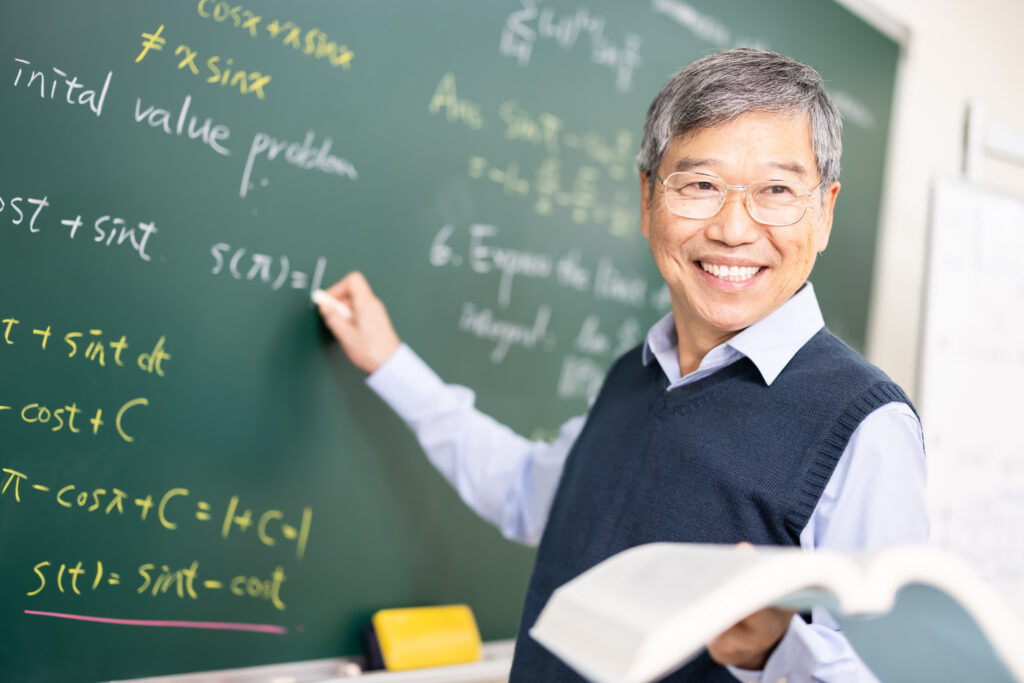
まずは「先生」にまつわる言葉について、以下4つの言葉をピックアップ。その差をまとめました。
・先生
・教師
・教諭
・教員
先生とは
「先生」と聞くと、やはり中心となるイメージは「teachする人」ではないでしょうか。
例えば、
- 学問を教えてくれる人(学校・塾の先生など)
- 技術を教えてくれる人(スキーやピアノの先生など)
などがすぐに思いつきます。
また、「先生」は人を指導する立場の人や学問・技術の専門性が高い人にも使いますよね。
例えば、
- 人を指導する立場にある人(政治家など)
- 学問・技術の専門性が高い人(医師・音楽家・芸術家・漫画家など)
などが挙げられます。
「先生」という言葉は教えてくれる人、または敬意の対象となる人に使うようです。
教師とは
「教師」という言葉は、
- 学問を教えてくれる人(数学教師・家庭教師など)
- 文化や道徳を教えてくれる人(宣教師など)
などを表すときに使いますよね。
“師”という言葉には手本となる人という意味があるため、道徳的な部分まで教え導くイメージが強いのがこの「教師」という言葉のようです。
教諭とは
こちらは格式高いイメージがありますね。
「教諭」とは正規雇用されている、教育や保育をする人を指します。
非正規雇用の先生の場合は「講師」と呼ばれますのでご注意ください。
また、「教諭」は学校教育法などで定められた主幹教諭、司書教諭といった職位を意味することもあります。
正規雇用された学校の先生や先生の職位を指すとき、「教諭」を使うとおさえておきましょう。
教員とは
こちらも「教諭」同様に、先生の仕事をしていない人はほとんど使わない言葉でしょう。
「教員」は学校をはじめとする教育機関で保育や教育をする人を指します。
教育基本法第九条でも、
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
教育基本法第九条第二項
と、学校の先生を示す言葉として「教員」という言葉が使われています。
また、教育職員免許法では「教員」という言葉を以下のように定義しています。
第二条 この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。
教育職員免許法第二条
学校で教育を行う教育職員。これが「教員」というわけです。教諭と講師を合わせたものと考えてもよいでしょう。
先生・教師・教諭・教員の違い まとめ
違いについて一覧にまとめました。
| 「先生」にまつわる言葉 一覧 | |
|---|---|
| 先生 | 人を指導する立場の人や学問・技術の専門性が高い人 |
| 教師 | 学校などで指導し、道徳的な部分まで教え導くイメージが強い人 |
| 教諭 | 学校で正規雇用されている、教育や保育をする人 |
| 教員 | 学校をはじめとする教育機関で保育や教育をする人 |
いかがでしょうか。先生の対象は幅広いです。
なので政治家や医師などが「先生」と呼ばれているのですね。
児童・生徒・学生の違い

続いて「学生」にまつわる言葉について、以下3つの言葉をピックアップしました。
それぞれの言葉がどのような人を対象としているか知っておきましょう。
・児童
・生徒
・学生
児童とは
「児童」は、法律によって定義が異なります。
例えば、
- 学校教育法:初等教育小学校・義務教育学校※の前期課程(前期6年間)・特別支援学校の小学部で学ぶ人
- 児童福祉法、児童虐待防止法、児童の権利に関する条約など:18歳未満の人
- 道路交通法:6歳以上13歳未満の人
- 児童扶養手当法:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの人
となっています。
※義務教育学校…2016年に制度化された学校形態の一つ。小学校・中学校を一貫して教育を行ういわゆる小中一貫校のうち、さらに小学校と中学校における垣根を取り払った9年制の学校。学校にもよるが、中学校1年生にあたる年を7年生と呼ぶ。
一般には小学生を指す言葉だとおさえておくとよいですが、例外もあると知っておきましょう。
生徒とは
「生徒」は、中学校・高等学校・義務教育学校の後期課程(後期3年間)・特別支援学校の中学部および高等部・中等教育学校※で学ぶ人が対象となります。
※中等教育学校…1999年に制度化された学校形態の一つ。中学校・高等学校を一貫して教育を行ういわゆる中高一貫校のうち、さらに中学校・高等学校の垣根を取り払った6年生の学校。学校にもよるが、高校1年生にあたる年を4年生と呼ぶ。
こちらは中学生・高校生を指す言葉だとおさえておくとよいでしょう。
学生とは
「学生」は、短大、大学、大学院、高等専門学校(高専)などで学ぶ人が対象となります。言い換えれば、高等教育を受ける人を指す言葉です。字のごとく、学びに集中した生活を送る学生だとおさえておきましょう。
学校教育法では小学校などの初等教育では「児童」、中学・高校などの中等教育では「生徒」、大学などの高等教育では「学生」と明確に使い分けがされています。公文書の作成の際には気を付けましょう。
児童・生徒・学生の違い まとめ
違いについて一覧にまとめました。
| 「学生」にまつわる言葉 一覧 | |
|---|---|
| 児童 | 主に小学生に用いる。法によって使い分けがある |
| 生徒 | 主に中学生・高校生に用いる |
| 学生 | 主に短大生、大学生、大学院生、高専生に用いる |
特に「児童」の範囲については就職試験でも問われることもありますので、学生に伝えてみてくださいね。
専門学生は生徒?学生?
学校教育法では専修学校(専門学校・高等専修学校などの総称)に関する記述に「生徒」が使われていますが、実際には学校や先生によって呼び方が違います。
様々な技術を身につけてもらいたい学校・先生は「生徒」、机に向かう勉強を頑張ってほしい意識が高い学校・先生は「学生」と言うことが多いような気が私の体感としてあります。
【おまけ】進学とともに変化する言葉
ほかにも小学校→中学校→高校→専門学校・大学へと進学とともに変わる言葉をまとめてみました。
算数と数学の違い
こちらはざっくりいえば、証明をするかどうかです。計算をして答えを導く能力を育てるのが「算数」。数字を学問として研究し、AはBか?と考えるために必要な能力を育てるのが「数学」です。
運動会と体育祭の違い
いずれも学習指導要領上では特別活動に位置する学校行事です。その目的は小学校も中学校もほとんど同じです。
参考:文部科学省『小学校学習指導要領 第6章 特別活動』『中学校学習指導要領 第5章 特別活動』
しかし、運営する主体が異なります。体育祭は「実行委員会」が発足され生徒主体で運営されますが、運動会は先生が運営するのが実態です。ここに差があります。なお、あまりにも先生主体の行事にならないように、小学校学習指導要領解説※には「児童自身のものとして実施することが大切である。」という記載が入っています。
参考:文部科学省『【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説』
プリントとレジュメの違い
プリントはプリントです。印刷物です。英語で配布物はhundoutなので英語圏でプリントといっても通じないので注意。対するレジュメは要約を表すフランス語です。
今までプリントと言っていたのに、急に学生になるとレジュメと呼ばれます。初めて「レジュメ」と聞くと全くどんな意味か想像ができない言葉のため、春先にSNS上でよく炎上しています。
カリキュラムとシラバスの違い
カリキュラムとは、ゴールに向かうための総合的な学習目標や計画を指します。言い換えると、教育課程です。このカリキュラムに則り、年間、数か月単位の授業計画として示されるものがシラバスです。
シラバスもレジュメ同様に、急に耳にする用語です。学生に違いを教えてあげると喜ばれますよ。
おわりに
いかがでしょうか。「たぶんこういう違いがあるのかな?」が「こういう違いがあるんだ」に変わっていると嬉しいです。他にも先生が気になる言葉がありましたら、ウイナレッジ編集部まで教えてください!
\ぜひ投票お願いします/
宇井 馴次 (うい なれじ)
ウイナレッジ編集部所属のバーチャルヒューマン
双子の父でありプロレス好き
毎週金曜日はスタバでベンティサイズのフラペチーノを嗜む