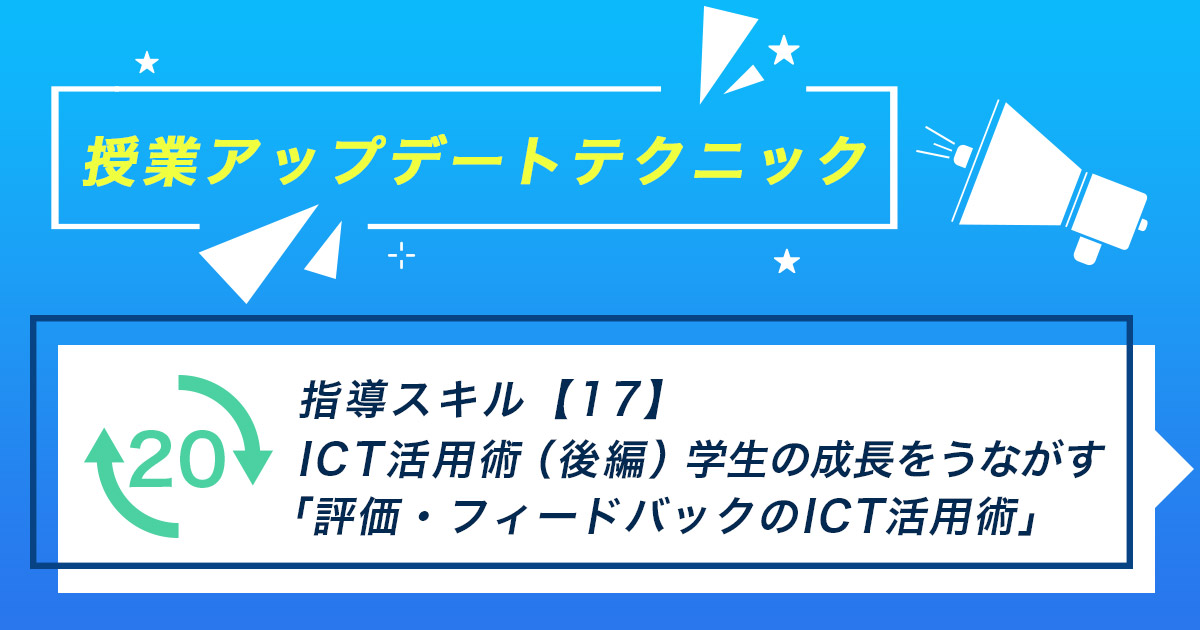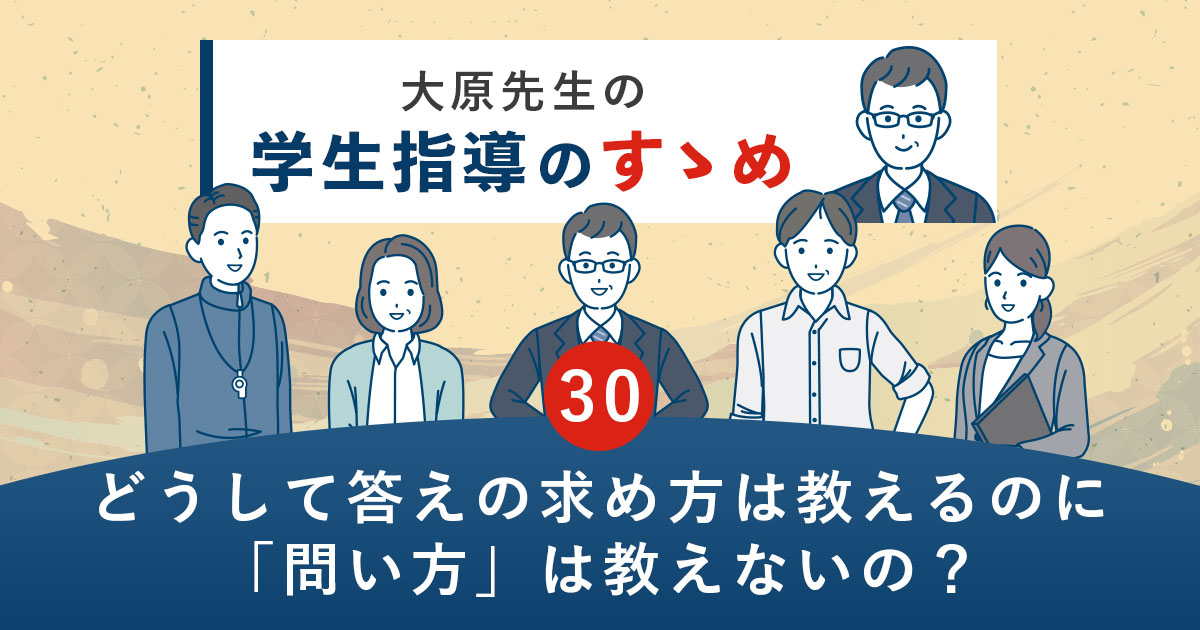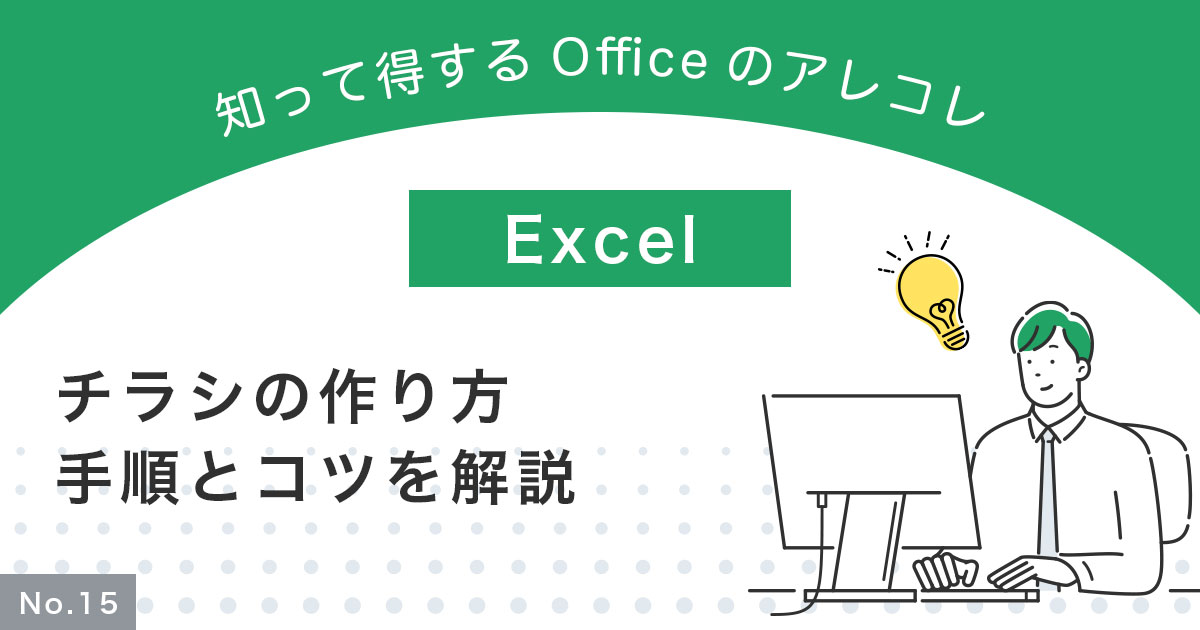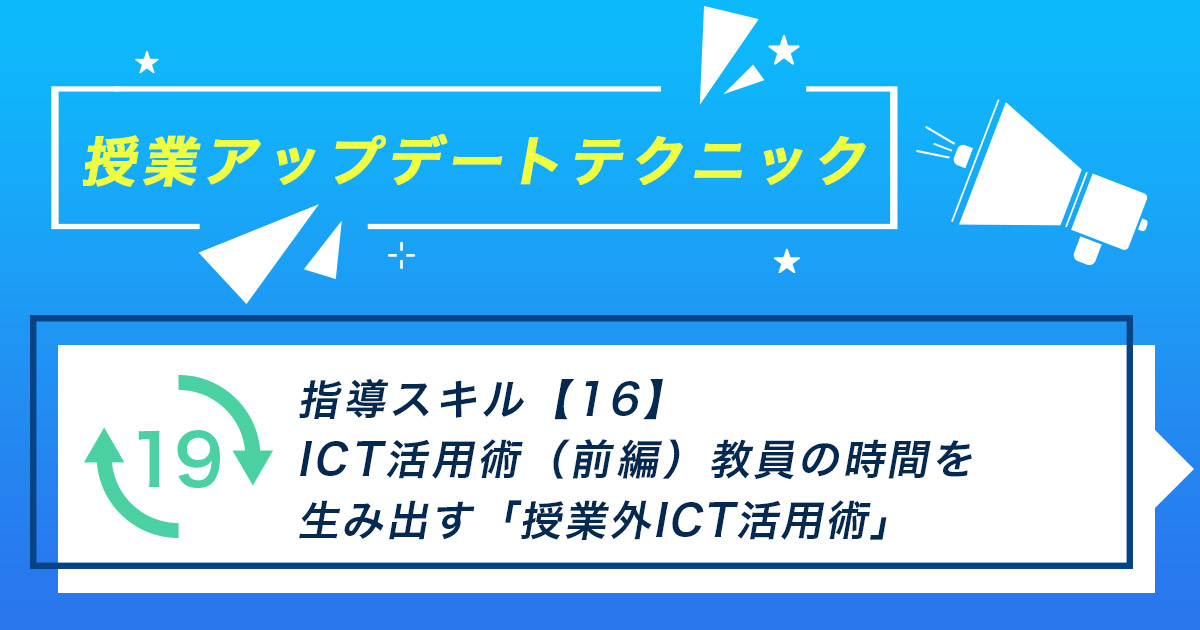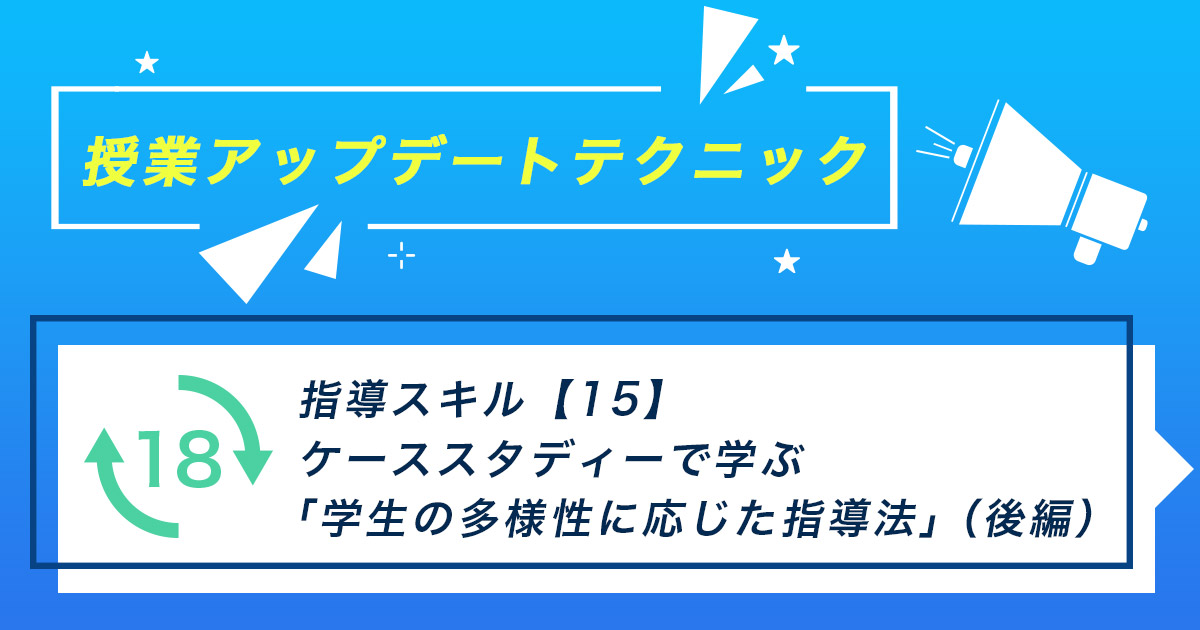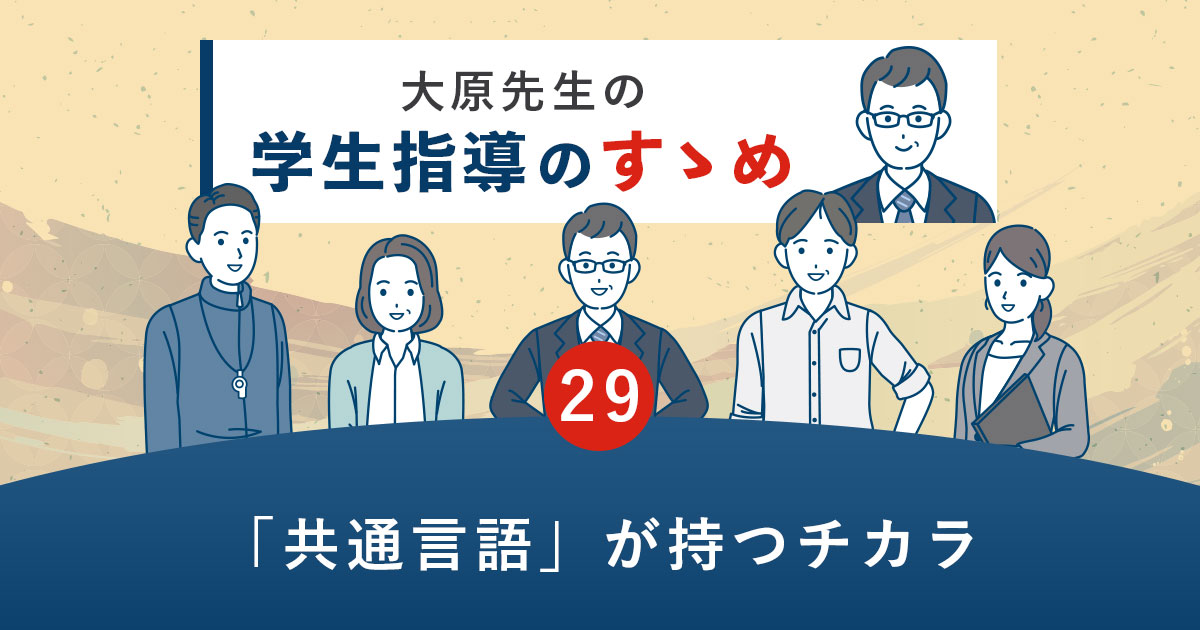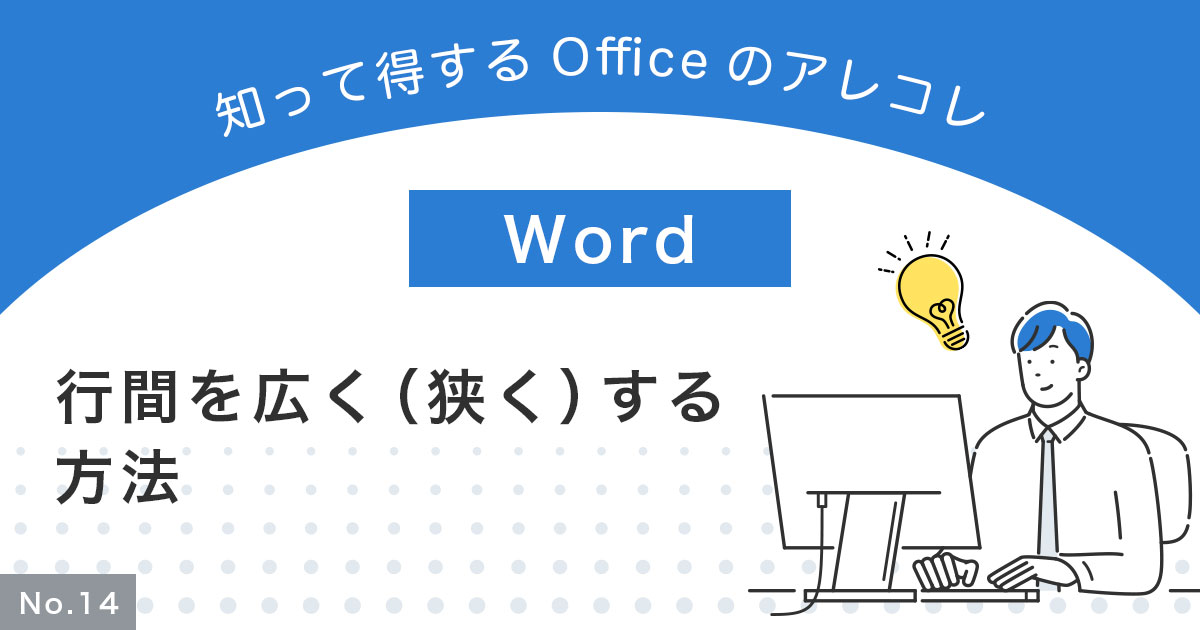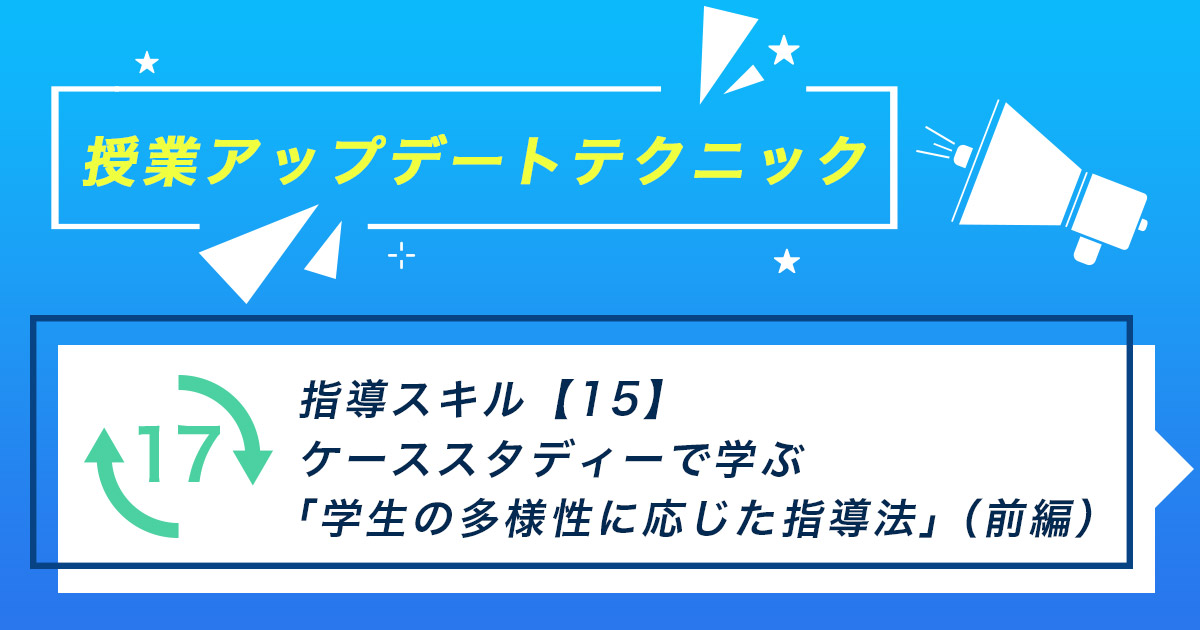新生活が始まり、あっという間に数カ月が経とうとしています。新しい出会いや体験を楽しむ学生がいる一方で、周囲に馴染めず孤立している学生が増えているのをご存じですか?放置すれば、学校生活に嫌気が指して自ら退学を選択する恐れも。
学校は単に知識を習得するだけでなく、人間関係を築いて社会性を養う重要な場でもあります。本記事では、孤立しやすい学生の特徴や対策をまとめました。全員が楽しい学校生活を送れるよう、先生側もサポートしていきましょう。
おすすめの資料

【中退防止】今すぐ使える!モチベーション低下対策チェックリスト
目次
新生活スタート直後から「ぼっち」で悩む学生が増えている
実際どのくらい孤立に悩む学生がいるのか、正確なデータはありません。しかし、Web上で学生の声をリサーチすると、新生活開始から周囲に馴染めず、人間関係に悩む学生が多く見受けられました。
専門学校に入学したのですが、ぼっちのような状態になってしまいました。話せる人は1人いるけれど、いろいろネガティブに考えてしまい、周りがみんな敵に見えてしまいます。お弁当も1人です。
専門学校でぼっちになっちゃった。入学式からグループができているから入りにくい。自分から話しかけて連絡先を交換した子はいるけど頻繁にしゃべる感じでもないし、もう1人でもいいかな。
専門学校に入学して5日目。入学式の時点でグループができていて、うまく輪に入れませんでした。実習中や昼ご飯のときも常にぼっち。思い切って隣の子に声をかけたら、嫌な顔をされたように思えます。それからはぼっち飯です。この学校に入ったことを後悔しています。
専門学校の場合は同じ専門性や目標を持つ者同士が集まるため、気の合う仲間に出会いやすいのが特長です。しかし、状況によっては馴染めないケースもあります。先生側でも、常に気にかけておくことが大切です。
孤立しやすい学生の特徴5つ

学校生活で孤立してしまう学生には、いくつか共通項があります。主な特徴は、次の5つです。
- 自分から話しかけるのが苦手
- クラスの雰囲気が合わないと感じている
- 空気を読めているか不安で積極的に行動できない
- 強い劣等感を持っている
- SNSに参加していない
それぞれ解説します。
1.自分から話しかけるのが苦手
人見知りや内気な性格で積極的に話しかけることが苦手な学生は、周囲との距離を縮めることが難しく孤立するケースがあります。特に、新しい環境や人間関係に慣れるまでは緊張や不安を感じやすく、なかなか自分を出せません。気づけば周囲から乗り遅れ、孤立してしまうのです。
2.クラスの雰囲気が合わないと感じている
思い描いていた理想とは違い、実際の雰囲気が合わないと感じて孤立する場合もあります。周囲が異なる価値観や興味を持っている人ばかりだと、居場所がないように感じてしまうのです。
たとえば「静かに過ごしたいのに、騒ぐのが好きなメンバーばかり」「アウトドアが好きだけどインドア派が多くて話についていけない」などと感じれば、自ら距離を置くようになる学生もいるでしょう。
3.空気を読めているか不安で積極的に行動できない
周囲の雰囲気を察知するのが苦手で、積極的に行動できない学生もいます。相手に話しかけてみたものの、あとで「上手に反応できていたか」「不愉快な思いをさせなかったか」などと気になってしまうのです。結果的に誰かとかかわるのが億劫になり、孤立するケースがあります。
4.強い劣等感を持っている
自分に自信がなく、劣等感を持っている学生も孤立しやすい傾向があります。「話しかけても私なんか相手にしてくれないだろう」「周りに比べて顔もスタイルも劣っている」「返信がこないから嫌われているんだ」などネガティブに考え、周囲との関わりを無意識に避けてしまうのです。
5.SNSに参加していない
近年は、SNSを通じたコミュニケーションが盛んです。たとえば「4月から○○学校○○学科に入学します!仲良くしてください」「私も同じ学校です!よろしくお願いします」などのやりとりも頻繁にあります。
そのため入学式の前からグループが完成しているケースも多く、SNSに参加していない学生が入りにくい雰囲気になっていることもあるようです。
学生をひとりぼっちにしないために!学校側ができる4つの対策

「孤立している学生がいます。仲良くしなさい」とクラス全体に呼びかけることは雰囲気を悪化させかねませんが、放置も問題です。ここでは、学校側ができる対策を4つ紹介します。
- 初日に自己紹介の時間を設ける
- レクリエーションを実施する
- 授業にグループワークを取り入れる
- クラスのメンバーでランチを食べる日を作る
それぞれ見ていきましょう。
1.初日に自己紹介の時間を設ける
積極的な行動は苦手でも、きっかけがあれば話せる学生は多くいます。入学式やオリエンテーションの日に自己紹介の時間を作ることは、学生同士が交流するきっかけとして有効といえるでしょう。
クラスにどのようなメンバーがいるか知ることで、気の合いそうな人や話しかけたい人を見つけやすくなります。自己紹介の内容から会話が弾み、仲良くなるケースも多いです。
2.レクリエーションを実施する
自己紹介と併せて、レクリエーションを実施するのもおすすめです。協力型のレクリエーションを開催すれば、連帯感や達成感を味わえて孤立を防ぐ効果も期待できます。絆も深まりやすくなるでしょう。
また、先生もレクリエーションを通じて学生の性格を把握しやすくなるため、その後のサポートにも役立ちます。おすすめのレクリエーションは以下の記事にまとめたので、併せて参考にしてください。
関連記事:学生同士の関係構築に!入学式後におすすめの学級レクリエーション10選
3.授業にグループワークを取り入れる
先生が一方的に説明するだけの授業では、学生同士で交流できません。そこでおすすめなのが、グループワークです。協力して課題に取り組む機会を作ることで、打ち解けるきっかけができます。また意見交換や役割分担により、コミュニケーション能力や協調性も養えるでしょう。
4.クラスのメンバーでランチを食べる日を作る
孤立した際に悩むのがランチの時間。なかには、トイレに閉じこもって過ごす学生もいます。そのような学生を増やさないためにも、クラスのメンバーでランチを食べる日を作ってみてはいかがでしょうか。
たとえば週に1回、メンバーはランダムに4人と設定すれば、普段はなかなか話せない学生同士が交流を深めるきっかけとなります。先生も参加すれば、学生の様子を把握できるでしょう。
すでに孤立している学生を見つけたら
どんなに学校側が配慮しても、孤立してしまうケースはあります。孤立している学生を見つけたら、さりげなく先生側から話しかけてみるのも一つの方法です。
「学校生活で困ったことはない?」「クラスの雰囲気はどう?」など、さまざまな視点から聞いてみましょう。聞くことで、どのようなサポートが必要か理解しやすくなります。
もしかしたら「きっかけがなくて相手に話しかけられない」などと打ち明けてくれるかもしれません。この場合は、グループワークの時間を提供することで解決できる可能性が高まるでしょう。
「自分から話題が提供できずに沈黙が怖い」と悩む学生がいれば「まずは相手の話を聞くことに集中してみよう」などとアドバイスするのも有効です。
まとめ
学生が人間関係を築くにあたって、必要以上に先生が介入するのは避けるべきです。しかし、見て見ぬふりをすれば退学者が出る恐れもあります。先生側にできる配慮や工夫で学生の孤立を防ぎ、全員が楽しく学校生活を送れるようサポートしましょう。
おすすめの資料

【中退防止】今すぐ使える!モチベーション低下対策チェックリスト
\ぜひ投票お願いします/
株式会社ウイネット
ウイナレッジを運営している出版社。
全国の専門学校、大学、職業訓練校、PCスクール等教育機関向けに教材を制作・販売しています。