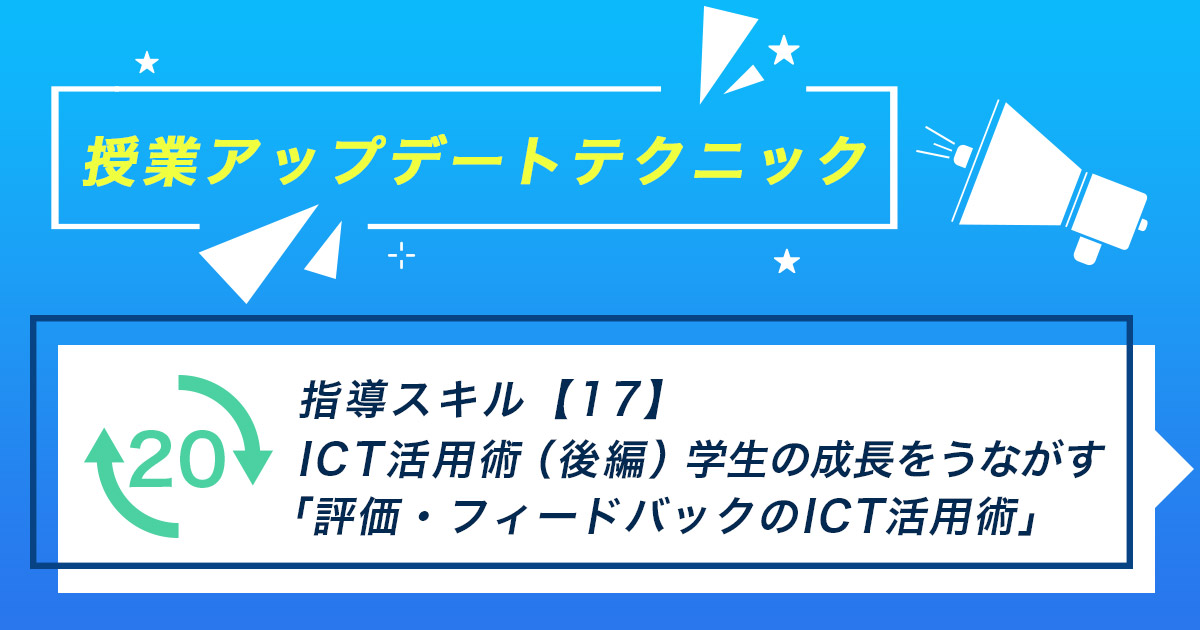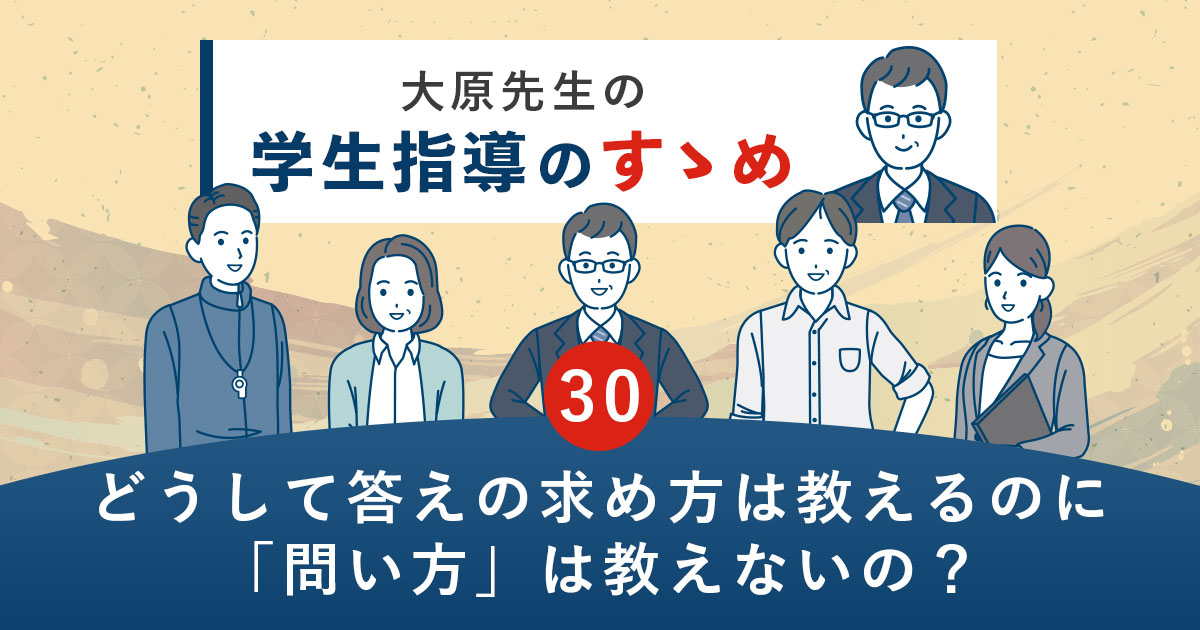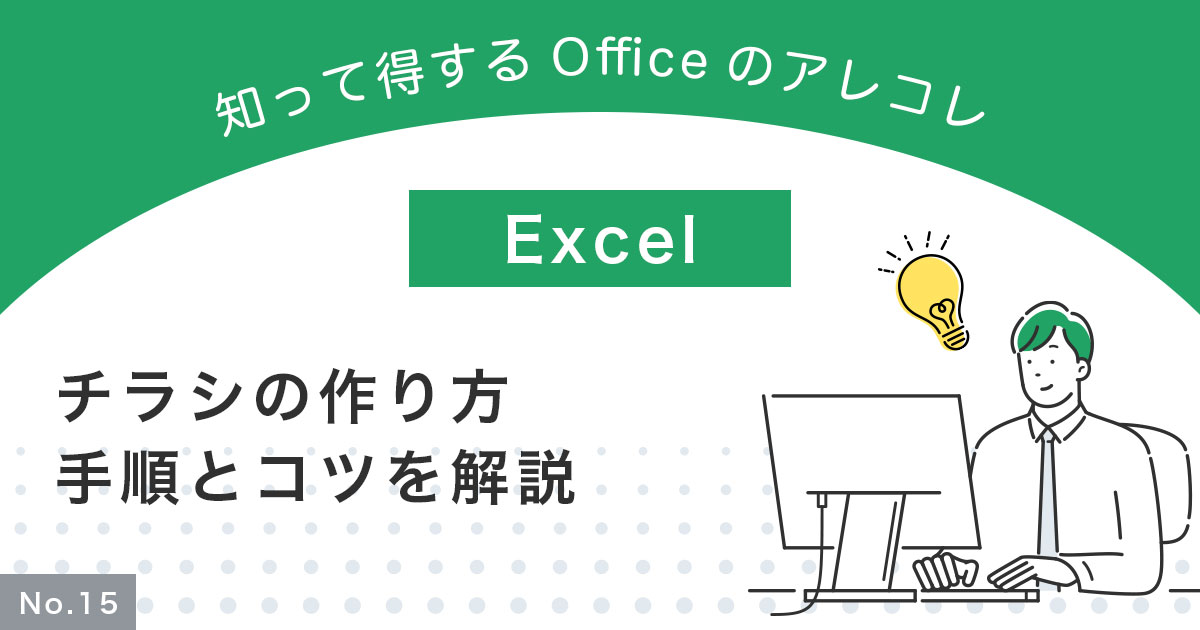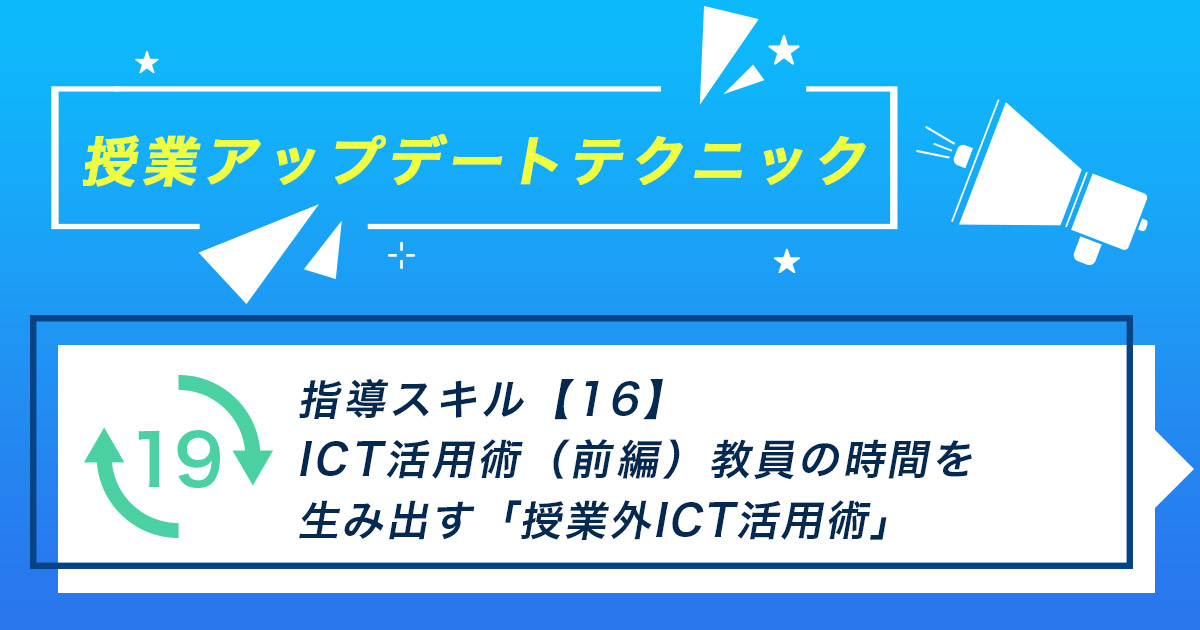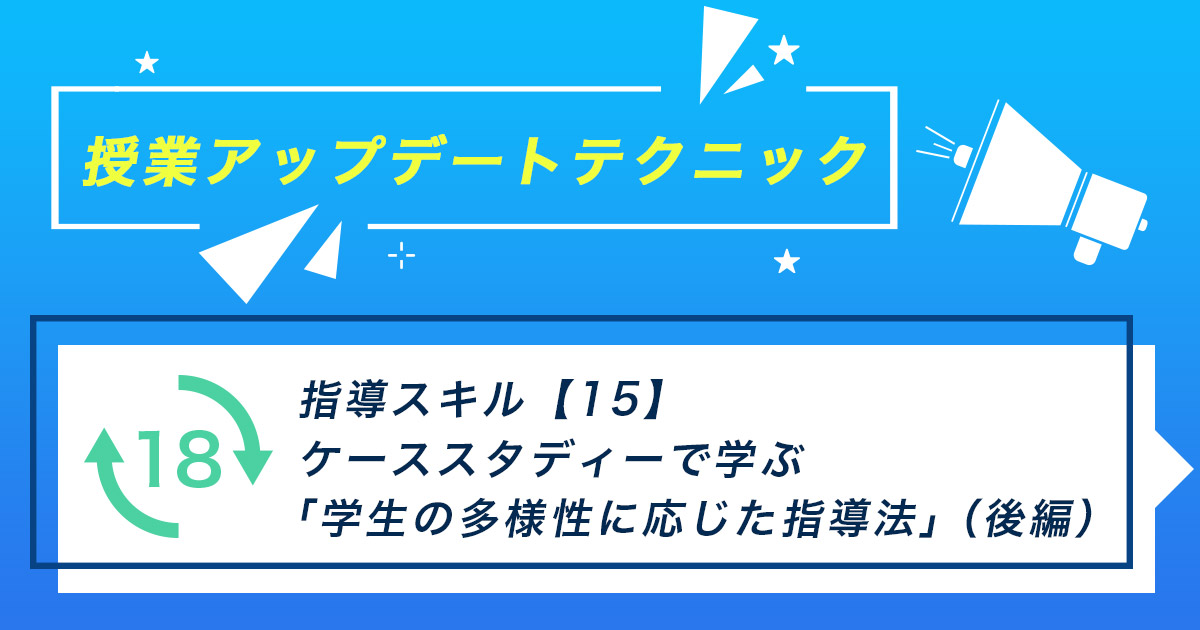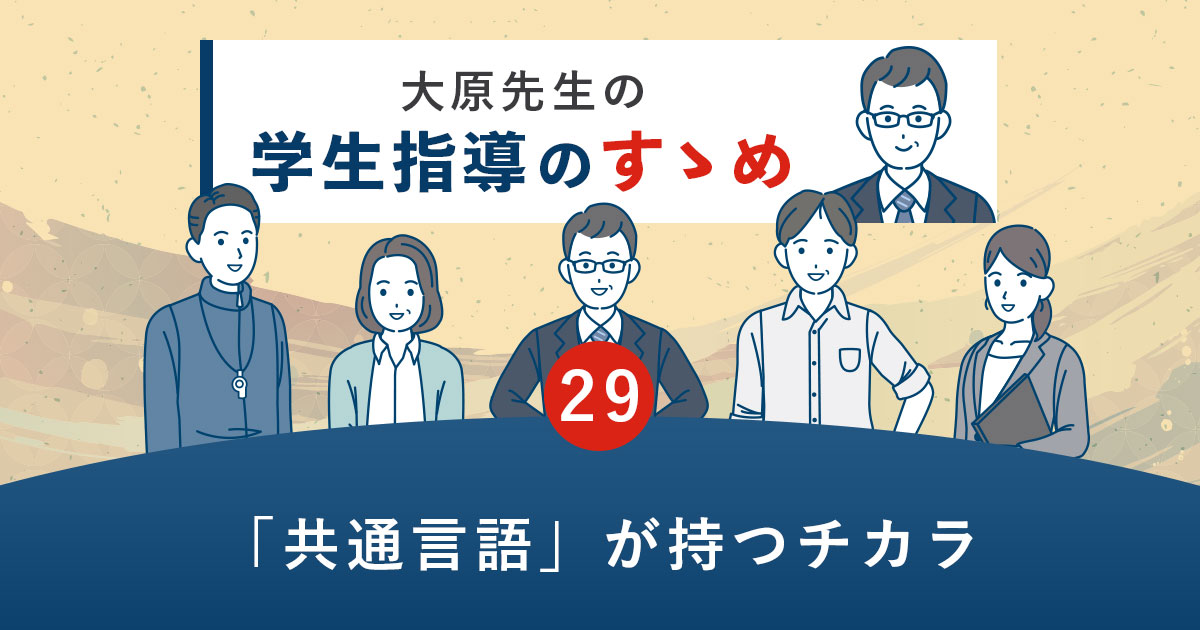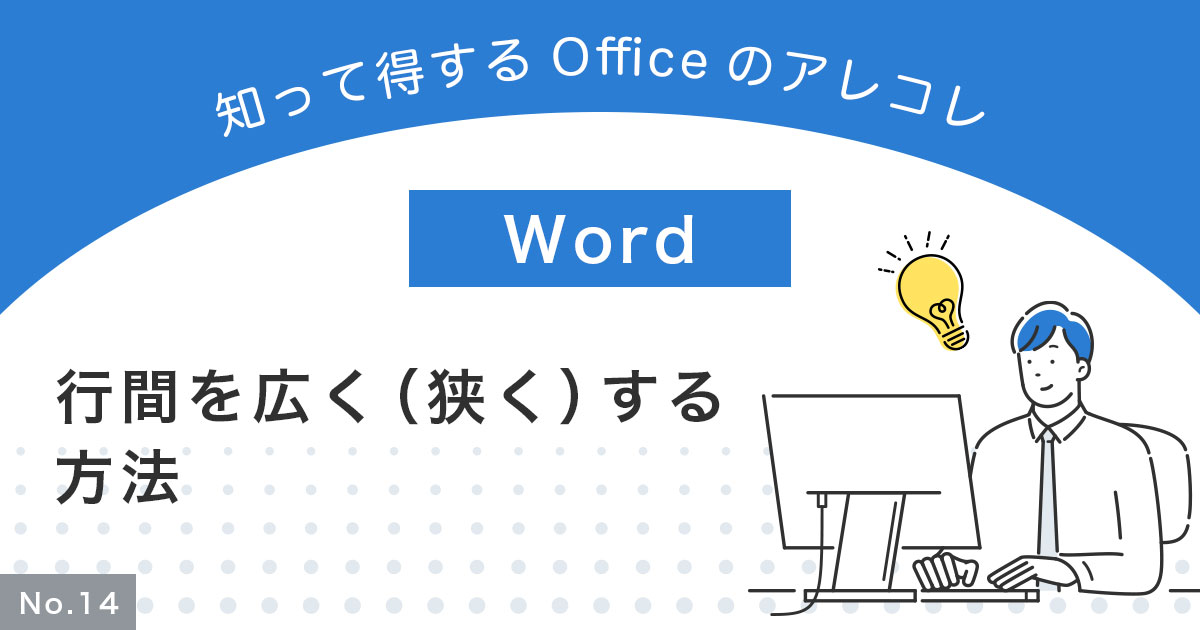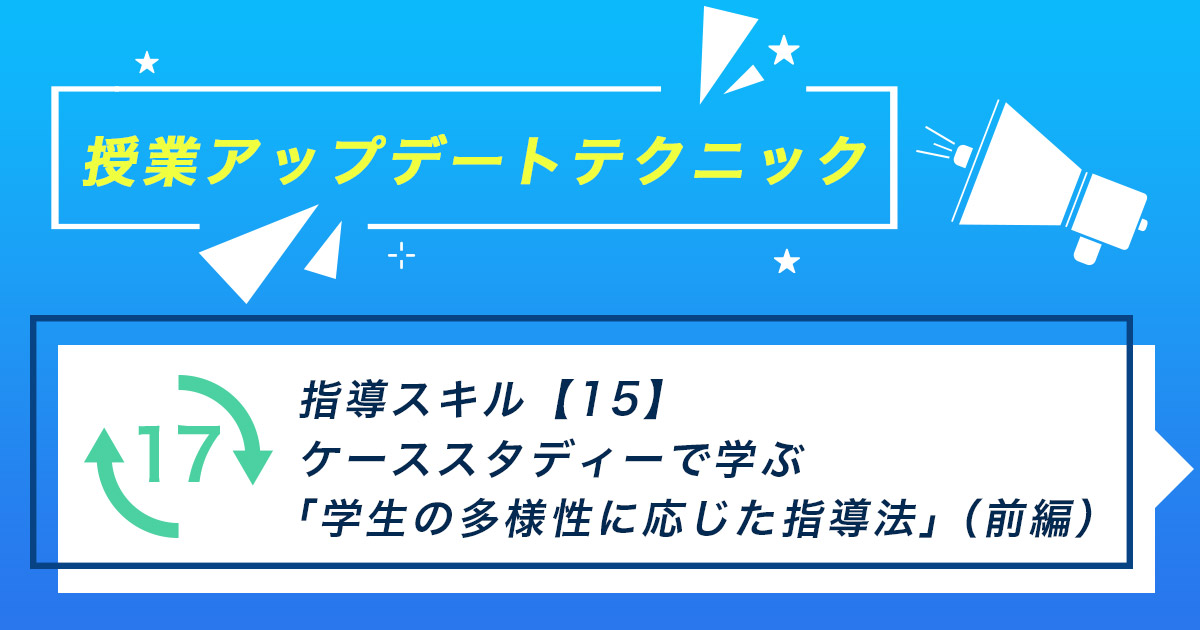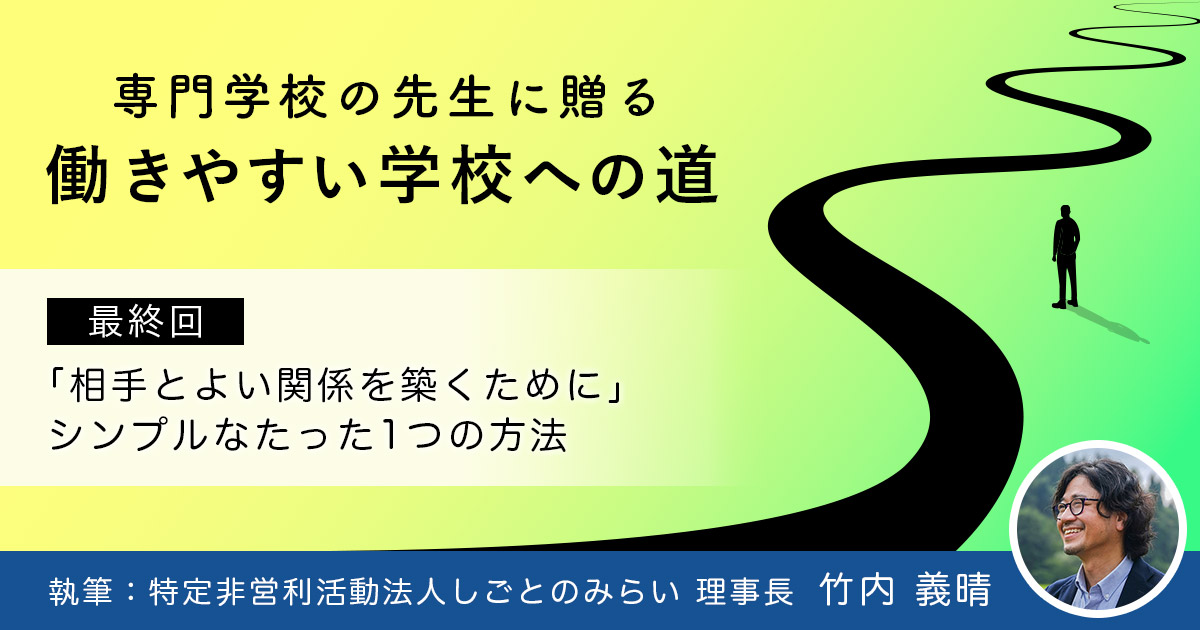
連載専⾨学校の先⽣に贈る「働きやすい学校への道」
働きやすい職場づくりには、「人間関係を円滑にすること」が何より大切!この連載では「楽しくはたらく人・チームを増やす」をテーマに活動を行うNPO法人「しごとのみらい」の竹内さんが、コミュニケーション術やチーム⼒を上げるアイデアを伝授。実践すれば、より働きやすい学校へブラッシュアップすること間違いなし!
しごとのみらいの竹内義晴です。本連載では、専門学校の先生方に向けて、ほかの先生や学生のみなさんとの⼈間関係やコミュニケーション、働きやすい職場づくり、ハラスメントや世代間ギャップの課題解決について、お話ししています。
5回にわたってお届けしてきたこの連載も最終回となりました。今回のテーマは、相手とよい関係を築くための「シンプルなたった1つの方法」についてです。
目次
世代間ギャップとコミュニケーションの課題
私の専門は、ビジネスシーンにおける「職場での関わり方」です。専門学校に限らず、近年はビジネスパーソンの間でも世代間ギャップやコミュニケーションの難しさが課題になっています。
多く寄せられる課題は、「異なる世代が何を考えているのかよくわからない」「パワハラ・モラハラと言われないか不安」「本当は自分から関わっていきたいと思うが、何からはじめたらいいか分からない」といった話が大半です。
そのため、いただく講演やアドバイスの依頼は、「異なる世代の価値観は何か?」「異なる世代の人とよい関係を築くためにはどうすればいいか?」「どうすればコミュニケーションが円滑になるか?」「成功事例を教えてほしい」といった内容が多く寄せられています。
そもそも「対話しているか?」
こうしたコミュニケーションの課題を前に、いろいろな方と接する中で改めて思うことがあります。それは「相手が何を考えているのか分からない」と感じている人の多くが、「そもそも、対話していない」という問題です。
相手と対話していない。だから、何を考えているのかよくわからない。そこで、異なる世代の価値観を知ることで、相手と関わる糸口を見つけたい。そうした背景が垣間見えます。
しかし、「〇〇世代の特徴はこうだ」といった各世代の統計的な価値観を知ったところで、異なる世代のことを理解できるようになるでしょうか。かえって「〇〇世代はこうだ」といった思い込みがコミュニケーションを難しくしてしまうように感じます。
世代論が生む世代間ギャップ

たとえば近年、「Z世代」という言葉をよく見聞きするようになりました。1990年後半~2010年前半に生まれた若手世代のことです。それ以外にも、1980年代~1990年代前半に生まれた中堅世代を「Y世代(ミレニアル世代)」、1960年代後半~1980年頃に生まれたベテラン世代を「X世代」と言います。
各世代の特徴や価値観は、次のようなものがあると言われています。
Z世代(若手世代)
- 幼少期からスマートフォンやSNSが日常の一部
- 動画プラットフォームが情報源
- 環境問題やSDGs、ジェンダー平等など社会課題への関心が高い
- 多様な価値観やライフスタイルを自然に受け入れる柔軟な感覚を持つ
- 個性や多様性の尊重を最優先(固定観念に縛られたくない)
- 社会や企業の倫理観を重視(環境保護や公平性に敏感)
- 体験の共有を重視し、リアルとデジタルの両方でコミュニティーを大切にする
- 「効率第一」「合理性」を求める傾向があり、短時間で結果を出すことを好む
Y世代(中堅世代)
- インターネットとリアルを行き来する「デジタルネイティブ第1世代」として成長
- バブル後の「就職氷河期」を経験し、非正規雇用が増えた時代を知る
- ソーシャルメディアでの情報収集や発信に慣れている
- ワークライフバランスを重視(「働き方改革」への意識が高い)
- 経験や共感、つながりを大事にする(モノ消費よりコト消費)
- 多様性を尊重し、柔軟な生き方を求める
- 転職や副業にも積極的で、安定より「自己実現」や「挑戦」を重視する
X世代(ベテラン世代)
- バブル景気やその崩壊を経験。日本では「失われた30年」を体感した世代
- アナログ文化からデジタル文化への転換期を経験してきた
- インターネットやスマートフォンも使いこなせるが、アナログ的な仕事の進め方も得意
- 仕事に対する忠誠心や忍耐力を重視
- 「頑張れば報われる」という価値観を持つ人が多い
- 物質的な豊かさや安定を重要視する傾向
- 家族やコミュニティーを重んじる一方、自由な個人主義にも関心を持ち始めた
こうした情報をお読みになると、「そうか、〇〇世代は□□の特徴があるのか」と思われるでしょう。
一方で、「そうか。Z世代は多様性やジェンダー、倫理観に対する意識が高いのか。じゃあ、下手なことは言えないな」と思うX世代や、「そうか。X世代は忍耐力重視なのか。それならば、ちょっと体調が悪いぐらいで本心は言わないほうがいいな」のように思うZ世代もいるかもしれません。
本来、人はそれぞれ違う
本来、人は、顔も価値観も異なる多様な存在です。「〇〇世代はこうだ」とは、ひとくくりにできません。
話は少しずれますが、私には大学生と高校生の娘がいます。同じ親から生まれ、同じ時間を過ごし、同じ食べ物を食べて育ったのに、2人の性格は全然違います。同じ家庭で育った子どもですらこうなのですから、どんなに「〇〇世代の価値観は□□だ」といった統計的な情報から相手を知ろうとしても、本当の意味で相手を理解することは難しいでしょう。
相手と対話しない中で、相手のことが分からないのは、ある意味当然です。もし相手をよく知り、よりよい関係を築きたいと思うなら、「対話する」しかないのだろうと思います。
対話する――これが、相手とよい関係を築くための、シンプルなたった1つの方法です。
「話しかけづらい問題」をどう解決するか?
とはいえ、先生方や学生と「もっと対話しろ」と言われても、「それが難しいんだよ……」という気持ちも、とてもよく分かります。声をかけるのは勇気がいりますよね。また、声をかけられたとしても、うまく話せるか、会話が弾むかも不安です。
その不安を解消する……ことにはならないかもしれませんが、ここで、私の経験談をお話しします。私の経験は、年下・年上の同僚との話ですが、対話する相手を同僚の先生や学生さんと読み替えてください。
私は以前、プログラマーでした。本来は、生涯エンジニアでいたかったのですが、あるとき、中間管理職を任されてしまいました。メンバーは15名ほどおり、年齢は若いメンバーもいれば、いわゆる「年上の部下」もいます。気の合うメンバーばかりではありません。膝を突き合わせて、面と向かって話したことがない人もいます。特に、年上の部下は、何を考えているのかよくわからない状況でした。
けれども、「せっかくなら、メンバーと良好な関係を築きたい。なんなら、自分自身もっと気分よく働きたい」と思っていたため、一人ひとりのことをもっと理解しようと、毎月1人30分。全員と話をすることにしました。
もともと人見知りで、それほどコミュニケーションが上手ではありません。自分から声を掛けることも苦手です。ですが、ここは勇気を出して対話することにしたのです。
最初のころは、何を話したらいいのかよくわからず、30分がとても長く感じました。自分から話すのは苦手なので、積極的に話を聞くことを意識しました。
回を重ねていくにつれて、「最近A君の調子が悪いのは、体調が悪い家族がいるから」「何も考えていないように見えていた年上のBさんは、意外と会社のことを考えてくれていたんだ」など、メンバー一人ひとりのことが少しずつ分かるようになってきました。
メンバーのことが分かるようになってくると、「〇〇さん、この間話した□□、最近どうですか?」のように次の会話が生まれるようになり、関係も少しずつ良好になりました。チーム全体の温度が少しずつあたたかくなっていくような感覚がありました。
このような経験を通じて思いました。「やはり、一人ひとりと対話することって、大事だな」と。「良好な関係を築いたり、人を動機づけたりする方法はいろいろあるけれど、最終的には、対話がもっとも大事なんだな」と。これは私にとって、とても大きな気づきと発見でした。
最後は「対話」に尽きる

先生同士や学生さん全員と1対1で話す時間をとるのは、なかなか難しいかもしれません。ですが、5分でも10分でもいいから、話す場をつくって話をしてみる。話を聞いてみる。最後はこれに尽きるのではないかと思います。
そうすれば、意見が合わないことはあっても、「何を考えているのか分からない」といったことは、いまよりも少なくなるはずです。
また、最初から、全員とよい関係を築こうとする必要はありません。ときには、会話が弾まないこともあるでしょう。中には拒否する人もいるかもしれません。それでも、分かってくれる人がいるはずです。私自身、勇気を出して声を掛けたら、「実は、相手も話したいことがあった」ということが何度もありました。そういう人が、たった1人いるだけでいいのです。
時には、「話してみませんか?」と声を掛ける。そして、自分の意見を言う前に、相手の話をしっかり聞く。それが相手を理解する最初のステップだと思っています。
未来のために
この連載では、専門学校で働くみなさんが、少しでも気分よく働けるように、いくつかのテーマでお話ししてきました。
みなさんのまわりには、さまざまな課題があると思います。中には、すぐに解決策が思い浮かばないものもあるでしょう。
「若い学生の成長を支援するために」――専門学校で働くみなさんなら、もちろん、学生の成長も大切です。
ですが、もっとも大切なのは、みなさんご自身が気分よく、楽しく働くことです。そのためにも、先生同士や学生のみなさんと対話してみてください。「この環境をもっとよりよくしよう」という気持ちで取り組めば、すぐにはうまく行かなくても、いい経験にはなるはずです。失敗はありません。どんなにうまくいかないような事象も、すべてはうまくいくためのフィードバック。そこから何かを学び、何かを得られれば、それでよいのですから。
\ぜひ投票お願いします/
株式会社ウイネット
ウイナレッジを運営している出版社。
全国の専門学校、大学、職業訓練校、PCスクール等教育機関向けに教材を制作・販売しています。