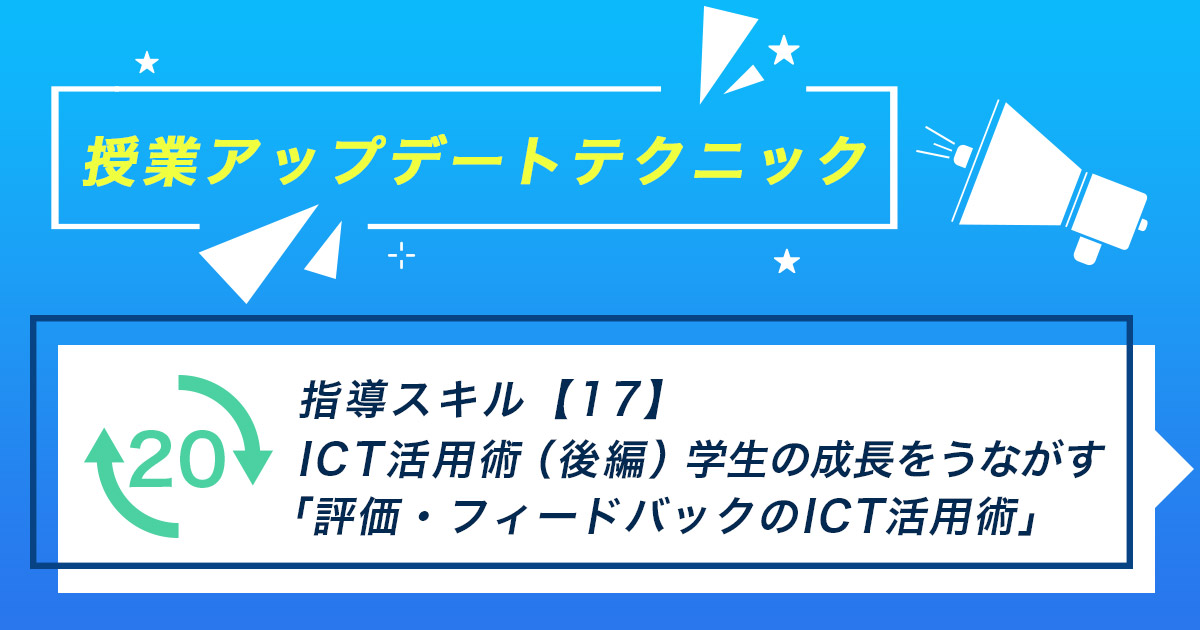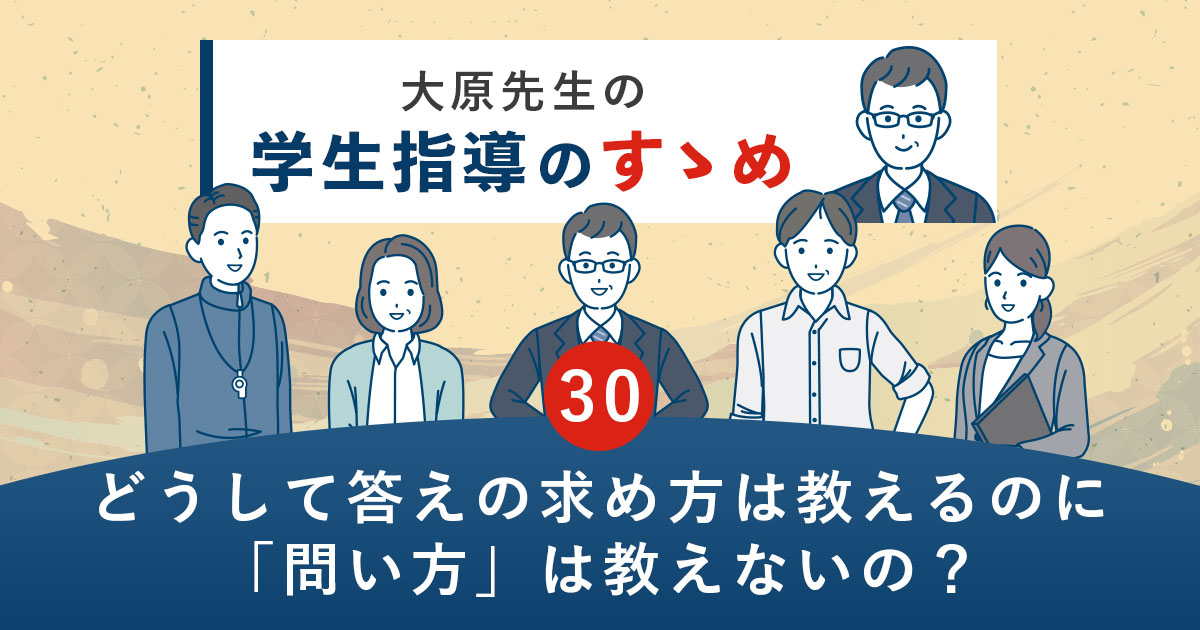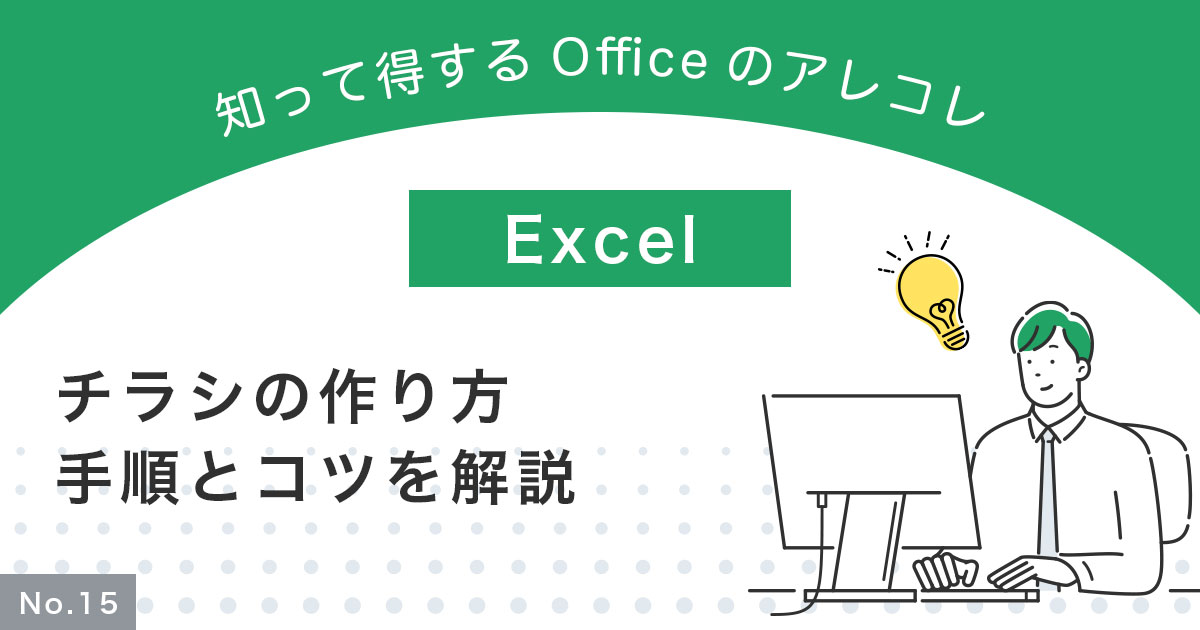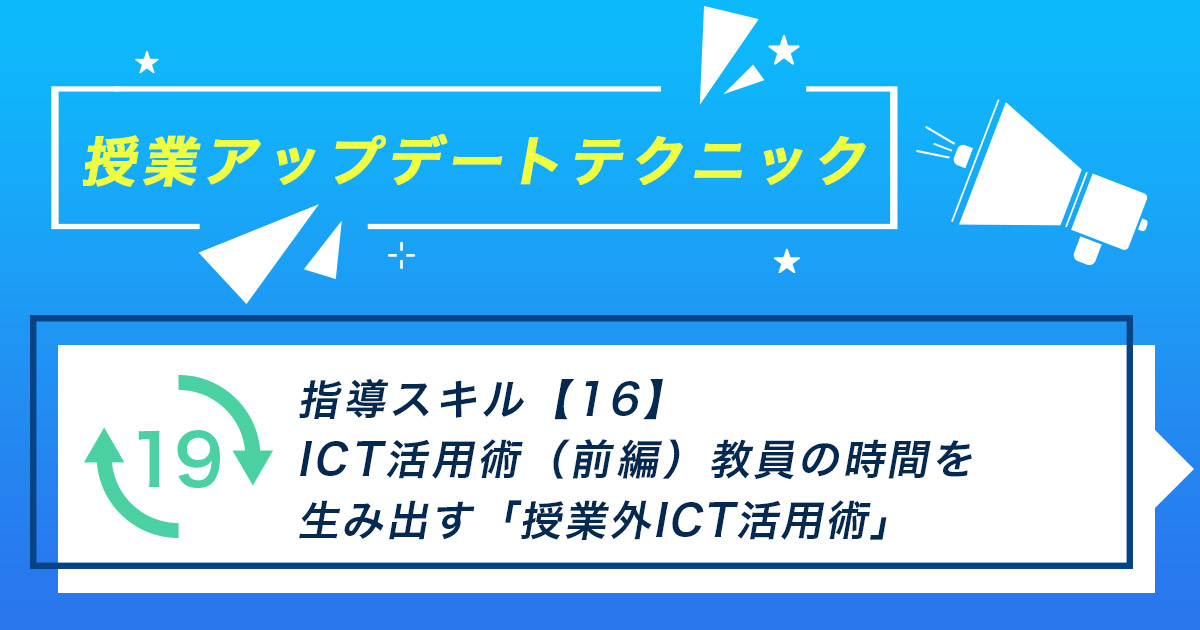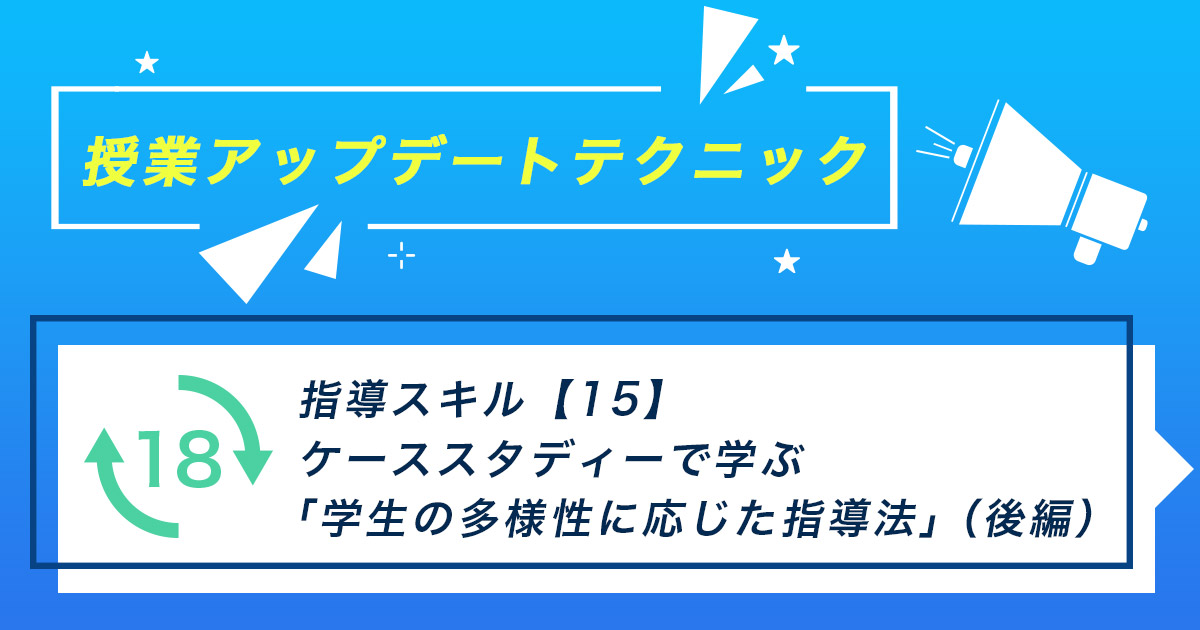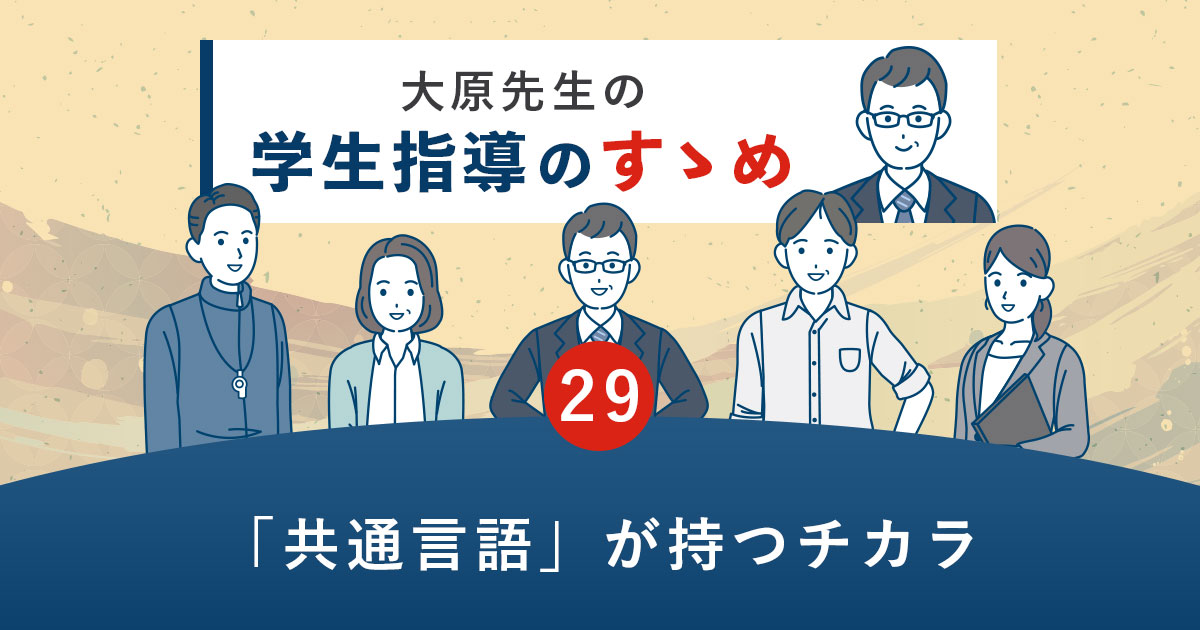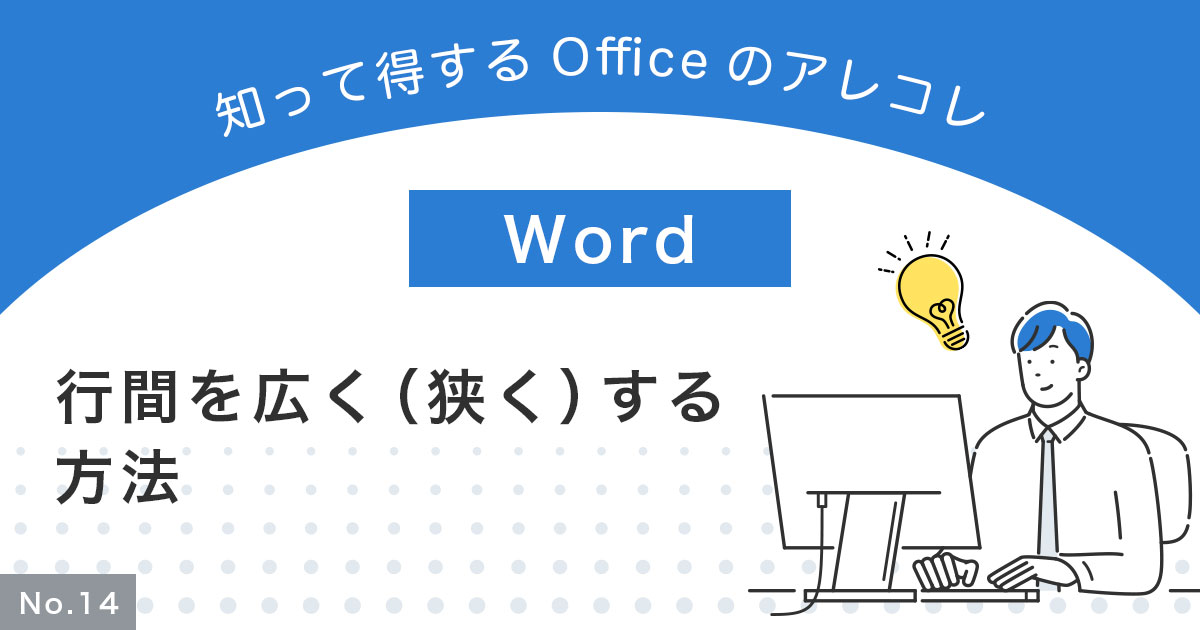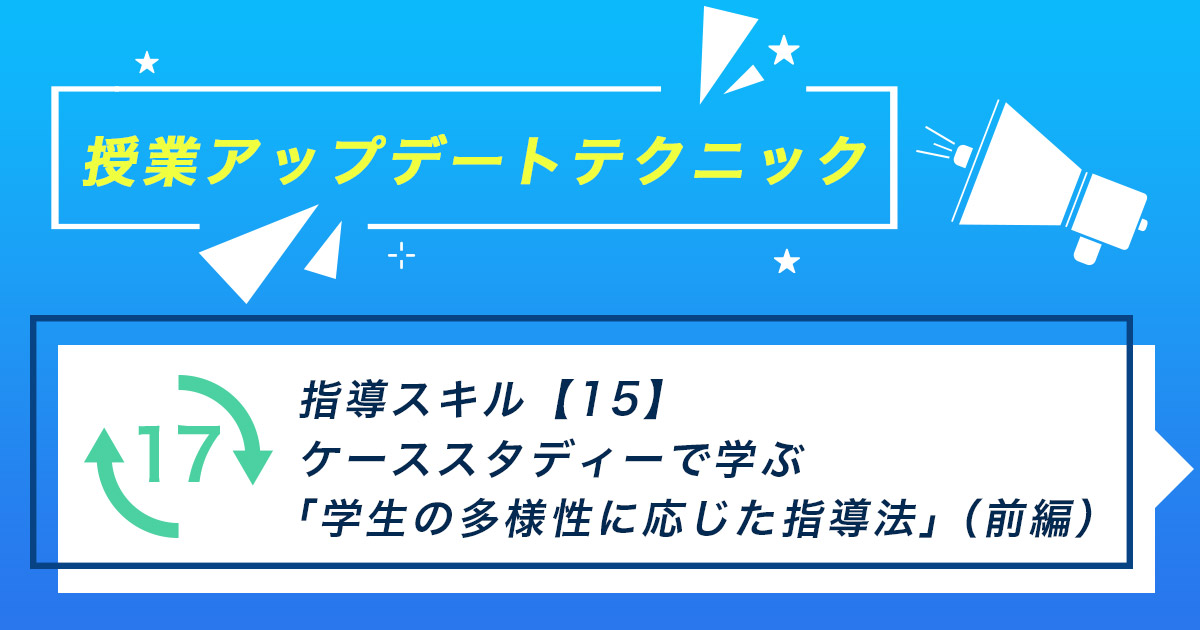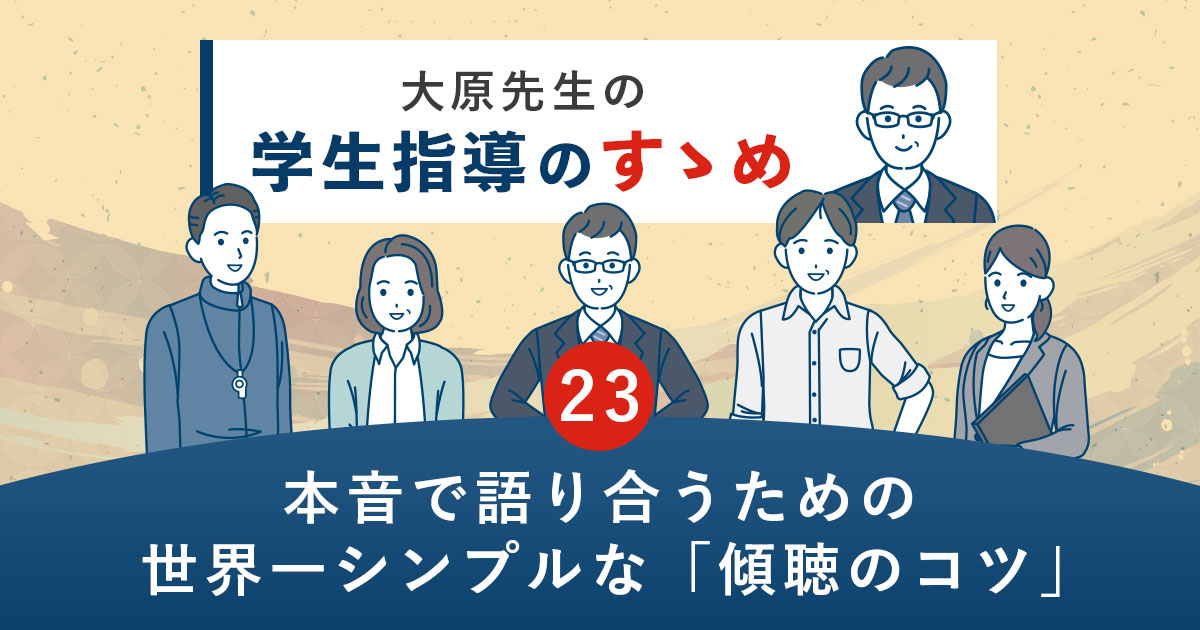
連載大原先生の学生指導のすゝめ
動機づけ教育プログラム「実践行動学」を開発する「実践行動学研究所」大原専務理事の学生指導のすゝめ。 学習塾での指導歴25年の大原先生が、実例を用いて学生への接し方をお伝えするシリーズです。 テンポのよいユニークな文章は、一度読んだらハマること間違いなし。
「この人にはどうも本音が話せない…」
誰しも、なぜか威圧感があって話しにくいと感じる相手がいるのではないでしょうか。ただ、学生が先生に対してそう感じてしまっているのなら、良好な関係を築くことは難しそうですよね…。
今回は、相手に「話しにくい」と思わせないために気を付けたい行動と、世界一シンプルな「傾聴のコツ」について、実践行動学研究所の大原幸夫専務理事から寄稿していただきました。
目次
相手の心を閉ざさせる4つの行動

ここ最近、ファシリテーションの面白さにますますハマってきている大原です。
ファシリテーションの学びは仕事や子育てにもとても役立つことが多いので、“みんなもっとファシリを学べばいいのに”と思ったりもしますが、余計なお世話ですね(笑)。
さて今日は、ファシリの学びで得た日常に生かせる知恵の一つをご紹介させていただきます。
学生と話していると、「心を開いて率直な意見や思いを聞かせてほしい」という場面はよくありますよね。
そんなとき、皆さんはどうしていますか?
もちろん「率直に聞かせてほしいんだけど」と伝えるとは思うのですが、それだけでは相手の心の扉は開きませんよね。
ファシリテーションのスキルは、まさに相手の心を開かせる知恵の宝庫です。
(”開かせる”という言い方は、ちょっと違和感がありますが…)
そこでまずは、「相手の心を閉ざさせる4つの行動」と題して、逆さから見た形でその知恵をシェアさせて頂きます。“これをやったら相手は話してくれなくなるよ”という4つの行動をご紹介しますので、ぜひ普段の言動を振り返りながらお読みください。(笑)
1つめは「否定」
これは分かりやすいですよね。言ったことを否定してくる相手には、何も話したくなくなるのは当たり前です。
2つめは「批評」
否定とまではいかなくても、発言に対していちいち評価・判断を下すような相手だと、警戒心が高まって思ったことを言うのを躊躇するようになります。
あなただって、いつも批評をしてくるような相手とはあまり話をしたくないですよね?
3つめは「分析」
言ったことに対して、ああだこうだと事細かに掘り返されるのは気分がいいものではありません。
相手に心を開いてほしければ、「なるほど。あなたはそう思うんだね」と受け取ることに徹しましょう。
そして4つめ。それは「求めてもいないアドバイス」
これは親子関係や先輩後輩、または上司・部下の関係などにありがちなパターンです。もちろん相手がアドバイスを求めているときは、どんどんしてあげた方が相手は喜ぶでしょう。でも、そうじゃないときのアドバイスは、相手には否定にしか聞こえないこともあります。
せっかく良かれと思って「こうしたらいいよ」と言ったつもりでも、「きみのやり方は間違っている」と言われたと感じることもあるのです。挙句の果には、「あんたにそんなこと言われたくねぇし」と思われてしまうことも…
4つの行動の根底にあるもの
さて、これらの4つの行動の根底にあるものは何でしょうか?
それは、自分の方が相手よりも有能であることを証明したいという「マウント欲求」です。
「マウント欲求」なんて呼ぶところに、ちょっとした悪意がありますが(笑)、誰しも人に認められたいという承認欲求はありますし、上下関係の中ではより有能な自分でありたいと願うのは当然のことだと思います。
そう考えると「マウント欲求」は、謙虚なあなたにとっても無縁な話ではないかもしれません。
心を開いて語り合いたいなら、相手の心を閉ざさせる4つの行動である
- 否定
- 批評
- 分析
- 求めてもいないアドバイス
はせずに、聴くことに徹しよう!
言うのは簡単、やるのは本当に難しいのですが…。(苦笑)
世界一シンプルは「傾聴のコツ」とは

先週、9つの会社の社長さんが集って各社の理念を深め合うという主旨の研修会の設計と実施をさせていただきました。
医療、福祉、電力、人材派遣、お酒販売など、多様な業界の社長さんとの対話はとても刺激的で多くの学びがありました。
研修会といっても私が異業種の社長さんに教えられることは1ミリもありませんので、話し合いのプロセスをデザインし、対話の中から気づきや学びを得てもらうという方法で実施させていただきました。
※弊所は小学生から大学生までの対話型・体験型の学習プログラムと指導者向けのファシリテーション研修を提供していますが、これからは本格的に社会人教育にも力を入れていくことにしました!
久しぶりの丸一日の対面研修。
家に帰ったら“足が棒”でしたが、充実感はいっぱいでした。
会の中で特に印象に残ったのが、インタビューワークの事前練習で行った”傾聴”のトレーニング後の、ある社長さんの一言でした。
”相手の話を聴くのは日常的なことですけど、こうして相手を理解しようという聴き方はあまりやってこなかったことに気づきました”
めちゃくちゃ鋭い洞察!!
これはまさに「世界一シンプルな傾聴のコツ」に繋がる気づきと言っても過言ではありません!
話を聞くときのスタンスはいろいろです。
・相手から必要な情報を聞き出そうとして相手には何の興味も示さない聞き方
・よいアドバイスするために解決方法ばかり考えている聞き方
・とりあえず聞いてはいるが、最後は自分に従わせようとする聞き方
…どれも“傾聴”とは言いがたいですよね。
学生と話すときは、“最後にはこちらの言い分を分かってほしい”というケースが少なくないと思います。
けどまずは、「相手を理解するために聴く」というスタンスで臨みたいもの。
とはいえ社長さんがおっしゃったように、なかなかできないのもこの聴き方…。
人は自分を理解してくれない人の話は聴きません。
逆に自分を理解してくれる人の話は心に響きます。
まずはしっかり意図することから始めてみましょう!
※この記事は、実践行動学研究所のメールマガジン「しなやかな心と学ぶ力が育つメルマガ Colorful Times」163号、233号を再編集したものです。
\ぜひ投票お願いします/
大原 幸夫
一般社団法人実践行動学研究所 専務理事
学習塾に25年勤務。その後小~中学校向けのワークショップの開発、及びファシリテーターの育成に従事している。またコーチング研修等の講師・講演を行う専門家でもある。